双黒:太宰の包帯の下をめぐる話です
横浜の夜に闇はない。眼下に広がる夜景はいつだってきらめいていた。高層建築の灯りが一等目立つが、その更に下には人々の生活のちいさな灯りがある。自動車のヘッドライト、携帯端末の画面、煙草の火……もちろんそれらをそれと認識することは不可能だ。しかしそれは、今日も確かに横浜に灯っている。
* * *
「包帯、また付けたの?」
シャワーを浴びて火照った肌を疎む太宰に女は言った。
「傷痕があるからね」
あくまでもやさしく、太宰は言った。
そこはホテルの一室だった。ラブホテルではなく一般の――といってもそれなりの値段の――ホテル。階はそれなりに高め。シックな雰囲気で自己主張の薄い部屋。
女は一見するとおとなしめだが、物憂げな下向きの睫毛の隠す瞳に破滅願望を孕んでいるのを太宰は見逃さなかった。ねえお嬢さん。太宰は話し掛ける。君、もしかしておうちに帰りたくないのかい。私は出張で横浜に来たものだから、当然今夜はホテルなんだ。よかったらおいでよ。どうせ経費で落とすのだから、何かお酒でも飲まないかい――そういうと、女は一瞬怯えた顔を見せたが、やがてはぱっと睫毛を上向かせた。
ふたりはベッドの上にいた。女のバスローブは既に肌蹴ていた。なだらかな肩、控えめだが形のいい乳房、臍の皺、……。
「苦しいことがあったのかい」
太宰は女の手首に目を遣った。そこにはすこし膨れ上がった筋が三つ程あった。刃物による自傷の痕であることは明らかだった。
「あなたも?」
女は太宰の視線を拾い上げて言った。
「私のは『そう』じゃあないよ。……聞きたい?」
「……聞きたい」
太宰は女の手を取って醜い傷痕にくちづけた。
「いくつの頃だったかな。きっとまだ小学生だった。家が火事になったんだ。夜だった。そんなに遅い時間ではなかったよ。風呂を済ませてさて眠ろうかという頃合だ。
自室に居たんだが、ふと嫌なにおいが鼻をくすぐった。不審に思って扉を開けると、廊下の角の向こうから赤いものがちらちら見える。私は妙に冷静に袖を口に当ててしゃがみこんだ。煙を吸ったら大変だからね。
そこではっと両親のことを思い出した。両親の部屋はその廊下の向こうだった。私は角を曲がった。そこはもう轟々と燃えていて、これはもう無理だろうなあと思ったよ。諦めて自分だけでも逃げようとしたとき、炎の向こうから声が聞こえた。母の声だった。私は思わず炎の向こうに手を伸ばした。――そのときの火傷だ」
「……ご両親は」
「だめだった」
至極あっさりと太宰は言った。
「そう……」
「近所じゃあ前々から虐待やネグレクトの噂があってね。私が火をつけたんじゃあないかって噂になったんだ」
太宰は儚げに微笑して女の頬を撫でた。女の瞳を覗き込み、くちびるの端に親指で触れた。
「……はじめてなのに、こんな男でいいの」
「ッ……いいの」
「ふふ、悪い子。先生や同級生に見られてないといいね」
「……どうして学生だってわかったの?」
「内緒」
太宰は女が学生であることなどはじめからわかっていた。わかっていて声を掛けた。若輩の扱いやすさを太宰は好んでいた。
「出火の原因はライターだと言われたのだけど、両親は煙草なんて吸わなかったはずだ。誰のだったのかなあ」
太宰の手つきはどこまでも優しく、女に快楽と安寧を与えた。
赤毛の女だった。
* * *
中也の主立って暮らすセキュリティマンションは、ポートマフィアの不動産のものではない。マフィア所有の家も持ってはいたが、ほとんど使うことはなかった。
彼がその家を本拠地としはじめたのはいつからだったか――あれはたしか数年前。太宰が突如失踪してから暫くのことだ。
太宰は時折戯れのように手に入れた酒の名を留守電に吹き込んだ。声の後ろの雑音には決まって川のせせらぎがあった。そういう日は夜更けに太宰が当然のような顔で訪ねてきて、共に酒を飲む。中也は太宰の酒の趣味は嫌いではなかった。
「手前、俺が首領に密告したらどうすんだよ」
「しないでしょ。したとしても逃げられるけど」
「この高層ビルヂングからか?」
「飛び降りるにはいい高さだ」
彼らは互いに見張り合うことをしなかったので、中也はいつだってマフィアに連絡を入れることができた。そうすれば忽ち扉から彼らが雪崩込み、裏切り者の太宰に然るべき報いをもたらしただろう。
「手前を捕まえたら、殺すのは俺だろうな」
その晩は洋酒だった。ローテーブルの上には、二色のワインとウイスキー、アイスとチーズとクラッカー。ふたりしかいないがコップは六つあり内ふたつは空。中也は酒ごとにグラスを分けるが、太宰は味が混ざることに頓着しない。中也は太宰のそういうところが嫌いだったし、太宰もまた中也のそういうところが面倒だった。
ソファに並んで座るふたりは密着してはいない。太宰は肘掛に背中を凭れ、しばしば普通に座る中也の太腿を蹴っていた。中也は眉を顰めながらも黙って酒を煽っていた。
「さあねえ、芥川君かもよ」
「アイツに手前を殺せるか?」
「だから尚更でしょ」
中也は「どうしてここに来るんだ」と問うことはなかった。聞いたところで「嫌がらせだよ」と返ってくることはわかりきっていた。マフィアを抜けた理由がおそらくは織田作之助に関係することは知っていたが、詳しく尋ねることもなかった。今何をしているのかも謎だったが、尋ねても答えてはくれない確信があった。
中也はソファの背もたれに掛けていた上着のポケットから、煙草の箱とライターを取り出した。JPSと、サロメのSD9-40。もう随分と長く使っていた。一本の煙草を箱から出そうとしたところで、太宰がまたしても中也の腿を蹴った。
「……吸わないで」
それは太宰にしては珍しい、至極シンプルなつまらない懇願だった。中也はなぜと訊くことができなかった。中也のよく知っていたはずの太宰から、目の前の男は確かに乖離していたからだ。
「昔は何も言わなかったろうが」
「今は違う。煙に乗って死ねるだろうかと期待させるのが残酷だから」
うそだった。いやうそでないが、ほんとうではなかった。
探偵社には喫煙者がいないのだったと、太宰は今更のように思い至った。ゆらゆらと昇る煙は脳裏に記憶を蘇らせる。血溜りと煙草。濡れた赤毛。友の死。常ならばどうということもない。ただ、今は思い出したくなかった。
* * *
寝台の上で、太宰が中也を押し倒していた。中也の横目に太宰の腕が映った。すはだかに巻かれた包帯は妙に痛々しいものだった。
「包帯取れよ」
「いやだよ、今日は抱かれたいもの」
太宰は暗に包帯の下を見たら萎えるだろうと言っていた。そんなことを言われたら、ますます見たくなる――中也は思った。太宰は見られたくないと思っているのだ。それを見ることはいい嫌がらせになる。中也は太宰を見つめたまま食い下がる意思を見せた。
「っせえな、その下の武器を捨てろっつってんだよ」
「うるさくないでしょ、黙ってるんだから」
「目がうるせえんだよ」
「……」
太宰は沈黙のままに包帯を解いた。手馴れた様子で利き手の結び目も解いていた。仕込まれていた細長い針は床に落とされた。
果たして太宰の腕には、膨れ上がった切り傷の痕がびっちりと無数にあった。中也はなんとなくQを思い出しひとつ舌打ちをした。
「……消えねえのか、それ」
「すくなくとも、向こう二十年は消えないだろうね」
「痛いのはきらいとか言ってたじゃねえか」
「『だからこそ』痛いのは嫌だよ。苦しいのも嫌。ついでに言えば君のこともきらい」
死にたい死にたいとうそぶくくせに、彼は平気でそういうことを言う。中也にとって太宰は不可解な存在だった。
「どんなに痛くたって、死ねやしないのだよ」
「……酸鼻だな」
中也は太宰の腕をそっと舐めた。肘から手首にかけて、じっとりと。舌に触れる凹凸に痛みの軌跡を感じながら。理解し難い男の、理解し難い痛みを想像しながら。太宰はそれを、迷子の子供のように見ていた。
中也は太宰の首周りの包帯を解きはじめた。太宰は明後日の方を見ていた。
「……中也」
中也は答えなかった。太宰自身、なぜ彼の名前を呼んだのかわかっていなかった。
「恥ずかしいんだ、中也」
包帯が取られた。そこにはただまっさらな肌があった。生白く不健康そうな素肌。
中也は太宰の背面を見た。太宰は溜息を吐いた。中也の目がうなじに止まる。――そこには、うっすらと十字架の刺青があった。
「……手前、クリスチャンだったか?」
「母がプロテスタントだった。祖母だか曾祖母だかが北欧の人だったらしい。子供の頃に彫られたから、今はもうかなり薄くなっているけれど」
うなじに刻まれた十字架が、彼の死を肩代わりしているのだろうか――中也は思ったが言わなかった。太宰もまた同じことを考えていた。
「死というのは、生まれたときから誰もが孕む胎児なのだよ、中也」
うなじから、背骨を数えるように中也の手が降りてゆく。
「だのに人は、自分の子供を簡単に忘れてしまう。見えなくなってしまう」
向き直る。胸の尖りを軽く食む、齧る。太宰は中也の髪を掻きあげた。狭い額がよく見えた。
「忘れられた子供は復讐するのだよ。それが死の発露だ」
平素は包帯に覆われているセンチメンタルが完全に表出していた。中也はそんな太宰を新鮮に思った。この新鮮な太宰がきらいなのかは無意識のうちに保留されていた。
「わたしは忘れない。忘れられない」
風呂で準備は終えられていた。太宰はいつもそうだった。
* * *
炎は揺れて散っている。月も星もない夜。空に何もないからこそ、雲に覆われて見えないからこそ、どこまでも宇宙を無限に感じる夜。
少年はオイルが交換されたばかりのライターを手に立っていた。闇夜に溶けそうな黒に、月の代わりだとでも言いたげに輝く金のラインが走るライター。少年はぼっ……と火をつけると、絨毯の端に近付けた。
「……森さん、できました」
果てのない空に、煙が昇っていた。
* * *
「ねえ中也。やっぱり私も吸いたい」
「ハァ?」
そうは言いながらも、中也は煙草とライターを差し出した。太宰はそれらを受け取ると、しかし煙草を中也の口に含ませた。吸わない割に慣れた手つきで点火する。中也も黙って顎を突き出し、その煙草に火が灯された。
「ほら、私の分は?」
中也は億劫そうにもう一本を取り出した。太宰は楽しそうに笑ってそれを加え、中也の煙草の先端にくっつけ火を貰った。シガレットキスだった。
太宰は煙草を口から離し、中也の顔に息を吹きかけた。煙が晴れるとそこには中也のしかめっ面があった。太宰はなんだかおかしくなってカララと笑った。
中也は泣きそうな顔で笑う太宰をただ見ていた。
「……酸鼻だなァ、酸鼻だ」

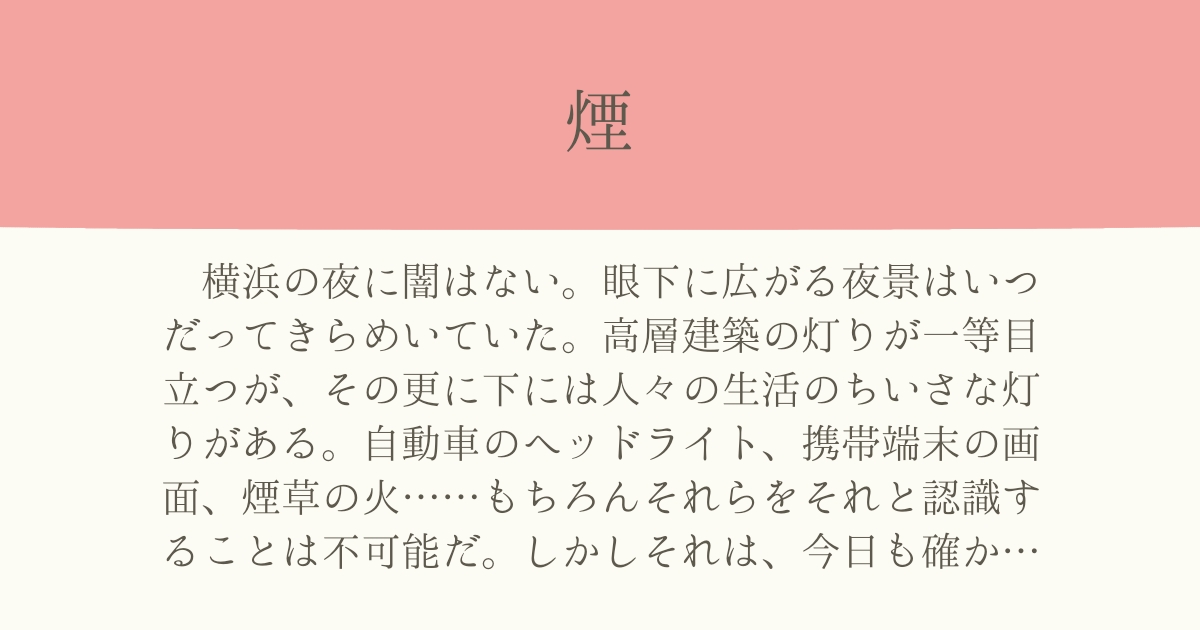
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます