双黒:太宰と中原がすっぽん鍋を食べる話です
東西に流れる川を流れ流れて、死ぬこともなく辿り着いたのは果たしてどこであったのか。横浜であることは確かだろう。そこはどこかの高架下だった。
「……ちぇっ」
舌打ちをひとつ、してみた。その男は太宰治。また死ねなかった、と孤独な壇上で大仰に嘆いて見せた。アスファルトを背に寝転がり、満ちているのか或いは僅かに欠けているのか、それは図りかねるが兎角大きな月を見上げて溜息を吐いた。道化に抜かりはない。たとえ誰も見ていなくとも、道化は道化。やめられぬ。やめるわけにはいかぬ。
湿った砂色の外套が肌寒くって堪らなかった。額や頬に張り付く髪はひやりと冷たく他人のようだった。どうしようもなく生きていた。
足音がした。随分と耳によく馴染むそれに、太宰は再び嘆息した。
――夜空の月がふたつになった。
「手前の悪運も尽きねえな」
ああ、そんなところまで流れてきたのか、と太宰は思った。中也の位置は把握していた。彼の気に入りの靴には発信機が仕掛けてあるのだ。
夜空に煌めくアンバーがふたつ。月と、相棒。元相棒・中原中也。
「久々の直帰だと思ったらこれだ。言っとくが、手前を助けたわけじゃねえぞ。ここで寝てるのを見つけただけだ」
太宰は脳内で地図を思い返す。中也の発信機が示していたのは確かあの辺りだったから、此処は……。
「ねえ中也、鼈を食べに行かないかい」
「は?」
太宰はむくりと起き上がり、頭を横に振った。生死の境界を揺蕩う朧気な意識から、完全な生の世界へ頭を切り替える。
「だって私、お腹空いたもの」
「勝手に行ってろ」
「京都から出てきた鼈の店で、一見さんお断りのところがある。紹介してもいい」
「……行ったことあるのか」
「勿論」
中也は沈黙した。かつて西方に半年程いた頃、『大市』という店で食べた鼈の味を思い出していた。目の前にこの男が座っていたとしても、それでも食べたいか。……食べたい。こんな寒い夜なのだ。熱く弾力のあるあの肉を味わいたい。
闇夜に白い手が揺れた。降参だとばかりにひらひらと両手を上げた中也は、念を押すように言った。
「割り勘だ」
太宰は笑いながら立ち上がると、外套のポケットに手を突っ込んで中也の方を見た。
「財布、流されちゃった」
「……探偵社の人間はそんな嘘で騙せるのか?」
「うふふ、ばれちゃった。でも私を引き上げたのはやっぱり中也でしょ。手袋は濡れたから取った」
今度は中也が溜息を吐く番だった。
〇と書かれた暖簾を潜り店内に入る。そこはもう空気が違った。においだ。濃厚でありながら爽やかでもある、鼈鍋のにおい。中也は後悔していなかった。鼈にはそういう力がある。
和服の女将は太宰の顔を見てから中也の方を一瞥した。
「私の連れだ。予約はないけど大丈夫かな」
「ええ。お座敷が空いてますよ」
品よく歩く女将の案内で座敷に通され腰を落ち着ける。太宰は夜気に晒されて冷えた外套を脱いだ。気を遣うような間柄でもないので、ふたりとも胡座をかいていた。
メニュー表なんてものはない。出されるのは鼈鍋と決まっている。麦酒をふたつ頼んでしまえば、彼らはただ待つだけだった。そしてコースで出てきた刺身や時雨煮をつつきながら、どうだっていいような話をした。
「意外と新しいな」
「丁度西方の抗争の頃に建て替えがあったよ。かなり古かったからね。こちらに来てからもう長いらしい。今の店主の祖父だか曽祖父だかの頃からだ」
生姜のにおいが心地よかった。濃厚に立ち込める鼈のにおいと正反対なのによく調和する。
「つーか、なんだっていきなり鼈なんだ」
「……月がきれいだったから」
「なんだそれ。自殺嗜癖がセンチまで決めて、どうしようもねえな」
「中也の身長の方がどうしようもないよ」
「うるせえ」
「ああ、一見さんお断りってのは嘘ね。京都から出てきてるのは本当だけど、流石に横浜でそんな店は見たことがない。ひとつ嘘を見抜いたくらいでいい気になっちゃあ駄目だよ」
「……はあ、もう完全に鼈の気分だからいいけどよ」
「まあ美味しいから」
中也は無性に煙草が吸いたくなったが、鼈の邪魔をするわけにはいかないので堪えた。ほんのすこしだけ後悔していた。麦酒を一口飲んだ。喉を通るつめたさに、これから食べる鍋の熱さを思った。
やがて彼らの前に素焼の鍋が置かれた。店員が杓子で鍋を優しく混ぜる。鼈の肉は鍋の中で震え、豆腐や椎茸、人参、……鍋を構成するすべてがあまりに完璧だった。黒々とした鼈の甲羅がなんだかおかしかった。
ふたりは沈黙のまま一口目を食べた。熱く、弾力のある、恬淡としてしかし濃厚な肉。口の中から全身に幸福が広がっていく。人間とはこんなにも単純な機構の生き物だったのか。むち、とろり。ふたりは黙して食べていた。口の中で踊る肉を噛むことが他の何よりも優先されていた。美味という意見の圧倒的な一致は水面下に閉ざされていた。
鍋を空にし麦酒を飲む。そこでようやく一息ついた。
「絶対口の中火傷したよ……」
「何が悲しくて手前と揃って火傷しなきゃなんねえんだ……」
「接吻でもする? 互いの舌で火傷したことにしようか」
「精をつけたそばから発散する算段をするな……」
「する?」
「……雑炊が美味かったら」
「じゃ、決まりだ」
そうこうするうちに店員が再びやってきた。雑炊の準備だ。鍋に餅と卵が落とされ、店員はにこやかに去って行った。
「本番だな」
「鍋なんて雑炊の前では前戯だもの」
「手前がいつもねちっこい、な」
太宰はすこしばかり驚いた。この男、なかなか乗り気だ……太宰は中也のそういうところが嫌いだった。彼は不意に予想していなかった言動をとる。
しかしそんな気分も鼈の前では霧散する。鍋の踊る肉とはすこし違う。踊るは踊るが幾分足取りがやさしい。卵の甘みと溶け合って、じんわりとあたたかい。
「なんだか、生き返ってしまった気分だ」
「生き返る前に死ねてもねえだろうが」
太宰は川を流れていた間のことを思い出した。死に近づいていく感覚は何かを思い起こさせる。遠い日のセックスだ。他の誰でもない、中也との。ああ、嫌だなあ。どうして中也なんだ。そう言葉にならぬ泡を吐き出し、海へ海へと近づいてゆく。死に向かって泳ぐ感覚。不可逆な境界に迫る感覚。
「思うに横浜は入水に適さないのかもしれない。西方浄土と言うだろう。しかし海は東にある。矢っ張り日本海がいいのかなあ」
「莫迦か手前。入水じゃなくても死ねやしねえ癖に。浄土なんざ烏滸がましいにも程がある」
そういえば中也は西から帰ってきたのだと、はたと思い当たった。
「苦しいのは嫌だ」
「入水は気持ちいいのかよ」
「……多分ね」
太宰は匙の先をちろりと舐めた。入水は快楽なのか。すくなくとも、快楽を追う行為には似ている。
路傍の犬に吠えられたような気分だった。しかし雑炊は裏切らぬ美味だった。
店を出たふたりはなんとなはなしに月を見上げて白い息を吐いた。
「ホテル? 君の家でもいいけど」
「……ホテル」
後のことなど考えずに耽溺したいから。中也は理由を言葉にせずに歩きはじめた。言わずとも太宰は理解していた。中也はそれを不愉快に思ったが、悪くはなかった。
「今夜の月、満月だと思う?」
「さあ? 十六夜ぐらいじゃねえのか」
「じゃ、私は待宵月」
「どっちでもいいだろうが、ほぼ満月みてえなもんだ」
月と鼈とは言うけれど、君の前では月の方が余程鼈だよ――太宰はそう思ったが、あくまで口に出すことはなかった。

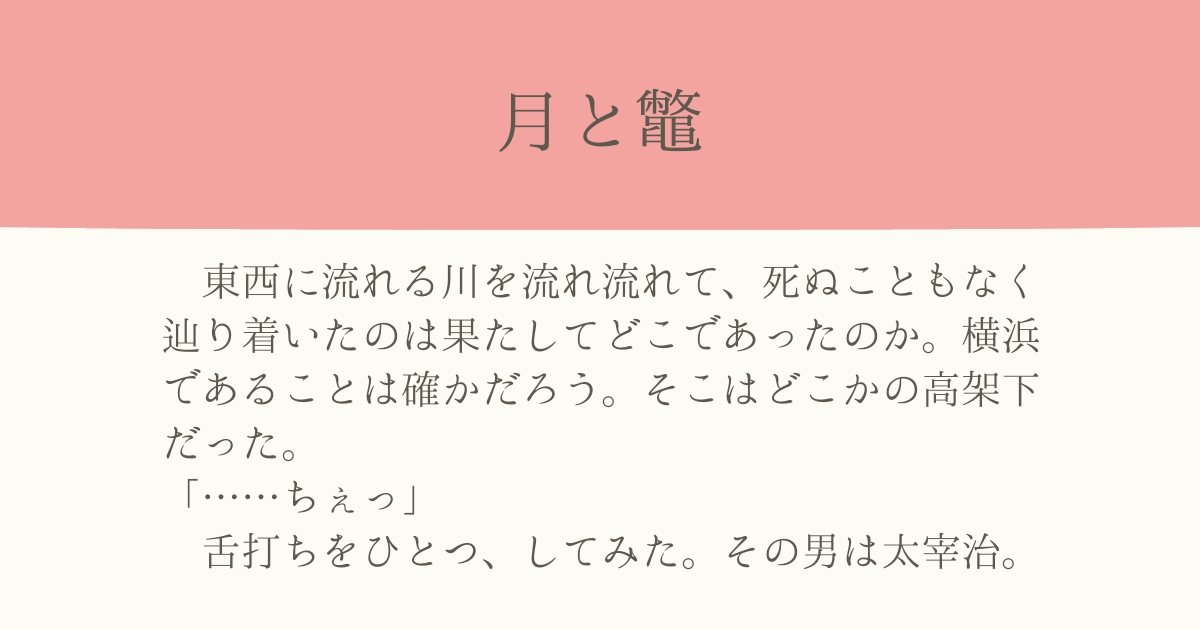
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます