双黒:殺人とピアノとセックスの話です
「ねえ、して」
真夜中、橙の明かりに照らされたその部屋で、太宰は言った。
「『エリーゼのために』というのは、実はそんなに難しくない。小学生でも弾けるものだ」
でっぷりと肥太った男の腹を踏みながら言う。左胸にはぽっかりと穴が開き、男は既に絶命していた。中也の拳が突き抜けた跡だ。声を出す間もなく男は死んだ。彼らが人を殺すのに、武器すらまるで必要ない。ただその身があればよかった。太宰が体重をかける度に床に水溜りが広がった。
生前男が暮らしていた屋敷は成金趣味のいけ好かないものだった。ただ寝室のピアノだけがうつくしかった。愛人あたりが弾いていたのだろうが、もしかすると男が弾いていたのかもしれなかった。
「弾いてよ、中也」
それは決して無理な要請ではなかった。第一に、そのピアノの譜面台には『エリーゼのために』の楽譜があった。第二に、彼は確かにピアノが弾けた。暫く鍵盤に触れていなかったが、エリーゼくらいなら弾けるだろうか。
中也は血に濡れた手袋を外して床に放った。それが承諾だった。
重い椅子を引く、浅く座る、何度かペダルを踏む、ドミファソラソファミ、レファソラシラソファ、……、グー、パー、グー、パー、息を吸って吐く。
「熟々悪趣味だなァ」
探り探り奏でられる音は、しかし不安そうではなかった。中也だって楽しかったのだ。ばかみたいに豪奢な部屋に、上質なピアノと、世界一嫌いな相棒と、醜い男の死体があって、そんな空間でピアノを弾く。もうあと十人くらい殺していたら、きっと彼らは笑い転げて鍵盤の猫を踏んだだろう。しかし死体がひとつであるなら、このくらいが丁度いい。
君にはクラシックよりジャズが似合う――太宰はそう思ったが口にはしなかった。代わりに「黒社会最悪のふたりに、お固いクラシックは似合わないね」とだけ言った。
「ジャズか。聴くのは好きだが弾いたことがねえな……」
太宰はどうしようもなくざわついた。まただ。この男は度々そうだ。太宰が口にしないと判断したことを、当然のようにわかっている。おそらくは推理などではなく、ただほんとうに、わかっている。
「君の好きな音楽か。私にはさっぱり理解できなさそうだ」
だから太宰は、こう言うしかない。
プティの卵は中也の手の中に安らかにある。軽やかで楽しげな音は、確かに彼の指が奏でたものだった。
中也のエリーゼはどんどんアレンジされてきていた。もう彼は楽譜を見てはいない。冒頭のメロディだけを使って、跳ね、沈み、揺れる。ジャズは弾けないと言っていたが、このスイングはジャズのようだと太宰は思った。太宰にはジャズに深い造詣はないし、魅力だってよくわからない。ただやはり、彼のような無法者にクラシックは固すぎると思った。
中也の指が縺れて転ぶ。それでも彼は笑いながらグリッサンドに流してしまった。
そうして再びあのメロディを弾こうとしたとき、太宰の左手が中也の右手を鍵盤に押し付けた。不協和音。プティの卵は割れてしまった。太宰の手が離れようとしたとき、中也は自然とペダルを踏んだ。鍵盤にはもう誰の指も触れていない。けれども音は鳴り続けている。
その不協和音の中で、なんとなく彼らはキスをした。
きれいな旋律は似合わないと、中也はぼんやりと思った。そんなきれいな接吻ではない。
太宰の腰が鍵盤を押す。不協和音が厚みを増す。それは彼らの青春に似ていた。上手にペダルを離せないまま、音が重なり、濁ってゆく。けれどその濁りの持つ力に、大人たちは圧倒される。
くちびるを何度も啄んで、ようやっと離れる。そのとき中也の足もまた、ペダルから離れた。
「君は誰に捧げる?」
「……誰でもない、この一夜に」
「ふうん」
ベートーヴェンがテレーゼに捧げたらしいこの曲を、一体誰に捧げればよいのか。そんな相手を彼らは持たない。ただ一夜一夜を重ねてゆくだけだ。きっとペダルを離さぬままに。
「ここを出て、すこし進めばモーテルがある」
「へえ」
中也は太宰の言わんとすることに否定も肯定も返さなかったが、代わりに立ち上がると鍵盤の蓋を閉めてしまった。
太宰は男を転がし顎を破壊すると、再びひっくり返し、いつの間にやら手にしていた拳銃で胸を三発撃ち抜いた。
「それ俺のだろうが」
「拝借したよ。はい」
太宰は飄々と中也に銃を返し、ピアノの曲線をツゥと撫でた。中也はそれを呆れたようなポーズで見たが、手袋を拾い顔を上げたときにはもう愉快そうに笑っていた。
「中也」
「……行くんだろ? 早くしろよ」
So Do Me

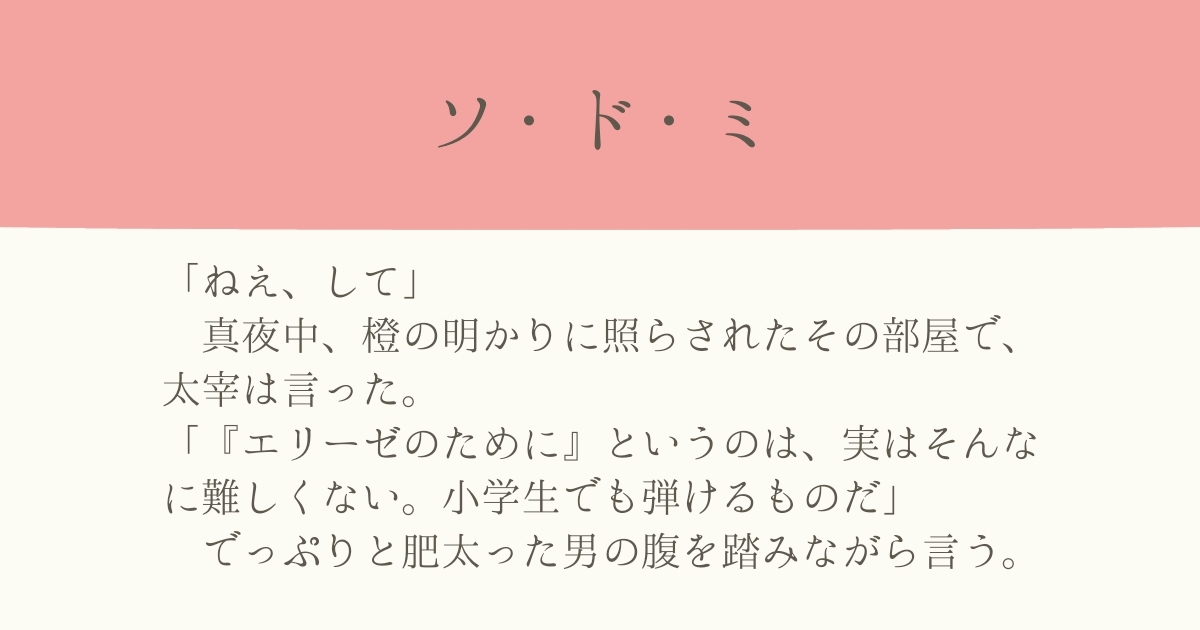
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます