双黒:双黒復活直前、コーヒーを淹れて国木田に飲ませようとする太宰の話です
国木田は太宰を知らない。太宰という男が何者であるかを知らない。つい先刻のことだ。彼の前職がポートマフィアであることを知った。だがだからといってなにかがわかったわけではない。そう思わせるカムアウトだった。
ポートマフィアといえば、真っ先に浮かぶ顔は芥川龍之介だ。人を殺めるのに一切の躊躇をしない黒外套の男。太宰もかつてはそんな男だったのだろうか。あるいは、今も。我が理想に反する。
国木田が給湯室の傍を通ると、なにやらバリバリガリガリと音がしていた。不審に思いつつ中を覗くと、其処では太宰が珈琲豆を挽いていた。どこから取り出したのか手挽きのミルをくるくる回している。そういえばいいにおいがしていた。
自分も茶でも飲もうかと給湯室に入る。声を掛けないのは不自然な気がした。普段はどうしていただろうか。意識していないためわからなかった。
「手挽きか」
迷った末、たったそれだけを言った。
「おいしそうでしょう。ひとり分だよ」
「……知ってる」
「今ちょっと期待したでしょ」
「誰がするか。貴様の珈琲なんぞに。なにが入っているかわからん」
太宰はそれ以上言わなかった。だから国木田も、なにも言えなくなった。
――手前には珈琲の善し悪しなんざわかんねえだろ。酒と消毒液の違いもわからねえくせに。
――中也は姐さんと私を間違えるくせに。
――ったくいつの話だよそれ。
いつの間にやら太宰はサイフォンを取り出していた。随分と本格的だった。燐寸でアルコールランプに火を点け、サイフォンに湯を入れる。彼の手付きのすべては、慣れを感じさせるものだった。国木田はそのことに違和を覚えた。器用さではない、慣れなのだ。
「いいかおりだ」
「……頻繁に、そういう風に入れるのか?」
国木田は口を開いた。訊いてみたくなったから訊いた。まるで自然な会話のようだった。ひそかな手応え。
「そんなには。凝り性の女の子の前でやると反応がいいけど」
「へえ」
「教わりたい?」
「結構」
――どうだ太宰、おいしいだろう。
――おいしいけど、別に普段と変わらない気がする。織田作にはわかるの?
――お前以外の大半の人間はわかりそうなものだがなあ。
国木田は理想に生きる男だ。だから、太宰という存在が割り切れない。しかし割り切れないなりに、彼のあまりに黒い過去には説得力があった。ふわふわとした掴めない男には、なぜだか重い罪が似合った。
「国木田君はすぐ顔に出る」
奇妙な台詞だった。なぜなら太宰は国木田に背を向けて珈琲を淹れているのだから。
「君は三十五人殺しをどう思う? 法に則るならまず死刑だ」
「彼女は……一度だって、望んで殺人をしたことはなかった」
国木田はどうにかそれだけを言った。
「そうだね」
太宰はなんだかそっけなかった。国木田だって太宰の顔は見えないのに、彼のつめたい瞳がわかった。……そもそも、彼の瞳が冷たくないときとはいつのことだ? 国木田は自分が彼とともに過ごしてきたはずの時間がわからなくなるような心地を覚えた。
「私は君の理想に反する存在だろう。多分私には、探偵社員よりマフィアの幹部が向いている。けれど私は、自分の選択で探偵社にいるんだよ」
「……なぜ、探偵社に?」
「企業秘密」
ぽこぽこと間抜けな音がした。湯が沸いたのだ。太宰は準備していたフィルターをセットしフラスコに粉を入れ、さっと拭いて漏斗に挿した。
国木田は、太宰が秘密だと言ったことになぜか安堵した。どんな理由を聞かされても、それはきっと嘘にも本当にも思えただろうからだ。
「……そういえば、さっきはバナナの皮を剥くのも面倒がっていただろう。どういう風の吹き回しだ?」
太宰はゆっくりまばたきをした。
「スイッチングに儀式を求める程度には、私は若いということだよ」
国木田にはよく理解できなかった。けれどもなんとなく、太宰のことを近しく感じた。
湯が上りきったフラスコを箆で掻き混ぜる太宰を見ながら、国木田は彼の入社試験を思い出していた。銃などはじめて触るというような体で、六蔵少年を切り捨てた太宰。そこで国木田ははっとした。
――あのとき……お前の入社試験のとき、もしもお前が探偵社員になろうとしていなかったのなら、お前は『六蔵少年を使わなかった』のか?
国木田は恐れながら、結局その質問を口にすることはなかった。太宰は湯気を昇らせる珈琲を、国木田の臆病に感謝しながら揺らしていた。
「ねえ、国木田君。この珈琲は確実においしいけれど、おいしいかい?」
太宰はそう言ってマグカップを差し出した。
「……どういう意味だ? 毒味か?」
「飲んでくれ給えよ、私の珈琲を。きっとおいしいから」

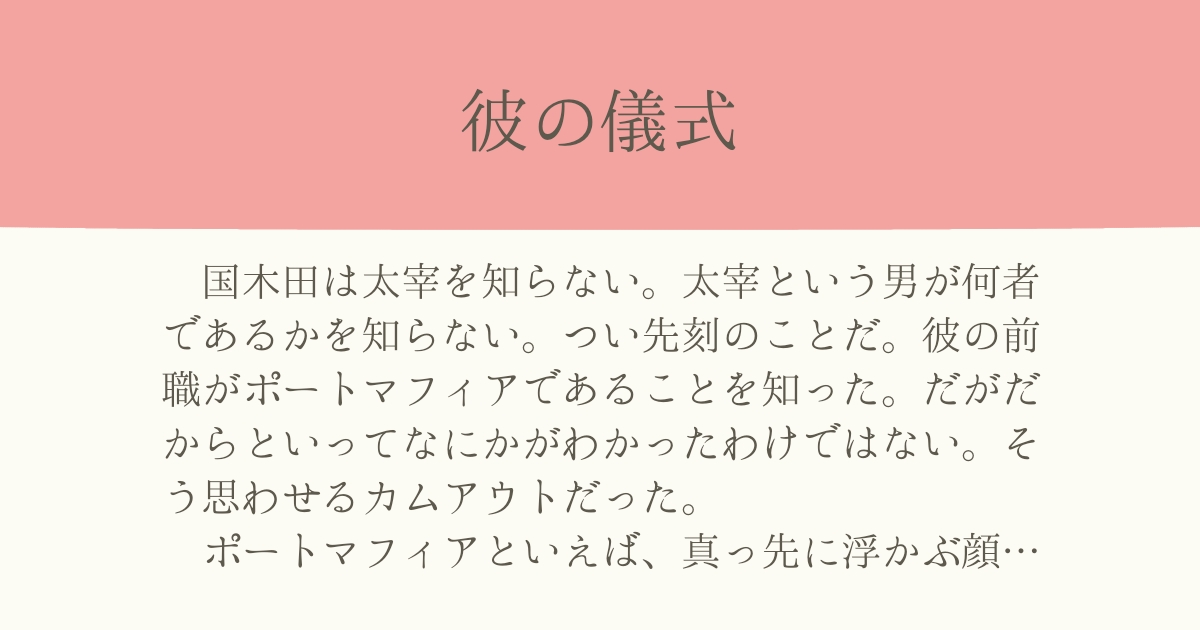
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます