双黒:はじめて汚濁を使った中原の話です
月がきれいな晩だった。しかしその月はやがて汚濁に覆われてしまった。そうして真実の月が姿を現す。彼の金色は汚濁の中でさえ闇夜に揺れて輝いている。頼りなく、覚束無い足取りで、なのにふらりと振られた腕からは世界を壊す混沌が放られる。彼はその夜、誰よりも強い力を持っていた。そして同時に、誰よりもその力に屈服していた。
太宰はそれを見つめていた。太宰自身の気持ちはいつも太宰から遠いところにある。何枚もの薄い膜に隔てられて、手を伸ばしても届かないから、最近はもう手を伸ばそうとしてすらいない。けれど時折疾風が吹き荒ぶと、膜が捲れて幼子のように不鮮明で不明瞭な感情が剥き出しになる。太宰はそれを苦しいと思う。
その疾風を連れるのは、多くの場合、彼だった。
そのとき太宰がすべきことは、力を暴走させる中也に一刻も早く触れることだった。だから太宰は一歩一歩彼に近づいていた。けれど太宰は走らなかった。生命を削って世界を否定する中也は、おぞましく、うつくしく――太宰は自分の感情を認めたくはなかった。だって、こんな中也、まるで鏡を見ているようじゃあないか!
彼らは世界を否定していた。世界が彼らを否定しているいるとも思っていた。太宰は自殺を試みた。中也は汚濁を発露させた。太宰の自殺は未遂に終わる。中也の汚濁はその身を滅ぼす。その前に汚濁は終わらせられる。他でもない太宰の手で。
太宰は中也に触れたかった。太宰は中也に触れたくなかった。そのとき太宰は、生まれてはじめての感情を抱いていた。それに名前を付けることは太宰には困難だった。
――君を止めさせてくれ。最適解として、私は君を止めなければならない。君はこのままがいいかもしれないけれど、同時にこのままは嫌なはずだ。君を止めさせてくれ。私は、君がこのまま世界を壊してしまったら、どんなにかいいだろうと思う。私は、君がこのまま世界と共に壊れてしまったら、どんなにかいいだろうと思う。けれど、けれど私は――……
そういうとき、多くの人は、わがままでごめんね、と思う。
* * *
汚濁ののち、中也はくったりと死んだように眠っていた。太宰は中也の肉体を支えることはできないし、端からそんな気もない。だからすぐに応援を呼んだ。
翌朝、首領に報告を済ませた。
「彼はとんでもない獣を飼っていたのだねえ」
案の定、森は太宰に言った。
「彼のそばにいなさい。彼の獣は未知数だ。何が起こるかわからない。君の力が必要になることもあるだろう」
だから太宰は、中也のそばにいなければならなかった。それが最適解なので、森が太宰にそう命じない可能性は存在しない。だから太宰は、もしも首領の命令がなかったら自分がどうしていたかを考えることを、しない。
中也はやはり死んだように眠っていた。窓の向こうから注ぐ穏やかな太陽の光を浴びていたから、ここが霊安室のわけがなかった。そんな理由で生存を確認する程だった。
マフィアと繋がりの深い病院の一室は、不気味な程に真っ白だった。似合わない、と太宰は思った。こんな部屋で眠っているのは、中也には相応しくない。太宰は苛立っていた。中也が眠っていることに不満を感じたのだ。
太宰が寝台脇の椅子に腰掛けてぼんやりと次の自殺の算段を立てていたとき、中也の口許からひとすじの赤褐色がしたたった。血液とも汚濁ともつかぬ液体に、太宰は眉を顰めた。太宰はそれを拭うことなく中也の顎を掴み開いた。喉の奥に指を突っ込み舌の付け根を適当に触る。自身の異能が発動する感覚。汚濁の残滓か、或いは余震のようなものか。すぐに赤褐色の流れは止み、中也は思い切り嘔吐きながら目を覚ました。
「ッが、えぅ、な、に……」
太宰は大人しく手を引いた。中也の唾液で濡れそぼる指を忌々しそうに一瞥すると、立ち上がり手を洗いに行った。中也は訝しみながらも、自分が太宰に救われたことを自覚していたため黙っていた。
暫くして戻ってきた太宰は、その手に林檎とナイフを持っていた。
「……太宰」
「昨夜、君の異能が敵組織を壊滅させた。君自身には制御不能の暴走だ。……とはいっても、暴走は私がいればコントロールできる。君は倉庫の奥に仕舞われていた伝家の宝刀を見つけただけだ」
「諸刃の刃じゃねえか」
「おまけに鞘がないと来てる」
「……手前に飼い慣らされるのは御免だなァ」
太宰は再び椅子に腰掛け脚を組み、するすると林檎の皮を剥きはじめた。中也はそれを見てただ器用だな、と思い、その数瞬後に空腹を自覚した。
「私は君を飼い慣らせない。ただ、君が君自身の抱える貪汚を飼い慣らせるか否かというだけだ。……そのために、君に私が必要だというだけだ」
あの夜、太宰はたしかに興奮したのだ。そして同時に落胆していた。
酸化した世界に突如起こった想定外の爆発は、しかし太宰の掌の上だった。中也の汚濁を支配するには、他の無効化異能力者が現れない限り、自分が必要なのだという純然たる事実。そして沸き起こる破壊衝動。このまま世界を壊してしまえたら。
けれど太宰は気付いたのだ。中也が世界を破壊する間、太宰はひとりぽっちなのだ。そして中也が世界を破壊した頃、きっと中也はいないのだ。これでは「あちら」と「こちら」が入れ替わるだけで、自殺と何も変わらない。中也の汚濁で世界を破壊することは、中也と共に自殺を試みて、どちらかだけが死ぬようなものなのだ。……多分、どちらが死んでも、同じだ。そういうことだ。なんとなくそう思った。
太宰は心中相手に中也を選びたくはなかった。
太宰は中也を飼い慣らせない。中也に対する不鮮明な感情すら、飼い慣らせやしない。
「君が君自身を飼い慣らすしかない」
だから、太宰はそう言うしかない。
太宰はきれいに繋がったままの林檎の皮をゴミ箱に放り、器用に掌の上で林檎を八等分した。芯を取ってサイドテーブルの皿に乗せ、ひとつ食べ、またひとつ食べ、一向に中也に寄越す気配を見せない。
「太宰、一個寄越せ」
「嫌だ」
「ハァ? 病院で患者放ったらかして自分だけ林檎食う奴があるかよ」
中也は太宰のささやかすぎる嫌がらせに違和を感じた。こんな子供の悪戯じみた嫌がらせは、普段の彼なら選ばない。
太宰のそれは単なる意趣返しだった。昨夜からずっと抱いていた不満が発露しただけのものだった。太宰にはそれが嫌がらせであるという自覚がなかった。
「私たちの関係はフェアじゃない。君の利ばかりが大きくなった」
汚濁の存在によって、彼らの力関係の均衡が崩れる。相棒であることに明確な書類上の理由が生まれる。太宰はそれが嫌だったのだ。それはなにかたいせつなものを乱してしまう気がしたのだ。
「莫迦云えよ、手前にも利はある」
「どんな利があるっていうの」
「愉しい」
「は?」
「手前は、俺と組んでいるとき、愉しい。これでいいじゃねえか。お互いにプライスレスだろ」
「……中也、それ自分で言っててどんな気持ち? 恥ずかしくないの?」
「死ぬ程不愉快に決まってるだろうが! だがな、俺は手前にこの関係が対等じゃねえと思われる方が不愉快なんだよ!」
「……そう」
太宰は一欠片の林檎を口に咥え、寝台に手をつき腰を浮かせた。林檎を中也のくちびるに押し付けると、中也のくちびるが開かれた。そうして中也が歯を使って林檎を咥えようとしたそのとき、太宰は林檎をしゃくと噛みきって食べてしまった。支えを失った林檎は、万有引力に従ってシーツの上に落っこちた。中也はただそれを見ていた。
「手、洗ってくる。ついでに先生も呼ぶから」
「……足は洗うなよ」
「中也、チビのくせにそういう冗談を無理して言うのは格好悪いよ」
「うるせえ」
* * *
中也は簡単な診察を受けるとすぐに帰宅を許可された。もとより荷物など持ち込んでいないから、ただ帰るだけだった。
病院から出たところで中也ははたと思い当たり尋ねた。
「太宰、俺の帽子は?」
「中也が生み出した重力子の塊に飲み込まれて消えたよ」
「嘘だろ、気に入ってたのに……」
「嘘だよ、はい」
太宰はそう言ってどこからか取り出した帽子を差し出した。しかし中也が手を伸ばそうとすると、それをひょいと高く持ち上げてしまった。
陽光が、ひとりでは汚濁を飼い慣らせない男を照らしていた。光を浴びて透きとおる彼の髪を、太宰はじっと見つめていた。ややあって太宰は自ら帽子を中也にかぶせた。
太宰はなんとなく、白昼の中也には帽子をかぶっていてほしいと思った。だから言葉を選んだ。
「相変わらず変な帽子。どうせ家にいくつも同じのがあるんでしょ?」
「あ? 同じじゃねえよ、違いのわからねえ男だな」
期待通りの中也の返事に、太宰は安堵した。これでいい、と思った。
平和な横浜の街をふたり肩を並べて歩く。距離は決して近くない。けれど遠くはない。手の届く距離。
「鍵をかけなくてはならないね」
「鍵?」
「伝家の宝刀を仕舞う倉庫の鍵だ」
「開けるのは俺なのに閉めるのは手前か。癪に障るなァ」
「ふふ、私を飼い慣らしてご覧よ、中也」
「土台無理な話だな」
ちがう。そのとき太宰はそう思った。
それは決して無理ではない。なぜなら、中也が自身の汚濁を飼い慣らすためには、ただ太宰がいればよいからだ。そして太宰の自殺は成功しない。それがわかっていたから、太宰は、わかってないな、と思った。

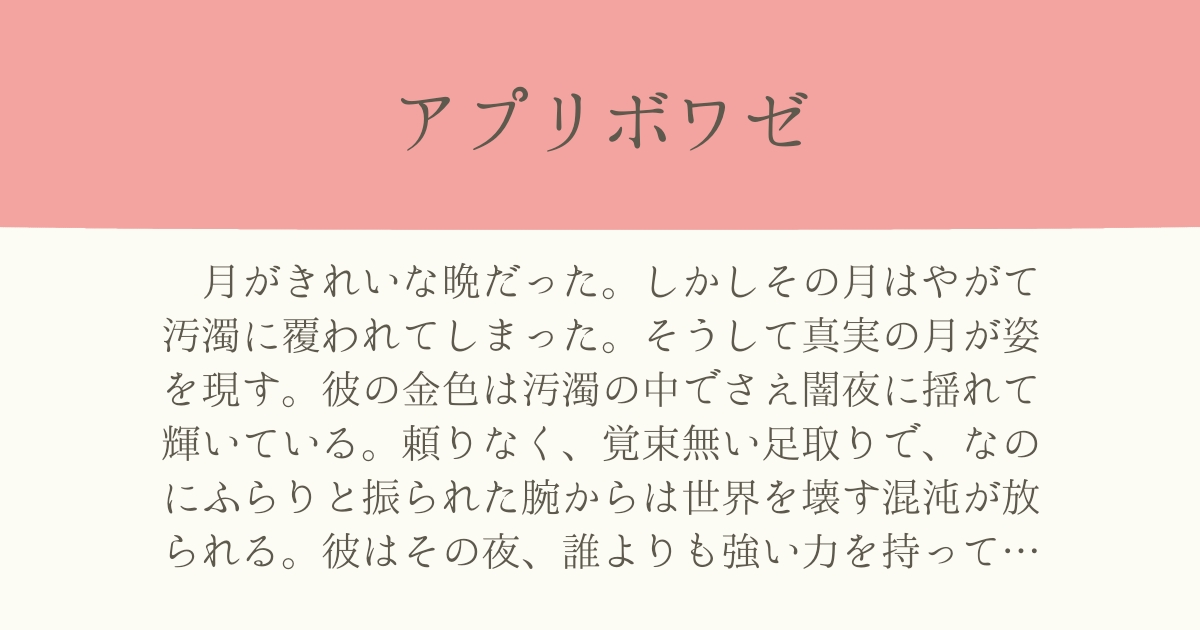
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます