彼がここにやってきた日のことを、ぼくは多分、一生忘れない。
ぼくはとあるバーでアルバイトをしている。皿洗いをしたり、つまみを皿に盛り付けたりの仕事だ。酒は作らない。店の裏で淡々と皿を洗い、ときにはグラスや皿を持ってカウンターに顔を出す。最初の頃は会話する必要のない皿洗いばかりしていたが、今では常連客としばしば話せるようになった。最近はもうひとつ仕事が増えたのだが、これがまたとても楽しい。
ここは日本だが、ぼくは日本人ではない。この地において、ぼくは異邦人だ。だからぼくには帰る故郷がある。香港だ。ここへは留学でやって来ていて、母国でも日本について学んでいた。日本語はある程度わかるが、決して堪能とは言えない。よくいる留学生だ。
彼がやってきたのは、嵐の夜だった。春の終わり、梅雨時の雨。香港の春も雨が降る。雨期はとても憂鬱だけれど、それは夏の予感でもある。早く晴れてほしい。
だからぼくは、きっと彼が夏を連れてくるのだと思った。
彼の肌は一足先に夏を過ごしてきたような色をしていて、おまけに自分自身が太陽なのだと言わんばかりの金髪をしていた。暗雲立ち込める夜の入口に彼はあまりに不似合いで、ひどく輪郭のくっきりした青年に見えた。彼が日本人なのかどうか、自信がなかった。
開店直後だった。彼は黙ってカウンター席に座った。ぼくは洗ったグラスを棚に収めに来たところで、バーテン兼マスターの男はちょうど席を外していた。
「すこし待っていてください。もうすぐバーテンが来ます」
ぼくはそう言って、彼を改めてよく見た。息を呑んだ。彼の瞳の中には、間違いなく夏が詰まっていた。
「……日本語、お上手ですね」
「……ありがとうございます」
経験上、どこから来たのか問われると思った。しかし彼はそれ以上を話さず、だからぼくも沈黙した。何も出さないわけにいかなくて、ナッツを皿に乗せて出した。
「雨が酷いでしょう」
ぼくはそう言った。男の肩は湿っていて、その上雨粒を乗せていた。寒そうだった。
「タオルをお出ししましょうか」
「大丈夫です。ありがとう」
彼は笑った。人好きのする笑みだった。
「……止むかなあ」
彼はぽつりと言った。
ちいさく、雨の音が聞こえる。まだ暫く止みそうになかった。さっきまで太陽が恋しかったのに、きっとちいさな太陽が訪れてくれたから、今はもう、この雨に止んでほしくなかった。
「ぼくは酒を作れません。でも、演奏ができます。よかったら、聴いてくれませんか」
「へえ。是非、お願いします」
このバーにはちいさなステージがある。ステージといっても、床が一段高くなっているだけのブースだ。そこにはピアノと、ギターと、アコーディオンがある。ぼくは真っ赤なBUGARIを手に取り、右手で鍵盤を撫で、左手で百二十あるボタンを撫でた。
定番のリベルタンゴ。これがぼくの新しい仕事。マスターからは、できるならもっと早く言ってくれれば弾かせたのにと言われた。今では週に一度か二度、客の前で演奏を披露している。
雨音が溶けて、アコーディオンのハーモニーが空間を満たしていく。演奏の半ばでマスターが戻ってきたため、ぼくはその手を止めた。
「お待たせしてしまいましたね。すみません。ご注文は?」
「……演奏、最後まで聴きたかった」
そう言って男はナッツを摘んでいた指先の塩気をちろりと舐めて、笑った。そしてこれまでぼくの方を向いていた身体をカウンターに向け直して、「スコッチを」と頼んだ。ぼくは彼にチョコレートを出すべきだと思った。アコーディオンを元の場所に置いて、カウンターへと戻った。
スコッチを飲む彼の顔が、とてもきれいだったことを、よく覚えている。
スコッチをロックで二杯干した後、彼はおもむろに「ギターを弾いてもいいかな」と訊いた。こんな雨の日だから店内に他の客は居なくて、マスターは構わないと答えた。
その日、彼はイングリッシュマン・イン・ニュー・ヨークを弾いた。ハミングは雨音よりもちいさな声だった。ぼくは皿を洗えなかった。彼のかすかな歌声に耳をすませたかった。マスターはぼくを咎めなかった。
雨が降り続いていた。他の客が現れたところで、彼は腰を上げた。
「傘、お貸ししましょうか」
ぼくは彼に声を掛けた。彼は一度断った。ぼくが安物の蝙蝠傘であるから返さなくてもよいのだというと、彼は困ったように笑って受け取った。
「ありがとうございます」
彼はぼくの蝙蝠傘をさして、雨の中に消えた。ぼくは彼の残したグラスをきれいに洗って磨いた。

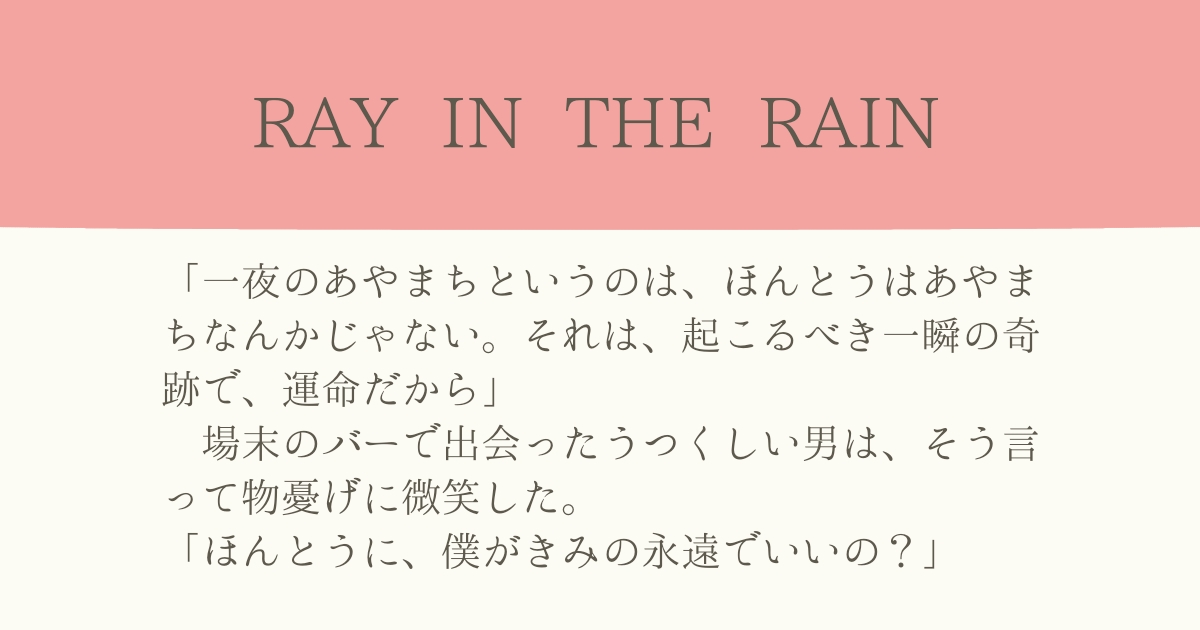
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます