それから、彼はしばしばこのバーに来るようになった。ぼくはギターをせがみ、彼はそれを許してくれる。
それは決まって雨の日だった。彼は毎回あの蝙蝠傘を持ってきたが、ぼくは受け取らなかった。梅雨はまだ終わらない。
彼は必ずスコッチを飲む。
ある日のことだ。その日も重たい空をしていた。マスターはぼくに言った。
「春が来たな」
春はもう終わる。そして夏が来る。よく意味がわからなかった。日本で暮らしていると、そういうことはしばしばある。
「どういう意味ですか?」
「最近楽しいだろう」
「はい」
「そういうことだ」
やはりよくわからなかった。けれどきっと、マスターは正しいことを言っているのだと思った。
案の定、彼は来てくれた。重たい蝙蝠傘をさして、こんな場末に来てくれる。
「きみは留学生?」
「はい。香港から」
彼が自分のことを尋ねてくれたことが、とても嬉しかった。
「日本はどう?」
「とてもいいところです。みんなやさしくしてくれます」
「それはよかった。あなたにとって日本がよいところであるなら、日本人として僕も嬉しい」
「あなたはどこから来たんですか?」
「……内緒」
彼はいつものスコッチを飲んで笑ってくれた。ひとさし指をくちびるに添えてまばたきをした。それはなぜか、銃身にくちづける様に似ていた。撃ち抜かれそうだった。
「傘、お返ししますよ」
「でも、今日も雨が降っているので、使ってください」
「じゃあ。梅雨が明けたら、返しに来ます」
「……どうして、雨のときしか来られないのですか?」
彼の言葉は、この梅雨が終わったら、もうここには来ないと言っているかのように聞こえた。
「雨が降ると外に出たくなるんだ。そして見えない星の光のかわりに、この店に惹かれて入る」
「情緒、というものですか」
「そういうことにしておこうかな」
グラスの中の丸氷は、その身を酒に浸していた。すこしずつ、スコッチが冷えて薄まってゆく。

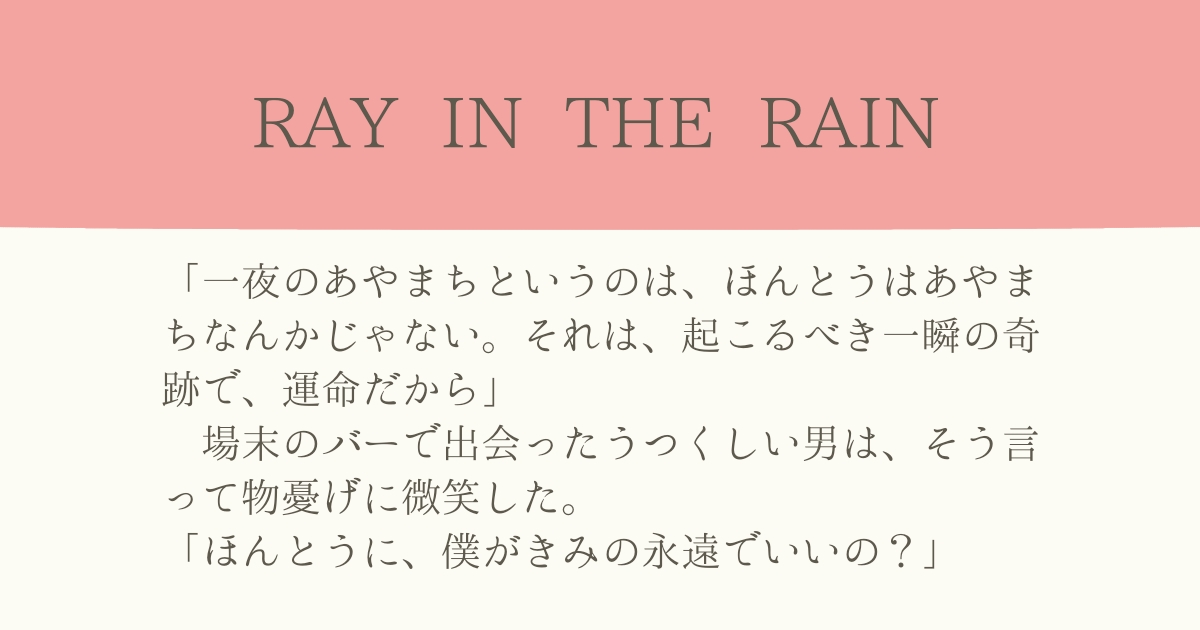
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます