ある澄んだ夜空の日、男がひとり来店した。闇夜に溶け込む黒ずくめの男は、怪物のようなみどりの瞳を持っていた。
男はカウンター席に座り、バーボンを頼んだ。それからは、ただただ酒精を舐めていた。
他の常連客が頼むので、ぼくは前掛けを外し厨房から出て、アコーディオンを抱えた。ぼくのレパートリーは多くない。すこし悩んでリベルタンゴを選び、奏で、脳裏にずっと彼がいたことに驚く。名も知らぬ彼の思い出は、いつの間にかぼくの中で永遠になっていたのだ。
厨房に戻ろうとしたとき、緑眼の男が静かに「ブラヴォ」と声を掛けてきた。
「サンクス」
「昔、こんな酒場で弾いたことがあった曲だ」
ぼくは意外に思った。男がぼくとのお喋りに興じようとするとは思っていなかった。彼の視線は未だに酒に向けられていて、ぼくを向いてはくれなかった。けれど彼は、ぼくと話したいようだった。
「あなたもアコーディオンを?」
「昔の話だ。酒場でアルバイトをしていたよ」
「へえ、あなたは格好いいから、人気だったでしょうね」
男がグラスを傾け、喉仏がかすかに動く。
「人探しをしていてね」
男はようやくこちらを見た。本題に入ったというところか、と思った。
「男を探しているんだ。褐色の肌で、金髪の」
ぼくはきっと、わかりやすい反応をしたのだろう。男はかすかに笑った。
「知りません」
ぼくは咄嗟に無様な嘘をついた。男は明らかにそれを見抜いていた。けれど彼はそれを追求することもなく、ただ「そうか、すまない」といって酒を飲んだ。バーボンはすべて彼に飲まれた。
梅雨が終わる予感があった。

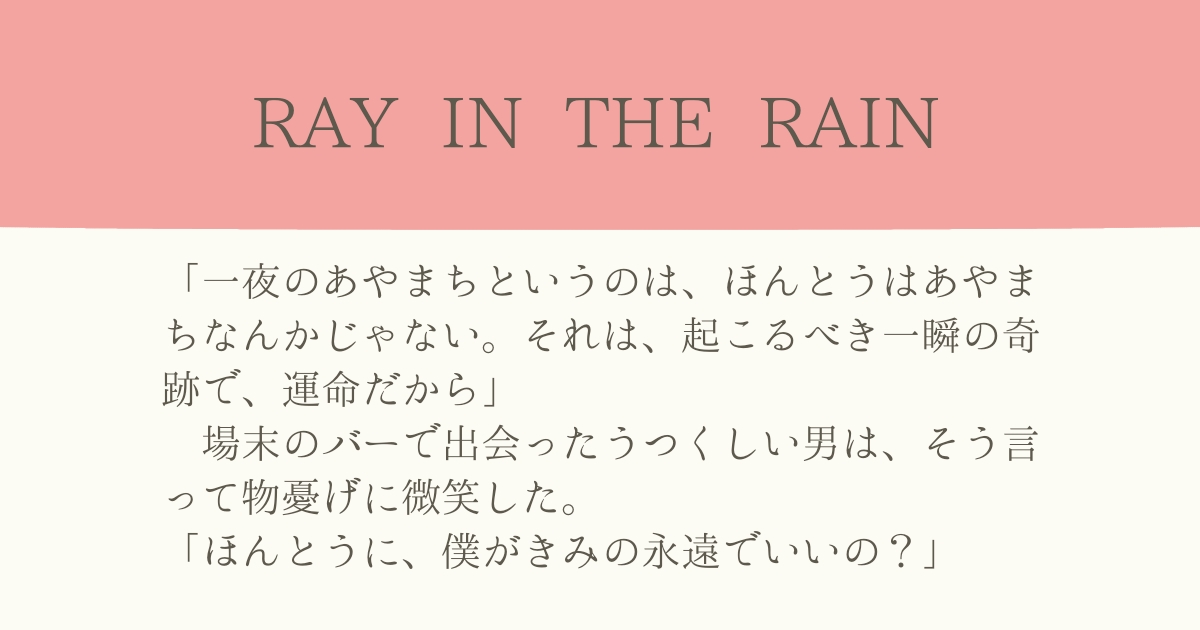
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます