断末魔のような雨だった。暦と天気予報によれば、梅雨はもうすぐ明ける。だからきっと、これが最後の雨なのだろう。
開店直後の酒場に、客はいなかった。
その日もやはり、彼は来た。今夜しかなかった。今夜を逃したら、この永遠は、やがて膿んで爛れてしまうかもしれないと思った。永遠は、ピリオドが打たれてこそ永遠なのだ。ピリオドのない永遠は、いつか腐る。
彼はお湯割りでスコッチを飲んでいた。確かに、この雨のせいかすこしばかり肌寒かった。スコッチのぬくもりに縋るように、彼の指先は何度もグラスを愛撫していて、それが無性に苦しかった。ぼくはスコッチになれない。
「一度でいいんです」
ぼくはそう切り出した。彼は見透かしたように微笑してみせた。マスターは沈黙していた。マスターの言っていた春の意味を、ぼくはもう完全に理解していた。
「あなたのキスが欲しい」
彼の笑みが深くなり、指先がスコッチから離れた。
「一夜のあやまちというのは、ほんとうはあやまちなんかじゃない。それは、起こるべき一瞬の奇跡で、運命だから」
それは多分、告解に似ていた。直感でわかった。彼は、永遠を腐らせてしまった人なのだ。彼は、やさしい、人なのだ。
「ほんとうに、僕がきみの永遠でいいの?」
彼は尋ねた。
「あなたがいい」
迷いはなかった。スツールを降りた彼は、ぼくの前を通り過ぎてステージに上がった。一歩高い場所から、声を掛けられて、ぼくもそこに登る。
「一緒に弾きませんか。なんでもいい。僕が合わせるから」
「……はい!」
ぼくはなんだかもう泣きそうだった。真っ赤なアコーディオンの蛇腹を開く。彼の震わせる弦の声は、ぼくの腹の奥にせつなく響いた。
ぼくは永遠なる刹那を手に入れたのだ。
すべてが終わって、彼は黙ってぼくを見た。ぼくもそうしていた。彼が目を閉じたので、ぼくは許されたのだと思った。
ぼくのくちびるが、彼のくちびるの温度を孕んだ。
店の扉が開いた。ぼくは彼に礼を言って、厨房に戻ろうとしたときだった。
「そのアコーディオンを、弾かせてはくれないか」
その声は多分、ぼくを引き留めるものではなかった。けれどぼくは立ち止まって、振り返った。彼の青い瞳は、声の主を見つめて、怒気にも似た何かを滲ませていた。だからぼくが許可を出した。ごめんなさい、マスター。
彼はきっと、店の外で待っていたのだと思った。煙草のにおいがした。
「どうぞ、弾いてください」
ぼくはもう、よかった。
* * *
赤井秀一の左手。
今まで、たくさんの命を奪い、救い、愛してきた左手が、百二十のボタンを押して、薮の中で喪われた命がかつて奏でていた音と、同じ音を鳴らしていた。
ピアノとベースの音色が、彼の両手から、生み出されている。
降谷は、自分の感情がわからなかった。わからないまま、ギターを弾いた。降谷は赤井のそういうところがきらいだった。この傲慢な男を、殺してしまいたい。けれど彼の左手には、いつまでも健やかであってほしいと思っていた。
彼がレフティでよかった。左手でベースの音を生んでくれてよかった。降谷はそう思った。
彼らには似合いの葬送歌だった。
* * *
ぼくの知らない曲だった。ぼくの知らない音だった。
カウンターの上には、ライとバーボンが並んでいた。彼がはじめてスコッチ以外の酒を頼んだことに、ぼくはあまり驚かなかった。そういうことなのだ、と思った。
「別に、きみと演奏がしたいとか、そういうことではないんだ」
「……ええ」
彼らの会話は途切れがちで、ひどくゆっくりだった。
「ただ、きみが他のアコーディオン弾きと演奏しているのは、……違和感が、あったんだ」
「自分勝手な人だ。僕の隣が空席じゃないと満足できないなんて。……そこに座ってはくれないくせに」
「座ってほしいのか?」
「御免だ。大体なんでここにいるんです? いつ以来ですかね」
「俺が帰国して以来だから、三年近く経っている」
「……俺のこと、探した?」
「追跡しようとはしなかった。けれど、常に視界に探していた」
「……さすがに経歴を洗わなくちゃならなくて。メンタルケアも言い渡されて潜ってました。……雨はいい。傘をさせるから、気が楽だ」
彼らはきっと、とても遠い世界を生きている。改めて、ぼくの永遠になってくれたことに、感謝を抱いた。
「近いうち、僕はまた戻ります。もしかしたら、またあなたと会うこともあるかもしれませんね」
「……そうだな。俺はきみと、またいつか、こうして酒を飲みたい」
「……そうですね」
茶番みたいだった。なぜかそう思った。けれどふたりとも、一生懸命だった。
流れるように、ふたりがキスをした。
ぼくは負けたのだと思った。そのキスはあまりにも相互に決定された運命だった。彼の許しがあってはじめて得られたぼくのキスとは違う。彼らははじめから、許しあっていて、当たり前のようにキスができていた。
「きみは俺の北極星だ。ただ遠くの変わらぬ場所で、輝き続けてくれればいいんだ」
「なら!」
緑の瞳の男は、こんなふうに、彼の激情を引き出せるのか。
「せめて一晩くらい、俺の隣人であれよ」
そうだ、と思った。見知らぬ男よ、きっとあなたは、彼の永遠になれるんだ。だから、頼むよ……。

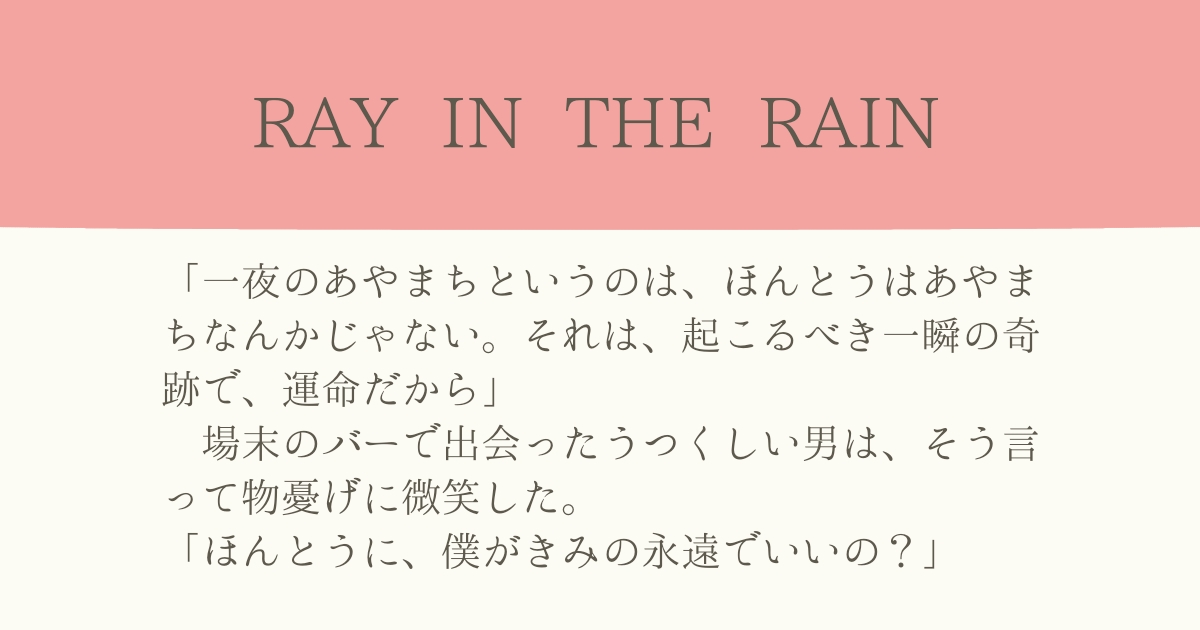
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます