赤安:海辺で沖矢昴と出会う少女の話です
砂、石、潮だまり、そしてテトラポット。わたしはこの海がすきだし、きらいだ。寄せては返す漣は、わたしを落ち着かせるし、ざわつかせる。
わたしには、海に対して抱くべき感情が、わからない。それでもわたしは学校からの下校途中に何度でもここを訪れ、夕陽が水平線に沈むのを見ている。
この海辺には、時折、ひとりの男がやってくる。彼はいつも小瓶を抱えていて、その中にはくるくると巻かれた紙が入っている。多分、手紙だ。届かない誰かに宛てた手紙。
彼はいつも眩しそうに目を細めていて、眼鏡をかけて、硝子越しの遠くを見つめている。夕陽の染みた赤っぽい茶髪を潮風に散らされながら、メッセージボトルを、決して放り投げたりはせず、大切そうに波に乗せる。
わたしは彼に話しかけてみようか悩んでいた。いつも、テトラポットのてっぺんに座って、ただ彼を見る。彼もきっとわたしに気づいているけれど、彼は一瞥すら寄越さない。
だから、あるとき彼に話しかけてみたことに、深い理由はなかった。あるとすれば、深まりつつある冬の気配がつめたくて、さびしくなったからだった。
「寒くないんですか」
彼がはじめてこちらを見た。予想に反してその目は尚開かれることはなく、わたしはすこし怖くなった。
「寒いのは、いやじゃないので」
柔らかい声だった。恐怖は一瞬で消えた。彼は多分、やさしい人だ。
「君こそ寒いんじゃないですか」
「寒いです。でも、ここにはつい、来ちゃうから」
彼はそれきり黙った。いつも通り、小瓶を海に流そうとした。
わたしはテトラポットを降りて、砂浜を歩いて彼の隣に立った。彼は海に向き直って、わたしは彼の横顔を見た。ローファーが砂にすこし沈んで、プリーツスカートがはためく。
「その瓶、お酒ですか」
「興味がありますか」
「……はい」
「気に入りの酒です。君にはまだ早い」
わたしは笑った。この海で笑ったのは久しぶりだった。
夕焼けがきれいだった。
「……どうしてそんなに、手紙を書くんですか」
「退屈なので」
わたしはちょっと返事に困った。年齢の掴めない人だけれど、それなりに若そうだし、そんな人が退屈って、一体どんな生活を送っているのだろう。
わたしにだって、小瓶に詰めて海に流すような手紙が、それをほんとうに読んでほしい人に届けられないものだということはわかる。だから、言葉に困った。
彼は波打ち際でしゃがんで、小瓶を波にさらわせた。小瓶は彼から離れるのを躊躇うようにゆらゆら揺れて、それでも最後にはすっかり見えなくなった。
そして、あんなに燃えていた太陽も沈んだ。真っ赤だった海が、一気に闇そのものになる。海はすべてを呑み込む。小瓶も、太陽も、わたしの姉も。
「二年前、ここで、姉が溺れて亡くなったんです」
なんでもない告白だった。
多分、わたしは友人が欲しかったのだ。クラスや部活が一緒とか、家が近いとか、趣味が同じとか、そういうのじゃない友人。自分の中のたいせつななにかを共有できる友人。そういうのに憧れたくなる、お年頃なのだ。きっと、お年頃のせい。
「奇遇ですね」
男の一言は、待ち望んでいたもののような気がした。
「僕の友人も、海に沈んでいるんですよ」
一瞬、風も波も鳴っているのに、時が止まったような気がした。
望んでいたはずの答えなのに、わたしはどこか後悔を覚えた。わたしが軽率だった。望んだものを得られた途端に、なぜだかそれが怖くなった。……それでも、彼しかいなかった。
「……この海が、ずっとすきだった。多分、今もすき。でも、きらいだし、怖い。それなのに、学校から帰る度にここを通るし、ここを通ると、浜辺に降りちゃう」
怖いはずなのに、彼のことが知りたかった。彼の見せてくれた感傷の一端を、掴んで離したくなかった。
どれだけその友人について尋ねても、答えてはくれない予感があった。だから自分の話をした。同じだけのことを、答えてくれる気がしたから。
「友人と呼べるかもわからないし、この手紙に宛名を書くことすらできない。けれど、この海が、あまりに呑み込んでくれるから、また出そうかと、思ってしまう」
呑み込んでくれる、と彼は言った。彼の友人を呑み込んだ海を、わたしの姉を呑み込んだ海を、どうしてそう言えるのか、よくわからない。
「君は、この海を憎んでいるんですか」
彼はわたしを見なかった。わたしばかりが彼の横顔を見ていた。彼の視線の先を見た。一番星が光っていた。
「……よく、わからない」
「水面の向こう側なんて、わかるものではありませんよ。海の怪物が悪戯をしたのかもしれないし、水底に光る宝石を見たのかもしれない。そんなものです」
彼の言いたいことは、なんとなくわかった。わたしには、海を愛することもできるし、海を憎むこともできる。その自由を大切にすればいいと、言ってくれているのだろう。
「複雑な感情を抱くことは、きっと疲れるでしょう」
「あなたも、疲れるんですか」
「……僕は、そうでもありませんよ」
うれしかったし、さびしかった。彼は自分の気持ちを決められるんだろうか。わたしよりも大人だから。
「あまり遅くならないうちに帰った方がいい。送っていってもいいが、見知らぬ男の車に乗ることもおすすめできませんからね」
そう言って彼は、踵を返して去っていった。彼の車は、ちょっとかわいい。すこし、乗ってみたかった。

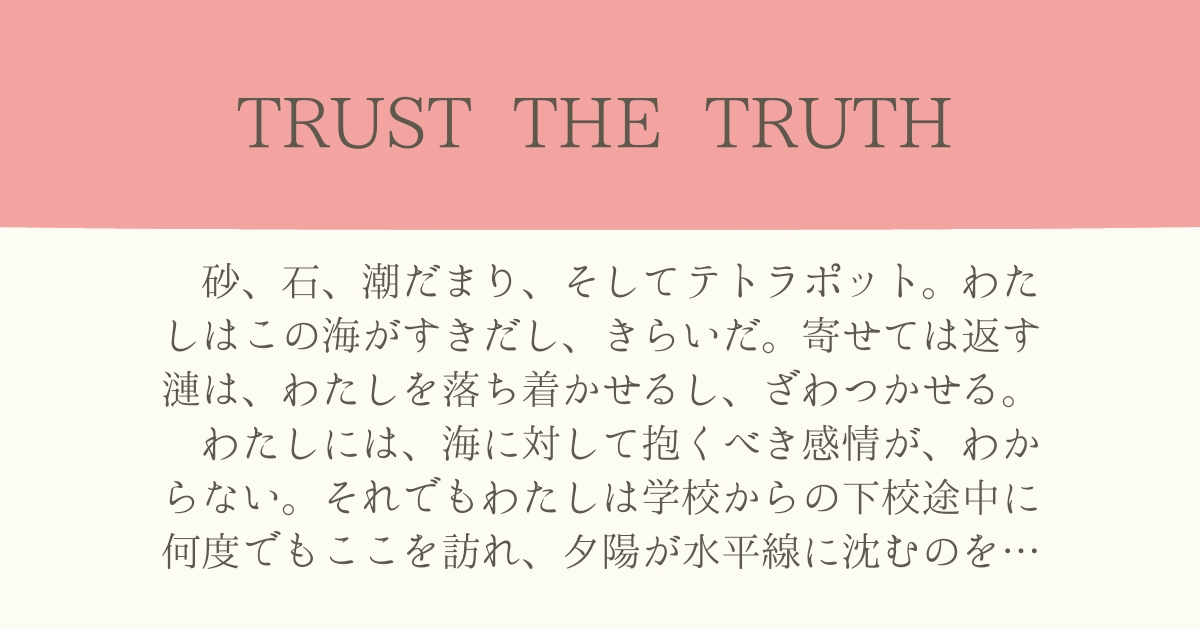
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます