それからも、今まで通り彼は来た。当然わたしも海に通った。けれどわたしは、もう彼に話しかけはしなかったし、彼もわたしを見なかった。きっと、あの日が特別だった。
彼は一度だけ、形の違う小瓶を流していた。その意味は、わたしにはわからない。けれどその日の彼は、いつもより長く海辺に佇んでいて、夕陽の中で、見えないなにかに引っ張られるように一歩を踏み出した。波で靴を濡らすところにまで行って、わたしは彼が入水しようとしているのではないかと思った。慌てて彼を呼び止めようとして、彼の名前を知らないことに気づいた。
「ねえ! おにいさん……行かないで!」
おねえちゃんみたいに、行ってしまわないで。今度は、絶対に死なせたくないの。
彼は足を止めてくれた。ズボンの裾が濡れていた。わたしはテトラポットから砂浜に飛び降りて、彼に駆け寄った。ローファーの中に砂が入って、足の裏が痛かった。膝に手をつき息を整え、顔を上げると、彼はこちらを見ていた。目が合う。
彼の瞳は、きれいな朝焼けのみどりいろをしていた。
「大丈夫ですよ」
「大丈夫に見えません」
「……怖がらせてしまったようだ。すみません」
海に呼ばれることは、ある。わたしはそれを振り切って家に帰る。彼にも、ちゃんと家に帰ってほしかった。恐ろしいのにどこか甘美な誘惑に、屈しないでほしかった。
「僕は死んだりしませんよ。……まだやることがある」
また、柔らかい声音だった。わたしを安心させようとしているのがわかった。わたしはなんだか泣きそうだった。
彼の手から、小瓶が滑り落ちた。そんなことははじめてだった。小瓶は夕陽と惹かれ合うように沖へ泳いだ。小瓶は流れ、夕陽は沈んだ。
「あの星、赤い」
水平線を見ていると吸い込まれそうだから、夜空を見上げた。
「今の時期だと牡牛座でしょうね」
「全然牡牛には見えないけど」
不規則に並ぶ星たちを、牡牛の形だと信じることは、自分にはできそうにない。たとえどんなにそれが牡牛なのだと教えられても、きっと無理。星は星だ。
「……それでも、そうだと信じれば、そう見えるのでしょうね」
彼の言葉は、おねがいみたいだった。
ちかちかまたたくかわいい星たちは、全然手が届きそうになくて、それがやさしかった。水平線は、流れてやがては届きそうだから、いけない。多分、だから人は、死んだら天に昇ると言われているのだろう。海に沈むなんて言われていたら、きっとみんな後を追ってしまうから。
彼がいつもの様に車で去って、わたしも帰ろうと思った。
けれど、そのとき、ひとつのメッセージボトルが流れ着いているのを、見つけてしまった。
彼が普段持っていた小瓶と、同じ形だった。いつかに流したものが、引っ掛かってしまったのだろう。剥がれかけたラベルでも、そこにある文字は読み取れた。
――メーカーズ・マーク。バーボン・ウイスキー。
絶対にそのままに、あるいは再び海に流すべきだ。そんなことはわかっていた。けれど、それでも、どうしても。
それが、彼への裏切りに値することは理解していた。それでも、わたしは、その小瓶を持ち帰った。

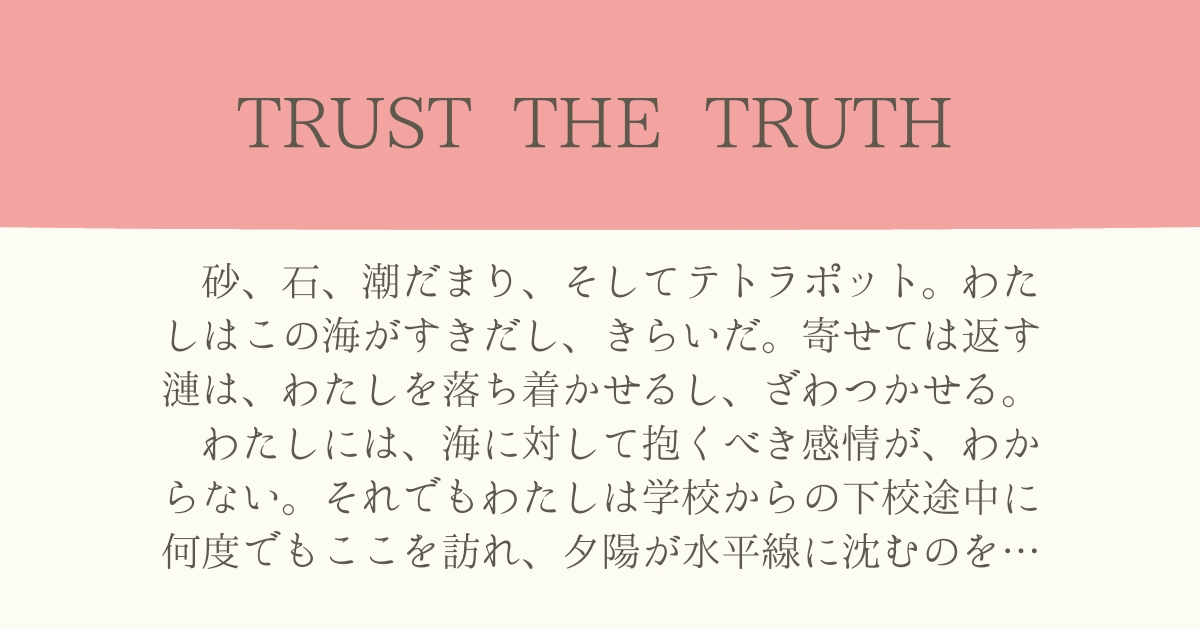
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます