赤安:セックスしながらよく喋る話です
・グロテスクな遺体の描写を含みます
すはだかの女がひとり、寝台に横たわっていた。そこに呼吸はなく、ただ沈黙と悪臭があった。開いた窓には風が吹き込み、カーテンがはためいて、女に降り注ぐ陽光に波を打たせた。サイドテーブルの目覚まし時計は見当はずれな時間を示して止まっていた。今、日本は何時だろう。
女の腹は開かれていて、そこからはいくつかの臓器が持ち去られていた。女は処女のままだったが、腹部の傷の奥からは精液が検出された。
同一犯のものと思われる、三件目の犯行だった。
アメリカ合衆国メリーランド州で発生したこの事件は、ひとりのスナイパーの弾丸で決着がついた。四人目の女はすんでのところで命を取り留めた。そのことに、赤井は六百ヤード彼方で安堵した。スコープ越しに見る女の薬指には、死を悟った男が最期に残した噛み跡があった。
* * *
すはだかの男がひとり、寝台に横たわっていた。そこに羞恥はなく、ただ信頼と諦観があった。闇夜の中の褐色の肌は時折揺れて、シーツと擦れて音を立てた。
男の上に、もうひとりの男が覆いかぶさる。彼は衣服を身に着けていたが、それもシャツ一枚だった。
明確な情事の気配があった。
布団が床に落とされた寝台の上で、赤井は降谷を組み敷き、兆しはじめた屹立にくちびるを寄せようとしていた。平素ならそれを受け容れる降谷が、咄嗟に両手で赤井の頭を掴んだ。降谷自身も戸惑っていた。二度のまばたきをして、彼はおずおずとその手を離した。赤井も無理はせず身を起こした。
「……すみません」
「いいや」
赤井はやさしい男だった。けれど降谷は怖かった。降谷は、自分の勘というものがそれなりに磨かれていることを自負していたし、その勘を信じる男だった。
「食べられるかと、思っ……て」
自分の口からこぼれた言葉に最も驚いたのは降谷だった。
赤井は降谷の手を取った。左手。その指先ひとつひとつにくちびるを当て、やがて薬指の先端で口を開いて舌を出した。
降谷の右手の指が一瞬震えた。彼に気取られぬよう、左手はそのままに。
ついに赤井はその薬指を口に含んだ。ぬめるあたたかい闇の中で、ただ薬指は舐められていた。
赤井の睫毛が頬に落とす影を見つめて、降谷の身体が弛緩する。降谷は、今マウントを取っているのは自分であると感じはじめた。奇妙な感覚だった。てのひらをひっくり返し、指の腹を上に向けた。赤井の口蓋を撫でると、ちいさく喘ぐ声が聞こえた。気分がよかった。やがて彼は離れた。
ふいに、肩に赤井の歯が立てられた。つめたい。こそばゆい。気持ちいい。それは降谷にとって既に快楽だった。何度も、何度も、咀嚼するように、噛む。しかしそれはどこまでもあまくやわらかいのだ。
やっと赤井の口が離れていったとき、降谷はなんだかもう挿入を果たされたような心地になっていた。
「噂の食人鬼を撃ったのって、あなたでしょ。女を殺して肉を食べてたっていう」
「……」
やさしい男だと、降谷は思った。こんなやわい歯型、明日の朝にも消えてしまうだろうに。
「ぼくのこと、食べたい?」
「違う」
あくまでも赤井は即答した。そうじゃない、そうじゃないのだ。すくなくともフィジカルな話ではない、はずだ。
ただ、自分のそれとひどく形の似ている欲望に、気づいてしまっただけ。今まで気づかなかった欲望が、輪郭を持ってしまっただけ。
「わかってる」
降谷はただただ受容する。赤井が実際にはそんなことをするはずがないと、よくわかっているから。彼は結局降谷を食べはしないだろう。ただすこし、今日のセックスがいつもと違うだけ。だから、せめてその欲望の存在だけでも、恥じることはないのだと、許す。
「あなたのために、おいしくなってやるよ。……来て」
降谷は今夜のフェラチオを諦めた。ほんとうはちょっとしゃぶりたい気分だったが、今夜は被捕食者の快楽を甘受するに努めることにした。それが降谷の愛だった。
再び降谷の脚の間に頭を沈める彼を見て、言い知れぬ感覚に酔った。信頼は恐怖を快楽に変える。
「……赤井。卵がそろそろ悪くなりそうだった、気がして。期限がすぎてて、加熱しないと、ッ、食べられない……明日の朝は、っなにか、ハァー、卵を……食べましょ、ア」
荒い呼吸と朝食の話題が混ざりあって降谷の口から出た。なぜそんなことを言っているのか、降谷自身もあまりわかっていなかった。ただ、ふいに頭に浮かんできたのだ。
――冷蔵庫の中の卵の数が、確か、ふたつあって……みっつだったかもしれない、そう、みっつ、みっつだったはず。……あれ、やっぱりふたつだったかな? 最後に使ったのは、月曜日の夜――……。
そんなことを考えているうちに、絶頂がすぐそこに来ているの感じた。赤井がきゅ、と口をすぼませて、降谷は抗うことなく達した。赤井は躊躇なく精液を飲んだ。
彼の舌が全身を這い、彼の歯が全身をあまく噛む。それでも鎖骨から上にはなんの痕も残さなかった。別に残したっていいのに、と降谷は思う。それでも赤井は、その首筋を舐めてはあまく食むだけなのだ。
「卵って、賞味期限が随分早くて、十個入りパックなんて、ン、せめて親子三人くらいの家族じゃなきゃ、とても買えない気がするでしょう」
愛撫をその身に受けながら降谷は饒舌だった。平素はここまでではないが、その夜だけはそうだった。彼の愛撫がしつこくて、なんだか黙っていたくなかった。
「でも、加熱調理さえすれば、一ヶ月くらいは平気なんだよな。知ってた?」
「……賞味期限なんて、さして気にしていなかった」
「あなたらしい。あっはは、は、ッア、ハ……」
赤井のくちびるが胸の尖りに辿り着けば、笑いは喘ぎにたやすく転ずる。かさついた男のくちびるが、赤子のまねごとをしているのに。
「でも、殻が割れてしまっ、……たら、もう駄目なんだ……赤井。殻が、割れたら……」
だめ。
降谷の手が赤井の顔に伸びた。頬を撫で、首筋をなぞり、シャツのボタンを外してゆく。茹で卵の殻を剥くように、丁寧に、中身を傷つけてしまわないように。おいしく食べるために。
赤井はその身を降谷から離し、されるがままになる。その表情はどこか憮然としていた。降谷はそれに気づきながらも構わなかった。せめて、これくらいは。
肩からシャツが落ち、寝台の下に放られる。剥かれた殻はもういらない。
「ハンプティ・ダンプティ……」
「マザーグース? 異邦人らしいことを言いますね。子供の頃に歌ったりした?」
「……さてね」
歌ったんだ、と降谷は思った。――王様の馬と家来の全部がかかっても、ハンプティを元に戻せなかった――少年期の彼はどんな声をしていただろう。彼は己のひとさし指で、赤井の喉仏を何度かさわった。赤井はくすぐったそうにしていた。獣を飼い慣らすようだった。
赤井の屹立が体内に埋まってゆくのを感じながら、降谷は事件の概要を思い出してみた。ソースは米国では知られた低俗なゴシップサイト。一体何割がほんとうのことだろう。
メリーランド州。三人の女性を殺した食人鬼。生前の職業は非常勤講師。薄給だったが亡き両親は資産家だった。恋人と思しき人物は浮かび上がっては来なかったが、彼の幾人かの友人たちはしばしば料理を振る舞われていたらしい。果たしてその料理には人肉が入っていたのだろうか。
はるか昔に観た『羊たちの沈黙』を思い返す。あれを観たのは、学生の頃、確か夏の夜だった。この世界のハンニバルは牢に入りはしなかったな……。
このあたりからもう駄目だった。侵入を果たした赤井のために、もうぐずぐずになってしまって、降谷はすこし泣いていた。赤井はずっと沈黙していて、それでも手馴れたセックスだった。
――明日は目玉焼きが食べたい。半熟で、黄身を割ると途端にどろどろになるような。ああでも、もしも殻が割れてしまっていたら、完熟にしたほうがいいかな――……。
赤井の手が降谷の耳を塞いだ。降谷はまっすぐに赤井を見た。まばたきすると涙がこぼれた。そうするとなぜだか声が我慢できずに喘いだ。自分の喘ぎが頭の中で反響して、それがまたどうしようもなく気持ちよくて、もしも赤井の声を聞き逃したらどうしようと思って、降谷は赤井のくちびるを観察した。熱く呼吸が漏れていた。
そういえば、コンドームを着けていなかったと、降谷は思い当たった。彼らにはめずらしいことだった。そしてそこから連想されたことがあった。被害者女性は処女のまま、しかし腹部の傷口の奥からは精液が検出――。
「中に出せ!」
降谷は強い口調で命令した。赤井ははっとして腰の動きを止めた。いや、寧ろ、降谷の脚によってがっちりと止めさせられていた。数拍ののち、我に返って降谷はゆるゆると脚をほどいた。ついでに先よりすこし開いて、赤井の動きを助けた。
「……赤井」
そこに滲んだのは謝意だった。寝台の上、セックスの最中で謝ることは避けたかった。だから名前を呼んだ。
「きみが、いいなら」
そういって赤井はふたたび動きはじめた。
降谷は自分の衝動を図りかねた。けれどあれは、たぶん、最後の一線だった。これはセックスであって、料理でも食事でもない。嘘かほんとうかも怪しいゴシップによもやこんな形で踊らされるとは。降谷は内心ひとりごちる。けれど、もしもあのゴシップが赤井の見たままの景色を語っているのであれば、彼には死体と自分を重ねてほしくなかった。彼が傷つくかもしれないから。
吐精の脈動を感じながら、降谷は確かに安堵していた。自分の腹部が濡れているのがわかったが、それは赤井が出したものではなく降谷のそれだった。赤井は誰も殺していないし、何も食べてはいない。すくなくとも、今この寝台の上では。
降谷はときどき、赤井とのセックスが不満だった。
稀に赤井は奉仕されること――愛されることを拒むような素振りを見せる。見返りもなく愛を捧げる男は実は、見返りの存在を恐れていた。己に罰を与えるように。己から愛される資格を剥奪するように。
だから降谷はそういうとき、赤井のわがまま――降谷はそれをわがままだと感じてしまう――に付き合ってなすがままになり、それでも遠慮がちに手を伸ばすのだ。受容だって愛なのに、愛されることを拒みながら彼の受容にあまえる赤井を、それでも降谷は、どうしようもなく愛していた。自分にだって、そういうふうに甘えたい日はあるから。
* * *
すはだかの男がひとり、寝台に横たわっていた。そこには安堵と不安の両方があった。男は朝食のにおいをかぎとった。昨夜のことを謝って、不思議の国のクッキーよろしくEAT MEとささやいてみようか。彼は悪趣味だと怒るだろうか。
男は食卓に並ぶ朝食を夢想し、寝台から降りた。

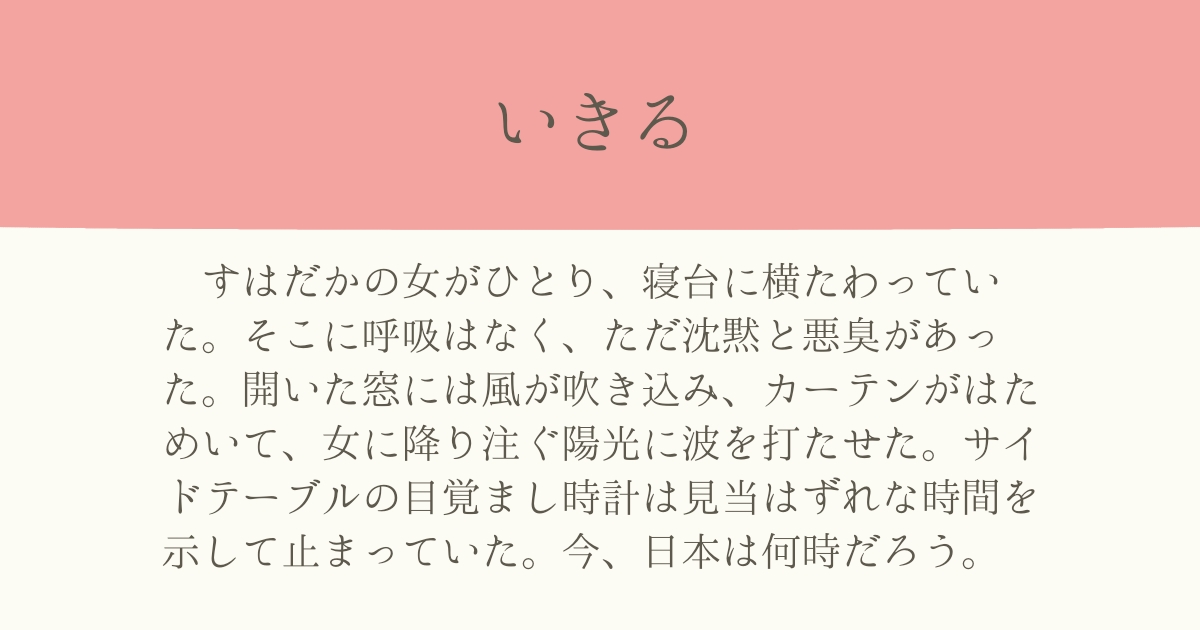
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます