赤安:焼き鳥屋で恋人になる話です
赤井秀一と会うのは、およそ二年振りのことだった。
安室透の携帯電話が久方振りに鳴ったが、表示されていたのは見知らぬ番号だった。なにがあるかわからないから、出ないわけにはいかない。ひと呼吸して電話に出ると、ひとこと「やあ」と声がした。その声だけで、誰なのかわかった。それでも切るわけにはいかなかった。なにがあるかわからないから。
「なんの用ですか」
用がないなら切るぞ、という意味だった。とはいえまさか、彼が用事もなしに電話を掛けてくるはずがないとも思っていた。
「……今、日本にいるんだが、よかったら会えないか」
それは果たして『用』なのだろうかと、すこし考えてしまった。
彼と最後に会ったのは警察庁の駐車場だった。空港までは見送らないが、最後のおつとめくらいは見送る。それが僕らの距離だった。
その日の夜空はきれいだった。なぜかそれはよく憶えていた。今でも、あの夜の澄んだ空気を肌に思い出せる。
なぜだろう。
「お元気で」
「君こそ」
庁舎を去る真紅のマスタングを見送って、そういえば彼はあの愛車をどうするのだろうと思った。そんなことも知らない仲だったのだ。僕と彼は。
そのはずなのに。どうしてだか、僕は彼と焼き鳥屋にいた。お互いカクテルには雑音が多すぎる人生を送ってきていたから、バーは避け、馴染みの店のひとつを予約した。赤井は結局ウイスキーを頼んでいた。ジャパニーズ・ウイスキーを飲む彼を見るのははじめてかもしれなかった。僕はもっぱら日本酒だった。
僕は結局、赤井のそれを『用』と看做した。酒を組み交わせる程度には彼は信用のおける男であったし、彼にとっては不本意だろうが、僕はあまり、彼の頼みを断れないのだった。
ただし、店はカウンター席のみのこじんまりとしたところにした。個室はない。機密性の高い会話をする気はないという意思表示であったし、彼も無難な会話しかしなかった。
「髪、また伸ばしたんですね」
彼の髪の毛は、彼とはじめて会ったときと変わらない長さになっていた。うつくしく艶やかなみどりの黒髪。焼き鳥屋に似合うものではなかった。
「験を担ごうと思ってな」
「へえ」
髪には生気が宿るとはよく言ったものだが、正直、すっかり短髪になった赤井秀一を見たときはぞっとした。そうして、あのうつくしくも疎ましかった長い髪が、彼を現世に留める重石のように見えていたことに気づいたのだ。だから、まるで、彼が現世にしがみつくことをまったく諦めてしまったような気がした。命の重さなんて、そんなことじゃあ変わらないのに。
「切るのはいつになるんです?」
砂肝を齧りながら尋ねると、彼はなぜか言い淀むように沈黙した。
「……僕は、今にして思えば、あなたの長髪が結構好きだったんで……悪くないと思いますよ」
砂肝を一本食べ終えるまで、静かだった。他の客の話し声は遠くにあった。程よい喧騒は却って静寂を招く。
「……いつ切るのかと訊いたな」
「ええ」
彼はひとくち酒を煽った。カウンターに戻されたウイスキーの水面が揺れて、僕はなんとなくそれ見ていた。
「君に愛を告げたときだ」
有り体に言えば、びっくりした。
ああそうか、彼は僕を愛していたんだ、でもそうだよな、だって彼にはいろんなことをしてきたし、それらは多分、愛していなきゃ許してくれないようなことなのだろうな。
そこまで考えて、ふと気づいた。彼は愛を告げたら髪を切ると言った。それは嫌だ。殺してやりたい男が髪を切ったときのあの苛立ちは、彼の髪を切る男は僕であるはずだという感情だった。けれど僕は彼に髪を切ってほしくない。それはつまり、彼の髪に誰もさわらせたくないということだ。
「なんて答えたら、あなたは髪を切らないままでいてくれますか」
「……その質問に対して、俺はいくらでも卑怯な解答ができるぞ」
「たとえば?」
「君が恋人になってくれたら、とか」
「意外。セックスしてくれたら、とか、言うかと思いました」
彼はすこし怒ったような顔をしていた。かわいい、と。それを見てかわいいと、思ってしまった。それで、覚悟を決めた。
「赤井」
僕は彼の皿からレバーを一本取った。彼の目を見て、口を開く。すこしはしたない迎え舌をする。最初の肉のひとかけら。咀嚼。嚥下。
ふたつめの肉。串の先端に気をつけて、くちびるをすぼめるように開いて、手にした串はそのままに顔の方を動かして、白い歯で肉を咥えて引き抜いて、食べる。
みっつめ。もう真正面から串を口に入れるのは危険だ。横から肉を咥える。目をつむり、肉を串から引き抜く。
「……零くん」
うそ、と思った。彼からその名を呼ばれるのははじめてだった。けれど彼もまた、うそだろ、と思っているに違いないのだ。挑発の成功。瞼をあげると、彼は見たことのない顔をしていて、絶対に今夜はこの男に抱かれるまで帰らないぞと思った。
「赤井。恋人になりましょう」
「……魔性だな。君は」
「いいでしょ。だって多分、僕もあなたのこと愛してる」
「君は……」
彼の言いたいことがわかった。
「こんなことするの、あなただけですよ」
彼の望む返事をする。だってもう、僕は彼をかわいいと思ってしまったから。
身体を彼に寄せ、耳元にささやく。
「あなたに抱かれながら、あなたのその髪の毛をひっぱってみたい」
僕は、串に残ったふたつのレバーを、箸を使って一気に皿に出してしまった。コツは串を回すことだ。

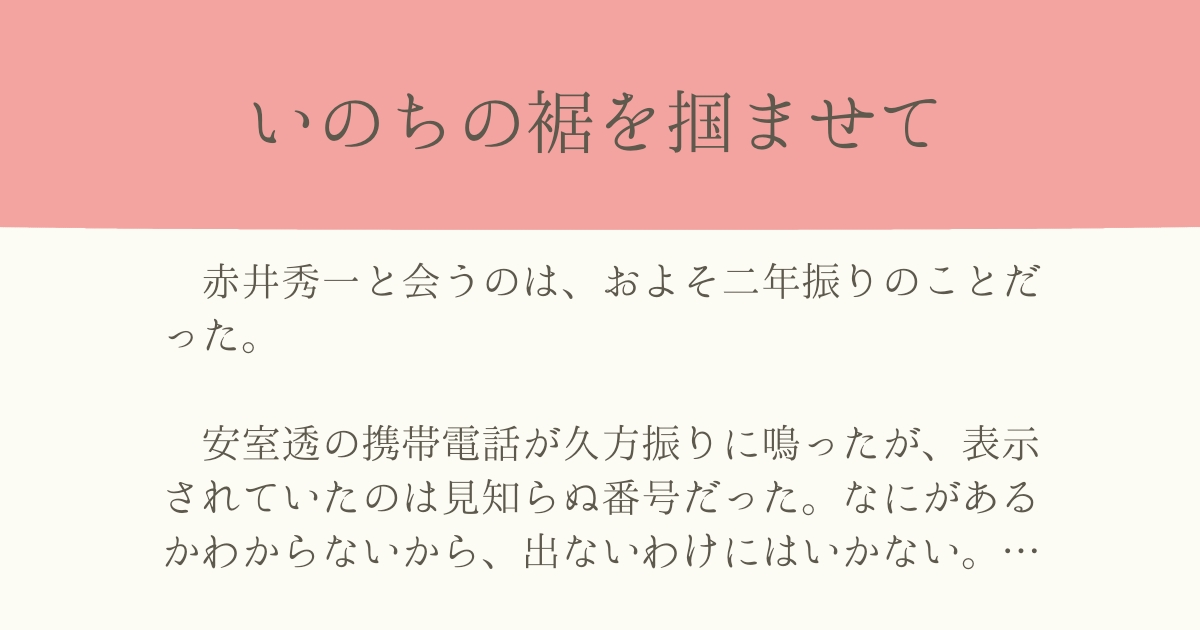
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます