赤安:降谷零の人生を見つめる赤井秀一の話です
・モブ×バーボンの肉体関係を示唆する描写を含みます
バーボンが人を殺す様子を、五七〇ヤード先から眺めたことがある。
「これは本来不要な取引です。上からの命令にもありません。この取引は、すべからく僕の慈悲によって行われています」
時刻は深夜一時を回って、そこは寂れた港湾だった。しばらくすれば、ひとつの男の死体が海に沈んでいることだろう。曇天。星や月は視野になく、空の果てが近くにあった。
その男は、自らの死が迫っていることをまだ知らないはずだった。彼はただ、次の仕事はバーボンと共に行うものであるということだけを聞かされていた。
バーボンはハンバーガーを齧っていた。こんな夜更けにそんなものを食べてよくも胃がもたれないものだ。一口齧ってはくちびるを舐め、三口に一度くらいは右手の親指でくちびるの端を拭っている。そういえば、彼は俺とはじめて出会ったときも何かを食べていた。確かそれは肉まんの形をしていたが、今思えば中身がなんなのかはわからない。あんまんだの中華まんだの、冬場の日本のコンビニにはそういう食品がやたらと豊富だ。
俺はスコープとインカムを通して男の様子を伺っていた。顔からも声からも、心理的に動揺がある様子は一切感じられなかった。
男の顔立ちからは、ラテン系の血が混ざっているのだろうと推測できた。黒髪黒目ではあるが、日本においては浮いている。ぱっちりとした二重がまばたきをした。睫毛が多く、再び覗いた瞳は濡れていた。
「へえ。それはどういうことだ?」
男は減らず口を叩いた。バーボンの顔は変わらなかった。彼は咀嚼の最中で、返答までに男を待たせた。
バーボンの右手が動いた。左手にハンバーガーを持ったまま、懐に差し入れられた右手は一丁の拳銃を握って出てきた。そしてそれは躊躇なく男に向けられる。嚥下。
「あなたにはNOCの疑いがかけられている。そして僕はあなたを始末するよう命じられている。……僕はあなたにこの事実を知らせずに殺したってよかった。ですが、ひとつだけ質問させてください。その質問の答えによっては、あなたの願いをひとつ叶えたい」
男の表情は動かなかった。
バーボンには尋問も命じられていたはずだった。男の属する組織を聞き出せと、ジンは確かに言っていた。にも関わらず、彼はそれを己の慈悲だと言った。ハンバーガーを食べながら。随分とぞんざいな神だ。右手には銃があるから、もう口元を拭うことができないのだろう。より大胆に舌を出して口元を濡らした。それは悪魔の舌なめずりそのものだった。
「De onde você é?」
バーボンが唐突に口にした言葉が何語なのかはわからなかった。しかし、それが男の故郷の言葉であることだけは明白だった。男の顔は、それを雄弁に物語ってしまっている。自分がこの組織で生き抜くために、同胞殺しに手を染めていることをまざまざと感じた。
「……悪魔め」
「僕はあなたを今から殺す。それはどうしようもないことだ。けれどあなたのお仲間のことをあなたの口から教えてください。何かひとつ、なんでも聞くから」
「どうしてそんなことをするんだ? おまえになんの得もない」
その通りだった。バーボンの取った手段が俺には甚だ謎だった。彼はなぜ懇願のような形で尋問を行っているのだろう。
風の凪いだ夜だった。水面はどこまでも穏やかで、なにもかもが静止した――死んだ世界のようだった。……そう思った途端、遠くで船の汽笛が鳴った。再び世界が動きはじめる。
「ベアトリス・メンデスのことは、パパにきちんと報告できましたか?」
「おまえに何がわかる! この悪魔!」
男をわかりやすく激昂させたそれは、覚えのある名前だった。半年前、組織によって殺された女。彼女もまたNOCであった。この半刻ほどのあいだに、俺はまたバーボンを恐ろしく思った。彼女は確かポルトガル人のスパイだった。ならば彼の先程の言葉はおそらくポルトガル語なのだろう。いったい何を囁いたのか。
「あなたの最後の伝言くらい、届けてあげてもいいと言っているんですよ。僕はその程度には、あなたのことを好ましく思っているんです」
思わず息を呑んだ。バーボンは一体何者だというのか。伝言くらいと彼は言うが、世界のどこに行ったって犯罪者である俺たちがそれをするリスクを、決して知らないわけではあるまい。彼の能力をもってすれば取るに足らないことだというのも頷けるが、そんな無用なリスクを負うのは彼らしくないだろう。いや、何がほんとうに「彼らしい」のかなんて、俺はひとつも知りはしない。
……と、ここまで考えて、ようやくバーボンの言葉が嘘である可能性に思い至った。自分はバーボンを信じすぎている。これは最近しばしば感じることだった。それが果たして己の理性なのか願望なのか、適切に判断が下せなかった。しかしどう足掻いても、あるいは彼もNOCであったなら――と夢想する瞬間が気紛れのように訪れるのであった。
「おまえは……いったいなんなんだ……」
男の問いは至極真っ当だった。まったくその通りだ。バーボンという男は、わからない。これが彼の尋問のスタイルなのだろうか。それにしてはあまりにリスクばかりが大きい。平素の彼の情報収集は極めて緻密で繊細だ。なのにどうして、不意にとびきり愚かなギャンブラーのような姿を見せるのか。
「あなたが僕を悪魔というなら僕は悪魔だ。ですが、僕を天使や神にするのはあなた次第だ。……さあ、選んで」
バーボンは突然男の方へ歩みはじめた。そうして男の耳元へくちびるを寄せると、何事かを囁いた。男の顔は見えず、ただバーボンの顔だけが見えた。五七〇ヤード越しの彼は、限りなく無表情で、それなのになんだか泣き出しそうに見えた。男もまたバーボンに何かを囁き返した。バーボンはくるりと身体を翻し、男を突き飛ばすとすぐさま照準を定めた。男の身体が海に落ちようというそのとき、サイレンサーの取り付けられたバーボンの拳銃が撃鉄を起こし、男の心臓は砕けた。男の身体は海に浮かんだ。コンクリートには血の一滴も残さずに。
ここでは何も起こらなかった。そういうことになるだろう。
「詳しいことは合流してから。出番がなくて残念でしたね」
彼はインカムに囁いた。無用な殺人がしたいわけではないためむしろそれは幸運だったが――彼の手を汚させたことにはどこか苦い気持ちがあるが、仕事を奪ったところで彼は喜ぶまい――特に訂正することもなく、俺はしばらく警戒を続けた。バーボンが立ち去るところを見届けてから、ようやく身体を起こし、合流地点に向かった。いつもの酒場へ。
「やあ、どうも。お先にやってますよ」
いつもの酒場は、薄明るい照明のこぢんまりとした店だった。カウンターのほかにはテーブル席がふたつだけ。時折、あまり上手ではないピアニストが楽しそうにジャズを弾いていて、俺はそれが好きだった。
その酒場の扉を開けたとき、バーボンは既に杯を傾けていた。酒杯の中の酒の種類はわからなかった。バーボンはいつも適当なカクテルを頼む。そしてそれが何によって作られた何という名前の酒なのか、最後まで知ろうとしない。味で検討は付いているのだろうが、知らないことに価値があるのだといつかの彼は語っていた。彼はそういうところに妙な潔さがあった。さっぱりとこだわりがなく、あんな組織にいながら、適当に酒を飲める男だった。俺はしばしばそれを羨ましく思った。特に、亡霊に付き纏われる夜には。
カウンター席のいちばん奥に腰掛ける彼の隣に、俺もまた座る。マスターにスコッチを頼み、煙草に火をつけた。マスターがグラスと灰皿を目の前に置いた。
「彼の名前はファブリシオ・セナ。SIEDMからのスパイです」
最初のひとくち。紫煙で肺を満たして、細胞を黒く染め上げる。脳が目覚め、世界の解像度が上がる。彼の横顔がよく見える。
「……あのポルトガル語はなんだ?」
バーボンは酒杯を口から離し、カウンターの上に置いた。ゆっくりとまばたきをして、横目にこちらの方を見た。震える睫毛が先程の男を思い出させた。
「Where are you from? ……ですよ」
それを男の母語で聞いたというのか、彼は。……なんという悪趣味だろう。おぞましい男だ。そもそも彼はベアトリス・メンデスと男の繋がりを見抜いていた。彼に何を聞かずとも組織の要求はクリアしていたはずだった。おそらくは確認作業だったのだろう。確認できなくてもそれはさしたる問題ではない。
あのときバーボンが男の耳元で囁いたのは、もしかするとなにか、とてつもなくやさしい言葉だったのではないか。ふとそんな気がした。けれどもそれと同じぐらい、悪魔のような言葉を囁いたようにも思えた。
男は彼を悪魔と呼んだが、あながち間違いでもないだろう。恐ろしい男だ。決して敵に回したくない。敵に回したが最後、きっと自分のすべてが、自分の知らぬ間に暴かれてしまうのだから。
――He is a devil.

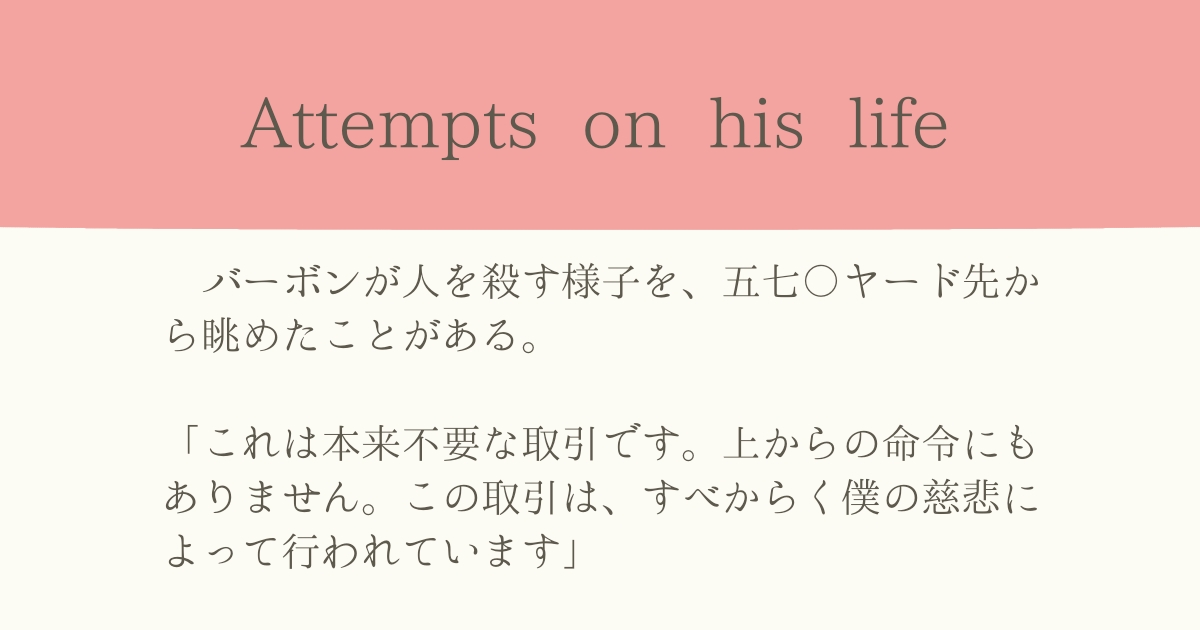
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます