あの夜の彼は……彼と俺は、なんだったのだろう。
「僕を抱いてみませんか」
ツーマンセルの任務のホテル、彼はある晩そう言った。俺の部屋の前だった。シングルを二部屋、それぞれ別の階に取っていた。二十三時を幾らか回った頃だった。
「……なぜだ?」
結局それだけを口にした。
中華料理屋への潜入を恙なく終えてから数日、新たな任務でバーボンと共に組まされていた。中華料理屋の件の顛末は結局聞いていない。推理は推理のまま、仮説は仮説のままだった。
「僕が香港のAVを観ていたあのとき、あなた、すごい顔をしていたので」
「ホォ――……すごい顔、ね」
わからなかった。あのときの彼の顔ははっきりと覚えているのに、自分の顔がなんらかの表情を出していたことにすら気づいていなかった。
思索の海から帰還すると、目の前のバーボンは愉快そうに笑っていた。完璧な微笑。計算高く作り上げられた繊細。
「飼い犬に手を噛まれた、って顔でしたよ」
そう言われた瞬間、自分で認識できていない自己まで彼に見抜かれていることがわかって、鳩尾のあたりがカッと燃えた気がした。自分を律することはそれなりに上手だったはずだ。それなのに、彼にこんなに乱される。
彼は一体何者なのだろう。
「僕はあなたの飼い犬じゃありませんけど」
俺はこんなにも苦しいのに、どうして彼は楽しそうなのだろう。そんなどうしようもないことを考えていると、くちびるの端にくちづけられた。
「くちびるは? 許してくれる?」
許すよ、と思った。なにもかも、すべて許すよ。人のこころを弄ぶ、この悪魔のような男を。しかしはっきりそう言うことはできなかった。かわりに自分からキスをして、彼を部屋に引き込んだ。オートロックの鍵が閉まった。
彼の髪に顔を埋めて、このホテルのシャンプーのにおいを嗅いだ。それだけですべてわかった。彼はなにもかもを終えてここにいるのだ。一旦彼から身を離し、部屋の椅子に掛けていた上着のポケットからコンドームを取り出した。
「あっは、いい男……」
その声はもう、ベッドの上から聞こえた。
彼の服を脱がすと、そこにはまだ新しい鬱血痕が散らばっていた。予想できたことだったが、手酷い裏切りを受けたような気持ちになった。なら、自分が新たにキスマークをつけるか? ……それをしたくはなかった。そんな独占欲を剥き出しにするようなことをして、また彼に愉快な思いをさせるのは御免だった。つまらない見栄だと自覚していたが、それでも大事なことだった。そうして鎖骨に軽くキスをするだけにして顔を上げると、射抜かれたような気持ちになった。
彼は、主人に捨てられた仔犬のような顔で俺を見ていた。
途端、この悪戯な仔犬に絶対に褒美を与えてなるものかと思った。今度は俺の方が楽しくなってきた。マウントが完全に逆転したのだ。
彼のくちびるにキスをして、そのまま舌を差し込んだ。歯列をなぞり、口蓋を舐め、舌をつつき、誘い、絡め、持ちうる技術のすべてを懸けて彼の快楽を呼び覚ましたかった。キスの始終、彼は受け身で俺のなすがままだった。それが堪らなく心地よかった。
息も絶え絶えに彼が脱いでと希うので、俺の方も服を脱いだ。そっと彼の屹立にふれ、そのままぱくりと咥えてみた。
「なんでっ、なんでおまえがそんなことするんだよ……っ」
頭上から焦ったような声が聞こえて、それでもそれを無視していた。構わず好きにしゃぶっていると、うーっ、と唸り声が聞こえて、視線だけ動かして彼を見るとほんとうに泣き出しそうな顔をしていた。やめるべきか、とも一瞬は思ったが、結局、やめなくていいか、と思った。このくらいはいいだろう。止めようと彼が本気で思っているのなら俺の頭を引っ掴んでいるはずだ。彼の手は口のあたりをさまようこととシーツをぎゅっと掴むことに忙しく、俺の方に伸ばされる気配はない。
「ローション……渇く前に、もう、挿れろよ……」
「なんだ、薄めてないのか?」
「……ッ早く突っ込んだらいいだろって言ってるんだよ!」
有り体に言ってぞくぞくした。彼は自分の部屋で抱かれるための準備をしてここまで来たらしい。彼のペニスから口を離してその奥の土留色に左手を伸ばすと、そこはしとどに濡れていた。きちんと薄められたローションは当分乾く様子もない。そのままそこに中指を入れ、抵抗なく受け容れられたことを確認して薬指も入れた。暫く指を遊ばせて前立腺を探す。俺の意図を察したらしい彼が何事かを口にしようとしたが、その口からこぼれたのは掠れた喘ぎ声だった。探り当てたそこを撫でながら、俺は再び彼のペニスを咥え込んだ。
「あ、うそ、やだ……アッ、なに、なんでっ……ァ、あ――……」
子供のようにぐずりながら達した彼がかわいくて、彼の白濁をそのまま飲んだ。今この瞬間突っ込んでやろうかとも思ったが、彼を眺めているとなぜかそんな気は起こらなかった。なんとなく満足していた。
果たしてこれは性欲なのだろうか、と疑問を持った。彼のそれも、俺のそれも。ここにいるのはペニスを勃起させた男がふたりだ。だが、今ここにある欲望を正確に認識できてはいないのだろうと感じた。彼も、俺も。
「挿れても?」
「……どうぞ」
彼は健気に呼吸していて、それがどこまでもいとおしかった。どうして彼はこんなにかわいいのだろう。どうして。
彼の膝を抱えて、スキンを被せた己の欲望を彼の孤独にあてがった。慎重に押し進めれば、そこはまったく俺を拒まなかった。奥へ奥へと招かれて、なぜだかどうしようもなく憤りを感じた。一方で快楽が湧き上がり、混沌。彼はというと、声を抑えることもなく、母音を上げて震えていた。
「あ、……ッアぁ……イ、っ……ライ……」
もうどこまでもひたすらに、彼を高みに昇らせたかった。これまで届いたことのないところまで。彼にこの夜を後悔させたかった。彼の中で永遠になりたかった。
彼の瞳が闇の中で光っていた。それは月に似ていた。まばたきの度に欠けては満ちる白銀の月。時の流れが濃密で、ほんの一夜のセックスが永遠に似て長かった。まぶたが上下するのに合わせて涙がこぼれてきよらかだった。
彼と目が合った。彼はじっとやすらかな表情でいたかと思えば、はっとして怯えるようにくちびるを震わせた。彼はだらりと垂れた俺の髪を一房手にして、そのまま口元まで持っていった。固くまぶたを閉じてしまって、祈るように呟いた。
「ぼくを……ゆるさないで……」
殴られたような衝撃だった。
彼はきっと熱に浮かされたピークだったのだろう。それを告白した数拍後に浅く喘ぎながら吐精した。俺はというと腰の動きを一瞬止めて、それでも次の瞬間には律動を再開した。過ぎた快楽に溺れる彼を宥めるように右手で撫でて、追い掛けるように精を放った。
――俺も、そうだよ、バーボン。俺も、許されたくなんかない。それでも君を許したいんだ。この我侭を、傲慢を、君は、君に……。……。
彼が、俺の運命であったらよかったのに。
――He is a blink.

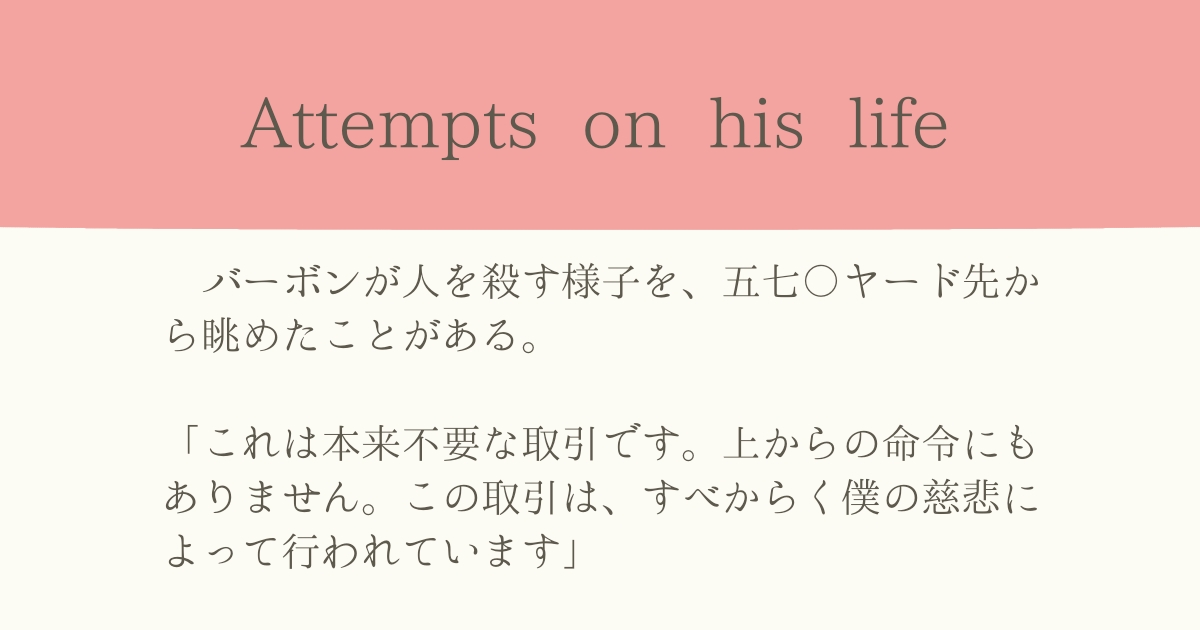
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます