俺が沖矢昴として身を潜めていた頃、彼は盲目の青年だった。
ブラインドレストラン、というものがある。その名の通り、まったくの暗闇の中で料理を食べるというものだ。スイスのチューリッヒを発祥とするこのレストランは、今では全国各地に見られる。そしてその一部の店では、ウエイターとして視覚障害者が働いている。
東都にできたブラインドレストランにバーボンが潜入しているらしかった。そこもまた視覚障害者を雇う店であり、そうなると彼は盲目を装っていることになる。……有り体に言って気になったのだ。
すこしその店を探ってみたが、組織が目をつけるようなものは見つけられなかった。
ふと、客として行ってみたいと思った。盲目の彼を真正面から見てみたいと。彼は沖矢昴の正体に解答を用意しているようだったが、組織のバーボンとして潜入しているときに赤井秀一に関する行動を起こすことはないだろう。
完全予約制のレストランを予約しようとして、その名前に困った。その名は彼の知るところとなるだろう。赤井秀一は以ての外だが、果たして沖矢昴の名で予約したとき、彼はどう出るか。勤務シフトを入れるのか、外すのか。暫し迷った末に小室泰六の名で予約した。明治時代に輸入されたシャーロック・ホームズの和名。彼なら偽名だとすぐに気づくだろうが、赤井秀一だと断定する程のものではない。その上で、なにかあると踏んで敢えてシフトを入れるのではないか。そういう期待をした。この期待が裏切られてもよかった。
棚からバーボンを取り出し飲んだ。フォアローゼスのロック。今となっては数すくない、雑念なく愛せる酒。
金曜日の夜。空は無限に澄んでいて、星のまばゆい夜だった。しかし月は見当たらず、どうやら新月らしかった。
レストランはこじんまりとした外観で、白い外壁が夜には眩しかった。中に入ればそこは待合室らしく、五人の先客がいた。橙色のランプの装飾が凝っていた。壁際の長椅子に座ると、ちょうどウエイターがやってきて、女性の名前を口にした。そのウエイターは降谷零その人ではなかったが、やはり彼も盲目らしかった。彼は手を差し出し、お手をどうぞ、と言った。女性はそれに手を重ね、男と共に扉の向こうへ言った。
ウエイターは、見覚えのある男だった。組織に殺されたはずの男。なるほど、彼の目的はこの男らしい。きっとなにか彼の持つ情報を知りたいのだろう。目的のひとつはそうそうに達成されてしまった。
メニューを渡され、食事の内容を決めるよう言われた。いちばんの人気はおまかせコースだそうなのでそれにする。アレルギーや苦手なものの確認をされたが特にないと答えた。メニューの内容は、ごく一般的な洋食屋、といった風情だった。
それから十分程経った頃、小室泰六さま、と声が掛かった。その声の主は間違いなく彼――降谷零であった。彼はまぶたを閉じていて、更にサングラスを掛けていた。
俺は無言で彼の傍に行った。気配でわかったのだろう、お手をどうぞと彼は言って、俺はその左手を取った。彼があくまでも全盲を装っているだけであり、俺の姿が沖矢昴のものである以上、下手に第三者の――小室泰六の声を用いるわけにはいかなかった。それに、寧ろ視界を遮断しているがゆえに、彼が一度俺を沖矢昴と認識すれば、全身で赤井秀一との共通点を探すことができてしまうことだろう。なにもかもが手探りだった。
扉の向こうへ行くと、そこは既に暗闇だった。念のため片目を瞑ってから入ってみたが、成程まったく役に立たない。完全な闇だった。彼の手だけが頼りだった。全身で様子を伺う。ああ、彼に、赤井秀一の声で、俺自身の声で、話し掛けてみたい。けれども何を話すというのか。逡巡して、それでも変声機に伸ばした手を、結局は元に戻した。
彼のてのひらのぬくもりを静かに味わう。それだけしか、許されていなかった。
もう一枚の扉を越えると、そこもまた闇だった。しかし先程よりも空間が広く、人の気配があった。おそらくテーブルが四つ、そしてそれぞれに人間がふたり、三人、ふたり、ひとり、計八人。確証が持てるとは言えないがおそらくは間違いない。すべてのテーブルが埋まっているということは相席なのだろう。彼の手に導かれるままに進み、立ち止まる。彼が椅子を引く音がする。
「どうぞ。……ふふ、なんだか随分と慣れていらっしゃるようだ」
ふ、と息だけを漏らした。それが限界だった。
彼がふと俺の左手に触れ、それを卓上のなにかまで導いた。冷たく硬い。水の入ったグラスだった。
「お水の位置はここです。……ナフキンをお付けいたしますね」
そういった彼は、紙ナフキンらしきものを俺の首回りに付けた。随分大きいようだった。暗闇なのでこぼしてしまう客も多いのだろう。うなじでナフキンが結ばれる間、このまま彼は俺を締め殺せるな、と思った。
「それでは、暫くお待ちください」
彼は俺の左手――赤井秀一の利き手――にグラスをさわらせた。彼は多分、気づいているのだ。
暗闇での食事は面白い体験だった。目の前にいくつか皿が並べられ、箸とナイフ、フォーク、スプーンが示される。皿が何時の方向にあるのか示され、手探りでの食事がはじまる。メインはハンバーグだった。サラダの中にはアボガドと玉葱が入っていたような気がしたが、ほかの食材はよくわからなかった。元々、毒性のあるものならある程度はわかるが、食材の判別などにはとことん疎かった。
盲者の振りをする、などということを視覚障害のない人間がやることはとんでもないことだ、と改めて思った。彼の「変身」は常軌を逸している。トリプルフェイスだけでも常人にはできないことなのに、それ以上にありえないことを微笑と共にやってのけるのだ。
食事を終えると、再び彼がやってきて、俺を出口まで導いてくれた。扉の向こうへ。依然まだ暗い。話し掛けるなら今しかない。彼の左手の感触だけで、まさか帰れるわけもあるまいと思いはじめていた。
「……いつから盲目になった」
悩んだ挙句、結局は俺自身の声で、たったそれだけを話し掛けた。彼に盗聴器が付けられている可能性を考慮すれば避けるべきなのは明白だったが、我慢ならずにひそやかに囁いてしまったのだ。
暗闇の中で、彼はどうしているのだろう。どんな顔をしているのだろう。
隣で動く気配があった。繋がれていた手が離れる。言い知れぬ不安と孤独。そして気づいたときには、くちびるに何かがふれていた。あたたかく、やわらかい、何かが。
「あなたに裏切られてから、ね」
彼はいつだって、たった一言、一挙手一投足だけで、あざやかに俺を殺してみせる。
――君は俺を裏切り者だというのか? 俺が持てなかった傲慢を、君はあのときからずっと持っていたのか?
それはずるい。ずるいよ、降谷零くん。
扉の向こうに出ると、世界は明るく、しかし彼はいなくなっていた。まさかあのときキスをしたのは、自然に手を離すためだったのか? しかしそれにしても一切の気配を感じなかったのは……。
こういうとき、日本を愛する彼ならきっと、狐につままれたような気持ち、とでも言うのだろうか。
裏切られたと思うのは、その裏切り者を信じてしまっていたときだけだ。だから、きっと。
――He was my friend… maybe.

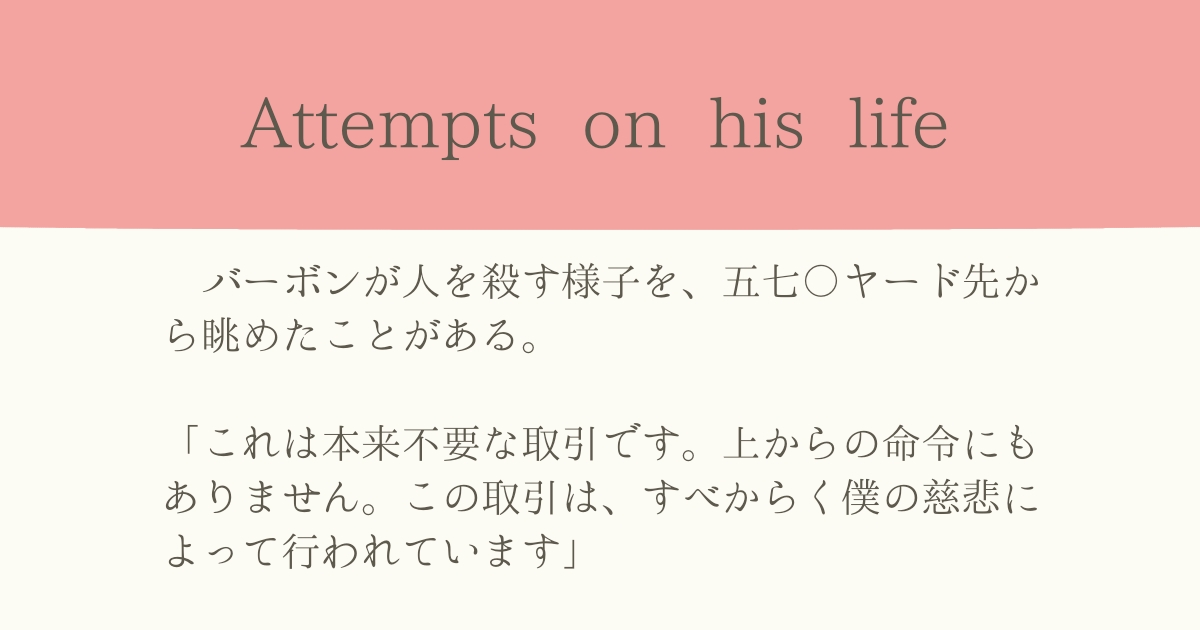
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます