僕の家に来ませんか、と彼は誘った。断る理由はどこにもなかった。酒場を出てタクシーに乗り、彼の指示したコンビニで降りる。店内に向かうので付いてゆくと、彼はバーボンを手にしていた。結局彼はバーボンだけを買ってコンビニを後にした。そうして彼に従って歩く。そう遠くはないのだろう。
十六夜の月がきれいな夜だった。
「いつだったか、君に手を引かれて闇の中を歩いたな」
「ああ、あのときは本当に馬鹿なんじゃないかと思いましたよ。こっちは遊びじゃないっていうのに。でも僕、やさしかったでしょう?」
「とてもやさしかったし、とても残酷だったよ」
「僕の味わう葛藤よりマシだ」
彼は幾分か開き直ったようだった。彼の右手が俺の左手を求めた。左手。俺の最も罪深い場所。
彼はあまりに遠い男だ。俺が彼にコミットできるのは、弾丸を放つときだけだった。その弾丸を、愛と呼ばせてほしかった。それなのに今、こんなにもすぐ傍で、手を繋いでいる。
「……覚えているか。君が組織でNOCの男を殺した夜、君は悪魔と言われていた。だが君はきっと、彼の最期の伝言を彼の仲間に伝えただろう」
「そんなこともありましたね。こっちとしても他国の情報機関に恩を売るのは悪くなかった」
「君は確かにエゴイストだが、できる善を欠かさない男だ。それは間違いなく君のやさしさだ」
「……ふふ、ありがとう」
言いたいことはたくさんあったが、どれも出てくることはなかった。それを咎める者はなく、彼も満足そうにしていた。それならば、すべてよかった。
彼の自宅についてから、ふたりベッドに腰掛けた。シャワーも浴びずに彼がそうしたので、それならいいかと俺も倣った。彼はサイドボードのふたつのグラスにバーボンと水を注ぎ、ひとつを俺に寄越した。
なぜそこにグラスがふたつあるのか。単にここでの晩酌が趣味ならグラスはひとつでいいはずだ。その疑問をここでぶつけてしまうのは、すこし格好悪い気がして黙っていた。
「今夜あなたを誘うことにしたとき、ここにグラスをふたつ置きました。あなたとここで、バーボンを飲みたくて。……そう言ったら安心か?」
「……ああ、とても」
彼には敵わないな、と思った。彼と一緒にいるということは、きっとずっとこんな感じなのだろう。でもそれが決して嫌ではなかった。
「……バーボンなんて、いつ以来だろう。最後に飲んだのなんて、潜入前な気がする」
その発言は、俺にとってとてつもなく尊いものだった。彼がささやかな儀式的行為を俺の傍で捧げてくれた。それがとても嬉しかった。
「バーボンは、いい酒だよ」
やっとのことでそれだけを言った。目が合った。視線のすべてが海容と承認だった。雄弁なまなざしは、彼もまたあらゆる言葉に不満足であることを物語っていた。それに従ってキスをした。
「待ってて。シャワー、浴びてくるから」
バーボンを舐めながら数十分が経った。準備もあるだろうがそれにしたって遅い時間だった。彼が見られたがらないであろう場面を見てしまう危惧もあったが、それでも心配になり、浴室に足を運んだ。
「降谷くん?」
シャワーの音が聞こえていた。途切れる様子もなく、ざあざあと流れている。すこし迷ったが脱衣所の扉を開けた。そうして目にした硝子越しのシルエットは、直立していると思しき状態のまま微動だにしていなかった。
「……零くん?」
すこし大きな声を出した。磨り硝子なのでわかりにくいが、彼の肩が揺れた気がした。
「あっ、赤井っ」
彼の上擦った声が聞こえた。
「あの、今、……僕の顔を見ないで……もう、すぐに行くから……」
忍耐を迫られていた。きっとかわいい顔をしているが、ここで無理矢理見るのは得策ではないだろう。理性がそう言っている。彼は結構よく拗ねるのだ。深く深く呼吸して――多分はじめて人を撃ったときよりも深かった――踵を返した。
「寝室で待っているから、その顔のままでおいで」
声に興奮が滲むことは避けられなかった。彼も気づいたことだろう。手慰みのバーボンを、もう一杯飲みたかった。
果たして寝室に現れた彼は、少女のような顔をしていた。そのくせ下着一枚で、アンバランスが憎かった。俺はグラスをサイドボードに置いてしまって、彼をベッドに招いた。彼の足取りはいつになく頼りなかったが、それでも俺の元へ向かっていた。
「零くん、愛しているよ」
愛している。その言葉だけが確実で、他のすべてが不確かだった。彼は泣き出しそうな顔をしていて、なのにたった一度だけゆっくりまばたきをすると、なんだか好戦的な表情になっていた。
ベッドに乗り上げた彼は俺の服を脱がしにかかった。甘んじてそれを受けながら、俺はシャワーを浴びなくてもよいのだろうかとぼんやり思った。しかし今更それを言うのもどうかというところまで来ており、彼が堪らないとでも言いたげな顔で俺の首筋のにおいを嗅いだのでどうでもよくなった。彼がズボンを脱がそうとしたので腰を浮かせて助けると、下着まですべて一度に脱がされた。そうして驚いている間に、彼はまだやわい俺の中心にくちづけてしまっていた。
「君なあ……!」
彼はなにも言わなかった。先端を吸い、横から幹を甘く食み、ちらりとこちらに視線を寄越す。根元から裏筋を舐め上げられたかと思えば、遂に咥えこまれてしまった。勃ち上がった屹立を飲み込んで、吸い付くあまりやや削げてしまった彼の頬を、それすらかわいくて撫でてみた。彼の耳が赤くなった。恥ずかしいらしかった。
彼の卓越した技巧は、彼の経験の証左でもあった。しかし、人間としての降谷零を抱くのは、きっと俺がはじめてなのだろう。
「離してくれ、もう出るから……」
腹を震わせながらそう言うと、彼はますます深く咥えた。どうせそうするのだろうと思っていたため、半ば諦めたような気持ちで吐精した。やはり彼は白濁を飲みこんでしまっていて、射精後の頭でまったくなにをやっていたんだと自嘲した。それでも冷めない気持ちがあった。その正体は愛だと思った。
彼のすべてを愛撫したかった。この罪深い左手にはその資格がある。なぜならベッドの上で最も尊いのはそこにいるふたりの法であり、俺と彼はふたりとも傲慢だからだ。
頬を撫でると擦り寄ってきた。首筋を撫でると吐息を漏らした。胸を撫でるとその身を捩った。何度も何度もキスをして、それらすべてが永遠だった。
「ね……そこの二番目の引き出し……ゴムとオイル、あるから……」
息も絶え絶えの声がしたが、俺は無視して愛撫を続けた。胸の飾りに舌を這わせて、満足するまで噛んでいた。彼の吐息に母音が乗って、シーツを掻くのが愛おしい。左手をようやく下へ下へと下ろしてゆき、腹を伝って、下着を脱がせて内腿をなぞった。彼の恨めしげな目をたっぷり五秒は見つめて、それからようやく彼の示した引き出しに手を伸ばした。この間五回は馬鹿と言われた。
オイルを指に纏わせ、体温に馴染ませ、ようやく彼の竅にふれた。侵入は拒まれなかった。彼はある程度解してくれていた。どうにも一抹のさみしさがあった。次の夜こそは、と思った。当たり前のように、未来について考えていた。
もういいだろう、というところまでやわらかくなった葡萄色のぬたつきに、そっと腰を寄せてゆく。濡れてきらめく彼の瞳と目が合った。堪らなくなって微笑した。途端に彼がびくりと震えた。視線を落とすと射精こそしていなかったが、彼の様子は、まさか。
「待っ……今、ちょっと」
「ホォ――……」
「あ、ッうそ、や、……ッ」
待つものか、と思った。彼に俺を刻み込みたい。忘れられない男になりたい。素直な衝動だった。そのための手段としてセックスはあまりにも愚かだが、殺し合いの代替としては十分に妥当だろう。愛は愚かなくらいで丁度いい。……かつてはほんとうに、俺のことなどやがて忘れればいいと思っていたのだ。それなのに、そうしなくてもよいのだと思わせたのは彼なのだ。彼が悪い。俺を傲慢にしたのは彼だ。
「ッ、ぁ……ン、だめっ、ア……ハァ……」
震えながら視線を泳がす彼がどうにもかわいくて、どうしても止めてやれそうになかった。脚が空気とシーツを蹴っていたので、膝を抱えてしまうことにした。
ようやくすべてを収めきり、深く深く呼吸した。彼の目を見ると、今度は彼が微笑した。
「ど、どうしよう……?」
困惑と幸福を織り交ぜたような微笑だった。彼は今、俺とのセックスにまっさらな状態で向き合ってくれているのだ。その試みがうれしくて、ぎゅっとくちびるを噛み締めた。なるほど、これは危うい。先程の彼を笑えない。すんでのところだった。
「楽しもう」
彼の反応を待たずに腰を揺さぶった。彼にこのセックスを楽しんでほしかった。
「じゃあ、キス、して……」
じゃあ、ってなんだ。夢中になってそのくちびるに飛び込んだ。舌を絡めて、時々まぶたを持ち上げて、睫毛の震えを眺めるだけで飛べそうな程しあわせだった。
ふと思い立って鎖骨のあたりに噛み付いてみた。ちゅ、と吸い付いて跡を残す。彼の顔はなぜだかすこし怒っているようだった。付けなければさみしそうにしたろうに。我侭な男だ。
「ッン、あ、ァ……」
そろそろ限界を感じはじめて、彼のペニスにふれてみた。どうにか彼を先にイかせてしまいたかった。ベッドの上でくらい、追い掛ける側でいさせてほしい。
「だめ、あかい、も……アっン、イッちゃ、から……ア……ッ」
彼の白濁を指に絡めて、数拍後には俺も達した。
彼と正面から向き合いながら、あたたかな湯船にふたり、浸かっていた。随分広い湯船だった。俺としては特に魅力的なものではないが、彼が広い湯船に価値を見出しているのであろうことはなんとなくわかったし、そんな彼が好きだった。
「赤井。どこでどう生きたっていいから、ひとつだけ約束しろよ」
これから俺たちはどうなるのだろう。どうするのだろう。きっとどうもしないのだろうとは思った。俺は一先ずこれまで通りにまたFBIで働くのだろうが、それでも東都にいる間にホテルを使うことはないのではないかとか、そういうことをぼんやり考えていた。しかし組織に方がついた以上、天職だとは思っているが、FBIを辞めることにもさしたる躊躇はない。しかしそれを彼のためにするのは如何なものだろう。そんなことをとりとめもなく思案していると、不意に彼が言葉をこぼしたのだった。
「約束?」
「僕が死んだら墓を暴け。死体がなければ僕を探せ。死体があればそれはあなたにくれてやるから」
「……君の方が先に死ぬのか?」
「一度死んだ男だろ。今度は僕の番だ」
彼の方が余程覚悟を決めている、と思った。その一方で、先のことはまた先で考えることにした。
どこでどう生きようとも、彼が俺の運命なのだから。運命に狂わされる人生も、悪くないと思いはじめていた。
――He is my neighbor.

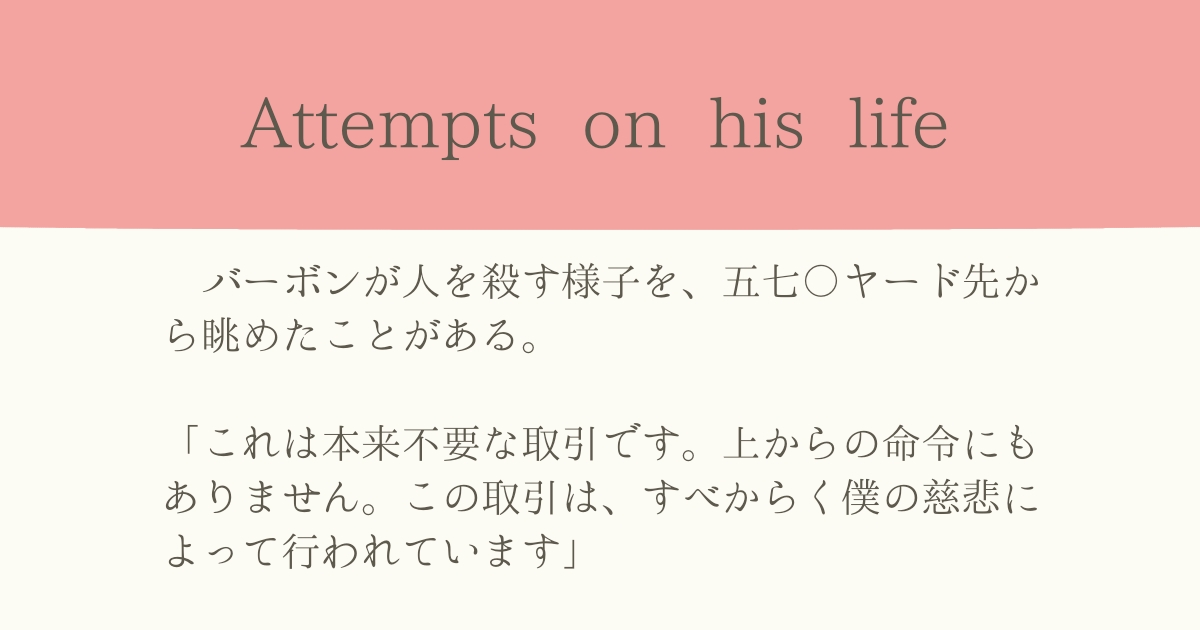
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます