赤安:記憶喪失になった降谷が赤井と一日を過ごす話です
深く深く潜っていた。ここちよかったはずの水が突如として激しくうねり、僕をこの安らかな世界から追い出そうとしている。さっきまで楽園だったのに、今はもう荒れ狂う濁流だ。水面が見える。迫ってくる。呼吸の仕方なんて、もう忘れてしまったのに。僕は再び産声をあげるのだろうか。それとも、誰かにキスでもしてもらうのだろうか。
* * *
世界は白い。その次に痛い。世界は白くて痛い場所だ。頭が痛い。どうして? だってこんなにも痛い。僕を覚醒させるのはいつだって痛みだ。……いつだって? これまでにそんなことが果たしてあったか? これまで……?
僕はおそらく記憶喪失なのだろう。ストンと腑に落ちた。普通はもっと動揺するものなんじゃないのか、と他人事のように思った。どうやらここは病院らしい。白い天井、白い壁。左腕に点滴、僕は右利きだと思う。窓の外には薄暮が見えた。洛陽は見えないのでこの窓は西向きではない。空の赤とは対象的に、僕のいるこの部屋は、蛍光灯のせいで純潔じみて白い。窓際のブリザーブドフラワー。元は薄桃色だろうが、夕陽のために薄っすらと赤い。部屋の高さは五階か六階くらいだろうか。外の景色と天井の高さからそう推定する。ベッドの傍にはパイプ椅子がある。右腕を伸ばし座面に触れるとまだあたたかい。さっきまで誰かいたのだろうか。すくなくとも僕は身元不明者ではないらしい。
世界の情報量がおそろしく多い気がした。自分が何者かもわからないのに、世界が雑多に流れ込んでくる。僕――記憶を失う前の僕――は一体どんな世界を生きていたのだろう。とにかくナースコールを押すべきだろう、と手を伸ばしたところで、扉が開いた。男だ。廊下の窓から差し込む真っ赤な夕陽を背負って立つ、黒ずくめの男。どこか懐かしいような気がした。ニット帽、そこからすこしこぼれた前髪。見開かれたみどりの瞳がどこまでも深くて、彼の奥に無限を見た。服の上からでも分かる筋肉質な身体。きちんと脚まで鍛えられている実用的な筋肉。高そうな靴だ。もう一度彼の目を見た。感情の読めない目をしていた。
「……れいくん」
男は声までうつくしかった。甘く低く身体の内に入り込んで、骨まで響く彼の声。内容が一瞬理解できなかった。れいくん。僕はきっと「れい」を名前のどこかに冠しているのだろう。あるいはコードネームか。……コードネーム? ちょっと常識的ではない。この思考はおそらく僕の記憶の名残から来るものだ。僕はどんな世界に身をおいて暮らしていたのだろう。
「……あ、……」
口からこぼれたそれが、果たしてただの感嘆なのか、自信がなかった。僕はなにかを言いかけたのではないか? 漠然とした衝動が出口をなくしてさまよっていた。
「目が、覚めたのか……」
どうやら僕は随分と長いこと眠っていたらしいと察した。いや、たとえ数時間でも数分でも意識不明だったのならそういう反応になるだろうか。ごめんなさい、と思ったが、今言うべきなのかはわからなかった。目が覚めたことは事実なのだから、はい、とだけ答えた。掠れた声だった。それが妙に恥ずかしかった。息が上がって、ひどく疲れた。病み上がりなのだから当たり前だろうが、この男のせいに思えてならなかった。彼はいったい何者なのだろう。知りたい。教えてくれないのなら暴きたい。
「俺は赤井秀一だよ、降谷零くん」
あかいしゅういち。僕は彼の名を呼びたかったのだろうか。わからない。
彼は病室に入り扉を閉めた。感情の乗らない声だった。さっきはあんなに胸を震わせる声で僕の名を呼んだのに。僕と彼の関係がまったく想像できない。彼は僕の健忘に気づいているのだろうか。
「記憶の混濁はめずらしいことじゃない。今夜はよく眠るといい。帰り際に看護師を呼ぶから、君はこのまま待っていてくれ」
彼はそう言って僕の手を握ると去っていった。じきに看護師や医師がやってきた。彼らは僕にいくつかのことを尋ねたが、僕は何も答えられなかった。自分がどうしてここに入院しているのか訊いてみたが、それは翌日訪れる人間が答えてくれるからと言われる。僕は自分が常識の範疇で考えうるところで生きている可能性は限りなく低いだろうと理解した。どこかアンダーグラウンドな世界の住人なのだろう。特に何も感じないが、背中に彫り物があったりはしないだろうか。なるほど、記憶を取り戻さないと生き難くなりそうだ。先程の男も言われてみれば――誰に言われたわけでもないが――堅気には見えなかったし、同業者なのかもしれない。それに、なんらかの事故か事件に巻き込まれて記憶の混濁した人間を何人か見てきたようだった。
その夜、もう彼は訪ねてこなかった。
翌日、午前中にあれこれと検査をして、ちょうど冷めた昼食を摂っている頃、病室のドアがノックされた。ノック。妙に心に引っかかった。心臓がざわざわする。あるいは神経が過敏になっていて、来客に過剰に反応してしまっているだけなのか。判断がつかない。そういえば昨日の男……赤井秀一はノックをしなかった。一瞬無礼な奴かとも思ったが、それもそうだろうと思い直した。意識不明の人間がいるだけの部屋に入るのにノックはいらない。
「どうぞ」
「失礼します」
男は律儀に断りを入れ、一礼した。僕は無言でパイプ椅子を勧めた。彼は目礼をしてからそこに座った。短髪に眼鏡。安くはなさそうだがやや草臥れているスーツに、履き潰す寸前の靴。清潔感はあるが、それと同じぐらいの威圧感がある男だった。
「私は警察庁警備局警備企画課の風見という者です。あなたの部下にあたります。呼び捨てにしてくださって結構です」
「では、風見。入院と健忘の経緯を教えてほしい」
風見と名乗った男は至極シンプルに説明してくれた。曰く、僕はとある事件に巻き込まれて頭部を強く打ったらしい。実に簡潔。彼が教えたのはたったそれだけだった。目覚めたのは昏倒から三日後で、上層部は記憶が戻るまで休職するようにと命じているそうだ。
「降谷さん、あなたの記憶にある情報は我々にとって無限にも等しい。率直に言って、あなたはあまりに危険な存在で、日本国家に傅いてくれているのが奇跡です。我々はあなたに記憶を取り戻してほしい。もしかすると、これはあなたにとって酷なことかもしれない。それでも、我々はあなたに、帰ってきてほしい」
どうやら僕は僕が思っていたよりもきな臭く微妙な存在らしかった。言葉だけなら非情な傀儡扱いにも思えたが、風見がひとりの人間として降谷零を慕っていることは伝わってきた。僕はいい上司だったのだろうか。だといいな、と期待めいて思った。
「つとめるよ。ありがとう」
「当たり障りのない個人情報はこちらにまとめました。申し訳ないですが、読んだあとは燃やしてください」
彼はそういって、A4サイズの茶封筒とマッチ箱を取り出して机の上に置いた。マッチ箱。なんとなく気になった。マッチにまつわる思い出でもあるのだろうか。
「ありがとう。今は昼休みなんじゃないのか?」
「気を遣わないでください。……燃やすところを見届けたら戻ります。食事中なのに申し訳ないですが」
「問題ないよ」
言いながら茶封筒を開けた。果たして僕の口の利き方は正解なんだろうか。わからない。それはこの紙にもきっと書いていないことだ。紙は一枚だけだった。
降谷零。三十一歳。警察庁警備局警備企画課。いわゆる公安。以前潜入捜査をしていたため、街中では安室透やバーボンの名で呼ばれる可能性があり、人のいるところでは本名を迂闊に口にしない方がよい。安室透は探偵兼喫茶店ポアロのアルバイターだった。彼はバーボンのコードネームを持ち某犯罪組織で情報屋として活動していた。現在某組織は既に解体。公安に申告せず独自に使っていた偽名がある可能性もあるため注意が必要。
ふたつの住所と三つの電話番号も書いてあった。にも関わらずこの場で燃やせというのか、と思ったが、存外諳んじるのは簡単だった。暗記が得意なのか、それとも記憶の残滓なのか。
言葉すくないプロフィールは予想以上の濃度だった。情報を反芻しながら茶封筒を折って紙箱を作った。この部屋には灰皿がなかった。マッチ箱にはマッチが一本だけ入っていた。失敗したら困るな、と思いつつ、なんの苦もなく火がついた。紙箱の中に灰が落ちる。身体に馴染んだ作業だと感じた。今まで何度もやったことがあるのだろう。入れ墨はないようだが、アンダーグラウンドに精通した人間なのは間違いないようだった。いや、仁義さえない世界なのだろうから、入れ墨があった方がマシだったのかもしれない。紙が灰になるのを見届けた風見は「あなたの無事を心から喜んでいます」と告げて立ち上がった。降谷零は部下に恵まれている。
「明日午前、今後あなたを支える者がやってきます。当面は彼の指示に従って動いてください。信頼できる男です。よろしくお願いします」
彼は去り際にそう言った。苦虫を噛み潰したような顔だった。彼は余程その男が嫌いなのだろうか。
午後から再び検査をして、入浴や食事が終わる頃にはもう黄昏時だった。点滴が外れたので自由に動ける。頭痛も和らいでいて、身体に異常があるとは思えなかった。スリッパを履いてベッドから降りる。窓を開けると夏の風が飛び込んできた。夏の夕暮れのにおい。虫が入るとよくないのですぐに窓を閉めた。
部屋に取り付けられた鏡を見に行った。今朝も見た顔が映っていた。記憶喪失になった人間でも、自分の民族がわからないということはすくないのではないだろうか。生え際を確認したが、金髪はおそらく地毛だ。肌はやや褐色で、夏本番はこれからであるから日焼けではなさそうだ。瞳の色は、灰色や青色と形容できる曇天と晴天の狭間。なるほど、正しきと悪しき、どちらにも転べる潜入捜査官らしい。西洋系なのかと思いきや顔立ちはアジア系のようだ。ハーフだろうか。どのみち日本では目立つ風貌だ。そういえば風見は僕の家族に関する情報は一切教えてくれなかった。配偶者はいないにせよ、父や母のことさえわからない。不自然だと思うが、職業を考えるとひょっとすると自然なことなのかもしれない。あるいは単に家族がいないのか。家族。いまいちピンと来ない。僕にとって家族とは常識の範疇にはないものなのだろうか。本当にいないのかもしれない。なんの感慨もなくそう思った。
そういえば、今日は彼が来なかった。
翌朝、検査結果を聞かされた。脳にも身体にも異常はないらしい。しばらくすれば記憶が戻る可能性もあるが、百パーセントではないそうだ。退院の準備をして迎えを待つように言われ、渡された服に着替えてベッドに座っていた。元々僕が持っていた服なのだろうか。新品ではないからおそらくそうなのだろう。年齢のわりに若々しいと思ったが、自分の顔を思い出して、おかしくはないなと思った。
手持ち無沙汰だな、と感じてからすこし経った頃、迎えの男がやってきた。赤井秀一だった。僕はそれを悲しく思った。僕が記憶を失ったことで、彼はきっとがっかりしているだろうから。そんな気がした。
「……赤井秀一さん」
「そうかしこまらなくていい。敬称は不要だ」
「秀一?」
「……彼は俺を赤井と呼んでいたよ」
一瞬の狼狽。気配だけで表情には出ていなかった。動揺の似合わない男だと思った。男は……赤井は僕が目の前にいるにも関わらず、降谷零のことを「君」などの二人称ではなく「彼」と指した。それだけでも、彼が降谷零に並ならぬ想いを向けていることが伺えた。やはり申し訳ないな、と思った。
「記憶が戻るまでは一緒に暮らすことになっている。今日はまず君の家に行って、それから俺の家に。荷物を置いたら君の所縁のある場所に行こう」
「わかりました。よろしくお願いします」
男の瞳は静かに寂寞をたたえていた。
彼の車はおそろしく目立つ真っ赤なものだった。マスタングだな、と瞬時に悟った。僕は車が好きだったのだろうか。それとも彼の車だから知っていたのだろうか。自分は車を持っていたのだろうか。
「いくつか質問をしてもいいですか?」
促されたとおり助手席に乗り込んでシートベルトを締める。かすかに煙草のにおいがしたような気がしたが、はっきりとは捉えられなかった。だからこそすこし気になった。いつかの同乗者が吸ったのだろうか。
「必ずしも答えられるわけではないが、それでもいいなら」
「ではまず、僕とあなたの関係はどのようなものでしたか?」
「……それは一言では説明できない。伝えられるとすれば、俺と君との間にあった出来事のすべてを伝えて、そこから君に考えてもらうことだけだ」
「でもそれって、あなたが僕との関係に影響していると思った出来事というだけで、僕の認識とはまた異なっているかもしれないわけですよね」
「当然そうなる。俺が君をコントロールできてしまうというわけだ」
「じゃ、結構です」
答えははじめから期待していなかったが、いいようにはぐらかされてしまった。しかし彼なりに誠実であろうとしていることはわかったのでよしとする。風見は彼を信頼できる男だといった。僕もそう思う。彼は僕に与える情報に注意を払っている。おそらくは、僕と彼自身のために。それはありがたいことだったが、記憶のある降谷零に対してもそういう態度だとしたら、それはさびしいことだし、ひょっとしたら腹立たしくさえあるかもしれないな、と思った。
「あなたは僕と同業者なんですか?」
「そう思ってくれて構わない」
「僕は事件に巻き込まれたということでしたが、具体的にはどういうものなんですか?」
「君の職務とは直接は関係のない事件だった。君はたまたま銀行強盗に巻き込まれて、その場にいた女性を庇って頭を強く殴られた。君は血を流して倒れていたが、警察が突入したとき、犯人は既に拘束されていた。犯人は君がやったと証言している。その前後の記憶もないのだろう?」
「ありません。その事件はニュースになりましたか?」
「ああ。様々なマスメディアが事件を報じたが、どこも君の存在については報じないよう徹底した。SNSでは被害者が君について言及しているが、みな手足を拘束されていたから写真は残っていないだろうとのことだ」
なんとなくピンと来なかった。自分の職業が警察官であることはわかっているはずなのに、同時に自分が見ず知らずの女性のために身を挺する状況がうまく想像できなかった。きっとそれが最善手だったのだろうと思った。
赤井はまっすぐ前を見て運転していた。
赤井は迷いなく僕の家……だという場所に辿り着いて、躊躇なく持っていた鍵で解錠した。部屋の中は物がすくなく、よく整頓されていた。どこかモデルルームじみていた。特に何かを思い出すこともなく、ひととおり部屋を眺めた。何が好きで、何にこだわるのか、そういうものがまったく見えてこない家だった。
ボストンバッグがあったので、それに衣類をいくらか詰める。寝室のサイドボードの引き出しを開けると拳銃が出てきた。持っていくか迷ったが、今の自分に殺すべき人間とそうでない人間を区別できるとは思わなかったので、置いていくことにした。降谷零の築いてきた社会性を今の自分が破壊してしまうのは嫌だった。
「赤井、携帯用歯ブラシの場所がわからないので、買っていっていいですか」
「ああ。コンビニに寄って行こう」
剥き身の歯ブラシをビニール袋に入れてゆくのはなんだか間抜けだ。戸棚を漁ったがストックはないようだったので、快諾してもらえて助かった。他に必要なものがあるとも思えず、もういいですよ、と申告した。なんら感慨のない自宅にいたのは三十分にも満たなかった。
殺風景な部屋を後にするとき、病室の花をそのままにしてきてしまったことにようやく気づいた。捨てられてしまったろうか。もう枯れてしまったろうか。それとも、誰かの手によってまだ生かされているだろうか。そもそもあれは、誰が贈ってくれたのだろうか。
適当なコンビニの店内を一周して、適当な歯ブラシを手に取った。財布を持っていないので、それを赤井に委ねる。レジを見てふと思い立った。
「煙草、買ってもいいですか?」
赤井は虚を突かれたようにこちらを見た。
「赤井、僕は喫煙者じゃありませんでしたか。なんだかそんな気がする」
自分が何者なのか思い出す糸口になるかもしれないと、すこし早口になった。赤井が驚いたように息を呑むのがありありとわかった。だが、赤井は素気なくこう言った。
「……さあな。俺の前では吸っていなかった。何か買おうか」
赤井がレジに向かった。やや唐突な動きだった。顔を見られたくないのかな、と思った。だがそれはなにより、僕が彼の表情を見たいと思っていたからに他ならない。僕は何か、おかしなことを言っただろうか。
赤井は既にレジにいた。僕は彼の横に並んで、外国人――名前と顔立ちからしておそらくはインドネシア人――の店員に「煙草、百四十二番を」と告げた。赤井は何も言わなかった。僕は歯ブラシに手近なライターを添えた。
かくして僕の手に、ラッキーストライクがやって来た。
「なぜそれなんだ?」
車内に戻ってから赤井が訊いた。それ、というのは銘柄のことだろう。
「なんとなく、そんな気がして。……だめでしたか?」
「……いや、だめなんかじゃないさ」
そりゃそうだ。三十路の僕が吸う煙草に、いいも悪いもありはしない。僕は何も言えなくなって、彼も何も言わなかった。沈黙の車内。まだ一日も経っていないが、赤井が寡黙であることはわかっていた。和やかさや賑やかさに重きを置かないタイプなのだろう。
「そういえば、財布や携帯はもらえないんですか?」
「俺としては渡してやりたいが、君の上から止められている。余程君に逃げられたくないらしい」
「じゃ、はぐれたら一巻の終わりですね」
「……そんなことはない。君がどこにいても、俺は必ず見つけ出す」
気障な男だと思った。彼はなぜこんなにも、僕に心を傾けてくれるのだろう。降谷零と赤井秀一の関係がまったくもって僕にはピンと来なかった。いちばん似ているとしたら、……そう、元恋人、とかなのではないか。何か事情があって別れてしまった元恋人。一度そう思うと、どんどんそんな気がしてきた。それはどこかしっくりくる話だった。
「……へえ、じゃあ、逃げちゃおうかな」
「酷いことを言わないでくれ。ほんとうのところ、君に逃げられてしまったら、見つけるには恐ろしく骨が折れそうなんだ」
赤井の苦笑を見て、すこし気分がよくなった。彼が僕を――厳密には僕ではなく降谷零だが――高く買っているのは、なんだかとても気分のいいことだった。彼の横顔が好きだと思った。
「昼食はどうする? 希望がないなら適当な店に入るが」
そう言われてようやく昼時であることに気づいた。そういえばすっかり空腹なのだった。そこではたと思いついた。
「……これからあなたの家に行くんですよね? あなたさえよければ、何か作らせてください」
降谷零の自宅にはそこそこの調理器具があった。職業柄なのか冷蔵庫は空に近かったが調味料は豊富だったし、僕はおそらく料理がそれなりにできるのだろう。ぼんやりとだがレシピも頭にあるような気がする。作ってみたかった。
「構わんが、俺の家にはロクな食品も調理器具もないよ。かろうじて鍋があるくらいだ。……ああ、食器は不揃いでよければなんとかなるだろう」
「酷いな。どうやって暮らしてるんですか?」
「日々かろうじて」
「米は?」
「ない。ついでに言えば炊飯器もない」
「……そういえば、あなたそもそも日本人なんですか? 瞳が緑だ」
「母親がイギリス人で、生まれはイギリスだ。それからは日本やアメリカで暮らしていた」
「なるほど。……じゃあパスタにしましょうか。スーパーに寄れますか? ソースの希望は?」
「君に任せよう。……楽しみだ」
「じゃ、トマトソースにしましょう。……うん、作ったことがある。わかる。きっとおいしいですよ、赤井」
記憶を取り戻したかった。それに、赤井に何か報いたかった。赤井の複雑そうな顔には気づいていたが、自分の――今この瞬間の降谷零の意志に背きたくなかった。
赤井の家も殺風景だが、雑然としていて生活感があった。リビングのテーブルに空の灰皿が置かれていた。彼も煙草を吸うのだろうか。
「荷物は好きに置いてくれ。ゲストルームはここ。トイレと風呂はそこだ。キッチンも好きに使ってくれて構わない」
「ありがとうございます。お世話になります」
「気にするな。寛いでくれていい」
ゲストルームには簡易のベッドがあった。おそらくは昨日、わざわざ用意してくれたのだろう。有り難かった。それ以外には何もなく、ただ真っ白な壁紙があるばかりだった。独房のようだった。
「すこし休むか?」
「いえ。もう作らせてください。お腹空いちゃった」
赤井の空腹については、敢えて言及しなかった。なんとなくそれは傲慢な気がした。
赤井家のキッチンはほんとうにかろうじて鍋と俎がある程度だった。お玉は埃を被っていたので洗った。棚の中には包丁と果物ナイフがひとつずつあった。フライパンはなかった。
玉葱をほんの四分の一と大蒜を一欠片。これらを細かく刻んで、たっぷりのオリーブオイルと共に弱火の鍋へ。泡立ってきたら火を止めてトマト缶を投入。ドライハーブを入れて、中火でしばらく煮込む。鍋がもうないのでこの間にパスタを茹でることはできない。余った玉葱もスープにしてしまいたいがこれまた鍋がないので様子見だ。もうひとつくらい鍋も買っておけばよかった。
「灰皿がありますけど、煙草は吸わないんですか? 喫煙者の恋人がいるとか?」
「家に来るような恋人がいるなら、君を家に泊めたりするだろうか」
「するかもしれませんよ。僕の見立てだと、あなたは職務のために恋人を捨てるタイプだ」
「……その答え合わせは君の記憶の中だ」
図星だろうな、と思った。推理という程のものではないが、何かを言い当てるのは気持ちのよいことだ。鍋がくつくつと煮立っていた。火を弱めて更に待つ。彼の指先がくちびるを撫でた。口寂しいのだろうか。あの灰皿や車内のにおいが示すのは、彼が禁煙中であるということなのかもしれない。……彼を健康で幸福にできるような忍耐強い女性が、いつか現れればいい。
早業で作ったトマトソースパスタとオニオンスープをふたりで食べた。実を言うと、僕は先程ひとつ言葉を飲み込んでいた。赤井秀一は職務のために恋人を捨てるタイプだろう。……そして、自分のために料理を作りたがるような女性を疎ましく思うタイプだろう。特に根拠はなく、それは単なる印象でしかない。しかし僕の昼食の提案を抵抗なく受け容れたと思しき彼の、どこにそんな印象があるというのだろう。これも記憶の残滓だろうか。……そうでなかったら、これは僕の驕りに他ならないことになる。
「とてもおいしい。ありがとう、降谷くん」
彼が僕の名前を呼んだ。それはあのときの「零くん」ではなかった。
「これから君が安室透として過ごした米花町に行く。君が記憶喪失であることはあまり明るみに出したくない事実なんだ。だから申し訳ないが、君は車から一切降りないでくれ」
再び滑り出した彼の車中で、彼は開口一番そう言った。特に不満はなかった。今の僕にはそうまでして米花町を歩きたい望みはない。
「わかりました。なるべく早く、思い出すようにつとめます」
「……無理だけはしてくれるなよ」
瞳の奥が揺らいだが、まったくの無表情だった。ポーカーフェイスが上手いというより、表情を作ることが下手なのだろう。稀に見せる頬の動きが不器用そうだった。格好いいが、同時に軽蔑すべき男だと思った。人を泣かせるタイプの男だ。
「しばらくすると左手に喫茶ポアロが見える。その上のフロアには毛利探偵事務所がある。君はそこである目的のために毛利探偵の弟子として活動していて、その一環としてポアロでアルバイトをしていた」
僕は探偵だったらしい。警察官や潜入捜査官よりも、探偵の方がしっくりくる。他者を暴き、愉悦を得て、それを生業とするプライベート・アイ。そちらの方が性に合っていて、自分のあるべき姿であるような気がした。喫茶店店員の方はよくわからない。だが先程赤井に料理を振る舞うのは楽しかった。それはそれで向いているのかもしれない。
そんなことを考えながら窓の外を眺めていると、三人の少女が歩いているのが見えた。制服だから中学生か高校生、おそらくは高校生だろう。記憶があれば制服で判断できたはずだが今の僕にはできない。三人のうちのひとりが妙に気になった。胸がざわついて目が離せない。ゆるく波打つショートの黒髪、気の強そうな目、スポーツをやっているのだろう、快活そうな肉体。元気がなさそうだが、気丈に振る舞っているようにも見える。
「赤井、あの子、あの三人組の黒髪の子、あの子……」
「……彼女がどうかしたのか」
「あの子、僕とつながりがあったりしませんでしたか? なんだかすごく……」
「すごく?」
この焦燥が何に似ているのか、わかりたくなかった。だってこれは、これはあまりにも恋に似ている。通りすがりの見知らぬ少女に、自分が何者かさえわからないのに恋をするなんて、そんな馬鹿げた話があるだろうか。だからこれはきっと、記憶の残滓で、記憶に至る手掛かりなのだ。それと出会えた興奮が、すこし恋に似ているだけ。……そう思い込もうとすればする程、形容し難い感情が腹の奥から迫り上がって胸に満ちた。
「……よく、わからないです」
赤井は一瞥を寄越したきり、僕のことも少女らのこともまともに見なかった。それが僕は不満だった。お願いだから、ちゃんと見てくれ。こんなに僕を惹き付ける彼女を。お前だって僕の記憶が、記憶のある僕が欲しいはずだろう。
「銀行強盗事件のとき、君が助けたのは彼女だ。君の病室の花は彼女が贈ったものだ」
「どうして、僕は彼女を……僕と彼女にどういう関係が……」
「……それこそ、俺にはわからないことだ」
弾かれたように彼を見た。それは彼から感じたはじめての拒絶だった。けれど僕は、既に自分が探偵であったことを知っている。だから傷つくよりも先に、彼の態度は、きっと有益な情報だと思った。一方で、くちびるを噛む彼の横顔に、どうしてか手を伸ばしたかった。
「彼女は僕が目覚めたことを知ってるんですか」
「まだ知らせていない。彼女は記憶喪失の君には合わせ難い人物だ。彼女のためにも……」
「早く、思い出しますね」
彼の言葉を遮って告げた。本心だった。彼女は既に遠くにいた。彼が速度をゆるめることはなかったから。
赤井の家に戻って、ベランダから夕暮れの東都を眺めていた。降谷零が守ってきた街。ふいに懐の煙草の存在を思い出した。安っぽいライターで火を灯し、息を吸う。咽ることなく味わった。やはりすくなくとも吸ったことはあるらしい。
紫煙の向こうの真っ赤な街を眺めながら、自分の頭の中の白靄がほどけていくのを感じた。もうすぐ記憶が戻る。そんな予感があった。多分、元々そういうさだめだったのだ。赤井と過ごしたこの一日で、眠った記憶が目覚める。
ラッキーストライクのにおいは郷愁に似ている。降谷零の故郷なんて知らないけれど、この胸の軋みは回顧の情だ。煙に満ちた肺ではなく、この心臓が締め付けられている。それでもどうしても、このにおいが嗅ぎたかった。僕は煙草が吸いたいわけではなかったのだ。ただ、この懐かしさを求めていただけで。
* * *
世界は白い。その次に痛い。世界は白くて痛い場所だ。頭が痛い。どうして? だってこんなにも痛い。僕を覚醒させるのはいつだって痛みだ。……ああ、そうか。僕はここ数日の間、健忘に陥っていたのだった。殺風景な部屋に差し込む朝日が白い。ここは赤井秀一の家だ。
こんなタイミングで記憶喪失になるなんて、赤井もついてないな、と思った。ここ数日、随分と苦しい思いをさせてしまったことだろう。特に昨日は。
ベッドから降り、顔を洗って、すこし迷ってキッチンに立った。戸棚を覗くとインスタントコーヒーがあったので、鍋で湯を沸かすことにした。
温度の高まる水を見つめて、昨日の自分のおそろしさに思いを巡らせた。記憶を忘れてしまっても、それでも彼の煙草のにおいに焦がれるなんて、どうかしている。世良真純にほんの一瞬で惹かれたのなんて最早笑えてくる。ほんとうに、どうしようもない。
銀行強盗事件の前日、赤井は僕に愛の言葉を告げていた。行きつけのバーで酒を酌み交わして、日本酒とウイスキーのグラスをぶつけて。別れ際、捨て台詞じみて君を愛しているとシンプルな言葉を放って彼は去ってしまった。返事が必要なのかどうかさえわからなかった。問題は僕もまた彼への執着を恋と呼べる可能性に気づいていたことで、どうやって断ったものかな、と考えていた。たしかに彼のことは劣情交じりに愛しているが、なにも恋人になりたいと思ったことはなかったし、自分の感情を伝える予定もまったくなかったのだ。
その翌日に記憶喪失になったのだから、赤井の感情はまったく計り知れない。思い返せば昨日の彼は複雑そうな心境を時折滲ませていた。そりゃそうだろう。昨日の自分はあまりに彼に惨かった。
あのとき世良真純を助けたのは、他でもない赤井秀一の妹だからだ。赤井の苦しむ顔は好きだが、赤井に恨まれたくはなかった。意識が薄れてゆく中で、僕の恨みを受け止め続けた彼のことを考えていた。そして彼は、僕が見ず知らずの女性を助けるために目の前の犯人を制圧できる可能性を棒に振るような人間ではないと知っている。
ここ数日の自分を思い出すと、もう彼に愛してると言ったっていいんじゃないか、と思った。というか、絶対にバレている。諦観は覚悟の形をとることがあるものだ。湯が沸騰したので火を止めた。あまりきれいではないマグにインスタントコーヒーを入れて湯を注ぐ。この家に砂糖やミルクの類はないらしかった。赤井らしい。
コーヒーを飲む。可もなく不可もなくインスタートコーヒーの味がして、ひとつミルクが欲しかった。自分は元々ヘテロなのだろう。それでも彼が好きなのは僕と彼との間にあった様々なことが原因で、しかしその原因の一切を忘れた僕が彼によく似た妹に惹かれたことは、逃げられない、と僕に思わせるに十分なものだった。恋の奴隷になるのは御免だが、あそこまで醜態を晒して白を切るのも御免だ。
何が郷愁だよ。そんなのただの運命じゃないか。
「降谷くん」
起き出した赤井がキッチンの入り口にやってきた。僕はコーヒーを一口飲む。
「赤井。煙草、もう吸っていいですよ。どうせ願掛けに禁煙してたんでしょう。……あと、僕のこと、零くんって呼んでいいです」
そのときの赤井の顔ったら! ほんとうにこの男は表情を作るのが下手だ。もっとわかりやすく喜んだらいいものを、どうしてそう不味いものを口に入れたような顔しかできないんだろう。
「愛してますよ、赤井」
コーヒーをもう一杯淹れておけばよかった。この家にもっと食材や調理器具があれば朝食のひとつでも作って彼を待っていたのに、何もないから、僕が買ってこなきゃならない。
「……ありがとう、零くん。愛しているよ」
「で? お互い好き合っていることがわかって、あなたはどうしたいんです?」
「君次第だ。今すぐベッドに行ってもいいし、健全なデートに繰り出してもいい」
「馬鹿、この歳でベッドに行かない健全なデートがあるかよ」
「言うじゃないか」
「ここに淑女はいないんだから。いるとしたら、あなたの心の中だけだ」
彼の左胸をトンとつついた。彼がにやりと笑った。そういう顔だけは格好いい、腹立たしい男だ。彼と朝食が食べたいし、それから彼の妹に挨拶に行かねばならない。そう思いながらもキスを仕掛けた。まるで馬鹿みたいに。

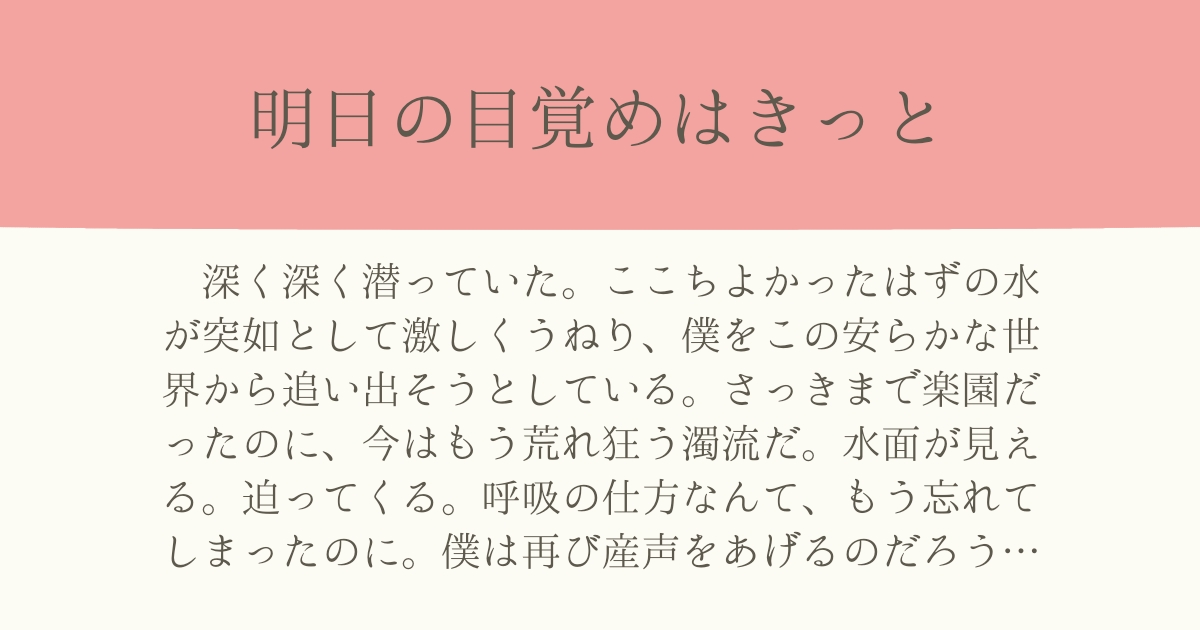
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます