赤安:沖矢昴の死と、死なない安室透の話です
今日、安室透はポアロを辞める。
思えば随分とこの店には世話になったし、たくさん迷惑をかけた。けれどその分できる限りの貢献はしてきたつもりだ。料理や掃除の一工夫、揉めごとを起こす客の対処に、力仕事に締め作業。打算ありきで入ったとはいえ、僕がこの店に憩わせてもらったのは確かなことだった。安室透は死なないが、一先ず一区切りとなるだろう。
最後ということで、店仕舞いまでを見届けて、店内をいつもより念入りに掃除してから、珈琲をふたりぶん淹れた。もしかすると、豆を挽くところから淹れた珈琲を人に振る舞うのなんて、一生のうち、これがほんとうに最後なのかもしれなかった。
「さびしくなります」
榎本梓はお世辞ではなく心からそう思っているようだった。そして僕のさびしさもまた、紛れもない本心だった。この場所には真実だけがある。安室透はどこまでも本物だった。決して虚構ではない。なぜなら目の前にいる彼女が、僕を安室透として扱っているから。僕を僕たらしめるのは僕ではない。
「こんなにおいしい珈琲を淹れられるのに辞めちゃうなんて。いっそ探偵よりも喫茶店で働いた方がいいんじゃないですか? ……なんて言ったら失礼ですね。安室さん、推理力もすっごいし」
立ち昇る湯気が空気の流れを教えていた。そこに珈琲があるから、見えないはずの空気が白く色づいて見える。安室透という存在によって見えるようになった世界が確かにあった。それはどこまでも穏やかで、どうでもよくて、愛おしい。僕はそれを知ることができてよかったと思っていた。
珈琲を淹れることも軽食を作ることも楽しかった。ほんとうに、楽しかったのだ。ただ、それよりもやりたいこととやるべきことがあっただけで。安室透は僕の世界を拡げたが、そこは腰を落ち着けるようなところではない。でも、時折休憩に足を運びたい場所ではある。
「また暇を見つけて飲みに来ますよ」
安室透は探偵業に専念する。そういうことになっていた。何も殺すわけじゃない。米花町を訪れたとき、あるいは知古に出会ったとき、僕は自動的に安室透なのだから。
安室透の設定は、なんというか結構ひどい。なにせ、RX‐7を乗り回すくせに三十路手前でアルバイトをしている人物なのだから。親の脛を齧りつつ本業としては探偵を、そして半ば趣味として喫茶店店員を。安室透はそういう男だった。そういうふうに生きてゆけたらそれはひとつの幸福だろう。だからといって、公安を辞めたいとは思わないけれど。安室透は所詮、降谷零の一部でしかない。
最後の珈琲はゆるやかに胃袋へ下っていった。熱く苦く、酸味はすくなく、砂糖は入れない。酸いも甘いもなんとやらというが、ポアロの珈琲は酸っぱくも甘くもないのだった。
「お元気で」
「梓さんこそ、お元気で」
マグカップを洗って店を出た。残暑はとうに去ってしまって肌寒い。すっかり日が沈んでいた。夜でもまばゆい東都の空に星はない。すぐに視線を下ろし、踵を返した。
向かいの路傍に見慣れた車が停まっていた。……スバル360。それは真紅のマスタングより見慣れていて、シボレーよりは見慣れていない、沖矢昴の車だった。運転席の窓が開く。やや張り上げた声。
「乗りませんか」
そこにいたのはやはり沖矢昴で、もう二度と会うことはないと思っていた男だった。安室透にはまだ価値があるが、沖矢昴にもう価値はない。なぜ、わざわざ。沖矢はうんと細めた胡乱な顔で僕を見つめていた。
「安室透さん」
何かある、と思った。彼が安室透の名をフルネームで呼ぶことには、きっと何か意味がある。僕が彼を沖矢昴と呼ぶときに意味があるように。
沖矢昴は、黒いシャツの襟を開いて、チョーカーを露出していた。
「どちらまで?」
彼は無言で同行をねだっていて、結局は僕の方から尋ねた。家まで送り届けるだけが狙いとは思えなかったし、そんなことを言い出されても困る。ドライブそのものが目的なのか、どこか連れてゆきたい場所があるのか。今更腹を探り合う関係でもないはずなのに、沖矢の顔を前にするとどうにも調子が狂った。僕はずっと同じ顔なのに、よくも彼はこうまで変わり、なのに何も変わらないものだ。同じ顔だからこそ、なのかもしれない。だとしたら随分アンフェアだ。
「月の裏側まで」
「お供しましょう」
なぜか迷いなく即答できた。彼の行き先に僕は満足していた。
月の裏側。地球から決して見えることのない場所。彼は誰にも見られないところに行きたいのだとわかった。彼は僕とふたりぼっちになりたいのだ。僕はそれに応えたかった。スコッチの死を巡る確執に決着をつけた僕は、赤井が存外不器用な男だということに気づいていた。
彼の愛車の助手席に乗り込んで、シートベルトを締める。ひとつ息をついて彼の横顔を見た。彼の身体を視線でなぞる。長い脚だ。こうして狭い車内に押し込められるとよくわかる。つくづく変装に向かない男だ。
赤井秀一を前にしたとき、僕は常に降谷零だ。だが沖矢昴とふたりきりになったとき、僕は自分が曖昧になってゆくのを感じる。僕は誰だ。確かに彼は赤井秀一だというのに。彼は誰を見ているのだろう。彼の瞳に映る男の顔を、彼は僕に見せてはくれない。
僕は沖矢昴を嫌悪している。赤井秀一へ向けていた憎悪とは違う。もっと幼稚な感情だ。僕の赤井を返せよ! そんな子供じみたわがまま。
「どうして、僕を?」
「理由が必要ですか?」
「僕は欲しい」
スバルの駆動音。伝わる振動。運転席を伺うと、男と目があった。いや、彼と目など合うはずもないのだが、確かに視線がぶつかり合っているのを感じた。彼は僕を見ている。
「……あなたと、星が見たくて」
どこに連れて行かれるのだろう。今の僕の所持品は、携帯、財布、小銃……その程度だ。どこでもなんとかなるだろう。赤井は僕を悪いようにはしない。癪だが彼はそうなのだ。僕はもう知っている。
「……悪くないですね」
いいですね、と言うか迷った。でも、それでも彼は赤井秀一だから、悪くないですね、と言った。
「明日の予定は?」
「夕方までに都内に戻れればいいですよ。沖矢さんは?」
妙な間が空いた。この男の沈黙は怖いな、と思った。明日の夜は降谷零としてちょっとした会食の予定があった。僕は帰してもらえるのだろうか。決して楽しいばかりの予定ではないので、行けないのならそれはそれでいいかもしれない。
「……僕は何もありませんよ」
変声機を通した声が、輪郭の掴めない感情を孕んでいた。
どこに向かっているのだろう。彼は星を見ると言った。都内ではなさそうだった。星の名所はいくつか知っているが、まだなんとも言えない。彼の運転に迷いは見られなかった。
「ポアロ、今日が最後だったそうですね」
「ええ。……まあ、勤めるのをやめるだけで、きっとこれからも時々行かせてもらうとは思いますけどね」
「……そうですか」
どうやらこの車は千葉方面に向かっているらしかった。山ではなく海か。死体でも捨てに行くかのようだが……海ならすくなくとも一時間以上、おそらくは二時間近く走ることになるはずだ。帰る頃には日付が変わるどころか朝になっているかもしれない。
わからない男だ。何が彼をそうさせるのだろう。思えばいつだってそうだった。彼の動機は不可解だ。一生かかっても解けなさそうな、彼という謎。
「星が好きなんですか?」
「嫌いじゃありませんから」
「あなたが星を見て感動する人間だとしたら、それは少々意外だ」
「僕に対してどういう印象を持たれていたんです?」
「そうだなあ、博識の読書家で星座には詳しいが実物の星空にはさして関心がない。本物の星空よりプラネタリウムの方が好きなんじゃないですか? ……そんなところですかね」
「……流石。すぐれた探偵でいらっしゃる」
僕をすぐれた探偵だと言う、隣りにいる男がよくわからない。彼が沖矢昴として話しているのか、赤井秀一として話しているのか。沖矢と赤井の境界はそれほど曖昧ではないはずなのに。わからない。
「あなただって、コナン君と何度も事件を解決したらしいじゃないですか。……僕を解いてみてくださいよ」
「……星には興味が薄そうだ。しかしあなたも大変博識と見える」
「無難ですね。あながち間違いでもないですが……つまらない」
不満足な答えだった。僕は彼に、僕そのものに挑んでほしかったのに。彼の推理を聞いてから、ようやくそう思い至った。彼に僕を暴いてほしい。そして一生、暴けないままでいてほしい。ずっと僕について悩んでいればいいのに。
暗い。とにかく暗かった。本当にこの車に乗っていて大丈夫なのだろうか。そう疑いたくなるほどに真っ暗だった。しかしなるほど、夜空はきれいで、東都では決して見られない空だった。もう既にこんなにうつくしいのに、彼はこれ以上どこに向かうのだろう。ヘッドライトの当たらぬ場所は何も見えず、世界が無限の闇で満たされている気さえした。
ほどなくして、スバルはどこぞの駐車場に入り停車した。ここが目的地らしかった。エンジンを止めた沖矢が降りるのでそれに倣った。どうやらここが月の裏側らしい。ふたりきりの世界。
「……きれいだ」
静かだった。寄せては返す波の音を、星のささやきだと錯覚しそうなほどに。ひとつやふたつ降り出してもおかしくないほど、綺羅星がまたたく空だった。一呼吸おいてから、寒い、と思った。うつくしいものに心を満たされるのは恐ろしい。生きてゆくために必要なことが後回しになってこぼれ落ちてしまうから。
沖矢昴の姿は闇に紛れてほとんど見えなかった。気配を探る。狙撃手に特有の静かで曖昧な気配。僕らが殺した友人も時折滲ませていたそれ。……やはり、沖矢昴はこんなにも赤井秀一だ。
「プレアデスの特徴を知っていますか?」
唐突に沖矢が言った。
「特徴? 和名が昴で、牡牛座の星団で……そういえば牡牛座のアルデバランは真っ赤な星だ」
牡牛座にはまだ早い季節だった。
「あなたの博識には驚かされますが、僕の言いたいことではありません。僕が言いたいのは……プレアデスはひじょうに寿命の短い星団だということだ」
「……あなた、沖矢昴を殺す気ですか」
牡牛座にはまだ早い季節だった。しかし、どうせ季節は巡る。彼にとって、沖矢昴が死ぬことは宿命だったのだろう。馬鹿馬鹿しいが、彼らしい気もした。
僕を安室透だと認識する人がいる限り、僕は安室透だ。けれど沖矢昴は違う。彼はもうその装いをやめてしまうのだろう。そうすれば、沖矢昴は消える。誰も彼を沖矢昴とは思わないから。それが死ぬということだ。現に今も消えかけている。沖矢昴が存在する意味がないから、僕は沖矢昴の顔をした誰かを沖矢昴として上手に認識できない。
しかしだからといって、僕を連れて星を見にくる理由はない。ただ、なんとなく、彼は安室透を求めているのだろうと思った。
「きちんと諦めるには、きちんと殺さなくてはならない」
ああ、彼は沖矢昴が〈お気に入り〉なのだ。腑に落ちた。お気に入りのものをきちんと手放すところを、僕に見ていてほしいのだ。また手を伸ばしてしまわないように。沖矢昴が少年探偵団に囲まれている光景が脳裏に浮かんだ。それはきっと、赤井秀一にはできないことなのだ。それを永遠に手放す覚悟。沖矢昴という甘美な時間を捨て去る決意。なんて不器用な男だ。傲慢、かっこつけ。そういうところを、僕にばかり垣間見せて、僕に暴かれようとする、かわいい男。
潮風が目に染みて、星が滲んだ。目を細めれば、夜空が小麦畑のようにまぶしい。
彼にはたくさんの〈お気に入り〉がある。酒に煙草に車に帽子。少年探偵団にも慕われているし、特にあの江戸川コナンとは随分親しくしているらしい。
僕に〈お気に入り〉はすくない。潜入捜査官はこだわりを持つと死に肩を叩かれるものだ。命すら秤にかけられるし、その傾きに従って行動できる。
彼だけだ。僕のものにしたいのは、彼だけ。
沖矢昴は赤井秀一に愛されているのだ。僕の世界一嫌いな男が、僕の執着している〈お気に入り〉に、別れ難いほど愛されている!
この感情がなんなのか、理解するのに数秒を要した。僕は嫉妬している。
……エレーナ先生には本当の子供がいて、僕はそれよりも決して優先されることのない存在なのだということを知ったときですら、ただそういうものなのだと、諦観のようなものを抱いていたというのに。なのに。生まれてはじめての嫉妬がこんなにも歪だなんて馬鹿げている。僕は沖矢昴に嫉妬している。だから。
「沖矢昴さん。……僕は、あなたのことが好きです」
最適解だが賭けだった。得られるものが最も大きい言葉に賭けた。いや、勝ちの決まった賭けは悪戯にひとしい。これは彼を揺さぶる悪戯だ。
闇の中の彼の表情をつぶさに観察する。頬がすこし震えた。くちびるが開きかけ、閉じ、彼の左手が首元へ、チョーカーにふれ、かすかな電子音、まぶたが徐々に持ち上がる。焦がれ求めたグリーンが闇夜の中でさやかに光る。僕はこれを探していた。ずっと、もう長いこと。……見つけた。どんな星より僕を惹きつける蠱惑のきらめき。そして彼は今度こそ喉をふるわせた。
「……認めない」
――赤井秀一も、沖矢昴に嫉妬したのだ!
ささやかな意趣返し。彼はなんて身勝手な男だ。多くの人間に愛された沖矢の仮面を手放すのが惜しいくせに、僕が赤井より沖矢を優先しようとすれば、即座にそれを放り捨て、自分だけを、赤井秀一だけを見ていろと言う。……とてもいい気分だ。僕の勝ち。彼はたしかに僕の執着を選んだのだ。
「お久し振りですね、赤井秀一。そのマスクを取ったらどうなんだ」
彼のくちびるが一瞬さまよう。僕の名前に困っているらしかった。呼べばいいのに。おまえが最も呼びたい名前を。
「冗談でも言ってはならないことがあるだろう。……降谷零くん」
「僕が本気だと言ったら?」
「……零」
「ふ、ははは、赤井、そう怖い顔をするなよ。……ふふ」
零だなんて、呼んだこともないというのに、この男は、まったく。でも、許せる。不器用なくせに傲慢でとびきり愚かなこの男を、許したいと思える。ぼくがずっと欲しかったのは、どうしようもなく彼なのだから。
「君に、共犯者になってほしかった。ただ見ていてくれればよかったんだ。俺が沖矢昴を殺すところを。二度と生き返らないように」
馬鹿だなあ、と思った。そんなに沖矢昴が好きなのかよ。そんなに好きなのに、僕のために捨てたのかよ。それがとてもうれしい。
「……生き返ったのは赤井秀一だけだ。多分もう、後にも先にも。僕はずっとあなたを見ていた」
「君は……君はいつもそうだ。君の憎悪がいつだって俺を救う」
僕の憎悪が彼を救った? ……そんな心当たりはまったくなかった。彼が何を言っているのかわからなかった。僕は彼を救ったことなどない。いつの間に勝手に救われていたんだ。僕の憎悪で。まさか僕の殺意が彼を生かしたとでもいうのか。だとしたら因果なことだ。
――僕は彼の愛に救われなどしなかったのに。
なんて傲慢な男だ。彼の愛で僕は苦しみ、僕の憎しみで彼は救われた。馬鹿みたいだ。それでも……それだから、彼が〈お気に入り〉だなんて。
ても、彼に星を見ようと誘われたのは、ふたりで月の裏側に行こうと誘われたのは、きっと、彼の立つ世界の中心に、僕も招かれたということなのだ。それはとても、悪くなかった。
「安室透は……沖矢昴と一緒には逝けませんよ」
「ああ。君は優秀だからな」
「……なんだか、ごめんなさい」
「なぜ謝る」
「謝罪の気持ちがあるから」
「妬けるな。やっぱり沖矢のことが好きなんじゃないのか」
「馬鹿……」
海鳴りが聞こえた。ひどく寒かったのに、それがどうでもよかった。闇の向こうの男は、沖矢昴の顔で、赤井秀一の声で、狙撃手の気配で、ただそこにいる。
ふと、キスがしたいな、と思った。まぶたを下ろして、宵闇と沈黙に包まれて、曖昧なキスがしたい。死にゆく男への手向けに、さびしい男への慰めに、このくちびるはならないだろうか。なってほしい。僕はそれになりたい。沖矢昴を殺したのも赤井秀一を甦らせたのも僕なのに、えもいわれぬさびしさを感じていた。さびしいのは僕の方なのだ。沖矢昴が嫌いだった。……だから、決してどうでもいい存在ではなかった。
「……そんな顔をするな」
「見えてないくせに」
男は言い返さなかった。
どのくらいそうしていたかわからなかった。隣りにいるはずの男は何も言わず、僕はただ星空を見ていた。遅々と回転する空を、不思議といつまでも見ていられる気がした。静かで、寒くて、死んでいるような気がした。
「……零」
その声だ。その一言で、僕は自分が生きていることを思い出す。
「車に戻ろうか」
「……昴」
男の方を向いてそう言った。そういえば彼は年下の男なのだった。彼に向かって手を伸ばし、首筋をなでる。変声機にふれ、彼が押していたスイッチを押す。
「何を……」
その声は間違いなく沖矢昴のものだった。
沖矢昴を凝視すると、彼の輪郭がわかった。彼の瞳がわかって、彼のくちびるがわかった。僕らの間の距離をつらぬく何かを彼が持たないというのなら、僕がキスを仕掛けるべきだ。僕のくちびるをそれとすべきだ。そう思った。だから僕はそれを為した。踏み出した一歩の足音が頭蓋の中に響いた。彼のまばたきの音が聞こえる気がした。それくらい静かなくちづけだった。
くちびるを離す。大嫌いな沖矢昴の顔。彼の髪色はどこか彼女に似ている。僕の初恋のひとに。そしてその人の娘に。多分僕らはふたりとも馬鹿なのだろう。そうする彼も、それに気づく僕も。
――これはさよならのキスだよ、沖矢昴さん。
そうして僕は再び変声機を撫でた。このまま絞め殺してしまおうかと思った。けれどこの男は、僕がそれをしたい姿ではなかった。男は目を閉じて死を甘受していた。あるいは細目で見ているのかもしれなかった。スイッチを押した。彼の声が喪われた。
ふたりで車に乗り込んだ。狭苦しいスバルの車内。ついさっきふたりで殺した男の胎内にいるような、感傷的で馬鹿げた錯覚。
フロントガラスを見遣る。硝子越しの綺羅星。生の星空でもプラネタリウムでもない、中途半端な場所だった。きっと、僕らに似合いの。
エンジン音と振動が夜明けの予感をもたらす。太陽はまだ見えない。
「どこまでお届けしましょうか」
「ポアロまでお願いします」
その近くに自分の車を停めていた。一度荷物を取りに戻らなければならない。僕が持っているのは財布に携帯、小銃、それにいとしい男がひとりきりなのだから。僕はそれだけでは生きてゆけない。
星が燃え尽きて、それを地球に暮らす人々が知るまでに一体何年かかるだろう。放たれた光が途切れても、それが地球に届くのはずっと先のことだ。米花町の人々がひとりの男の死に気づくのはいつになるだろう。彼はゆるやかに死んでゆく。
僕と彼だけが、今この瞬間、ひとつの星が燃え尽きたことを知っている。
海沿いを暫く走り、やがて遠ざかる。山並みは闇に溶けて見えず、水平線はどこまでも曖昧になっていた。けれど朝日はもうすぐそこにある。数時間後には、鮮烈な陽光が月と星の光を塗り潰すだろう。曖昧なのは今だけだ。
きっと今夜の降谷零は、赤井秀一を迎えにゆくだろう。

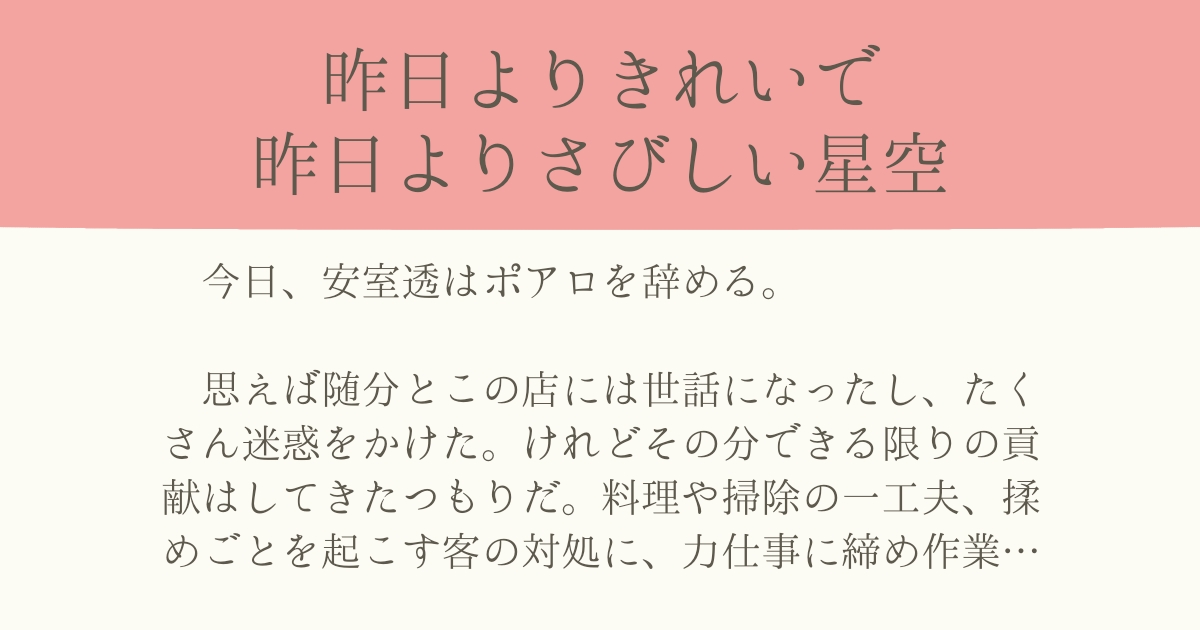
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます