赤安:ぬいの見えるようになった赤井が降谷と再会する話です
そのバーには、ひとりの男のためだけの予約席がある。カウンター席の奥から二番目。常にRESERVEDの札が立てられたその席に、彼だけが堂々と腰掛けることを許されている。
彼がそこを訪れるのはまったくの不定期だった。何日も続けてくることもあるし、丸一ヶ月訪れないこともある。しばしば不規則な生活を強いられるような仕事をしているのか、あるいは単に気まぐれな性分なのか、その場の誰も知ることはなかった。
彼、とは何者なのか?
彼はその街の夜の都市伝説のようなものだ。カウンターのいちばん奥の席に座った客は、彼に一杯のバーボンを奢る。ある者は無言で、ある者は饒舌に、彼を見つめ、その瞳を乞う。彼はバーボンをひとくち舐めると、それに応える。何もかもを見抜いてしまう透きとおるような瞳で、相手を一瞥し、口を開く。
「受験期の息子は本当に行きたい大学を黙っている」
「確かに夫は浮気しているが、そのどれもがワンナイト・ラブだ」
「彼女の借金はそろそろ桁が増える。金融業者は今のところ三つ」
彼は――俗にいう霊能力者だと言われていた。
彼の名前を知る者はこのバーにはいない。年齢も職業も、彼のすべてが謎だった。悩める人々はしばしば「どうしてわかるの?」と彼に尋ねたが、彼は黙って酒を飲み、煙に巻くことが大半だった。
「聖書に載っているようなものが見えているわけじゃない」
「エクソシストというわけじゃない。悪魔祓いは専門外だ」
「幽霊なんてものでもない」
「ただ、ちいさな探偵の話を聞いているだけだ」
人々が彼の能力について詳しく知ることはなかった。しかし彼がにおわせる能力の実態は、彼を信用させるに足るものだったし、彼もそれを狙ってこぼしているらしかった。
彼は決してアドバイスやカウンセリングをしなかった。いつだって、ただ彼らの知りたいことを簡潔に教えるだけだった。たとえそれだけであったとしても、きっと一杯の酒は安すぎる。だというのに、彼はそれでいいらしかった。

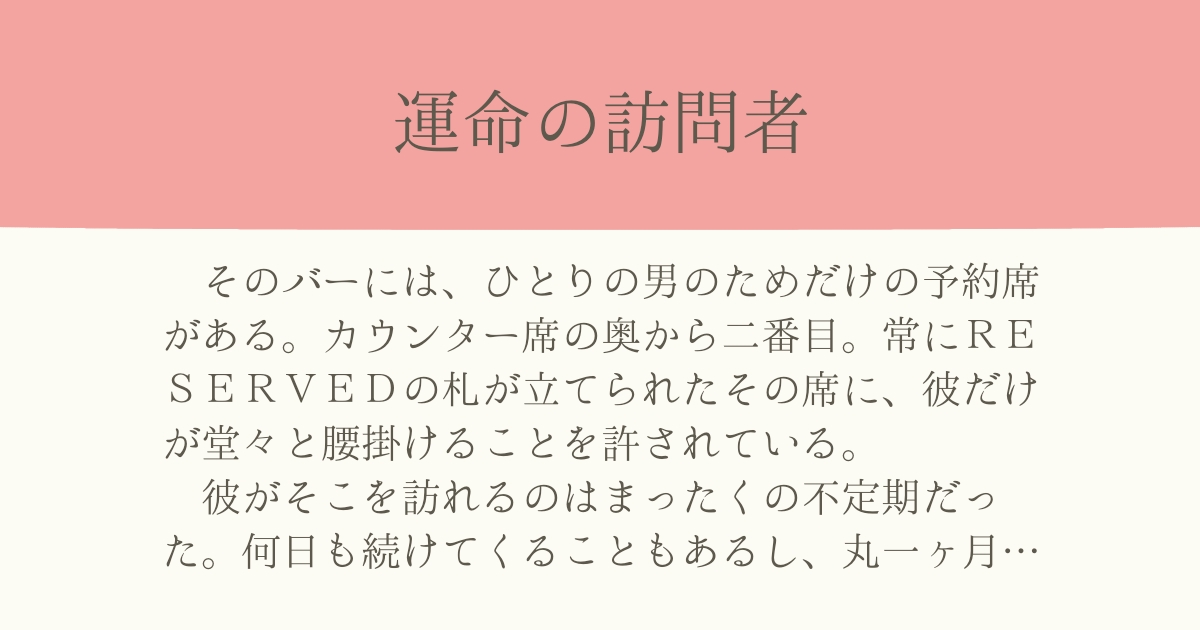
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます