一年前のことだ。
暫く日本に滞在していた赤井秀一は、結局、FBI捜査官としてアメリカで過ごすことを選んだ。彼の家族は日本に残るようだったし、赤井としても、FBIという仕事はあくまでも手段に過ぎなかったのでさしたる未練はなかった。日本でも、アメリカでも、あるいはシリアの戦場でも、赤井はどこだってなんだってよかった。けれど、彼は――降谷零はこれからも日本の捜査官であり続けるのだろうと思ったとき、自然と、自分もまだ捜査官でいようと決めた。だから、太平洋を越えた。彼に電話番号を一方的に押し付けて。
あれから一度も連絡は来ていない。
そしてD.C.の自宅で眠り、目覚めた赤井の世界は、以前より幾分やかましいものになっていた。
『おまえ、おれのことが見えているのか。丁度いい。洗濯してくれないか。ああ、洗濯と言ってもランドリーにぶち込むんじゃあない。洗面台に清潔な水をためて幾らかの洗剤を溶かして揉み洗いだ。仕上げの柔軟剤も忘れるなよ。ライフルだと思ってやさしくするんだ』
それは、布と綿でできているとしか思えない、ちいさなぬいぐるみだった。かわいい口を開くことなく、しかし流暢に人の言葉を喋っていて、どこから声が出ているのかわからない。ポリエステルの瞳がすべてを見透かすように光っていた。短い四肢をぱたぱたと動かす様子からは、明確に意志が宿っていることが感じられた。その光景はどこか不気味で、赤井はすばやく枕の下から銃を取り出して構えた。天気のよい朝、ベッドの上でのことである。
『まあ聞け、昨日の朝食は珈琲一杯で夕食はバーボン一杯、今朝は黒のドルガバ一枚のキザ野郎。おれのことを撃ってもおまえが大家に怒られるだけだ。大体おまえ、自分に似た人形を撃つことに躊躇はないのか? ぬいぐるみとか昔は好きだったろ』
まったく奇妙な人形だった。言われてみれば、それは確かにどこか赤井に似ていた。そしてなぜだかよく喋り、昨日の食事とも呼べない食事から下着の詳細まで、赤井についてどうでもいいことをよく知っていた。赤井はまず幻覚を疑った。自分の内から発生したものであるならば、自分のほぼ破綻していると言っていい生活が露呈しているのも頷ける。精神に支障をきたしてしまったのは残念だが、そうなってもおかしくはない半生だった自覚はある。
『街に出ればわかることだが先に教えておいてやろう。すべての人はその肩におれらを乗せているし、おまえもまた例外ではない。見えるか見えないかの違いだけだ』
「……お前は、誰……いや、何者だ?」
『〈ぬい〉だ。おれたちはそう名乗るし、先人たちもそう呼んでいた』
「〈ぬい〉、お前が事実を喋っていると仮定して、突然それが俺に見えるようになったのはなぜだ」
『……ひとつ教えてやろう。〈ぬい〉は嘘をつかない。人間と違ってな』
突然現れて赤井を煙に巻くこの〈ぬい〉の声を、赤井はどこかで聞いたことがある。
* * *
昼下がり、赤井は成田国際空港に降り立っていた。一年振りの日本だった。弟の結婚式を三日後に控えた来日だった。
空港には様々な人がいる。それは至極当然のことで、彼らがみな肩や頭に〈ぬい〉を乗せていることも、赤井にとってはすっかり日常になっていた。
喫煙所には数名の先客がいた。日本人らしきサラリーマンがふたり、スーツ姿のゲルマン系の男がひとり、ショートパンツからきれいな脚がすらりと伸びた東南アジア系の女がひとり。四人とも肩に〈ぬい〉を乗せている。
『こんにちは』
『こんにちは』
サラリーマンの〈ぬい〉同士が挨拶を交わしていた。〈ぬい〉の世界はいつだってシンプルだ。挨拶をすれば友人になる。彼らはもう機内食や異国の話で和やかに談笑していた。人間には、いや、すくなくとも赤井には真似し難いことだった。けれどきっと彼なら……あの懐かしき安室透なら、あんなふうに簡単に誰とでも打ち解けてしまえるのだろう。そう考えると、自分だけが彼の熾烈な憎悪を獲得していることは、どうにも光栄なことに思えた。
『海外出張が多くて参りますよ』
『まったくです。もしかすると、ここでまたお会いできるかもしれませんね』
『またいつか』
『ええ、またいつか』
人間は黙って紫煙を吐くだけの喫煙所で、〈ぬい〉だけが楽しげに出会い、別れた。
連絡先さえ知らないのに、彼に会いたいと思った。
ホテルのチェックインを済ませた赤井は、家族に来日の一報を入れるとスマートフォンをしまった。江戸川コナン――工藤新一に彼の連絡先を尋ねようかとも思ったが、知っているのか怪しいし、自分のためにあのボウヤが責められるようなことがあっては酷だろう。夜を待って警察庁に向かうことにした。報われる保障もなければ必要もない賭けだった。
〈ぬい〉は赤井より先にベッドに飛び込んで、スプリングで飛び跳ねて遊んでいた。彼の中にも綿が詰まっているはずだというのに、何がそんなに楽しいのだろう。そういえば、自分がベッドで跳ねて遊んでいたのは何歳頃までだったろうか――赤井はふと思った。遠い幻だ。
すこし眠り、目覚めると、部屋がうっすら赤かった。東都の薄暮はうつくしかった。思い返せばD.C.のそれもそうなのだろう。あちらにいるときは空模様をさして気にしていない自分に気がついた。彼の守る日本だから、きっとこんなにもうつくしい。
『感傷的だな。普段は夕焼けなんて見もしないくせに、そんなに見惚れて』
〈ぬい〉はからかうように言った。赤井は返事をせずに腰を上げた。そろそろ警察庁に向かってもよい時間だったし、何よりこの部屋からでは夕陽がよく見えなかった。
『日本で暮らせば毎日のようにこんな風景が見られる。家族にも簡単に会える。どうしておまえはアメリカにいるんだ?』
赤井は〈ぬい〉の質問に虚を衝かれたような気がした。あの組織に片を付け、父親を追うという目的まで達成してしまった今、自分には意志や信念と呼べるものが欠けている。それは誰より赤井自身が自覚していた。
「……俺が技量のあるスナイパーで、降谷くんが日本屈指の捜査官だからだ」
だから、そうとしか言いようがなかった。〈ぬい〉の表情が変わることはない。赤井がジャケットを羽織るのを見て、〈ぬい〉は彼の肩に飛び乗った。
* * *
再会は赤井の予想よりずっと早くにもたらされた。来日二日目の夕方だった。
「赤、井……」
まるきり不審者の様相で門の外から降谷の愛車を見つめていた赤井のことを、赤井が何も言わずとも降谷は見つけた。見つけてくれた。一瞬呆けたような顔をした降谷は、すぐに不敵な笑みを浮かべた。
「随分とお早い再会ですね。てっきり死んだかと思ってましたよ」
降谷は愛車から離れて赤井のほうへ歩み寄った。ピンと伸びた背筋、軽やかな足取り。何もかも、あの頃と変わらない。
「本当に死んでいたら、放っておいてくれないくせに」
そう言うと、降谷は何かを堪えるような顔をして、そうしてまた元の微笑に戻った。彼の心が揺れて、赤井は満足した。
「ま、墓くらいは掘り返しに行ったでしょうね」
「……熱烈な墓参りだな」
今度こそ降谷は、赤井を睨みつけた。
「で? どうして日本に? FBIがしゃしゃり出るような案件は僕の耳には入ってませんよ」
「だろうな。弟の結婚式だ。来週には帰る」
「ああ、太閤名人の」
「……よく知ってるな」
すっと降谷の目が細められた。
「知っているということを隠す必要がないですから。……あなたと違ってね」
降谷の脳裏に今は亡き男がいることは、赤井にもわかった。意地が悪い。しかし彼にはその程度の意趣返しは許されるべきだった。
「ここに居られると迷惑なんですが……」
降谷の視線がRX−7を指した。
「そう言ってくれると嬉しいよ」
「何も言ってない」
太陽が沈んだ。
その刹那、赤井はようやく違和感に気づいた。彼が何も変わっていないことこそが違和感の正体だったのだ。
降谷の肩には、〈ぬい〉が乗っていなかった。
網の上で肉が焼けている。降谷が――おそらくは他の警察関係者も――懇意にしているという個人経営の焼肉屋らしかった。いくつかの肉と米、それからウーロン茶を頼んだのち、彼は言った。
「僕は焼肉でも白米を食べたいタイプなんですよね。そういえば、むかし一緒に焼肉に行ったの、覚えてます?」
「ああ。薄汚い店だった」
「そのわりに家族連れが多くて。実際のところいったいなんの肉なんだよって、三人で」
三人。彼がなんでもないように口にするのが、赤井にはつらかった。赤井が秘匿していた彼の罪を、彼はいつの間にか手に入れていて、しっかりとした足取りで未来に向かって歩いていた。赤井だけがその衝撃でたたらを踏んで、今もそのまま踊り続けている。
「結局、連絡はくれなかったな」
「する理由がないので」
一年半前に彼に渡した電話番号について尋ねたが、彼の返事は素っ気なかった。
〈ぬい〉がテーブルの上をよちよちと歩き、降谷の方に向かった。そしてテーブルの上に置かれていた彼の手にふれて、慈しむように頬を寄せた。
降谷の視線が一瞬〈ぬい〉に注がれたのを、赤井は見逃さなかった。まさか。そんなはずは。だとすれば彼の〈ぬい〉にいったい何が。彼はそれに気づいているのか。
降谷の目が探るように赤井を見て、ふたりの目が合って、逸れた。しかし何も起こらず、ふたりはまた他愛ない話をして肉を焼いた。ポリエステルの瞳だけが、まっすぐ降谷を見つめていた。
「どうしてあんなところに?」
牛カルビを嚥下した彼は、そう言って今度こそ赤井をまっすぐ見つめた。赤井はいつだってこの目が恋しかった。ふいにそれを自覚してしまった。信念と狂気の光を宿らせ、爛々と輝く青い瞳。これが自分に注がれると、どこかが満たされるような気がする。
「君に会いたくて」
降谷の箸が宙で止まった。彼は赤井には読み解き難い表情をしていた。あの頃より――彼が赤井の秘密を知ってしまう前より、彼の表情は難しくなった。赤井はそう思っていた。
「……それは、遠回しな希死念慮なのか?」
赤井の肌が歓喜に震えた。赤井にとって、降谷の殺意にまさる愛撫はこの世に存在しなかった。彼はまだ、赤井を想ってくれている。
「かもしれんな」
「……お前のそういうところが腹立たしいんだよ、赤井秀一」
降谷はまた、何かを堪えるような顔をしていた。食べ頃の肉が炙られている。
* * *
結婚式は素晴らしかった。幸福には様々な形があるが、中でも結婚式はとりわけわかりやすい。しかし赤井は、改めて自分には無縁だと思った。こういう幸福は、自分には向かない。
にぎやかな歓声が心地よく、青空がどこまでも澄み渡っていた。絵に描いたような快晴。――まるで彼の瞳のような。
赤井はふと気づいた。気づいてしまった。青空をきれいだと思ったことなどこれまで一度もなかった。それはただ青いだけの空だった。けれど今なら、空気に散らばる青いきらめきが何もかもわかる。すべて彼のせいなのだ。彼の瞳がうつくしいから、今日の空がうつくしい。空も海も何もかも、この世のすべての透きとおるブルーが、今やまばゆく輝いている。
赤井は、ようやく、本当の意味で、この結婚式に列席できた気がした。無性に彼に会いたかった。
『降谷零くん』
〈ぬい〉がぽつりと呟いた。それは空を見上げていた。〈ぬい〉が人の名前を呼ぶのを、赤井ははじめて耳にした。
〈ぬい〉は嘘をつかない。
* * *
「今夜、会えないだろうか」
翌日、ホテルの一室。結局、赤井のほうから連絡した。彼は三コールで出た。先日手にした彼の番号は嘘ではなかったが、おそらく本当でもないだろう。
「いいですよ。……僕の家で、夕食でも食べます?」
「……いいのか?」
「……いいですよ」
いいですよ。降谷はそう言って赤井を許した。降谷の感情は見えなかった。
「十九時頃に拾いに行きます。場所は任せます。それじゃあ、また」
「すまない」
それで電話は終わった。四十九秒。
ニット帽の上を〈ぬい〉が転がり、赤井の左肩にちょこんと乗った。赤井は気にせず腕を動かしスマートフォンを仕舞った。〈ぬい〉は決して落ちない。そのくせ気まぐれに降りる。どうやらそういうものらしい。
「〈ぬい〉が居ないというのは……有り得ることなのか」
『この世界にはなんだってある。おれも見たことがなかったが、それはただ見たことがなかっただけだ』
「含蓄深い言葉はいらん。お前の推理を聞かせろ。彼はどういう状態にあるんだ」
〈ぬい〉は赤井の肩を降りて鏡台に立った。そしてそのまま灰皿のそばまで歩いた。そこにはいくつかの吸殻があった。
『彼は禁煙している』
それこそ煙に巻くような比喩に思えたが、赤井は口を挟まなかった。
『〈ぬい〉は煙のようなものだ。煙が棚引けば透明なはずの空気が見える。しかし見えなくとも空気はある。……それでも彼は、その空気を見たくないのだろう』
赤井には〈ぬい〉の言わんとすることがよくわからなかった。ただ無性に煙草が吸いたくなって、それとマッチに手を伸ばした。灰皿と〈ぬい〉を見て、顔をあげると、鏡の中の自分と目が合った。
「降谷零くん、か……」
溶けながら昇る煙は沈黙している。
「ここがいちばん調味料をたくさん置いてあるので。狭いですけど」
彼の招いた家は、決して広くはないアパートの一室だった。物がすくなく、畳張りの居間にはベッドとテーブル、それからギターがあるだけ。口ぶりからして、彼はここ以外にも家を持っているようだった。彼が本当に安らげる家はどこにあるのだろう。赤井はふと思ったが、邪魔するよ、とだけ言った。
「和食、嫌いじゃないですよね?」
「嫌いと言ったらどうなるんだ」
「好きにさせてみせる」
「……流石、君の日本だ」
降谷の表情は、どこかうれしそうだった。愛想笑いでないといい。赤井は柄にもなく願った。死地でさえ何かを願うことなどしないのに。
降谷の用意した料理の名前は赤井にはわからなかった。元来、赤井は食に対する関心が薄かった。
これは何という魚だ? 鰤ですよ。酒粕と酒、それから味噌を揉んで漬けるんです。あなた漬け焼きって食べたことあります? いや、多分はじめてだ。ふうん。これは? きんぴらごぼう。食べたことくらいあるでしょう? どうだったかな。こんなにうまいのははじめてだよ。この味噌汁にはなめこが入っているのか。ええ。なめこは知ってるのかよ。ああ、前に食べて嫌いだと思った記憶がある。……そのわりに、随分箸が進んでますね。うまいからな。
「納得いかないな」
互いの茶碗がきれいに空になったところで、降谷が箸を置いた。
「いつもより精細を欠くというか……すこしずつ狂ってる。これが僕の本気と思わないでください」
一拍置いて、赤井はようやくそれが料理の味の話であると気づいた。赤井にとってそれは本当においしい料理で、だから彼の言わんとすることが一瞬わからなかったのだった。
『いいじゃないか、家庭料理』
赤井が言葉を探していると、赤井の耳元で声がした。肩に乗った〈ぬい〉だ。降谷の耳は明らかにそれを捉えていた。赤井は確信した。降谷には〈ぬい〉が見えている。
『これ以上はプロの料理だ。家庭料理の域を超える』
赤井が顔を上げると、降谷はここ数日で最も苦しそうな顔をしていた。固く目を閉じ、眉を寄せ、くちびるはすこし震えていた。……かわいそうだ、と思った。はっきりとした理由はわからなかったが、赤井は、赤井の〈ぬい〉は、きっと残酷だった。愛撫のように薄っすらと、しかし降り積もる自覚があった。彼はおそらく、家庭料理を知らない。
「すこし待っていてください。すぐに戻ります」
そう言って降谷は立ち上がり、車のキーを手に取ると玄関を出ていった。彼の姿が見えなくなった瞬間、煙草が吸いたいと思った。
五分と待たせずに彼は帰ってきた。そのてのひらに、彼によく似た〈ぬい〉を乗せて。
『あかい』
降谷の〈ぬい〉はそれだけを言った。たったそれだけ。声変わり前の少年の声。赤井は殴られるように理解した。これは子供の頃の彼の声だ。彼の〈ぬい〉も、自分の〈ぬい〉も、きっと子供の頃と同じ声で喋るのだ。〈ぬい〉はそういうものなのだ。
『あかい、あかい』
赤井は昨日の結婚式を思い出していた。青い空。〈ぬい〉の漏らした彼の名前。
「やっぱり、あなたの〈ぬい〉もよく喋るんですね。……喋らないのは、僕の〈ぬい〉だけ」
降谷の顔には諦観が浮かんでいた。それは赤井にもはっきりわかった。彼は彼の車にずっと〈ぬい〉を閉じ込めていたのだろう。〈ぬい〉の声を聞きたくなくて。
「この一年、たくさんの〈ぬい〉の話を聞いてきました。みんな朗らかでおしゃべりで、探偵のようになんでも知っているくせに、子供みたいに単純だった。……僕の〈ぬい〉だけが、お前の名前以外、何も言わない!」
赤井は静かに高揚していた。あんなに饒舌で他愛ない会話を愛する彼の〈ぬい〉が、たったひとつ、自分の名前だけを繰り返し呼んでいるなんて! 赤井はきっとこういう降谷をずっと求めていたのだ。彼だけが決して赤井を諦めず、彼だけが赤井の墓を暴く。水が染み込むように全身がよろこびで満ちるのがわかった。彼だけが、赤井をこんなふうにする。まるで恋する乙女みたいに。
見ると、降谷の腕がかすかに震えていた。次の瞬間、赤井は口を開いていた。
『降谷くん』
「降谷くん」
ふたつの声がきれいに重なった。変声期を経る前と後のひとりの男の声が、ぴたりと。赤井は降谷の手を取って、その上の〈ぬい〉をそっと撫でた。赤井の腕を伝って肩から手に降りてきたもうひとつの〈ぬい〉は、降谷の〈ぬい〉をみじかい腕で抱きしめた。それを見て、赤井はようやく、自分が彼を抱きしめたいのだということに気づいた。
ところが、降谷の〈ぬい〉は赤井の〈ぬい〉を突き飛ばし、彼らは連れ立って畳に転落した。そして勢いよく――といってもちいさな足でてぽてぽと――赤井の〈ぬい〉にぶつかった。どうやら喧嘩をしたいらしかった。しかし所詮はぬいぐるみだ。じゃれあっているようにしか見えない。だから、どこか不気味で、すこしかわいいだけだった。赤井の手は降谷から離れていた。
「君も、一年前から見えるようになったのか」
結局、赤井はそんなことを口にした。それは明らかに至るべき真実への迂回路だった。もっと他に話すべきことがあるはずだった。
「……はい。なぜなのかは、未だにわかりませんが」
「俺もだ」
足元でじゃれあう〈ぬい〉の気配を感じながら、ふたりの男は部屋で立ち尽くしていた。
こういうとき、最初の一歩を踏み出すのが早いのは降谷だった。
「……僕は、あなたを追いかけたかったんだと思います。多分、あなたのことが懐かしかった」
降谷はもう、まっすぐ赤井を見つめていた。この瞳だ。赤井はいつだってこの瞳が恋しい。温度が上がれば上がるほど透明度を増してゆく、この世で最も尊いブルー。
「そのわりに、連絡はしてくれなかったな。待っていたのに」
一瞬の間。
「さびしかったよ」
「うそつき」
降谷は静かに、しかし間髪を入れず糾弾した。かつて赤井は下手なうそをついた。けれどそれは、今や確かに真実だった。
「本当のことだ。日本に来て、やっとそれがわかった。俺は今までさびしい男だったんだよ」
へえ、と降谷は言った。何かを考えているらしかった。それを隠そうともしない沈黙はあるのに、赤井はどうあっても彼の頭の中を覗けなかった。覗けたことなど一度もなかった。
「連絡しないほうが、正しく会えると思ったんです」
降谷は〈ぬい〉たちを避けながら歩いてベッドに腰掛けた。両膝にそれぞれ肘を乗せ、手を組み、そこに顎を置く。赤井は畳に座り込んでベッドに凭れた。降谷は特に咎めなかった。〈ぬい〉は依然として動き回っている。子供のような体力だった。
「正しく?」
「そう。会うか会わないか、あなたにまったく委ねてしまうほうが、きっと正しい」
「あの頃はあんなに追いかけてくれたのに?」
それがうれしかったのに。
「……だって赤井、向こうで元気に生きてるでしょう。追いかけて、会って、どうするんだよ。俺はお前と一緒に居たいわけじゃない」
赤井は何も言えなかった。それはまったくそうだった。
〈ぬい〉が遊んでいる。
「俺と君も、あんなふうに遊べばいいんじゃないか」
「……笑えるな」
「君との食事は楽しい。君はどうだ。降谷くん」
長い沈黙があった。今日の降谷はよく黙った。赤井はそれがなんとなくうれしかった。自分の前での降谷が平素の彼とは違うということに、言いしれぬよろこびがあった。
「楽しかったですよ。それは確かだ。けれど同時に、どうしようもなく腹立たしい」
駆け回る〈ぬい〉同士が正面からぶつかった。それを見た赤井は、次に彼と目が合ったら、キスしたっていいかもしれないな、と思った。彼は一先ず食器を洗うことにした。やらせてほしいと自然に思えた。すくなくともその程度には、降谷との関係を終わらせたくなかった。降谷はすみません、と言って、赤井を止めはしなかった。毒を仕込んだりはしないさ、と赤井は笑って、降谷はその場を動かなかった。
赤井が戻る頃、〈ぬい〉は並んで窓越しの星空を眺めていた。降谷はその光景を見ているようだった。
「赤井」
降谷は赤井を見なかった。
「僕はあなたと居ると、自分が自分でなくなるようで、それは……とても、嫌です。それでも……」
彼はそこで言葉を切った。赤井は口を挟まなかった。彼は待つのが得意だった。いついかなるときでも、今この瞬間も。
「それでも、あなたはきっと一生、僕の中から消えない。もう手遅れで、ここはもうそういう世界なんだ」
〈ぬい〉は空気を可視化する煙。赤井の〈ぬい〉はそう言った。降谷は、自分が赤井を求めていることを知らしめる〈ぬい〉が嫌だったのかもしれなかった。
「俺は君に何度もよろこびをもらったよ。俺も君の消えない世界を生きている。君は嫌かもしれないが、俺は君といると楽しい。……君の怒りが、いつだって俺はうれしかったんだ」
赤井はつい先日、結婚式の青空を見上げてようやくそれに気づいたばかりだ。降谷はいったいいつからこんな絶望――彼にとってはそうなのだろう――の中で生きていたのだろう。〈ぬい〉の現れたときからだろうか。それとも、あるいはそれよりずっと前から。けれど赤井には、それがいとおしくて堪らないのだ。
「これも君を怒らせるだろうが、俺は今とても君にキスがしたいよ。そういう気持ちなんだ」
降谷の心が赤井にはわからなかった。しかしそれでも自分の欲望をぶつけるだけの傲慢さを、赤井は持っていた。
降谷の肩が震えていた。
「本当に腹立たしい男だな!」
赤井のほうを振り返った彼は、そう言いながらも清々しい笑顔だった。すっくと立ち上がった彼は、その勢いのまま赤井の眼の前にやってきて、にやりと笑ってくちづけた。容赦なく舌を使われて、負けじと赤井もそれに応えようとした。しかし、キスでマウントを取り合う難しさを悟ると、すぐに降谷のなすがまま、流されることにした。どうやらそれも、彼を怒らせたらしかった。くちびるを離した彼の眉は、きれいに釣り上がっていた。怒ったときの彼の顔が、赤井はどうしようもなく好きだった。
降谷の肩越しに〈ぬい〉が見えた。彼らは何事かをささやきあっているようだった。赤井には逆立ちしたってわからないことが〈ぬい〉にはとっくにわかっていて、だから彼らはとうに友人になっているのだろう。いつか彼らのようになれるだろうか。赤井は思った。白髪の老爺になる頃には、あるいは。
「なあ、降谷くん。どうか地獄の果てまで追いかけてきてくれ。うっかり殺しても構わないから」
「俺の地獄はお前の影にあるんだよ、赤井。お前はいつだってそれを連れ歩いてるんだ」
――俺の楽園は君だと言ったら、きっとまた素敵な顔で怒るのだろう。
* * *
あれから何度かキスをして、結局はセックスをした。降谷は、これは悪くないな、と呟いて、またしても何かを考えているようだった。赤井が思うに、降谷はよく思考の海に潜り込むようになった。あの頃はあんなにすぐに突っかかってきたのに。これが今の距離なのかと思うとさびしいが、彼が赤井のことで思い悩んでいるのは、それはそれで気分がよかった。
目覚めて、十六時の便で帰ると告げると、そうですか、と返ってきた。よければ見送りに来てくれないか、と言うと、仕事ですとすげなく断られた。それでこそ彼だ。日本一の捜査官の彼。だから赤井は再びこうしてアメリカに降り立ち、FBI捜査官の日々に戻る。
スマートフォンの機内モードをオフにすると、着信が一件入っていた。見覚えのない番号だった。きっと彼だ。赤井はその数字を記憶に強く刻み込んだ。
D.C.はうつくしい快晴だった。降谷のおかげで青空のうつくしさを知ったことを、結局赤井は伝えていなかった。いつの日か、よく晴れた日に、彼の墓を掘り返しながら語りかけよう。これが自分だけの秘密である時間が、一日でも長いといい。降谷に殺してもいいと言ったくせに、赤井はもうそんなことを考えていた。
空を見上げ、赤井はかすかに口角を上げた。ほんのりと染み渡る寂寞に泣かず、運命を確信する僥倖に叫ばず、ただ微笑する程度には、赤井はもう大人なのだ。その肩に乗る〈ぬい〉の表情は変わらなかった。けれどぽつりと少年の声で、れい、とこぼした。

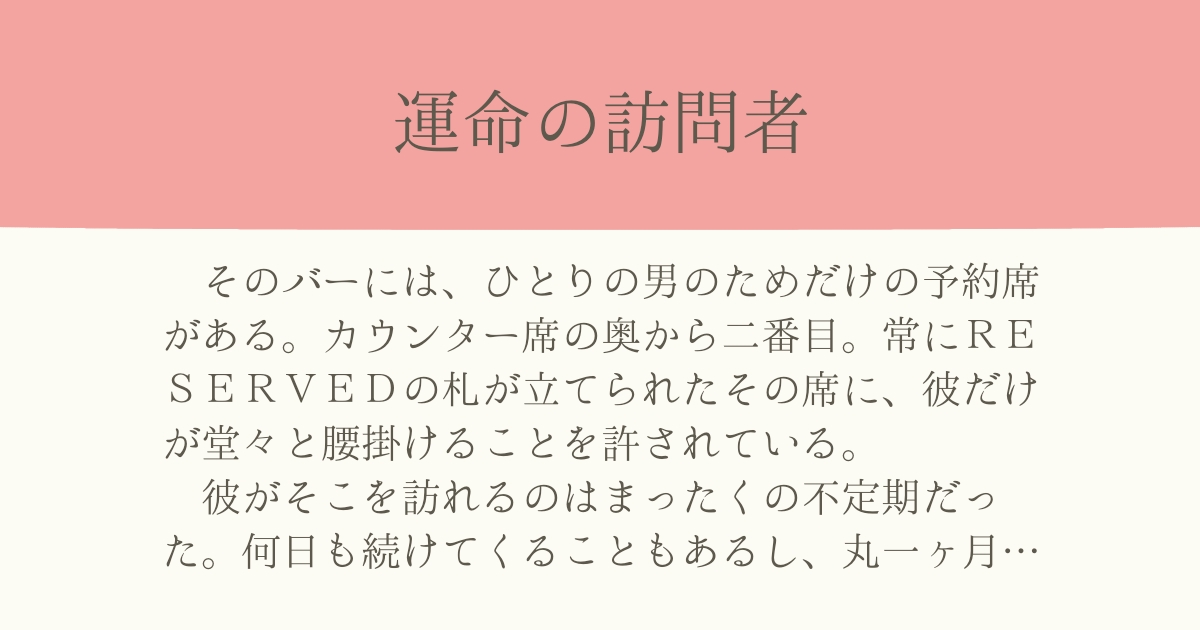
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます