赤安:赤井にかき乱される降谷の話です
・夢の中で降谷が赤井を屍姦しますが、現実では赤安です
赤井秀一とは何か?
その問いに明確に答えることは難しい。殺したいほど憎んでいる。なぜなら彼は僕の信頼を裏切ったのだから。けれど、決してそれだけではないことを、僕は今や自覚している。いや、たとえ頭に血が上って脳裏が真っ赤に染まるような瞬間があったにせよ、彼が単純な存在であったことなど、彼と出会ってから一度もなかった。
強いて言うなら、彼は……赤井秀一は、とうにふさがった傷の下に残された弾丸のような男だった。ふとした瞬間に違和をもたらし、思い出したように痛む、僕の中の異物。僕を不純物にする存在。そして、それは僕にすっかり癒着していて、たとえ彼が死んだとしても永遠に剥がれないだろう。覆水盆に返らず。ハンプティ・ダンプティ。僕は彼のために、純粋さを不可逆的に失ってしまったのだ。
* * *
夢を見た。あれは、赤井秀一が死んだと聞かされてから、幾許か経った夜だった。
何もない真っ暗な空間。塗り込められた一面の闇。そこでは上も下も右も左も曖昧で、風も匂いも温度もなくて、これは夢だとすぐにわかった。
そしてそこで、僕と彼はふたりぼっちだった。
立ち尽くす僕の足元に、果たしてその男は横たわっていた。赤井秀一。眠っているのか死んでいるのか曖昧だった。屈み込んでふれてみると、マネキンのように冷たく、しかし不思議とやわらかかった。頬には見慣れない凹凸がある。火傷の痕だろうか。脈はない。どうやらどちらかと言えば死んでいるらしい。すぐにこれは偽物だと思った。だって彼が死んでいるはずがないのだから。
だから、これは僕のまぼろし……僕だけのまぼろしだった。
僕は夜明けを待ちながら、彼を調べてみることにした。死後硬直は見られず、関節もよく動く。口元に手を当てるが、呼吸はない。顔を近付けても腐臭の類はなかった。ほのかに煙草のにおい。彼が着ているのは見たことのある服だった。記憶を辿る。これは、彼が炎に包まれて消えたあの日の服だ。間違いない。いつも似たような服ばかり着ている男だが、それでも確信がある。あの映像は既に何度も観ているのだから。
彼に跨って調べるうち、奇妙な欲望が湧いてくるのを感じた。目の前の赤井秀一は、僕に組み敷かれながら沈黙し、僕が動かせばその通りに動く、人形のような存在だ。……この夢が僕だけのまぼろしだというのなら、これは僕のもの、僕だけの赤井だ。
白状しよう。僕は彼が弾丸に撃ち抜かれ業火に焼かれゆくあのビデオで自慰をしたことがある。それも一度ではない。性欲と呼ぶにはノイズの多すぎるその衝動は、しかし勃起をもたらした。そしてそれは、驚くほどスムーズに僕を射精まで導いたのだった。
だから、彼の服を脱がせてみよう、と思うのも自然なことだった。彼をすはだかにしてみよう。
そのとき、僕は不思議なほどに冷静だった。きっと本当に彼と再会したら、こんなに穏やかな気持ちであるはずがない。彼の瞳を見てしまったら、彼の声を聞いてしまったら、こんな。
ゆるやかな憎悪を支配欲に昇華させながら、彼の服を一枚一枚剥ぎ取ってゆく。一度だって勝てたことのない男から霊長類の尊厳たる衣服を奪うのは気分がよかった。一抹のむなしさに気づいてはいたが、それは手を止めるには足りない些事だった。
靴下まですっかり取り去ってしまうと、ところどころに火傷の痕が見られるものの、懐かしさすらある男の身体が闇の中に浮かび上がった。
……彼の裸を見るのははじめてではなかった。僕は彼に抱かれたことがある。そして今夜、僕は彼を犯すのだ。
これは夢だ。わかっている。
この男のはらわたを引きずり出して暴いてやりたいと、ずっと思っていた。気障なポエットばかり抜かすくせに肝心なときに嘘をつくこの男が、いったいどんな秘密を抱えているのか。僕のリズムを乱し僕の世界を砕くこの男のすべてを、僕が征服してやりたい。だからセックスするだなんて馬鹿げていると自嘲したが、情欲の火は血管を通り淀みなく全身を巡るばかりだった。
そっと指先で腹筋の窪みをなぞった。この指先が刃物だったなら、彼の腹を切り開いて、欺瞞に満ちた肉の檻から解放された赤い血の温度を冷めきるまで慈しんでやったのに。
「赤井……秀一……」
男は愛撫に反応を見せなかった。当然だ。これは彼の死体なのだから。しかし、いくら当然だろうが、僕は苛立っていた。起きろ。お前は起きるべきだ。お前は僕を二度も裏切るというのか!
……彼の名を声に出したのは失敗だった。答えのない呼び掛けなどするものではない。ひとりぽっちが身に沁みるだけだから。とうに知っていたはずのことなのに。
手慰みにやわらかなペニスを弄んでいると、指先がぬかるみにふれた。彼の竅は僕を待っているらしかった。まったく馬鹿げた話だ。
これは夢だ。わかっている。わかっているが、諸星大、ライ、赤井秀一……彼を前にしたときの僕は、いつだって悪夢のように翻弄されていた。だったら今更なんだというのか。彼が死んでしまったはずがないのだ。だって僕は、寝ても覚めても今なおずっと、悪夢の中にいるのだから。
気づけば僕はすはだかだった。思えば最初から服を着ていたのか記憶がなかった。我ながら杜撰な夢だ。しかしだからこそ、こんなことができてしまう。ただ、もしも最初からすはだかだったのなら、その状態で服を着た赤井と向き合っていたことになる。それは癪だった。彼に劣っているみたいで。
赤井は僕を拒まなかった。冷たくぬかるんだ肉はグロテスクで、それでも僕は勃っていた。そうだ。僕は彼のこういうところが嫌いだったのだ。僕ばかりが燃え上がって、彼はいつも落ち着いたままで、僕は彼に突っかかって、彼はいなすどころか軽く受け止めてしまって。それでも腰を振れば快楽があり、刹那の優越感がある。何もかもままならない。赤井秀一が嫌いだ。僕には見えない高みの風景を見ているはずのこの男が、なぜ僕の友人の命を! なぜ!
気がつくと、彼の首元に手を伸ばしていた。無防備な首元に触れ、力を込め、そして絞める。
――ああ、僕はこの男を殺したいと思っていたのか。
でも、そうさせたのはこの男だ。彼の強烈な存在感は、僕の世界がすこしずつ褪せていっていることに気づかせてくれた。それほどまでに彼はあざやかだったのだ。その姿、その声、その生で、僕を驚かせてくれたのだ。
だから、彼があんなふうに死ぬはずがない。あんなにもぱっとしない幕引きは、彼に相応しい真実ではない。僕の世界には、未だあざやかな銀色がきらめいている。だから。
それでも、指先から生命の脈動が感じられることはなかった。
自分は失敗したということがありありとわかった。このセックスは、この夢は、僕の敗北宣言だ。彼を支配すれば、きっと忘れられると思ったのだ。けれど結局、僕は彼に勝てないし、彼を忘れることもできない。
そうであればこそ、あの男があんなに無様に曖昧に死んでしまうはずがないのだ。
吐精のリズムが感じられて、ようやく自分の鼓動に気づいた。肋骨が閉じ込めているはずの心臓は、随分と遠くにあったように思われた。いったいいつからこんなにも興奮していたのだろう。自分でもわからなかった。
呆然と彼の顔を眺めていた。誘われるようにキスをしてから、人工呼吸でもすればよかったのかもしれないと思った。この夢に迷い込んでからの彼に、あるいはあの夜あの屋上の友に。僕の悪夢は終わらない。僕にキスをくれる人はいないから。
* * *
「僕が目覚めてどうするんだよ……」
王子様のキスで、お姫様は目覚める。そんなお伽噺。これでは僕がお姫様のようだ。彼の墓を暴き偽りの眠りから覚めさせようとしているのは僕のほうだというのに。
されど悪夢は続く。
下着が濡れていることよりも、こめかみが濡れていることを認めたくなかった。
ああ、傷の下の弾丸が痛い。

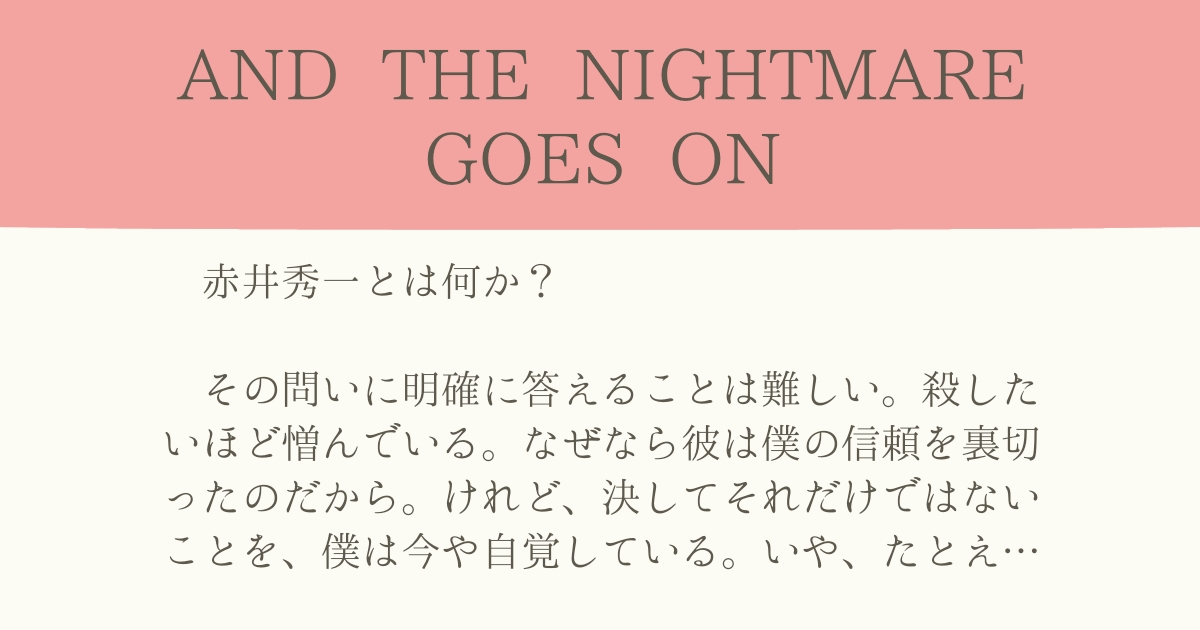
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます