そのとき、雨が降っていたことだけを、なんとなく覚えている。いや、僕に覆いかぶさる男の細く長い髪と部屋に満ちた湿った空気が、雨に似ていただけかもしれない。何はともあれ、もし僕が世界の主人公だったら、きっと雨が降っていただろう。そんな気分の夜だった。
彼とセックスするのはあれ以来だ。
「零」
目の前の男は生きていて、僕の名前を呼び、僕にお伺いを立てる。もうすっかり髪は短い。あんなに望んでいたのに、これが僕にとって喜ぶべき未来なのかどうかは、よくわからなかった。
「キスをしても?」
この男が嫌いだ、と反射的に思った。僕が彼に持てない余裕を彼は僕に持っていて、彼は生きて反応する僕を抱く。彼の存在はいつだって僕の世界から消えないのに、彼は僕を置き去りにしてあんなに長く眠っていた。
それでも僕は、したいならすればどうですか、と答えるのだ。そうするより他ないから。
彼とくちびるをあわせると、一瞬だけ、すべてを諦められるような気持ちになる。乱される自分も、彼という男も、彼と僕の間に満ちる運命も、何もかも諦めて、受け容れられるような気がする。けれどそれはほんの一瞬のことだ。くちびるを離して、まぶたを上げると、再び何もかも腹立たしくなる。やっぱりだめだ。この男が嫌いだ。僕は自分からキスをして、舌を差し出し、彼は口を開く。もう一度、すこしだけ長い刹那がはじまり、そして終わる。
服を脱いだ彼の肌には火傷の痕なんてなかった。そこには安堵もなければ落胆もない。どうでもいいことだ。彼が生きていて、透きとおるあざやかなオーラが変わらないのであれば、なんだっていい。火傷の痕が残る彼も男前ではあったけれど。
夢の中で痕があった場所を撫でていく。彼は怪訝そうな顔をしていた。それもそうだ。確信を持った手付きなのに性的な気配を微塵も感じさせない接触をしているのだから。互いにすはだかで、ベッドの上で、もう随分と前のことだけれど、セックスしたこともあるというのに。
これは現実だ。目の前の男は、僕のものではない。永遠に、そうなってはくれない。
「こら、おいたはよしてくれ」
彼の中心に手を伸ばすと、やんわりと止められた。彼は主導権を手放したくないらしかった。だろうな。あの雨の夜の僕はひどく反抗した覚えがあるが、今夜はそうしない。大人しく彼に身を委ねる。
癪だが、彼とのセックスはおそろしいほどに気持ちいいのだ。快楽の虜、なんてことはない。だが、セックスするなら彼がいい。もう嫌だ。こんなことってないだろう。
赤井秀一。彼はいい男だ。恐ろしいとさえ思う。何かを成し遂げようとするとき、こんなに頼もしい男はいない。
だが、彼は完璧ではない。僕と彼が関わるとよりいっそう……いや、彼から完璧さを奪うのは僕だ。あのときのように。あのとき――幼馴染が死んだあのときだって、僕がいなければ、彼は完璧なまま、景光を助けられたかもしれないのに。彼の抱える傷のいくつかは、僕が生んだ綻びだ。僕のせいで。けれど僕だって、彼のせいで。
一緒にいないほうがいい。また傷が増えるかもしれないのだから。けれど、離れることにも意味なんてない。出会ってしまったが最後、すべては無駄な足掻きなのだ。既に消えない傷の下に弾丸は埋め込まれてしまったのだから。僕にも、彼にも。
彼の指先が、見えない傷痕を撫でる。それだけのことで息が上がって、相性がいいんだな、とどこか冷静な自分が思う。相性がいい? 共に景光を殺したふたりが? そんな笑える話ってないだろう。ふざけるな。
色の異なる肌が吸い付き、ふれあうことが正解だと主張する。僕はそうは思わない。僕たちは今まさに間違いを犯している。それでもここは心地いい場所なのだ。
「何を考えてる?」
「あなたのことが、……嫌いだ、って……」
「そうか」
彼は楽しげに答えた。どうして彼はいつもこうなのだろう。僕ばかり乱されて、彼はなぜこんなにも。
「どうして……」
彼はしばらく僕の言葉を待っていた。僕にその先を紡ぐ意志がないことを察すると、彼のほうで喋りはじめた。
「君に愛されてるなと思って」
「僕にはお前を愛しているつもりなんてない!」
考えるより先に言葉が飛び出してきた。彼といるとこうなる。そういうところが嫌だ。年甲斐もない。自分らしくもない。自分が取るに足らない人間に成り下がったような気がする。
「君が俺のために悩んだり、苦しんだり、心を揺らして、そのかわいい顔を歪ませていると、どれほど満たされた気持ちになるか、君は知らないだろうな」
ああ、やはり、この男に出会いたくなかった!
彼の肌。彼の舌。粘膜のふれあい。グロテスクなコミュニケーション。僕と彼のコミュニケーションはいつだってグロテスクだった。セックスも所詮はその一端に過ぎない。いや、むしろセックスなんてかわいいものだ。肌の内側を探り合うよりもっとおぞましいことはある。
どうしてこの男はこんなにも尊大で傲慢で、僕をかき乱すのだろう。これが愛しているということなら、悪夢でなくてなんだというのだ。
これは夢ではないから、赤井は丁寧に僕の身体をやわらかくしてゆく。力を抜いて男を待ちながら、僕は彼を眺める。うつくしい男だ。まるで彫像のような、できすぎた男。彼のうつくしさが好きだ。僕を惑わすにふさわしいと思えるから。彼の骨。彼の肉。奇跡と努力の結晶。いい男だ。
何か他愛ないおしゃべりがしたかった。してもしなくてもいいような、何も世界を変えられないおしゃべり。なのにどんどん息が上がって、声を出したらきっと無様に掠れているだろうから、声帯をふるわせないように呼吸するばかりになる。
彼の汗がしずくになって僕の腹にこぼれた。それは他人のように冷たい。当然のことに、すこしだけ驚く。
挿れるぞ、と彼は言って僕を侵略しはじめた。キスのときはあんなにもしおらしく許可を求めたというのに、もうすっかり調子づいている。
「さびしいな……」
そう思ったときには口にしていた。僕に覆い被さる彼を見上げて、すっかり彼が短髪になっていることを実感した。僕を世界から断絶する檻のような彼の髪がすっかり失われて、それをさびしく感じる自分がいた。すっかり毒されているな、と自嘲した。情事の雰囲気に呑まれている。
「さびしい?」
「あなたの髪が……垂れてこないから」
「また伸ばそうか」
「僕のために?」
「君のために」
「……笑える、ッ、ン……」
ゆっくりと彼が腰を進め、僕の中に異物が侵入する。傷の下の弾丸に響く。僕の腹の奥底ですっかり肉と癒着した弾丸を、どうか、抉って、いや、ふれないで、もうそっとしておいて、やっぱり何もかも暴いて。
「零、つらいなら言え」
「言って……ア、ッぐ……それを聞いたあなたは……また……俺に愛されてると思うのか? そんなの、そんなの御免だ……」
堪らなくなって顔を腕で覆った。どうしようもない気分だ。どうしてこんな思いをしなくてはならないのだろう。全部、何もかも彼のせいだ。……彼と僕のせいだ。
ゆるやかな抽挿に身を委ねて、壊れた人形のように断続的に母音を発するばかりになる。なぜこんなことが気持ちいいのだろう。この世の不条理だ。
彼に腕を掴まれて無理矢理に顔を晒される。目が合う。自分は今、いったいどんな顔をしているのだろう。彼さえいなければコントロールできるはずのものなのに、彼がいるとまったくわからなくなってしまう。いや、どうせ酷い顔だ。それだけはわかっている。みっともない顔をしているに違いない。
「赤井……」
「うん?」
「くび、絞めて……」
そう言うと、赤井は動きを止めた。
「君の首を?」
「うん……」
ね、お願い。僕は甘えたようにおねだりをする。そうすれば、彼は僕の言うことを聞いてくれる。彼が僕に従順な場面はすくない。セックスは貴重な一幕だった。
彼の指が僕の喉にふれる。彼だって安全な絞め方は心得ているはずだ。何も問題はない。彼は躊躇しているようだった。僕からしてみれば、彼と寝ることも、彼に首を絞められることも、何も変わらないというのに。何もかも今更な話だというのに。彼にとっては違うらしい。
彼の指が、クッ、と、……。
頭が真っ白になる、なんて手垢のついた言葉をその身でもって味わう。気持ちいい。もうだめだ。自分がどこにいるのかもわからなくなる。ぬるい海に溺れながら、四肢がほどけて、自分が世界と溶け合うのを感じる。こんなに気持ちよくなって、ぼくはわるいこだ。
きっといま、ぼくはせかいでいちばんきもちいい。ここにぼくをみちびくのは赤井秀一だけだ。
「零!」
まただ。また、この男が、赤井秀一が、僕の世界を砕く! 僕を好き勝手に翻弄する!
「よかった、目を覚まさなかったらどうしようかと……」
「せっかく気持ちよかったのになんで起こしたんだ!」
僕は何も考えずに叫んで、彼にしがみついていた。彼の背中に腕を回しても、もうあの頃のような長髪はない。あ、こいつ、こんなときに硬くしたな、と腹の底でわかった。彼も大概、趣味が悪い。
「すまない。だが、肝が冷えたよ」
「勝手に冷やしてればいい。自分は長いこと死んでたくせに」
「……」
赤井は何も言わずに微笑した。一瞬だけ、好き、と思った。
彼とのセックスがこんなに気持ちいいのは彼を愛しているからだ、と言われたら、僕はなんて答えるのだろう。身体の相性がいいだけ? それだけで、本当にここまで昇りつめられるものだろうか。そんなふうに疑問に思ってしまう自分がいる。いずれにせよ、それはいま考えるべきことではない。もっとまともな頭のときに、彼のいないところで、考えなければならないことだ。本当に? 彼を前にしたときの僕は僕の望む僕じゃない。けれど、出会ってしまったから。
僕はもう、彼が死んでも、どこにいても、彼に出会った僕なのだ。その姿、その声、その生を、知ってしまった僕なのだ。
僕が思考に耽るのを阻止するように彼は動いた。セックスのときだけじゃない。彼はいつだってそうだ。彼が果てるまで、僕は僕の輪郭を保つことさえままならない。
「僕ね、夢を見たことがあるんです」
彼の煙草をくすねて、気怠い身体で吸っていた。彼はそれを満足げに眺めていた。ベッドの上でふたり。
「どんな夢だ?」
「死んだ赤井を抱く夢」
そう告げると、赤井は難しい顔をしてしばし沈黙した。何を考えているのだろう。別に、生きている赤井を抱きたいわけじゃないな、とぼんやり思った。すくなくとも、今は。
「一時期は……EDだったんだ」
「……え」
それはすくなからず衝撃だった。男の浪漫、男の誉を体現したようなこの男が、ED! いっそ痛快だ。かわいらしいとさえ思える。この男にもそんな繊細さがあっただなんて。
「聞かせてやろうか」
「何を」
「沖矢として潜伏しはじめてからしばらくEDだったが、治ったのは、君と観覧車の上で会ったあの夜だ」
どんな顔をしていいのかわからなかった。喜べばいいのか怒ればいいのか、自分の感情を探ることが容易ではなかった。それはつまり、どういうことなんだ? その事実を僕はどう捉えればいいんだ。
「そうか、君の夢の中では、俺は屍姦されていたのか」
呆然とする僕を置き去りに彼はどこか納得したように頷いて、僕の手から煙草を取り上げた。
* * *
赤井秀一とは何か?
その問いに明確に答えることは難しい。殺したいほど憎んでいる。なぜなら彼は僕の信頼を裏切ったのだから。けれど、決してそれだけではないことを、僕は今や自覚している。いや、たとえ頭に血が上って脳裏が真っ赤に染まるような瞬間があったにせよ、彼が単純な存在であったことなど、彼と出会ってから一度もなかった。
ときどき、彼が僕の運命のひとなのだと思うことがある。けれどそれは、運命という曖昧な箱に雑多な感情を押し込んだに過ぎない。僕と彼の運命は決してきれいではないし、不純物が紛れ込みすぎている。しかしだからこそ、神のいたずらに抗うように、僕は箱に蓋をして、日々のつとめを果たすのだ。その姿、その声、その生で、彼が再びその蓋を開くそのときまで。僕の人生、あと何度この蓋が開くのだろう。もう一生、開かなくたっていいのに。
読者よ、僕の無様な心のうちを覗いたからにはどうか墓まで沈黙してくれ。僕があなたの墓を暴くことは絶対にないから、そのときは安心して眠っていい。僕が暴いた墓は、後にも先にも彼のものだけだ。

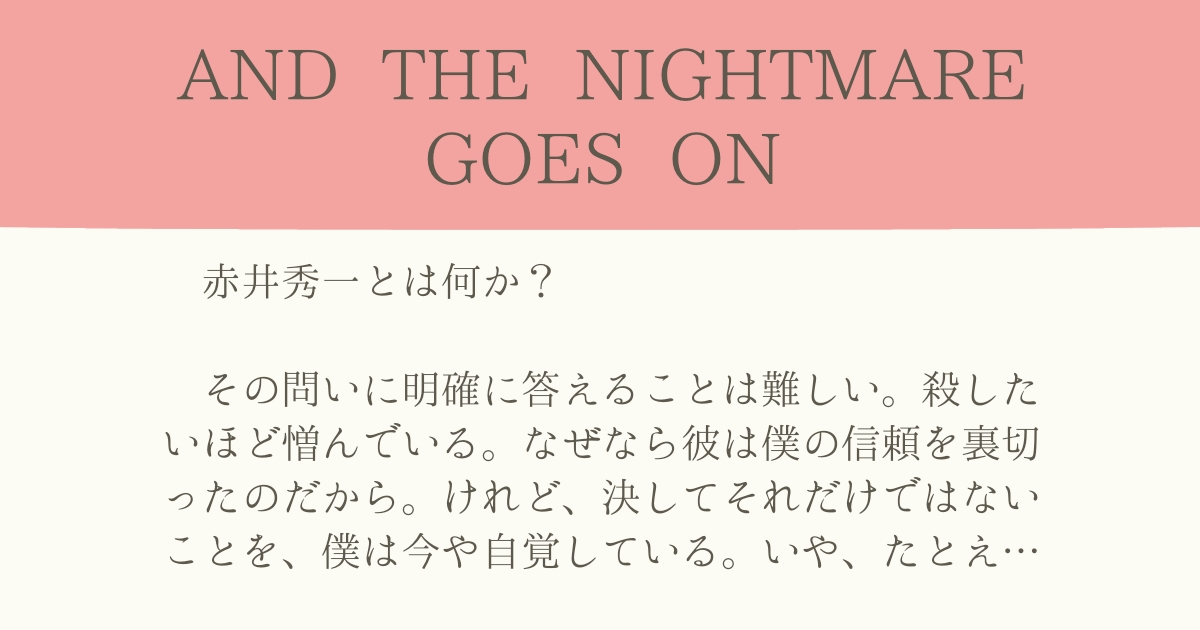
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます