赤安:タクシー運転手にでたらめの身の上話をする降谷零の話です
・作中に特定の職業や商標、施設、地名などが登場しますが、実在のものとは一切関係なく、また、それを非難・中傷する意図はありません
・作中の人物が古典的価値観に基づいた思考をすることがありますが、それを支持・推奨する意図はありません
日付を回って午前〇時三十七分、訪れたその客は、随分と若そうな男だった。
うつらうつらしていたところにコンコンとドアガラスを叩く音が聞こえ、後部座席のドアを開ける。
キャップからもれる目の醒めるような派手な金髪、こぼれんばかりに大きな青い目。それがゆるりと細められ、おやすみ中すみません、と告げた声はやわらかい。人当たりのよさそうな青年……いや、少年と呼ぶべき年齢だろうか。白のだぼついたパーカーにジーンズを履いたその姿は、どこかさびしそうな若者に見えた。
「取り敢えず渋谷方面に向かってもらえます?」
わかりました、と告げて、わたしはアクセルを踏んだ。
「……君、十代? こんな時間に出歩いて大丈夫かい」
ミラー越しの少年は遠慮がちに笑った。
「うん、ええ、大丈夫……じゃないだろうけど、遊びに行くわけじゃないから」
「へえ」
「……兄さんを迎えに行くんだ。よかったら、聞いてくれませんか。こんなこと、誰にも話せないから」
わたしのほうでは深く追求する気はなかったが、少年のほうから語りはじめた。しばしばこういうことはあった。運転手とおしゃべりしたいがためにタクシーに乗る人もいる。車内という密室と、あつらえたようなこれきりの他人。タクシーは後腐れのない語らいに丁度いいものだ。
「僕と兄さんは年が五つ離れてるんです。僕が十六で、兄さんが二十一。僕を産むときに母が死んで、僕は母を知りません。父親も僕が五歳のときに消えました」
想定よりも重い話だった。現代でも出産は完璧に安全なわけではないという。ふと母親の顔を思い出した。オリンピックまで生きると豪語する、耳の遠い母。
「兄弟ふたりを一緒に預かれる親戚なんていなくて、僕らは別々のところに引き取られたんですけど、子供の頃の僕は泣いて嫌がって。兄さんだけが僕の家族なのに、兄さんはとても冷静で、これは仕方のないことだから、いつか絶対に迎えに行くから、それまで待ってろって言ってくれて、僕は泣く泣く遠縁の家に引き取られました」
五歳の弟が十歳の兄に縋るところを想像した。弟の目に冷静に見えても、きっと兄も内心では複雑な思いを抱えていたはずだ。なのにそれだけのことを言ってみせるなんて、きっといい兄なのだろう。そう無責任に思った。
「……インスタグラムって知ってます?」
「おじさんだから詳しくはないよ。若い子が写真をたくさん載せてるやつだよね?」
「はい。兄さんもね、それをやってるんです。自分が承認した人だけに投稿を見せる形で。……僕は兄さんをフォローしてます。兄さんだけを。そして兄さんは僕を承認してくれている」
この話はどこに向かうのだろう。すこし間が空いて、少年は話を再開した。
「兄さんね、向こうの親戚と折り合いが悪かったみたいなんです。高校を出てから就いた仕事をすぐに辞めてしまって、フリーターっていうんですかね、そういうことをやって、ガラの悪い連中とつるんでるんです」
「そりゃ……難儀な話だ」
少年の視点で物語られているからこそ、なんだか兄のほうに同情してしまった。若くして死んだ母親、子供を置いて蒸発した父親、親戚の家で多感な時期を過ごす幼い子供……ありふれた悲劇かもしれないが、想像すればやはり胸が痛んだ。弟からは大きく見えただろうが、それでもほんの五歳差だ。いくら大きく見えた兄貴でも、ヒーローではない。あてどない屈折や煩悶を持て余し、期待どおりの人生を歩めないこともあるだろう。
十歳のときの約束なんて覚えているのも難しい。ましてや泣く弟を慰めるためにその場で咄嗟に取り付けた約束だ。弟は兄を裏切り者と詰るだろうが、兄は兄できっといっぱいいっぱいなのだろう。
「今ね、兄さんはATOMにいるんです」
「渋谷のATOMっていうと、クラブの?」
「そう、それです。やっぱりいろんなお客さんを乗せてるんですね」
それは渋谷のクラブだった。あまりいい印象のある場所ではない。想像上の兄の姿が一気に現実味を帯びてくるのがわかった。
「今日ね、僕の誕生日なんです」
そりゃあおめでとう、と言おうとして、言えなかった。彼にとってはめでたいばかりの日ではない。
「兄さんのインスタグラムに、ついさっきそこで撮った写真がアップされていて、それを見たら居ても立ってもいられなくなったんです。会いたい。会って殴りたい。僕を迎えに来てって言いたい。……それを言いに僕が迎えに行ったんじゃあ世話ないですけどね」
車窓の外を眺める少年の横顔が、ぞっとするほどうつくしかった。寂しげで、儚げで、これは学校でさぞもてるだろうなと思った。
「でもね、兄さんは……決して僕のことを待っていないわけじゃないと思うんです。きっと僕を拒んだりしない。僕を迎えに来てはくれないけれど、でも、僕が迎えに行くのが嫌なわけじゃないと思う。だって、僕に追われたくないんだったら、最初からインスタで僕を承認するなんてしない」
それはどうだろう、と思った。若者の文化に詳しいわけではないが、その投稿を彼だけに見せたわけでも、待ってると文章を添えたわけでもないただの写真が、本当に彼を拒まない証明になるだろうか。投稿ひとつで弟が自分を追ってくるなど、むしろ想定外のことではないだろうか。どうにも希望的観測がすぎるように思える。数十分後には、この少年は手酷く傷ついているのではないだろうか。そんな予感があった。
だが、ミラー越しに見た少年のひとみの輝きに、結局、沈黙を選んだ。
「君の親戚はこのことを知ってるのかい。なんなら、クラブの近くで待っていようか?」
「いえ、大丈夫です。おばさんたちはもちろん知りません。こっそり抜け出してきちゃいました。……仲が悪いわけじゃないけど、別によくもないっていうか、やっぱりおばさんの子供とは違うから。……いや、僕が悪いんです。僕が悪い。おばさんはすごくよくしてくれるのに、僕がいつまでもよそよそしいから……」
そんなことはない、と言いたかった。愛しても愛が返ってこないのは確かに悲しいことだが、それでも君は悪くないのだと、何か慰めを与えたかったのに、うまく言葉が出てこなかった。兄についてもそうだった。きっと君のお兄さんは君を待っていると、言いたかったけれど、どうしても言えなかった。もう二度と会わないであろうこの少年を、裏切りたくなかった。
「……ばかばかしいと思ってるでしょ」
「そんなことは……」
「自分でも思ってるから、大丈夫ですよ」
「ほんとうに、そんなことはないよ。ただ……ただ、君が傷つくような可能性を考えてしまうし、そんなことがなければいいと、思ってる」
「やさしいなあ。……ふふ、でもね、これから僕が言うことを聞いたら、きっとばかばかしいと思いますよ」
そう言って少年は、先程までのあどけなさが嘘のように、老獪な賢者の顔で妖しく微笑した。
「わかるんですよ。兄さんは僕を待ってる。血が繋がってるからじゃない。兄さんは僕が生まれる前から僕を待ってたんだ。僕が迎えを待つんじゃなくて、僕が兄さんを追いかける。これが僕と兄さんのあるべき姿なんだ。……わかるんですよ、不思議とね」
ね、ばかばかしいと思うでしょう――そう言われたが、まったくそうは思えなかった。この少年は気休めも慰めも何も求めていないのだと心底わかった。いや、それよりも先に感じたことがある。
この少年が、怖い。
「お話、聞いてくれてありがとうございます。全部うそですから、忘れてくれていいですよ。僕、ほんとうは色々と面倒が多い家のボンボンで、これから友達と合流して遊ぶだけなんで。家族と折り合いが悪いのはほんとう。でもひとりっこだから兄貴なんていません。運転手さんいい人だね。それじゃあ、いい夜を。……あ、そうそう」
すっかり混乱していると、少年は幾らか多い紙幣を出した。
「今日はね、兄さんの誕生日でもあるんです」
そう言って喧騒に向かって去っていく少年の背中を、しばらく見つめていた。白いパーカーが闇夜に溶けて、すべてが夢だったような気がした。

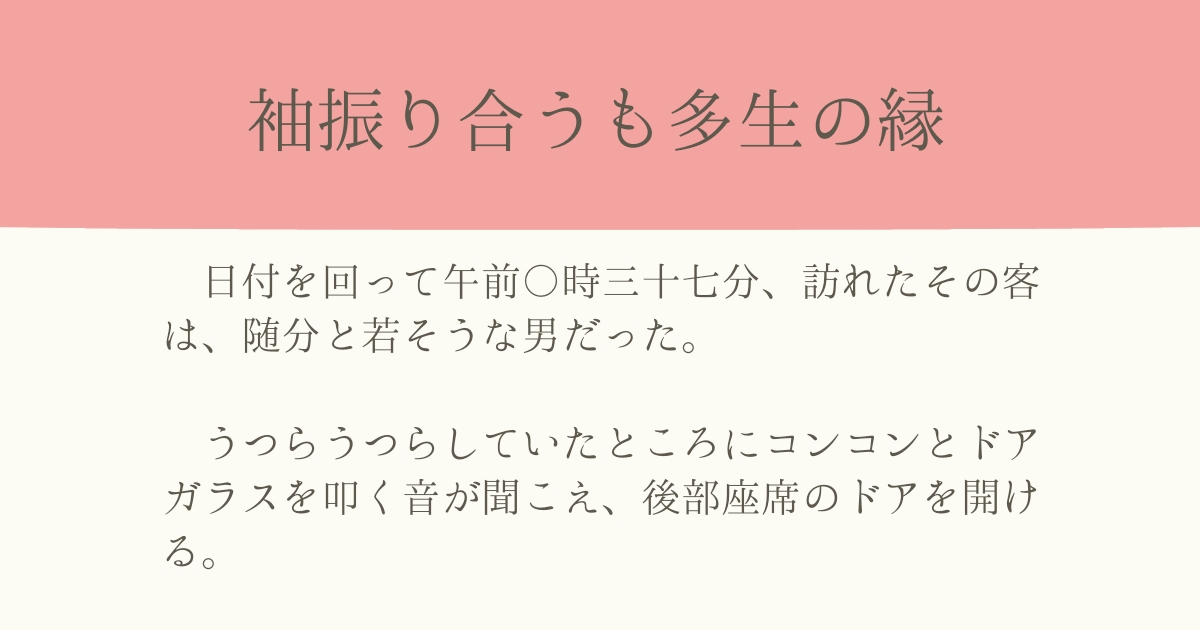
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます