冬の儚い夕焼けが終わろうという十六時四十二分、ひとりの青年がこちらに向かって手を上げた。
「こうも寒いと敵いませんね」
後部座席に乗り込んできた青年に無難な話題を振ってみた。青年は派手だが上品な服装で、しかしそれがはっきりした顔立ちによく似合っていた。
「そうですね。……でも、僕は結構好きですよ。日本の四季はそれぞれ好きです。ほんとうは歩きたかったんですけど、間に合いそうもなくて」
「はは、風流だねえ、お客さん」
青年は歌舞伎町へと告げた。軽く返事をして、アクセルを踏み込む。
「タクシーの運転手って、やっぱりお客さんとの会話は多いですか?」
「お客さん次第ですかねえ。黙って運転だけしてくれればいいって人も多いですから」
「そういうものですか。……僕、すごくおしゃべりなんですよ」
「あっはは、なんでも聞きますよ。私は喋るのも聞くのも好きですからね」
人好きのする顔に、耳障りのいい声。彼の話を聞ける人は幸福だろう。きっと聞き上手な恋人がいそうだと思った。
「僕、ホストをやってるんです」
「へえ。どうりできれいだと思った」
「女の子たちの話を聞くのは楽しいですよ。でも、自分の話を人に聞いてもらいたい気持ちもどうしてもある。……よかったら聞いてもらえませんか」
「いいねえ、なんなりとどうぞ」
素直に楽しみだった。きっと彼にはたくさん友達がいるのだろう。息子ほど歳の離れた青年に、そんなことを考えた。
「僕ね、こう見えてこの冬、帝都大を受験するんです」
「えっ、あの帝都大学? へええ、頭いいんだねえ」
「あっはは。本当は高校を卒業してすぐにでも……と思ったんですけど、お金がなくて。昼も夜も働いて、そろそろいいかなって」
不思議な青年だった。一見すると浮ついて軽薄そうだが、すくない言葉を交わすだけで聡明な人なのだろうとわかる。そしてたちまち気に入ってしまう。
ふと、とうに巣立った息子のことを想った。成績はあまりよくなかったが、手に職をつけて今では立派にやっている。きっとそのうち孫の顔も見せてくれるだろう。こんなことを言うと、気が早いよと彼は困ったように笑うのだけれど。
「奨学金とかは借りられないの?」
「大学のランクを落とせば借りられるでしょうけど、帝都大だと難しそうで。なるべく自分でなんとかしたいんです。……どうしても帝都大に行きたい理由があるんです」
「へえ、そりゃどんな」
知らない世界があるものだな、と思った。帝都大学に行けるほど成績がよくても奨学金を借りられない世界。いや、そもそも自分は奨学金について詳しいことなどとんと知らない。調べようと思ったことすらなかった。
「昔、結構ひどい事故にあって。中学三年生だったかな。今も腹に傷跡が残ってる。……僕ね、AB型のRhマイナスなんですよ。聞いたことあります?」
「ええ。なんでもとびきり数がすくないんだとか」
「そうそう。日本人のおよそ〇.五パーセントと言われています。欧米なんかだともっと多いみたいですけどね。間の悪いことに、運ばれた先の病院で血が足りなくて。すわ死亡かと思われた矢先、たまたま近くにいた人が輸血に協力してくれたんです。自分もRhマイナスだからって。すごい偶然でしょう」
「なんだかドラマみたいな展開ですね」
〇.五パーセント。ピンと来ない数字だ。学校の同学年にひとりいるかいないかといったところか。いや、もっといるものだろうか。やはり実感がわかない。ともかく、彼の血はこの日本では圧倒的マイノリティというわけだ。
「その人、帝都大の院生だったんです。今は帝都大でいくつか授業を受け持っているらしくて。どうしても彼の後を追ってみたくて。無茶をしました」
「いやはや、本当にドラマの主人公みたいだね」
「そんな、僕は……僕は主人公じゃないですよ」
青年は曖昧に笑った。どこかアンニュイな雰囲気で、そんな顔さえきれいだった。
「あれから僕、ときどき献血に行くようになったんです」
「立派ですねえ」
そのとき、ちいさな音で流していたカーラジオが耳に入った。――臓器提供にご協力ください、ACジャパン。それはどうやら彼にも聞こえたらしい。
「免許を取ってから、意志表示カードも記入したんですよ。臓器ぜんぶ提供しますって」
「そういや、私は真っ白だな。流してるあいだに散々聞いたラジオだってのに、いかんねえ。後で記入しておこう」
「それがいい。献血も楽しいですよ。お暇なときにでもぜひ行ってみてください」
「そうしましょう。しかし私ゃO型ですからね。あなたの血ほど需要はないでしょうが」
「きっと誰かの役に立ちますよ。献血も臓器提供も、自分の肉体がこの日本に希釈されて誰かの役に立つんだと思うと、……とても晴れやかな気持ちになる」
優等生のような感性だ、と思ったが口には出さなかった。きっと帝都大学を目指す前から頭がよかったのだろう。聡明で立派、容姿端麗。彼の両親はきっとしあわせだろう。今に彼はいい企業に就職して、彼らに楽をさせてあげるに違いない。
「そういや、前に乗ったお客さんがこんなことを言ってましたよ。道路は日本の血管、ってね。じゃあ私らはいま血液なわけだ」
「……素敵だ。ほんとうに、素敵な言葉ですね」
「気に入ってもらえたようなら何よりですよ」
目的地はまだ先だろうに、ここでいいですよ、と彼は言った。ホストクラブの類はもうすこし先だ。
「おかげさまで間に合いそうですし、寒さを味わって歩きます」
「ほんとお客さん、風流で頭もよくて、お袋さんにとっちゃあ、さぞ自慢の息子だろうねえ」
「どうかなあ……心配させてるから」
「うちの息子なんか、心配かけてるなんて思っちゃいないよ。そう思ってくれてるだけうれしいもんさ」
財布を探りながら彼は言った。前髪が影を落とした顔で、彼はやさしそうに微笑していた。
「ありがとうございます。でも、あなたの息子さんもきっとあなたに感謝してますよ」
「そうかねえ」
「そうですよ。……それが親子ってものでしょう」
不覚にも目頭が熱くなった。彼を降ろしたら、息子に電話してみようか。元気でやってるのか、どうか。たったそれだけのことでも。
「ありがとうねえ。なんだか私のほうが元気をもらっちゃったよ」
「あはは、お互い頑張りましょう、ということで」
「それじゃ、受験がんばってね」
「はい」
すっかり夜が更けて活気づく街に、青年は消えていった。青年が溜息のように吐いた息が白い。それが空気に溶けるのをなんとなく見届け、タクシーを走らせた。今日はいい日だ。

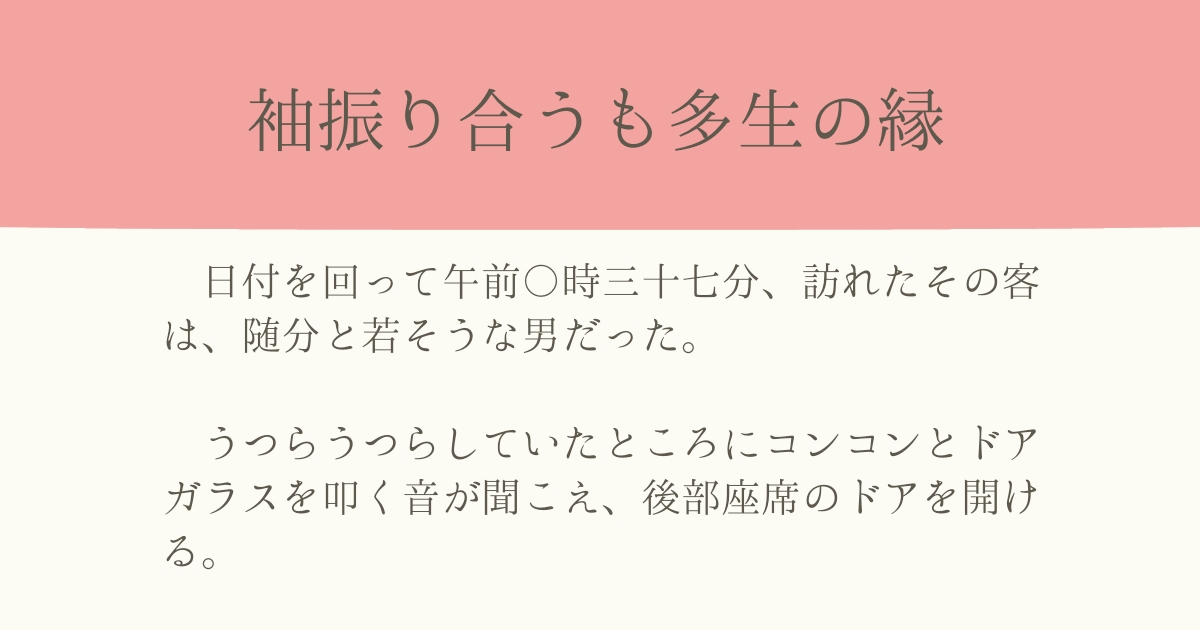
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます