青、橙、桃、紫。色素の多い黄昏の十六時二十九分、その青年は現れた。
「米花町に行ってください」
「はいよ」
金髪、褐色、色素の薄いブルーの瞳。ハーフだろうか、外国人だろうか。雑誌から抜け出したような洒落た格好の青年は、流暢ではあるがどことなく日本語のネイティブではないように思えた。
「お客さん、外国の人? 日本語お上手ですね」
「ありがとうございます。留学でこちらに」
「ほお、どこから?」
「……フランスです。あなたのご出身はどちらですか?」
「私は鹿児島でね。九州の……わかります?」
「ええ。桜島のところですね。ニュースで見ましたが、噴火は大丈夫でしたか?」
「ああ、程度の差はあるけど、噴火自体は日常茶飯事だからね」
うれしかった。自分の故郷が知られているのは喜ばしいことだ。自分はこの歳までついぞヨーロッパなんて行かなかったのに、まだ二十歳前後だろう青年は遥々極東の島国で生活している。これも時代だろうか。つい先月産まれたばかりの三人目の孫の未来に思いを馳せた。
「こっちに来て長いんですか? 家族はさびしいんじゃないの」
「……ふふ、僕ね、勘当されてるんです。二度と帰ってくるなって、そういう意味で日本に送られたんです」
「えっ……」
まずいことを聞いてしまった。しかし彼は気にしていないようだった。あっけらかんと笑って語る。
「不義の子ってやつですよ。本家からすごく嫌われてます。父親が東洋人だったことも気に入らないらしい。このまま日本で就職して、日本に骨を埋めるんじゃないかな」
「そうかい……気の毒だね」
何もうまいことを言えなかった。ただ相槌に万感の思いを込めることしかできなかった。笑ってこんな話ができるなんて、かえって残酷ではあるまいか。
ふと故郷の茶畑を想った。定年後、本当は鹿児島に帰ろうかすこしだけ考えた。けれど地元の親類はほとんど鬼籍に入ってしまっていたし、何より東都に家を買っていた。子供も孫もみな関東にいる。妻も二度ほど入院したがまだ元気でやっている。これからもやっていくつもりだ。……結局、空いた実家は潰して土地も売ってしまった。自分の帰る場所、自分が骨を埋める場所を本当の意味で決めたのはそのときかもしれない。
「私が言えたことじゃないけど、日本も悪いところじゃないよ。いい人もたくさんいるから。お兄さんならきっとなんとかなるよ」
「……ありがとうございます」
青年はとてもうれしそうだった。
「ルームメイトのイギリス人が、長期休みのたびに帰省して、お土産を持って戻ってくるんです。僕はそれが羨ましい。……でも、そのぶん僕は京都や沖縄、北海道、日本のいろんな場所に行って、いろんな人と話すんです。そしてお土産を買って帰って、交換する」
なんとなく妻を思い出した。盆と正月のたびに旦那の実家に帰省し、さぞ気を使ったことだろう。今ではふたりで孫が来るのを楽しみにしている。この東都の家で。
「僕は何も言わないし、彼も何も聞かない。たぶん何もかもわかってるんです。僕のことを、何もかも、見透かしたみたいに」
「そりゃ随分な名探偵だね」
あんな浅慮な質問をしてしまった自分とは大違いだ。
「……ほんとうに、参るくらいの名探偵ですよ」
彼は心底困り果てたふうに言うのに、どこか満足げにも見えた。
「しかし面白いねえ。フランスとイギリスって、同じヨーロッパでしょ? そんな国の人どうしがこんな遠い日本で会うなんて、数奇なこともあるものだ」
ごく自然に、帰国してからも会いやすい、と言いそうになって、慌てて口を噤んだ。さっき反省したばかりなのに。自分のこういうところがよくない。よく妻にも怒られている。
「どうでしょうね。……ここまで話しちゃったし、もっとお話してもいいですか?」
「どうぞ」
青年はひとつ呼吸をして、それから口を開いた。
「この間、そのルームメイトとセックスしちゃって」
「へっ」
正直、驚いた。なんとなく潔癖そうな男だと思っていたから。彼自身も愛人との子だというのなら尚更。だというのに、彼はなんでもない表情をしていた。
「もちろん合意ですけど……あ、運転手さん、そこで」
「あっ、ええ」
「鹿児島も、今度きっと行きますね。それじゃあ」
メーターを一瞥した青年は釣りの出ないようぴったり払って、にこやかに車を降りた。自分だけが混乱していた。そもそも男女がルームメイトという事態が想像しづらかった。……いや、青年は「彼」と言っていなかったか。ということは。
「えっ」

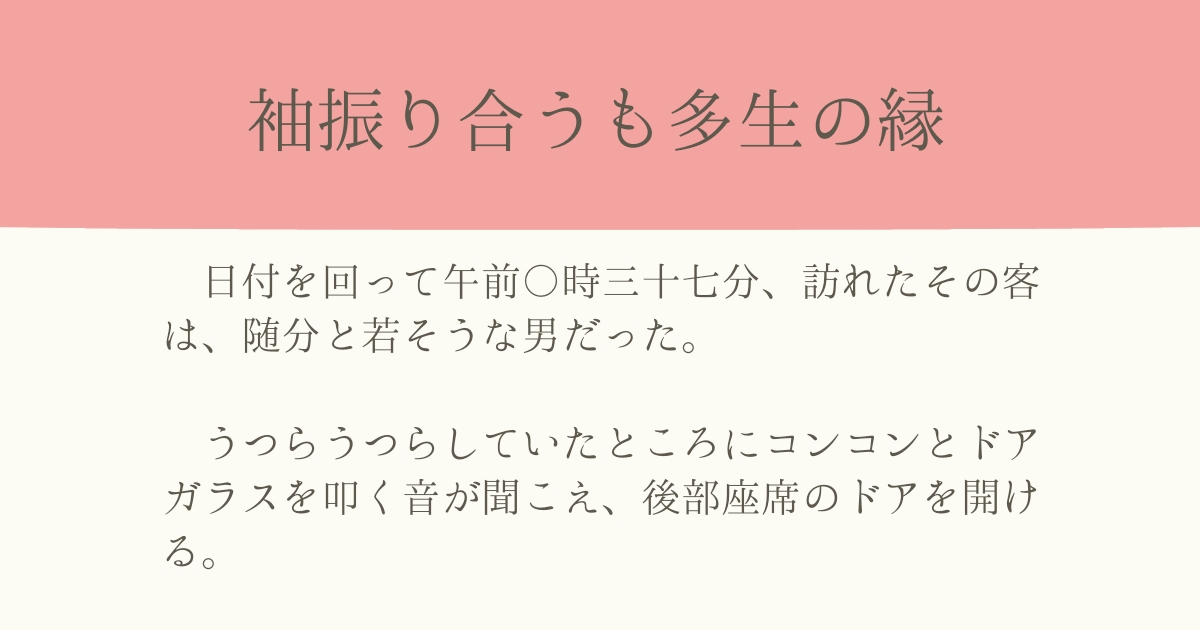
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます