とっぷり暗い二時五十三分、身奇麗だが危うげな少年を乗せた。
砂色の髪が月夜に似合う、透明感のある少年だった。コートを着込んでいるのに透明感があるというのはどこか奇妙な気もするが、ともかく今にも輪郭のほどけてゆきそうな佇まいをしていた。この仕事をはじめてから幾度となく耳にした幽霊の逸話を思い出さずにはいられなかった。言わずと知れた幽霊タクシーというやつだ。
「どこに行こうかな。横浜に向かってくれます?」
大丈夫かな、と思った。運賃は足りるのだろうか。横浜までタクシーで行くなんて酔狂をするにはあまりにも若すぎやしないだろうか。十代後半、多く見積もっても二十代前半に見える。コートもそんなに高価そうには見えない。しかもこんな時間に出歩いているなんて、確実に訳ありだ。いっそ心配になる。
「こんな時間に出歩いてどうしたの」
「仕事帰りですよ。……あ、もしかしてティーンに見えました? これでも二十歳は超えてるんですよ。条例には引っ掛からないんで、安心してください」
「ほんとうかい? まったく、安心したよ」
「でも僕、四千円しか持ってないんですよ」
ひとまず胸を撫で下ろした矢先、少年はとんでもないことを言いはじめた。
「はっ? いや君、それで横浜なんて行けるわけ……」
「だから運転手さん、抜きでどうです?」
「……抜き……って……君……」
内容を理解するのに数秒かかった。この少年は、性的なサービスを対価に横浜まで連れて行けというのか。
「ふふ、嫌ならそのへんで僕を降ろして」
冗談だろう。男に奉仕されるために運賃を負けるなんて、そんなばかな話があってたまるだろうか。いや、それ以前に、これはきっと罠だ。同僚から酒の席で聞いたことがある。こういった誘いに乗ってホテルに行くと、部屋で危険な稼業の人々が待っていることがある、あとは推して知るべし、と。
「あははは、冗談ですよ! お金は持ってます。たしかに僕はセックスワーカーだけど、そんなに安くないですから」
そう言われたが、高揚にも似た緊張感は消え去らなかった。自分がどんな顔をしているのか、皆目検討がつかなかった。
「運転手さんには、忘れられないセックスってあります?」
「……お客さん、探偵とかじゃないよね?」
「まさかあ」
「……じゃあ言いますけどね、ここだけの話ですよ? 家内と結婚する直前だったかな、その頃に……その、一晩だけ、他所でね? ……それがいちばん……忘れられない夜だね」
「あは、浮気だ。いけないんだあ」
「まあ、ねえ。男の本懐と言いますか……」
少年は愉快そうに笑っていた。それはどこか苦痛を堪えているようにも見えて、性的な雰囲気を連想させた。参った。とんだ夜だ。
「僕にもね、ありますよ。忘れられないセックス。その相手はやっぱり恋人のいる男だったなあ。でも、それであんなに気持ちよくなっちゃうんだから、男ってどうしようもない生き物だね」
じわりじわりと、少年がどんどん不思議な魅力を増していくのがわかった。これまでの人生で当たり前に信じていた自分の指向が揺らいでいく。妻と最後にセックスしたのはいつだったか。だがそれは自然なことで、周囲の夫婦にもセックスレスの悩みは尽きない。いや、しかし、これは……。
すん、と少年が鼻を鳴らした。泣いているのだろうか。泣かないでほしかった。面倒な客は御免だという気持ちは不思議と湧いてこなかった。
「君は……その、男が好きなの? あー、こういうことを聞いていいものなのか……」
「そういうわけじゃないけど。強いて言うなら、誰も好きじゃないのかも。その男のことも嫌いだし」
「嫌いな相手とやったんだ」
「流れで。嫌いっていうか、憎い。でも多分、こんなに執着してるからこそすごいセックスだったんだろうな。いや、とにかくあいつがめちゃめちゃ上手いんだけど……」
「なんでまたそんなに嫌ってるんだい」
「贅沢なんだよ、あいつは。あいつ自身にもどうしようもないところで、贅沢。だからあいつに怒るのは筋違いなのに、全部受け止めようとするから、なおのこと腹が立つ。その余裕も贅沢だから」
そう言いながらも、どこか達観したふうな声音だった。贅沢、と繰り返されるたび、どんどん彼が薄幸そうに見えてきた。二十歳は超えているというが、それも疑わしい。ほんとうは十代で、家に帰りたくなくて、こんな夜更けまで出歩いている、ほんの子供なんじゃないだろうか。だって、こんなにかわい――……
「君、横浜まで何しに行くんだい」
一瞬、思考が危うい方向に向かった。慌てて引き戻し、話題を変える。
「……夜明けを見に、かな」
「帰りはどうするの」
「電車でもなんでも」
心配だった。親が子を想うように心配できたらいいのに、この少年が変な誘いをかけたものだから、複雑で手に余る感情を抱えてしまっていた。
「僕ね、ほんとうは詩人になりたいんだ」
唐突な告白が胸に刺さった。性風俗で金銭を得る、詩人になりたい少年。約束された悲劇の映画の主人公のようだった。夢だけじゃ生きていけない。あきらめてまっとうな昼の仕事に就いたほうがいい。そう言えるはずもなかったが、願わずにはいられなかった。
「素敵じゃないか」
ほんとうに、心の底からそう思っていた。
「ありがとう。でもわかってるから。この世界は、僕が詩人になれる世界じゃない」
神様。葬式でしか思い出さない存在に、こんなときに祈った。神様、この素晴らしい少年を、どうか詩人にしてやってください。
「それじゃあ」
いらないと言ったのに、少年はきっちり運賃を払って港のほうへ消えた。彼の見る夜明けは、きっと何よりうつくしいに違いない。いつの日か彼の言葉でその光景を知りたい。どうしようもなく焦がれていた。
ふと、足を洗おう、と思った。座席の下の違法薬物を、今すぐ捨てたかった。そして妻の待つ家に帰ろう。たまには土産でも買って。

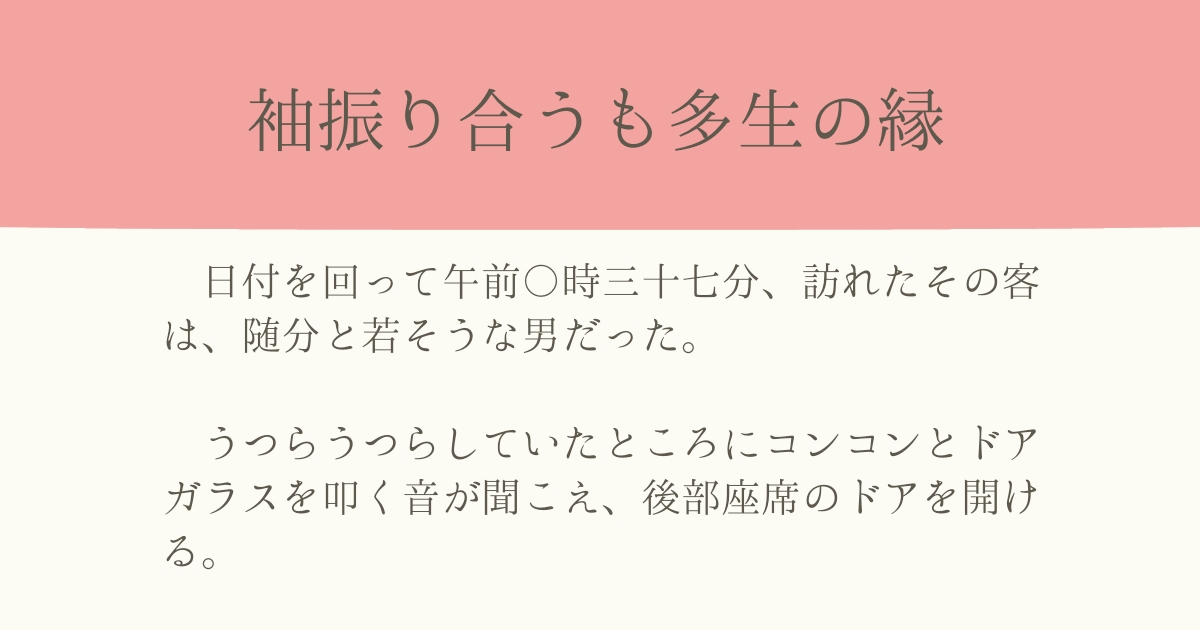
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます