ぴったり正午十二時、グレースーツの男がこちらを見て手を上げた。太陽の似合う男だった。
「中野にお願いします」
「あいわかりました」
車を走らせて幾許、黙って窓の外を見ていた男が口を開いた。
「人生相談、してもいいですか」
「はあ、自分でよければ」
黙っていても絵になる男だったが、声まできれいだった。就活生……のスーツには見えない。いいところの新人の営業職だろうか、と適当にあたりをつけた。
「この歳になると、いろんなことをあきらめないといけなくなるじゃないですか」
「この歳って……お兄ちゃんいくつ? まだまだこれからでしょうに」
「こう見えて三十路に片足突っ込んでるんですよ。運転手さんは僕くらいの歳の頃、何かをあきらめたりしました?」
驚いた。とても三十には見えない。嘘だろう、と思ったが、どうでもいいことだった。タクシーという刹那の密室では、たとえ嘘をついたとしても、証明できるはずもない。ここには嘘も真もない。彼が三十路だと言うなら三十路なのだ。
「そうだねえ……結婚したこともそうだけど、やっぱり家を買ったことかな。定年前は印刷会社にいたんだけど、ローンを組んじゃうともう辞められないでしょ。小遣いだって減った。それでも買わなきゃいけない気がして……なんだろうね、マイホームを持たないと、一人前の男になれない気がしたんだよね。それがまあ、三十代のあきらめかな」
「一人前の男、か……」
「今の人からすれば、ばかばかしいかもしれないけどね。同僚から所帯を持った、子供ができた、家を買ったって耳にすると、悔しかったものだよ」
「いえ、わかりますよ」
男は凪いだ瞳をゆるく細めた。ハンサムだな、と思ったが、これも死語かもしれない。
「先日、入院しましてね。いいから休めと仕事もさせてもらえなくて、いかんせん退屈で、色々と考えてしまって」
「ああ、私もあなたぐらいのときに盲腸で入院しましたよ。もう暇で暇で、人生について考えてしまった」
「……ちょっと怪我をしまして。知人に輸血されたんですよ」
さらりとすごいことを言ってのけた。今までの人生、自分は輸血などされたことがない。
「ちょっとどころか大怪我じゃないですか。大丈夫なんですか」
「今はもうご覧のとおり。ただ、その知人がね、肝が冷えた、心配した、結婚しようって言うんですよ。冗談だろうと笑おうとしたら、そいつの目が真剣で、笑えなくなりました」
「……まだ結婚はしたくない、とか?」
「まだ、というか、そもそも結婚する気もなかったので。僕が人生で最も心を割いてきたのはその知人だけど、平和に結婚できるような仲じゃない。僕も知人もわかってる」
知人、という言い方からして付き合っているわけでもないのだろう。にも関わらずいきなり結婚とは、恐れ入る。だが、彼も彼で頭ごなしに否定せずに検討している。もうその時点で可能性はゼロじゃないのだろう、と思ったが、口に出すのはやめておいた。彼だってわかっていることだろう。
「知人もほんとうに結婚しようと言っているわけじゃない。ただ、要するに、彼は僕にあきらめてほしいんですよ」
「何を?」
「……お互いがお互いにとって、どうしようもないってことを、かな」
彼は悩ましげに溜息をついた。
私は軽はずみなことを言うまいと気をつけなければならなかった。気を緩めると、まるで運命みたいですね、と言いそうになってしまうからだ。結婚に必要なのは運命だけではない。三十路にもなれば、そんなことは大抵の人がわかっている。
「結婚は人生の墓場、なんて言いますしね。慎重にもなりますよ」
躊躇の末、当たり障りのないことを言ってみた。なのに彼は、ぱちりと大きな目を見開いて何度かまばたきをした。墓場、墓場か……とちいさく呟いた。
「そいつに輸血されるのは、これが二度目なんですよ」
彼がさらりと告げた言葉はそれなりに衝撃だった。どんな人生を歩んでいたら二度も輸血されるほどの怪我をするのだろう。あるいはなんらかの病気があるのだろうか。もしかすると、彼は暴力団関係者なのではないか? あらぬ可能性が頭を巡った。
「昔は半ば趣味みたいに献血に行ってたんですけど、それはこの国の誰かの身体に巡って、結局自分に流れてくるのは彼の血なんだなと思うと、もうあきらめてもいいかなって、ちょっと思ってしまうんですよ」
「ますます運命的だねえ」
「ますます?」
「あっいや……実を言うとさっきから思ってましてね、運命的だなと」
話を聞いているうちに注意を忘れてしまった。つい口から出ていた。気分を害しただろうか、と様子を伺うと、彼は存外楽しそうにしていた。
「ときどき言われるんです。そいつとのことを話すと、運命だ、数奇だ、ドラマみたいだって」
こんな話を聞かされれば、誰だってそう思うだろう。そういう相手がいる人生は、いったいどんなものだろう。とても想像がつかなかった。こんなことを言うと、妻に怒られるかもしれない。
「……でも、結婚は人生の墓場、がいちばん胸に刺さりましたよ。確かに、あいつを墓に引きずり込むのは悪くない。悪くないな……」
男は噛みしめるように笑った。あんまりきれいな微笑なものだから、それだけで、きっと彼の結婚相手はしあわせだろうと思った。
「私はね、結婚もマイホームも、今となっちゃあ後悔していませんよ。歳を取るってのはそういうことです……なんて、ジジくさいことを言ったかな」
「いえ……覚悟が決まりました。ありがとうございます」
「そいつぁ何よりだよ」
そこで停めてください、と彼は言った。コンビニの前だった。彼はこれからどこに向かうのだろう。釣りはいらないと言うのでありがたく受け取った。彼のどことなく晴れやかな表情を見ると、他人事ながら自分までうれしくなった。
彼が去るのを見届け、しばらく空車で走らせていると、派手な真紅の車とすれ違った。なんとなく目に留まったが、私はすぐにそのことを忘れてしまった。

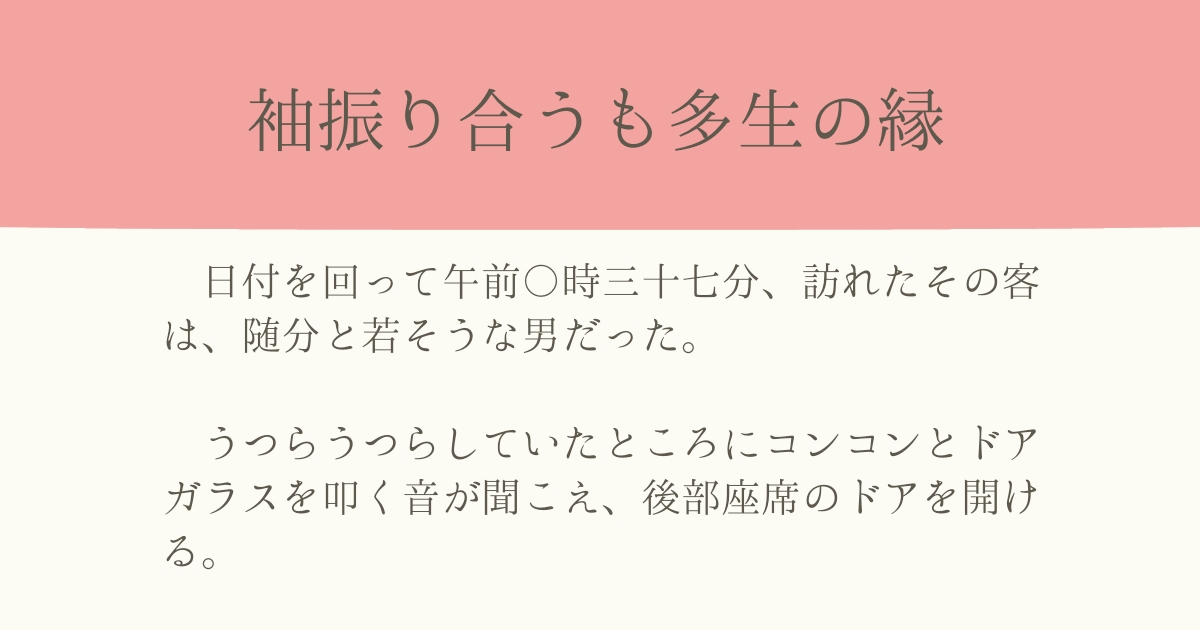
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます