赤安:セックスしないと出られない部屋で「恋人」について考える話です
知らない空気で呼吸した。
昨夜、僕が眠りについたのは自室のベッドのはずだった。しかしここは違う。広くやわらかなベッド、白い天井、白い壁、見渡す限り窓も扉もない、夢のように不自然な部屋。いったいなぜこんなことに。どうやって? ここはどこだ。……いや、最も重大な問題は、なぜか隣で眠っている男だった。彼が僕の隣にいるはずがない。なぜなら彼は――赤井秀一は、はるか太平洋の向こうで、僕の知らない生活を営んでいるはずだからだ。
「ちょっと、起きてください、起きろ、赤井秀一!」
赤井の覚醒は早かった。無言でまぶたを開き、僕と見つめあったのは一瞬、部屋を一瞥すると即座に身体を起こした。
「状況は?」
「残念ながら僕にも。……あなたは昨夜どこに?」
「自分のベッドで寝ていたさ。君は誰かとお楽しみか?」
「まさか。あなたと同じですよ」
「そのわりに素っ裸だが」
「ひとりの夜はいつもこうです」
赤井はスウェットを身に着けていたが僕はまったくすはだかだった。お互い眠っていたときの格好そのままなのだろう。何か緊急事態が発生したら――どう考えてももう発生しているのだが――僕のほうが不利だ。せめて下着ぐらい履いておくんだった。今後は習慣を変えるかもしれない。
壁、床、天井、その他すべてをひと通り調べたが、人間の力での脱出は不可能という結論に至った。酸素がどこから供給されているのかさえわからないのだ。超次元的な力が働いているとしか思えない。そう話せば、「随分受け容れるのが早いな」と感嘆したように赤井は言った。彼は論理的な解決を諦めていないようだった。僕が執念深く諦めなかったのは赤井秀一の生存くらいのものだが、それだって、決して論理的な思考と呼べるものではなかった。僕には彼と違って〈探偵〉の資質がない。
当面の問題は食料がないことだ。シャワールームが併設されているので水は出てくるが、ちいさな冷蔵庫の中には、幾らかの酒とジュース、ペットボトルの水があるだけだった。
フェイクの可能性は捨てきれないが、この状況を打開する糸口はたったひとつ存在した。ベッドサイドに置かれていた紙切れ。まったく信じ難いが、現状それしか手掛かりがない。ご丁寧にペーパーウェイトまで乗せられたそれにはこう書かれていた。
“ここはセックスしないと出られない部屋です”
「ここで飢えて死ぬよりは、試してみてもいいんじゃないですか?」
問題の紙の隣にはローションボトルとコンドーム、ティッシュボックスが置かれていた。ホテルのようだと思ってはいたが、改めて見ればセックスのために必要なものが備わった部屋と解釈することもできる。つまるところそれがホテルだと言われればそのとおりだが。
この部屋の仕組みを論理的に解き明かすことへの関心を僕はほとんど失っていた。それよりも、提示された脱出方法を検討するほうが有意義だろう。
「いいのか? そんなに軽く言ってしまって」
「軽くも何も……僕とあなたですよ?」
そう、僕は赤井の身体を知っているし、彼もまた然り。僕らは、まだ互いの本名さえ知らなかった頃、一度だけセックスしたことがあった。そういう夜を経てここにいる。
「ああ、それとも……向こうにいい人がいるんですか? だとしたら申し訳ない」
息をするように嘘をついた。どうでもいい。申し訳なく思う気持ちはない。だって赤井だから。
「俺はさびしい男だよ。……本当にいいのか?」
「ええ。吐いた唾は呑みません。しましょうか、セックス。久し振りに」
赤井は不承不承といったふうに頷いた。それは僕にとってすくなからず不快……いや、きっと悲しいことだった。
「……シャワー、浴びてきます」
かつて僕らがセックスしたのは、凍えるような夜だった。
僕も彼も人を殺して、気が滅入っていたのかもしれない。……そうだ、あの夜、赤井の道具はライフルではなかった。思えば、彼がライフル以外で人を殺したのは、僕の知る限りではあのときだけだった。それは彼にとって忌まわしい記憶なのだろうか。だから僕を求めたのだろうか。透明な汚れに塗れた手で愛撫して、彼の中で何かが変わったりしたのだろうか。それは僕の知るところではない。ただ、モーテルの一室で覗いた彼の瞳は、きっと誰かの体温を求めていた。……本当に? 彼の瞳を鏡にして、僕自身の欲望を映し見ただけなのではないか。……考えても埒が明かない。いずれにせよ、みだらで爛れた夜だった。
「煙草、吸いたいんですか?」
バスローブがあったのをこれ幸いにそれを羽織って部屋に戻ると、赤井がくちびるを撫でていた。考えごとをしているときにそれをする人もしばしばいるが、この男の場合はヤニ切れだろう。彼は困ったように笑った。
「まあな」
「……じゃ、尚更さっさと済ませましょうか」
「俺もシャワーを」
「別に構いませんが、あなたが気にするんならどうぞ」
「君が浴びたんだ。俺も浴びるさ」
そう言って彼は僕の返事を待たずに消えた。
「……似合わないな」
立ち去ったのは彼なのに、自分のつぶやきのほうが捨て台詞じみてむなしかった。
赤井のいない間に部屋をふたたび見渡す。扉も窓もない部屋。奇妙な密室もあったものだ。
――密室。あの少年――江戸川コナンのことを思い出す。ゆく先々で事件に出会うというあの少年は、いったいどれほどの密室殺人に出会っただろう。某所でテニスをしたときなどは、僕さえも密室殺人に出会った。まるで彼に導かれたように。
だがここに彼はいない。いるのは僕と彼だけだ。ここで工夫を凝らして赤井秀一を殺したら、あの少年がやってきたりはしないだろうか。ちらりとそんなことを考えたが、そんな光景を彼には見せたくはない。彼は赤井を慕っているようだから。
ただひとつ言えるのは、赤井を殺せばこの部屋からの脱出は不可能になるということだけだ。セックスにはふたり必要で、ひとりではできないのだから。殺人事件にふたり必要であるように。
「早いですね」
「煙草が恋しくてね」
すまして笑う彼の顔はこれが皮肉だと告げていた。そんな顔さえ格好がつくのが恨めしい。
「君は本当にいいのか?」
すっと頭に血が上ったが、つとめてそれを抑える。
「……あなたは、あの夜を後悔してるんですか」
だとしたら嫌だな、と思いながら言った。その願いが滲んだ乞うような目になっていないといい。僕は彼の前では完璧に演技することができない。
彼はベッドに乗り上げて、僕をまっすぐ見つめた。いい男だ。勝手に死ぬのは許せないが、それでも遠くにいてほしい、そんな男。
「……こんな機会だから言うが、そうだな、後悔……しているよ。君と恋人になりたいと思ったこともあったからな」
二の句が継げなくなってしまった。この僕が。有り体に言って驚いた。そうだ。僕は彼のそういうところが嫌いなのだ。恋人なんて手垢のついた言葉で僕らを簡単にまとめてしまうような彼が。僕の抱える複雑な煩悶をいとも簡単にいなしてしまう彼が。思春期の子供じゃあるまいし、これが恋じゃないことなんてわかりきっているというのに。
「君と共にいたいと、そう思ったこともある。何も言わないままだったが」
「……僕はずっといるでしょう、この日本に。それでいいはずだ」
「傍にいたいとは言わないさ。だが、君の隣が俺の席だと思いたい」
「それをお前は恋人と呼ぶのか?」
「きっと」
「それを僕に承認しろと?」
「それでは不足だ。君にも俺との関係を恋人だとみずから思ってほしい」
「我儘な男だな」
腹立たしさを隠しもせずに睨みつけると、赤井は楽しそうに笑った。僕がいつも思い出すのはこの顔だ。
「知っているか。君の瞳は怒りが増すにしたがって透明になっていくんだ。俺のいちばん好きな顔だよ。君の宇宙が覗けそうで、ずっと見つめていたくなる」
僕は今にも叫びだしそうだった。感情の奔流を持て余し、この傲慢な男に殴りかかってしまいたかった。……そしてそれを、どうか彼に受け止めてほしかった。その気持ちを否定できないのがたまらなく嫌だった。どうしようもない。何もかもどうしようもなかった。何かを叫んだところで、それはどうせ赤井秀一という音になるのだ。
深く息を吸って吐く。僕がつとめて冷静であろうとする様を、彼はさびしそうに見ていた。彼は僕が吠えるところが見たかったのだろう。彼の期待を裏切ったのに、勝った気はまったくしなかった。
「……僕は、あなたとどうにもならなくてよかったと思ってるんですよ」
「……そうか」
「あなたを追い掛けていた頃の情熱は、もう薄らいでいる。けれど、あとに残った感情はそう悪いものではないと思えて、それをそのままにしておこうとした。だから、僕らのあいだに太平洋が欲しかったんです。なのに、なのに! お前は何度でも現れて簡単に僕を熱くする!」
結局みじめに激昂した。見なくたってわかる。そんな嬉しそうな顔をするな。これ以上、僕を掻き乱さないでくれ。出会っただけでじゅうぶんだ。お前は遠くにいればいいんだ。知りたくもないゆたかな感情を僕に与えないでくれ。生きることがこんなに熱いなんて知りたくなかった。
「……俺は、君が俺を諦めないでいてくれたことが、君が俺を見つけてくれたことが、ほんとうにうれしかったんだよ、降谷零くん」
やさしく笑うのがとことん下手な男だ、と思ったその瞬間、すとんと胸に何かが落ちてきた。彼は本当に僕のことが好きなのだ。この男をはじめてかわいいと思った。不思議な感覚だった。
最悪だ。僕も彼も。でもきっと、それが僕らに似合いなのだ。
「……僕の負けです。今ちょっと……改めて、あなたに抱かれたいと思った」
彼の表情からわだかまりが抜けた。難しい男だ、と思ったが、あるいはそれは僕のほうなのかもしれない。もしかすると、彼はとても単純なのではないか。今更のような発見だった。
「キスをしても?」
「……あなたにキスされるのが嫌だなんて思ったこと、ない」
そう言うと、彼の顔がふたたび曇った。だから僕は、いたずらごころを忍ばせてささやいた。
「こんなこと、あなたにしか言いませんよ」
間髪をいれず彼のくちびるが降ってきた。舌が入り込むまで数秒もなかった。だがようやく作法がわかってきた。キスの作法ではない。赤井秀一を転がす作法だ。
やがて離れたくちびるが楽しげに弧を描いた。
「いいことを教えよう。恋はいつだって惚れたほうの負けだ。だから、そんなに煽ってくれるな」
やはりこの男は何もわかっていない。それは勝者の余裕ゆえに出てくる言葉なのだ。そんなものは慰めにもならない。
あの夜のおざなりな愛撫とは違う、丁寧な手つき。赤井は本当に僕をいつくしみ大切にしたいのだと、どこか冷静な頭で思った。それに快楽を得ながらも煙たく感じる自分は薄情者だろうか。うれしい、とは言い難い。しかし、彼にしか喚び起こせない熱が身を焦がしてゆくのははっきりとわかった。
一瞬、ほんの一瞬だけ、僕と彼の運命がもっとわかりやすく恋の形を取ればよかったのにと思う。あるいはふたりで育てれば、やがて恋の果実に成長するだろうか。だがそれは、たとえよく似ていたとしてもきっと毒林檎なのだ。王子様を待つ眠りなんて甘さのない、死に至らしめる毒。西洋の民話の多くには解呪の方法が存在するが、日本の民話はそうではない。呪いを解く方法などはじめから与えられていないのだ。日本に骨を埋める僕には。
「赤井は……セックスの最中におしゃべりなひとをどう思いますか」
「君のおしゃべりは好きだよ。君がリラックスできるのならなんだっていいさ」
すこし迷って、口を開く。
「……この部屋、密室だから……殺人事件にお誂え向きだなって……」
「俺を殺すか?」
赤井秀一について知っていることは、決して多くない。だが、彼はきっと、僕が彼に殺意を向けるとうれしいのだ。それだけは確信している。それでよく恋人になりたいなどと言えたものだ。
「こんな奇妙な密室で殺したら、あの少年が来てしまうでしょう」
「……ベッドの上で他の男の話か?」
「それを言って様になるのが、本当に嫌味な男だよ」
彼の手が迷いなく中心に触れ、思わず息を詰める。数度の往復を経てさらに奥へ。確かめるように二、三度そこをノックして、ローションボトルを取る。手に出したローションを持て余すようにこちらを見た。つめたいままでは酷だとでも思ったのだろう。そんなところでやさしくされても、僕は困る。ほんとうに持て余しているのは、ローションではなく僕の感情だ。
「殺人も、セックスも、ふたり必要という点では同じだなって……思ったんです」
「それはいい。殺人も、セックスも……裏切りも恋も、ふたり必要だからな」
「は……なんだそれ」
「すべて、今の俺にとっては、君としかしたくないことばかりだよ。この部屋は何もかもにぴったりだ」
そのとき、不意にわかった。彼が僕の中に宇宙を見ていること。僕の宇宙、彼の宇宙。彼の宇宙が僕にも見えた。朝焼けのようなみどりの宇宙。ぜんぶ同じだったのだ。僕と彼のあいだのすべては、互いの宇宙に手を伸ばす旅路だったのだ。
「なあ、降谷くん。許してくれないか。どうか俺にそれを」
僕がこの国への献身を恋になぞらえるように。多分、それと同じなのだ。何も変わらない。ただ、それを恋と呼んでみるだけで、それによって何かが変わるわけではないのだ。思春期の少女ならそれで何か変わるかもしれないが、僕らはとうにそうではない。
「……恋人たちなんて、星の数ほどこの世にいる。その中には、こんな星めぐりの悪い恋人がいたっていいと、そう思わないか」
「……降参」
そうつぶやいて、不意をついてキスをした。ほんの一瞬。それでじゅうぶん。こぼれたローションが腿を濡らした。それさえほのかに快楽で、もうだめだ、と思った。
「いいですよ、恋人。……でもあなた、二番目だけどいいんですか? 秀一なんて名前なのに」
「ホォ――……」
一番目は? などと尋ねるような真似はしなかった。僕が言わずともきっとわかっているのだろう。彼のそういうところは好ましく、しかし同時に恐ろしい。
「構わんさ。俺が好きなのはそういう君だ。……誇りに思うよ」
「勝手なことを言うな! 僕の献身が正しいかどうか証明するのはこの国の歴史だ! 僕はお前の一存で認められて舞い上がるような男じゃない!」
「……は、はは、く、ははは……」
衝動のままに声を荒らげたが、彼は心底愉快そうに笑った。彼がこんなふうに笑うのをはじめて見た。ぐらぐらと沸き立つような怒りが身を焼く。
「愛してる」
赤井秀一が泣きそうな顔をしているのも、はじめて見た。
「……お前だけだ」
何もかも、彼だけだ。僕の持つ返事はそれだけだった。彼だけが、僕の。
ぬるいローションが馬鹿みたいな音を立てる。果たしてこの穴は宇宙につながっているだろうか。馬鹿な音に引きずられて馬鹿なことを考えてしまう。ふと見上げた赤井の顔が妙に真剣で、参るなあ、と思った。
「も、挿れれば……」
「もうすこしな」
ああ、そういうことを言うんだ。今の彼は。彼の恋は、彼の愛は、そういう形を取るのか。ほんとうにもう、挿れてしまっていいのに。僕の望まぬいたわりが彼の愛だというのか。健気だな、と思った。思ってしまった。すくなくとも今この場では、それは間違いなく快楽だった。
彼の手がついにコンドームに伸ばされたとき、僕はもう焦らされきって泣きそうだった。思えば僕が彼に焦らされなかったことはなかった。待つことに慣れきったスナイパーは、たぶん待たせることにも躊躇がない。それでも彼を追い続けるのが僕だった。僕は僕で、存外健気なのかもしれなかった。
挿入はゆっくりと行われた。息を吐きながら暴れる心臓の鼓動を聞く。身体が全力で生きている。セックスでそんなことを感じるなんて、野暮というか、枯れてないというか。僕は彼を枯らさないし、彼もまた僕を枯らさない。彼の胸にそっと手を当てた。脈拍のせわしさに微笑すると、彼は突然すべてを一気に埋め込んでしまった。思わず声を上げてしまって抗議のひとつでもしてやろうとしたが、彼の腹筋が震えていたので満足してやめた。暴発寸前といったところか。何も狙わなくたって、僕がただ思うままに振る舞えば、それで彼を撃ち抜けてしまえるらしい。これまでもそうだったのだろうか。
「……食われそうだな」
彼の言葉があんまり悔しそうなので、僕は口角が上がるのを抑えられなかった。これは歓喜だ。これこそ僕の待ち望んだ歓喜! 命を危険に晒すスリルにも匹敵する快楽。
触れあえば温度は移動する。僕の中で燃え盛る熱はすこしでも彼の肌を焼いただろうか。彼を焼くのはどうか僕の火であってほしい。かつて来派峠で彼を包んだ炎より、もっと熱い僕の火。お前の酸素で育った火。女のように水のあふれる穴を、僕は持っていない。あるのはこの火だけだ。
はじまる律動に身を委ね、抑えずに母音を漏らす。息のたくさん混ざった喘ぎはときどき笑い声にも似ていて、それがなんだかおかしかった。
快楽に思考を呑み込まれ、すべてがあやふやになってくる。そうだった。この男とはいやに身体の相性がいいのだった。
「あかい……」
お前だけだ。
暴力に似た絶頂が僕を訪ねたとき、どうやら彼もそうらしかった。れい、と彼が口にするのが聞こえた。そう呼ばれるのはいつ以来だろう。この男にそう呼ばれるのははじめてのはずだった。生意気な盛り上がり方しやがって。そう思うのに、なぜか悪い気はしなかった。僕の心は不条理にできている。
ガチャリ、と音がした。ふたりで即座に視線をやると、先程までなかったはずの扉が出現していた。解錠の音だろうか。彼が僕の中から出ていき、かすかに喘ぐ。赤井は一瞬だけ恨めしげな目でこちらを見たが無視してバスローブを羽織る。ベッドから降り、扉へ向かう。シャワーを浴びたいが、それよりも先に確認しなくてはならない。やっとこの奇妙な密室から解放されるのか。
果たして扉は開かなかった。どうやら鍵がかかっているらしいが、それらしきものは見当たらなかった。
「中に出すべきだったのか?」
「ぬけぬけと……だが、ドアは出てきたんだから、蹴破れば問題ないでしょう」
「いかにも密室殺人らしいな」
「それじゃあ……」
「待て」
扉から数歩離れたところで、赤井に制止される。この期に及んで何があるというのか。
「君はこれから、俺を恋人だと思って生きてくれるのかな」
それは疑問というよりつぶやきだった。なぜだか途方もない祈りにさえ聞こえた。
僕は目を閉じて、これからの人生を想った。僕の献身がわかりやすく報われることは、すくなくとも僕が存命のうちはないだろう。かといって僕の名が歴史の教科書に載ることはないし、どこぞの巨匠のように死んでから評価されることもない。それでいい。それが僕の望む僕の人生だ。けれど、いつか死神に肩を叩かれたとき、瞼の裏にあざやかに蘇るのは、きっと赤井秀一のことだ。褪せてゆく青春の思い出とはまた違う何か。それを恋と呼ぶのは、悪くないと思えた。
「赤井秀一。あなたが僕の恋人です」
彼が驚いた隙にくちびるを奪った。永遠なる刹那のキス。
ガチャリと、今度こそ解錠の音がした。
* * *
目を覚ますと、視界にあるのは見慣れた天井だった。
身体に残る倦怠感が夢ではないと告げていた。彼から連絡があるだろうか。そもそも彼は僕の連絡先を知っているのだろうか。僕も彼も調べようと思えばどうとでもできる。しかしそれは今更どうでもいいことだった。これが僕のひとりよがりな夢だったとしても、彼は既に僕の恋人なのだから。
吸い終わった煙草に火をあてても、ふたたび燃えることはない。僕と彼もとっくにそういうものだと思っていた。しかしどうやらそうでもないらしい。彼と顔を合わせるだけで、何度でも蘇る。この火は、きっと死ぬまで、どこにいても灯っている。逃れられない呪いのように、旅路を照らす松明のように。
あれから彼はきっとすぐに愛飲する煙草に火をつけただろう。だがここにはそんなものはない。煙ははるか太平洋の彼方だ。
だから、これは僕の幻臭なのだ。

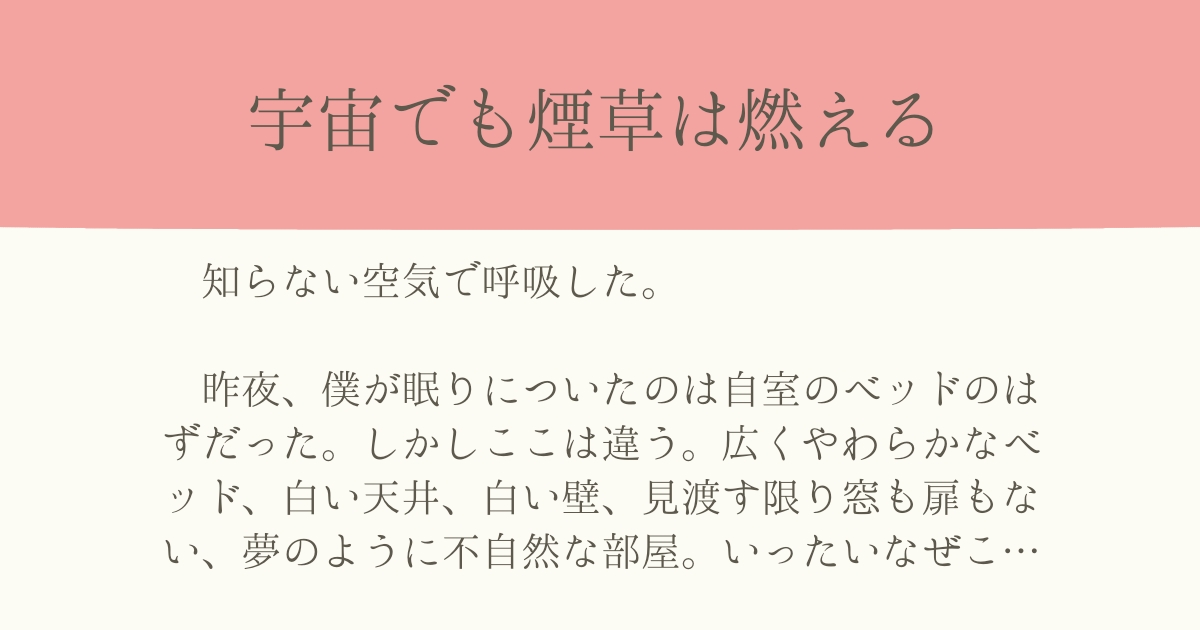
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます