赤安:映画館でバッタリ会って立ち話をする話です
映画を観るのは久し振りだった。
数日前、映画のチケットをもらった。組織の件で世話になった工藤夫妻からだ。著作が映画化したそうで、よければ是非にと。公開は帰国の二週間前だった。立て込んでいる頃だろうが、都合はどうとでもつけられる。二つ返事で了承して、ありがたく受け取った。
そして来る当日、仕事の合間に映画館に赴くと、そこにはよく見知った男の姿があった。
「……こんなところでお会いするとは」
降谷零だった。狙い澄ましたような笑みを浮かべて近づく彼は、不自然なほど完璧だった。警戒されている。そんなに緊張しなくても、今の俺の背後には何もないのに。長く抱えていたいくつかの秘密を既に彼は手に入れていた。かといってその過程で和解や友情が生まれたわけではない。ただ推理と駆け引き、そして諦観があっただけだ。世界は白と黒だけでできているわけではない。
いつかもこんな鉢合わせがあったな、と思い出す。あのシンガーの事件。今日の彼はどうしたのだろう。趣味で映画館に来るほど暇じゃないはずだ。彼もまた工藤夫妻と懇意にしているのだろうか。
「やあ。君も券をもらったのか?」
「ええ。……僕に声がかかるということは、あなたもだろうと半ば思っていましたが、まさか鉢合わせるなんて」
「……会いたかったのか?」
そう言うと、彼は虚を突かれたようにたじろいで、敵意のようなものを滲ませた。ほんの一瞬の感情の遷移は、平素の彼ならたやすく隠せるだろう。それを俺には見せてくれる。まるでプレゼントのようだな、と思う。
「会ったところで、何もないでしょう」
つとめて冷たい声だった。
映画は面白かった。原作となる小説は既に読んでいたためおおよその展開は知っていたが、それでも見応えのある映画だった。場内が明るくなってからもしばらくそのまま座っていた。満員に近かった場内がすこしずつ静かになっていく。
いつの間にか、彼がそばに立っていた。
「……赤井」
見上げると、彼はなぜか傷ついた顔をしていた。望まぬ相手にファーストキスを奪われた少女のように、何かを壊された顔だった。
「赤井、泣いてる」
言われて頬に手をやると、たしかに自分は泣いていた。久し振りだな、と思った。涙を流すこと自体。ましてや映画を観て泣くなんて、果たしていつ以来だろう。
「ああ……エンディングが、とてもきれいな曲だったから……」
心底そう思っていたから、そう言った。それだけだった。しかし、流石にもうわかる。彼はきっと、俺に裏切られたからそんな顔をしているのだ。たしかに彼の言うとおりだ。会ったところで、何もない。ただ裏切りを重ねるだけだ。どうやらそういう宿命らしい。
「赤井も泣くんですね。そんなことで」
ひとりごとのようだった。俺が隣りにいるのに。
シアターを出て、ラウンジの端でふたり並んで、行き交う人々を眺めていた。ドリンクを片手に持ち歩く人、楽しげに感想を語り合う人、皮肉げに批評する人、ポップコーンの甘いにおい。彼の視線の先には何があるのだろう。俺のことを考えながら、何を見ているのだろう。
「俺をなんだと思ってるんだ。俺だって泣くさ。この歳になれば人に見せないだけだ」
「でも僕には見せた」
「君が見たんだろ」
むずかしい男だ。彼自体が解けない謎のようだった。彼の関心を引くことは容易で、そのために俺は何もしなくてもいいのに、その先に踏み込むことは難しい。彼という迷宮に、俺は入ることすらできない。
「君は泣かないのか?」
「さあ。最後に泣いたのがいつだったのかも覚えていません。子供の頃から、涙をこぼさないように必死だった気がする……」
彼がその先に続く言葉を呑み込んだのを察して、うるんだ瞳で必死に涙をこらえる少年を想った。それは多分、痛々しいと形容すべきものだった。――泣かないのね、我慢したのね、とても立派、男の子だものね、いいこいいこ。子供の頃にかけられたそんな言葉がふと蘇る。誰に言われたのかなんてもう忘れてしまったのに、擦りむいた膝の痛みとともにそれらは己に沈着していた。不思議なものだ。彼の奥底には何があるのか、計り知ることはできない。
「そうか」
彼は混乱しているのだろう、と朧げに感じた。俺はたぶん、彼の理想のような何かを裏切ったのだ。だから、きっと俺の涙ひとつのために、あんな顔をさせていた。
――俺の人生には、こんなにかわいい男が訪ねてきてくれるのか。だとすればいい人生だ。
「君は泣けないのか……」
彼の涙が見たいな、と思った。きっと怒ってこちらを向くと思ったのに、彼はむずかしい顔をして前ばかり見ていた。
そのとき、ふとよく通る男の声が耳に飛び込んできた。
――全米が泣いた! あの映画がついに日本上陸!
ラウンジに設置されているモニターが、近々公開予定らしい映画のトレーラーを流していた。犬と戯れる少年の姿が映っている。どうやらペットの映画らしい。
「犬を飼った経験、ありますか」
隣を伺うと、彼は顔を上げてモニターを見ていた。そういえば、彼は犬を飼っていたことがあるらしい。今も飼っているのかはわからない。
「いや、俺自身はない。だが、子供の頃、近所に住んでいた婦人の犬をよくかわいがっていたよ。血統書つきの利口なレトリーバーで、婦人の自慢の犬だった。俺にもよく懐いていた」
「……来週末公開か」
彼の犬はなんだろう。なんとなく柴犬を想像した。彼は日本を愛しているから。推理とも呼べない想像。だがきっと似合う。
「来週末、またここで一緒に観ないか」
正気か? という顔をしていた。そうだろうな。俺たちはそんなふうな関係じゃなかった。
「行くわけないだろ」
でも、彼と観てみたかった。宣伝文句がなんだろうと別に泣かなくたっていい。ただ、彼の心が生活になんの実害もなく揺れるのを、隣で感じてみたかった。
「いつか泣きたくなったら、俺のところに来てくれないか。待っているから」
君は俺の涙を見たんだ、いいだろう。それでイーヴン、それでフィフティ・フィフティだろう。自分でもおかしかった。目的ありきの理論構築だ。ほんとうはただ、君が泣くのは俺の隣にしてほしいだけだ。
「……それじゃあ、僕は永遠に泣けませんね。二度と会わない男に呪いをかけて別れるのか、赤井秀一」
呪い。それは魅力的な響きを持っていた。なんだか、ひょっとして、とんでもなく俺たちにふさわしいような。彼に呪いをかけるのは他の誰であっても嫌だ。それは俺の役目だ。なんの根拠もなく、そう思った。そうあるべきだと。
「君がこれまでなんの呪いで泣けなかったのかは知らないが、これからは俺の呪いだ。俺が君の魔女だよ、降谷くん」
「……どこぞの林檎が聞いたら笑いますよ」
「違いない」
あの銀幕女優なら、演技でいくらでも泣けるだろう。あるいは彼もそうだろうか。目的のために必要ならば泣けるのか。自分のために泣けないだけで。
「あなたの前で泣くなんて絶対に嫌だと思っていました。それは負けだと。……でも、あなたがなんの衒いもなく泣いているのを見たとき、最初から負けていたことに気づいたんです」
笑ってください、滑稽だから。彼はそう言って、何かを鎮めるように息を吐いて目を閉じた。愛しいな、と思った。ほんとうに笑ったら怒るくせに。
どちらからともなく映画館を出て、あてもなく街を歩いていた。別れの挨拶を探しあぐねて、ただただ連れ立って。
「君の犬を当てられたら、来週また一緒に映画を観てくれないか」
勝算はなかったが、万にひとつでも可能性があるならそれでよかった。このままではどうせ来てくれない。しかし、なぜだか勝てるような気がしていた。彼は俺を裏切らないから。それどころかいつだって期待を超える。彼が行動してはじめて、自分が何を期待していたのか知る。そんなことばかりだ。
「当たりませんよ、どうせ」
「柴犬。もしくはそれに近い雑種。……どうかな」
「根拠は?」
「ない。君が柴犬を飼っていたらいいなと思っただけだ」
彼は苦虫を噛み潰したような顔をして、数拍置いて溜息をついた。当たりだな、と思う。
「……来週、十三時にあのラウンジで」
不承不承ながらも彼は自らそう言った。年甲斐もなく胸が騒いだ。
「野良だったのを拾ったので、ほんとうのところは僕にもわかりません。でも、多分そうだろうなと、僕も思っていました」
ほら、と誰に言うでもなく思う。彼はこんなに素敵なんだ。自慢じみた感情だった。
「万にひとつ、僕があなたの前で泣いたとして、あなたはどうするんですか?」
「どうもしないさ」
どうもしないよ、ただかわいいなと思うだけだ。
「うそつき」
その声に糾弾の厳しさはなかった。何かを確かめるように、それはむしろやさしく響いた。
「いや、うそつきとは違うか。隠しごとが多い。言葉が足りない。お前が言わなくてもいいと思っていることは、大抵とても大事なことなんだ、赤井」
そうかもしれない。だってそういえば、君があんまりきれいで泣きそうだった日があることを、俺は君に伝えていないのだから。

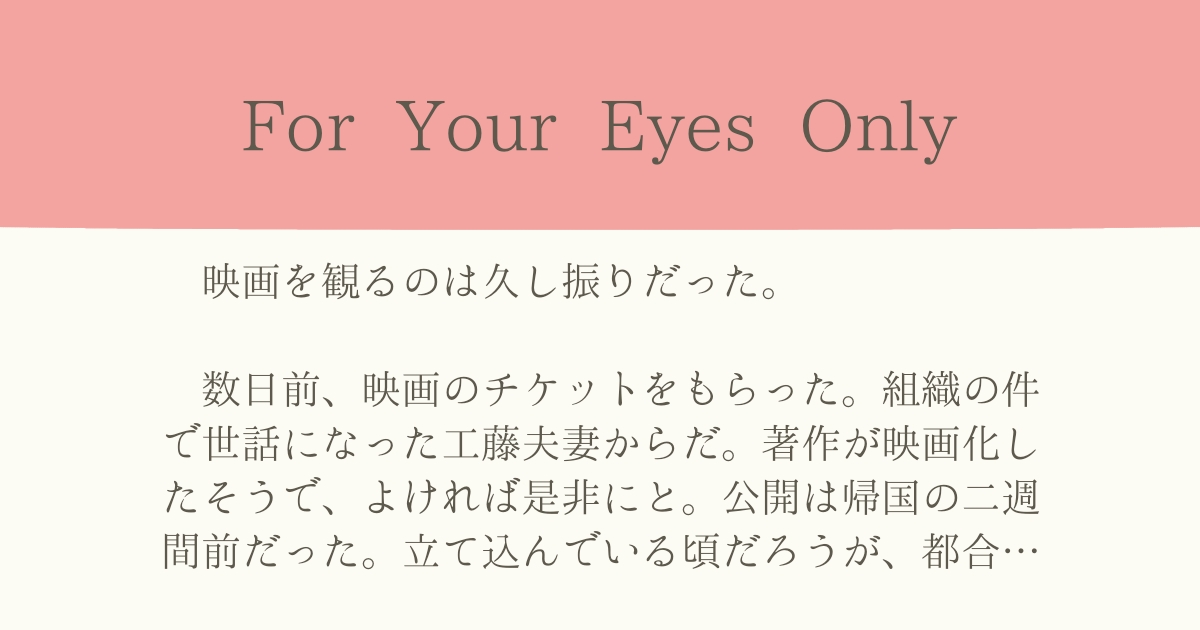
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます