瀬田薫夢:少女の初恋の話です
初恋は実らない。巷でよく囁かれるジンクスだ。初恋が実るラブロマンスもそれと同じくらいあふれていると思うけれど、それはフィクションの話であって、初恋の相手と結ばれてしあわせに過ごしているふたりのサンプルを、現実で見たことはない。すくなくとも、これまでの十五年と幾許の人生では。
……いや、そういえば一組だけ知っている。かつての友人とも言えないクラスメイトの両親は、たしか幼馴染同士で結婚していたのだった。ぼんやりと覚えている。
私の初恋の記憶も、いつかこんなふうにぼんやりしてしまうのだろうか。それは嫌だな、と思う。なんとなく確信しているけれど、だって彼女は――私の初恋のひとは、たぶん、私を忘れないでいてくれるから。そういうひとだから。
彼女の名前は、瀬田薫という。
* * *
最初は、正直に言って、なんだか変な人だな、と思った。羽丘女子学園。大学進学を視野に入れて高等部から編入した私は、彼女のことをまったく知らなかった。何も、今にして思えばほんとうに何も。羽丘内部のみならず学外にまでファンがたくさんいることは後から知った。演劇なんて興味がなかったから。
どこでだって息をするように大仰な一人芝居をする彼女。そんな彼女を取り囲む大勢のファンの女の子。へんてこだな、ひょっとしてこれが女子校ってやつなのかな、なんて呑気に考えていた。学園の王子様。そんな漫画みたいな存在がほんとうにいるなんて、ばかばかしいとすら思っていた。
部員勧誘を兼ねた演劇部の公演会を観に行ったときも、深い感慨は抱かなかった。
シェイクスピア四大悲劇に数えられる『リア王』。見事に主演をつとめた彼女は、たしかに素晴らしかった。アマチュアの高校生とは思えない胸を打つ芝居だったけれど、はまり役なのだろうとしか思わなかった。そのくらい彼女に興味がなかったのだ。オーラのある人なんだな、とだけ。そのときは不遜なことに、もしも端役を演じることがあったなら、そのときは主役を食いそうだな、とさえ思った。……瀬田薫という役者を舐めていたのだ。まったく恥ずかしい話だ。
結局、部活はどこにも入らなかった。思っていたよりも勉強がずっと大変で、これからのことを考えると気が抜けない。そのために羽丘に来たのだから。青春にうつつを抜かす暇などなかった。
それから数ヶ月後、私は彼女への認識を改めることになる。
テスト明け、好感触に高揚した気分でなんとなく立ち寄った、演劇部の幾度目かの公演。そこで彼女が演じていたのは、女の幽霊だった。胸元に血のように赤い薔薇をあしらって、この世を呪うように呻く、古井戸から湧き出す怪異。
そのとき、よくわからないけれど、とにかく衝撃を受けたのだ。彼女がオーラのある役者なのは間違いない。でもそれだけではなかった。彼女は、オーラを自在に操れる役者なのだ。舞台の上の彼女はなんにだってなれる。王様にも、幽霊にも、そして王子様にも。
彼女の演じる怨嗟と無念が私の心と反応する。恐ろしい。悲しい。……愛おしい。自分が幽霊の一言一言、一挙手一投足に、感情を揺さぶられているのがありありとわかった。舞台に引き摺り込まれてゆく。自分はこんなにも虚構に惹かれる素質を持っていたのか。
舞台はあっという間に終わった。幕が下り、やがて緞帳の向こうから演劇部の声がする。けれどそれはがたがたと大道具を運ぶ音と変わりなく、言葉としては耳に入ってこない。観客はみんな立ち去っていて、私だけが椅子に腰掛けて呆然としていた。まばたきをすると涙がこぼれた。目が乾いていた。
「やあ、子猫ちゃん」
舞台が終わってはじめて耳に届いた、意味のある言葉だった。だから、子猫ちゃんとは私のことなのだと、自然に思えた。
「瀬田、先輩……」
あ、このひと、背が高いんだ。座ったままで振り返ると、会場の入り口に彼女が立っていた。背中に夕陽を浴びて、逆光の落とす影が神秘的で、そこは既に舞台だった。彼女がただそこに佇み呼吸をするだけで、世界は舞台になる。やっと理解した。私がこれまで彼女の観客ではなかっただけで、彼女はずっと役者だったのだ。
「そろそろ下校時間だよ。ここも鍵が閉められる」
彼女が一歩ずつ足を運んで、こちらに近づいてくる。指の先まで神経の通った優雅な所作に、魅入られて、動けない。
「どうしてここに……」
「下校の前に今日の舞台の余韻に浸ろうと思ってね。そうしたら素敵な子猫ちゃんに会えたというわけさ。今日はいい日だね」
今日はいい日。彼女にとっても。本当に? だとしたら私は、とても、うれしい。
――今日は、私にとっていい日だったのか。
そう気づいた途端、どんどん気持ちが逸って、勢いで立ち上がっていた。
「あのっ……、瀬田先輩! 今日の舞台、本当に素晴らしかったです! 私、舞台であんなに感動したの、はじめてで、動けなくなっちゃって……えっと、ありがとうございました!」
彼女は一瞬だけ驚いたような顔をして、それからまたいつもの完璧な微笑を浮かべた。気取ったような、でもそれが素敵で、今の自分は間違いなく彼女の観客なのだとわかった。昨日までの私とは、もう違う。彼女はずっと変わっていない。私を招いて待っていたのだ。私は最初から、彼女の子猫ちゃんだった。
「ああ、なんてことだ! 私の儚さに魅了されてしまったとは……なんて罪深い……! ……しかし、下校時間は待ってくれないからね。そろそろ出ないと」
さあ、と差し出した彼女の手を見つめる。私はこの手を取っていいのだろうか。ほんとうに? それは……それはなんて、しあわせなことなのだろう。
逡巡は彼女の微笑が終わらせた。私はきっと何もかも許されていた。
彼女に手を引かれて臨んだ薄暮は、これまでで最も尊くあざやかだった。彼女の儚さが世界のきらめきを増すことを、私を世界でいちばん輝く女の子にしてくれることを、もはや疑いようもなかった。肌を撫でる風すら心地よく、そのとき私はきっと世界の主人公だった。
儚さは刹那。
翌朝、登校した私は、見慣れた風景だったはずのファンと戯れる彼女の姿にたしかにショックを受けていた。あ、私、かわいくない女の子だ。彼女はみんなの王子様。だけど、それは……嫌だ。私はあのファンの子たちとは違う。彼女たちのようにはなれない。馴染めない。あんなふうに、みんなにひとしく注がれるやさしさをみんなで喜ぶことは、できない。
どうしよう――。
漠然と不安だった。曇天、かすかな寒気。なんだかとてもひとりぼっちで、どうしようもなく恋だった。
テストが終われば次のテストが待っている。この授業もちゃんと聞いておかないと、後悔するとわかっていた。それなのに、十六世紀末の歴史は頭の中まで入ってきてくれない。
恋。恋っていったいなんだろう。あまりよくわからない。けれど、彼女のためにこんなにもかき乱されるこの気持ちを恋と呼ばないのなら、今後の私の人生に恋が訪れることなんてあるのだろうか。……先のことなんてわかるはずもないのに、そんなことを考えてしまう。今この瞬間、私はきっと恋をしている。そうでなくては、私と世界の関係の変化を説明できない。恋とはまばゆさと疎外感なのだろうか。
好き。瀬田先輩が、好き。
それだけで、全身の細胞が生まれ変わったみたいだった。
放課後の雨は静かに降り籠めていた。傘は持っていない。止む気配はなかった。何をするでもなく玄関でぼうっとしていると、今日一日ずっと頭の片隅にいた彼女が歩いていくのが見えた。よかった。彼女は傘を持っていて、雨の中をちゃんとひとりで帰れる。傘を持つ白い指先すらうつくしい。なぜかうれしくなった。
ふと、彼女がこちらを振り向いた。目が合う。どうしてだか近づいてくる。違う、咄嗟に自制。だって彼女は他の用事でこちらに来ているだけで、そこにたまたま私がいるだけかもしれない。そうやって必死に自惚れまいとしているのに、彼女はやはり私を見ていた。
「やあ、子猫ちゃん。昨日振り。ひょっとしてお困りかな」
困っている。傘がないこと、彼女がやさしいこと、私が傲慢なこと、何もかもに困っていた。だって、ひょっとして彼女は傘を持たない哀れな私を送ってくれようとしているのではないか。浅ましい期待に高鳴る胸がうるさくて、けれども彼女の微笑はまたしても私を許していた。
「傘が、なくて……」
「それは大変な悲劇だ……! ここで再会したのも運命。どうか私を、君を家まで濡らさずに送り届けるナイトにしてくれないかい」
ほら! 彼女は私の期待を裏切らなかった!
どうしようもなくうれしくて、けれどなぜだかさびしかった。
傘を打つ雨の音が至上の音楽に聴こえるのははじめてだった。雨は世界で最も細い檻、傘は世界で最も狭い密室だ。だから私は、今だけ先輩とほんとうにふたりきりだった。私が傘を持つべきだと思ったけれど、彼女のほうが背が高いからと断られてしまった。
「瀬田先輩は、あのとき困っていたのが私じゃなくても、こうして傘を差し出しましたか?」
「きっとそうしただろうね。でも、だからこそあの場にいたのが他の誰でもなく君だったことは、運命だと思っているよ」
彼女がそう答えるのは、頭のどこかでわかっていた。けれど、実際に彼女の声でそう言われると、嫉妬はすっかり鳴りを潜めて、ただただよろこびだけが湧き上がってきた。不思議だった。彼女の声は魔法みたいに心まで届いて染み渡るのだ。
「瀬田先輩。……恋って、なんなんでしょう」
声は傘にぶつかって跳ね返って、滴る雨に閉ざされて、どこにも漏れていかないような気がした。だから、簡単に口からこぼれた。
「恋、か……以前、恋に落ちた男の役を演じたことがあるよ。愛しく、切なく、苦しく、狂おしく、胸が締めつけられるような思いだった。この恋のためなら人生を擲ってもいい。心からそう思っていた」
「瀬田先輩は、恋をしたことはありますか」
「そうだね」
そうだね。そうだね、ってなんだろう。ただの相槌なのか、肯定なのか、どちらとも取れるような調子だった。
「私にとっての恋は、シェイクスピアの言葉だ。私を惹きつけて止まないよ」
なんだかホッとしたような、がっかりしたような、複雑な気持ちだった。
「それ、恋なんですか?」
「私が恋というのなら、それは既に恋さ。言葉の解釈は人それぞれだからね」
そうか。そうなんだ――。
突然、何かがわかった。彼女の恋が、私の恋を許してくれた。そんな気がした。その方向はちぐはぐなような、噛み合っているような、それはよくわからないけれど、きっとたしかに許されていた。それを彼女は私にくれた。
「瀬田先輩が好きです」
躊躇はなかった。そのとき私はなぜだかとても、彼女のことを信じていた。
「恋、してます。瀬田先輩に」
「……ありがとう。うれしいよ」
決して必要以上の言葉はなかった。けれどそれがじゅうぶんで、最適で、最も私にふさわしかった。
彼女のやさしさそれ自体が、この恋の行き止まりだった。それはもうわかっていた。それでも、彼女はただ彼女であるというだけで、私の恋をやさしく許して、殺さずにいてくれた。付き合うだとかフラれるだとか、そういうわかりやすい形で実ることはなく、けれど日陰で腐ることもなく、不思議につぼみが膨らむのがわかった。
「私の初恋が、瀬田先輩でよかったです」
「……それは光栄だね」
「そう思ってもらえると、うれしいです」
不意に、だいすきがあふれた。頬が緩んで、うずうずした。
なんとなく、こんなに彼女と話し込むのは最後のような気がした。なんでも話してみたかった。彼女は何もかも受け止めてくれる気がして、それに甘えてみたくなった。
「私、中学生の頃、夢ができたんです。そのためにはじめて将来のことを考えて、大学に進学したいと思って、勉強して、受験して、羽丘に来たんです」
彼女が全身で私の話を聞いているのがわかった。すこしだけ歩幅を狭くした。それでも雨は私を打たなかった。彼女の傘はずっと変わらず私の上にあって、なんだか泣きそうになった。
「羽丘に来てからも毎日がんばって勉強して、それでいいと思ってたんです。でも、昨日の公演を見て、こういうのがあってもいいんじゃないかって思いました。たしかに将来の夢はあるし、そのためにがんばらなきゃいけないけど、もっと別の、毎日がきらきらするような……そう、青春が! そういうものがひょっとして私はずっと欲しかったんじゃないかなって……だから……」
私の要領を得ない言葉を、彼女はちゃんと聞いていた。彼女の顔を見上げると、彼女も私を見てくれた。
「これからも、私の青春のために、瀬田先輩を追いかけていてもいいですか」
「もちろん。私は大歓迎さ」
やっぱり、彼女は何もかも受け止めて、私の期待に応えてくれる。
「……古い友人のことを思い出したよ。彼女も、目標に向かって堅実な努力を欠かさない人でね。彼女の夢は私の元にはなかったけれど、どうやら楽しくやっているらしい。私が君の青春の一頁になれるのなら、こんなにうれしいことはないさ。感謝するよ。ありがとう」
たぶんそのとき、私ははじめて彼女の中にも存在するやわらかい部分をうっすらと見た。見せてもらった。幾重ものベールの向こうにある、瀬田先輩の大切。きっと私が自分の話をしたから、彼女も同じだけ話してくれたのだ。そう思った。ほんとうに、どこまでもやさしいひとだった。
「瀬田先輩は、夢とかありますか? ……あ、役者として引く手あまたって感じなのかな」
すっきりとした凪いだ心で、何かを繋ぎ止めるように尋ねた。家が近い。まだ、もうすこしだけ。
「この世は舞台、人はみな役者。どんな仕事であれ、私は世界を笑顔にしながら生きていくよ」
「世界を、笑顔に……」
それはあまりに途方もなくて、驚いたけれど、とても彼女にふさわしかった。似合っている。カッコいいな、と思った。
「これは私が言い出したことではないんだ。最近、ハロー、ハッピーワールド! というバンドでギターを弾いていてね。世界を笑顔にしようと誘われたんだ。近々ライブをやるから、君にもぜひ来てほしい」
「はい! 絶対、絶対に行きます」
とうとう家についてしまった。もうとっくに雨脚は弱まっていて、走って帰ってもいいくらいだった。それでも私は何も言わず、彼女も沈黙してくれていた。
ほんとうにありがとうございました。大事な子猫ちゃんに風邪を引かせるわけにはいかないからね。それじゃあ、また明日。また明日、今日はあたたかくして寝るんだよ。
そうやって別れた。先輩の家はどこなのだろう。もしもまったく反対だったら、申し訳ないことをしてしまった。けれどこの放課後は、私にとって大切な思い出だった。
それから、私は演劇部の公演も、ハロー、ハッピーワールド! のライブも欠かさず行くようになった。ファンの子たちと一緒に話すことはまだすくないけれど、それでもなぜか、何かがとても大丈夫だった。勉強ももちろんするけれど、毎日それだけではなかった。羽丘に来てよかったと、何度も何度も思った。
ホワイトデーの公演では、うっかり泣いてしまった。黄色い歓声に包まれてきらめく彼女を、心から好きだと思った。彼女はみんなの王子様。だから、こんなにも好きになった。
一輪の薔薇と、私に宛てたメッセージカードを貰った。名乗ったことなんてないのに、彼女は私の名前を知っていた。きっとここにいるみんなそうなのだ。「彼女とみんな」ではない。観客の数だけ「私とあなた」がある。
瀬田先輩はすごいな。瀬田先輩がだいすき。そう思う気持ちに、嫌な感じはもう混ざっていなかった。どうしてなのか、説明することはできない。でも、彼女のおかげだった。
私の初恋は、たぶん、実ってはいない。けれど、たとえ実らずに咲く花だとしても、とてもきれいだ。いつかこの花が枯れたら、そうしてすこしゆたかになった土に、また新しい花が咲くのかもしれない。でも今はなんとなく、この花は永遠に咲いているような気がする。
受け取った薔薇は、小瓶に生けられて今も咲いている。プリザーブドフラワーにしてみようかとも思ったけれど、とてもいい香りだからやめた。
これは瀬田先輩に貰った薔薇。

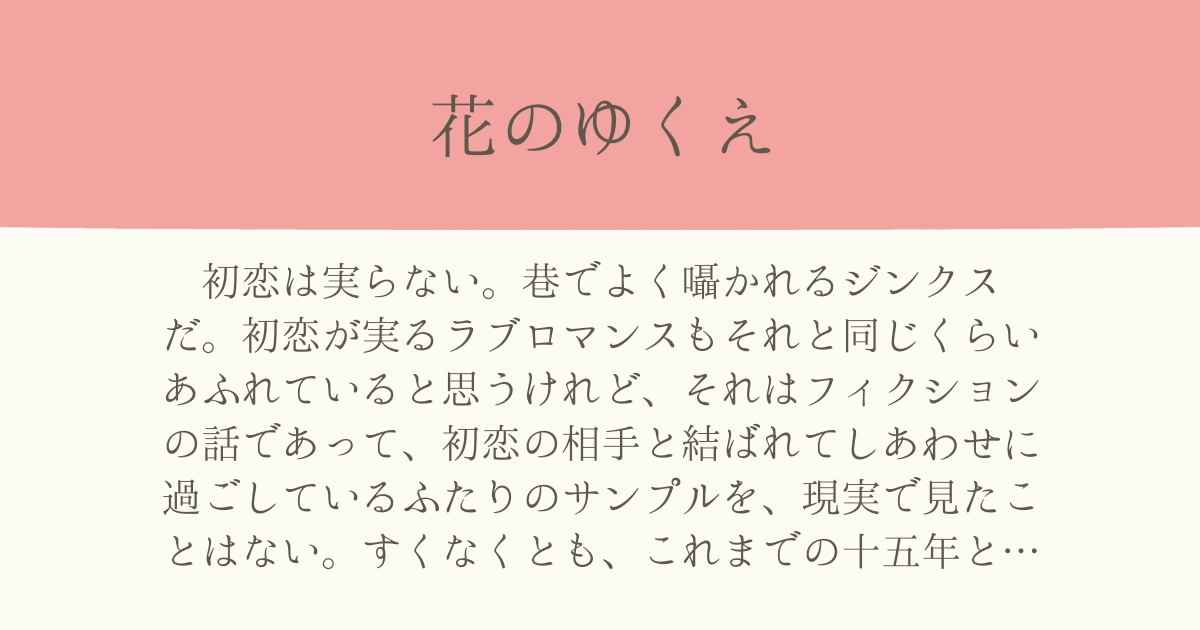
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます