かおちさ:キスシーンを演じることになった千聖が喫茶店で薫とお喋りする話です
白鷺千聖は、窓際の席に佇む女性が物憂げな表情で本の頁を捲るのを、店の外からしばし見ていた。本来ならば、ほんの数分といえど彼女を待たせていた千聖は、慌てた様子で店のドアベルを鳴らしてみせるのが正解だろう。けれど千聖は、そうする必要があると上手に感じることができずにいた。幼馴染がもたらす理解と感覚の乖離。深呼吸をひとつして、自分を整える。
喫茶店のドアベルが軽快に鳴り、待ち人は顔を上げた。既に何度その動作をしたのだろう。たぶん、毎回きちんと確認して、赤の他人でも目が合えば微笑したのだろう。
「ごめんなさい、前の仕事が押してしまって……」
それは完璧な発声だった。千聖のことを知る誰もの期待を裏切ることのない、いつもどおりの声音。
「気にすることはないよ、千聖。君を待ちながらシェイクスピアの言葉と戯れる時間も、とても有意義なものだったからね」
彼女、瀬田薫もまた完璧な微笑を千聖に向けた。こういうどこか上滑りするようなやりとりは、自分たちらしいような気がした。そう感じるたびに、千聖は遠くに来たように思う。
本当に意味を理解しているのか怪しい戯曲を愛読する薫が、千聖の目には滑稽に映る。けれど同時にそればかりではないことも知っていた。ひとたび役をその身に降ろせば、理解などはるかに超えた次元で薫は完璧な演技ができる。天才役者。思考が一瞬だけ過去に飛ぶ。天才子役・しらさぎちさとちゃん。けれど本当は。ばかばかしい。回想終了。
そこは、千聖の一等お気に入りの喫茶店のひとつだった。敢えて順番をつけるなら三番目くらいだろう。徒歩圏内で、適度ににぎやかで、しかしうるさすぎない、居心地のよい店。アイスティーとガトーショコラのおいしい素敵な場所。
「いい雰囲気の喫茶店だね。相変わらず趣味がいい」
薫の前には一口ぶんだけ量の減ったアイスティーが置かれていた。グラスは汗をかいていて、千聖は改めて彼女を待たせた時間を想った。店員に自分もアイスティーを注文して、薫を見つめる。彼女と美醜の価値観がおよそ一致することへの、不満、諦観、安堵、信頼。薫は何もかも了解したように笑う。わかっているのかいないのか。
今日ここに薫を呼び出したのは千聖だった。両親からの頼まれごとというわけでもない。だから薫は、千聖が何か相談……相談というのも癪だが、話したいことがあるのだということを知っているはずだった。けれどだからこそ、薫から切り込んでくることはない。
「何を読んでいたの?」
「君もよく知っている、ロミオとジュリエットさ。めずらしい君のお誘いなんだ。私たちの思い出に浸りたくなってね」
それは千聖にとって都合のいい会話の糸口だった。正直、呼び出したはいいものの、どう切り出せばいいものか迷っていた。
「そういえば、麻弥ちゃんから聞いたわ。薫、私が稽古に合流する前に脚本に手を加えていたそうね」
「……そんなことが、あったかな……」
薫は一瞬だけ目を泳がせて、アイスティーに口をつけた。そうしてほっとしたように表情を緩ませる。そうよね、ここの紅茶はそういう紅茶だわ。千聖も飲みたくなったが、まだ彼女の紅茶は来ていなかった。
「なんでも、先輩方の残していた脚本には、フリとはいえキスシーンがあったそうじゃない。それを書き換えるよう頼んだんですってね」
「ああ、そうだったね」
千聖はこの先の追求についての言葉をすこし悩んだ。薫を困らせることは息をするようにできるが、今はそのときではないと思った。
「どうしてそんなことをしたの?」
結局、千聖は当たり障りのない疑問を投げかけた。
「ジュリエット役はあの白鷺千聖――そう銘打たれた舞台にキスシーンがあれば、ますます話題になるだろう。……君は芸能活動をしているプロだ。もし君の不利益になるような噂が立ったらと思うと、気が気じゃなかったのさ」
薫の言うことは至極当然だった。千聖は胸がほっとするようなざわつくような、曖昧な苛立ちを覚えた。そして、苛立っている一方で、どこか冷めてもいた。薫は時々そうだった。他人を顧みずにマイペースに自分の世界を生きているようで、不意に他者への配慮を見せる。千聖はただ溜息をついた。それしかすることがなかった。それ以外のすべてがきっと不正解だった。
「……それだけじゃないんじゃない?」
まだ何かあるだろうと千聖は踏んでいた。薫の声音は、彼女の子猫ちゃんならそこで引くようなものだったが、生憎千聖はそうではなかった。
「……たとえ役者であっても、身体はひとつだ。君のくちびるを大切にしたかった」
それはどこか芝居がかった台詞で、なのに瞳はやさしかった。ほら、と千聖は思う。そうやって不意をつく。
千聖にはある境界が、薫にはない。それを感じるとき、千聖は困惑したような心地になる。
千聖が他者に対して引いている一線は明確だ。女優やアイドルとしての『白鷺千聖』と、素の白鷺千聖は違う。ほんとうに打ち解けたい人間には、素の白鷺千聖を見てほしいと考える。
しかし薫はそうではない。大仰な仕草も名言の引用も、ときたま見せる鋭さも、何もかも一直線上でつながっている。
薫は変わった。たしかに千聖はそう思っていた。今の薫のことが、千聖にはわからない。ふと千聖の脳裏に氷川日菜の顔が浮かんだ。パスパレのみんなはあたしのことをわかろうとしてくれる。今の薫をわかろうとすることを、千聖はたぶん、最初から諦めていた。そのための努力を怠った。ふたりの今はその結果だった。
千聖の視線が落ちる。アイスティー、飲めばいいのに。溶けた氷で水嵩が増していた。もう最初の味には戻らない。
千聖がそう考えたところで、薫はストローに口をつけた。そのくちびるをなんとなく見つめる。おいしいね、千聖。ええ、私、このお店のアイスティーとガトーショコラがお気に入りなの。へえ、次に来たときにはガトーショコラも頼むよ。そう、好きにしたら。
そのとき、店員が千聖の頼んだアイスティーを運んできた。礼を言ってひとくち飲む。それは期待通りおいしかった。
たとえ役者でも、身体はひとつ。他愛もないやりとりを重ねながら、千聖は薫の言葉を反芻していた。身体をメンテナンスして、コントロールして、千聖はステージに立ち、フィルムに映る。『白鷺千聖』として当たり前の行為だ。
「薫は、キスしたことはある?」
「あるよ」
照れる様子もなく即答する薫に、千聖は一瞬だけ面食らったが、すぐにその理由を察した。
「ちいさい頃におばさまと?」
「そうだよ」
「もっとちゃんとしたキスは?」
「ちゃんとした? 母とのキスだってちゃんとしていたさ。私は愛を受け取ったからね」
埒が明かない。しかしそれは千聖のせいでもあった。千聖はあわよくば自分が抱えているものを何も打ち明けることなく薫から何かを得たい思っていた。薫がそれを察したところで自分を責めることはないだろうとも、心のどこかでわかっていた。
「……薫は、もし今度の舞台にキスシーンがあったら、どういう気持ちで演じるの?」
「……それはもう、儚い気持ちさ」
千聖はまた溜息をついて、あなたに聞いたのが間違いだったわ、と言おうとした。そのとき、不意に薫が名前を呼んだ。千聖。会話のテンポが乱れる。
「舞台の上で醜くなることを恐れる必要はないよ」
それは確信めいて発せられた言葉だった。すこし不本意だが、千聖はたしかにこれを待っていた気がした。
「醜くなることを恐れずに演じていれば……千聖があらかじめ持っているうつくしさが滲み出す。そしてそれはきっと『千聖』のものにもなる。……そういうことさ」
そういうこと。どういうこと? ほんとうに? 刹那よぎった疑念を打ち砕いたのは、脳裏に浮かんだアイドル――Pastel*Palettesのボーカル、丸山彩の姿だった。
千聖は、自分の容姿がこの現代日本においてかわいらしい、うつくしいとされるものであると自覚していた。それに磨きをかけるための営みを日々怠ることはなかったし、人前に出るときは、どんな瞬間でも誰かに見られている自覚を持って、緊張感を忘れないようにつとめてきた。
それは、ずっとアイドルを目指して努力し続けてきた彼女だってすくなからずそうだろう。摂取カロリーのコントロールを忘れがちだったりするけれど、彼女だって自分磨きを意識して過ごしている。けれど思い返してみれば、未熟で、けれども懸命で愚直な彼女は、どんな瞬間もうつくしかった。泣きそうでぐちゃぐちゃな顔も、盛れていない他撮りも、今では不思議と愛しさを呼び起こす。それは、表面的な美醜を超えた、あらかじめ彼女に備わっている内面的なうつくしさなのだろうか。
そう言われたならば、自分はきっと納得するだろうと、千聖は思った。それどころか、彼女のうつくしさを否定されるようなことがあれば、自ら進んでそう考え、主張する姿さえ想像できた。彼女は応援したくなる魅力を持ったアイドルだ。――だって、私も隣で、応援している。
キスシーン。薫に仮定として投げかけたその問いは、今まさに千聖が直面しているものだった。今後のキャリアを考えても確実にこなすべき役に課せられたキス。それ自体に抵抗があるわけではない。しかし千聖は、それを演じることに一抹の不安があった。
もとより千聖は薫のような天才肌ではない。役に対する理解を深めてすこしずつアプローチしてゆくタイプだ。だが、キスは? 何も自分自身がキスを学ぶ必要はないだろう。そもそもそんな打算的なキスが演技の糧になるとは思えない。けれど、キスの演技に応用できるような自身の体験が、どうにも千聖には思い浮かばなかった。
麻弥からロミオとジュリエットの話を聞いたのはそんな折だった。そこにあるはずだったキスは、薫の手によって遠ざけられていて、千聖はそれを知らずにいた。それに向き合うことで、必要な何かが得られるという予感があった。輪郭すら掴めていない何か。そしてそれを、やはり千聖は薫から得た。
役者であっても身体はひとつ。……たぶん、千聖は不安だった。もとよりパーソナルスペースが狭いほうではないが、決定的な身体の接触によって、素の自分と『白鷺千聖』の境界が揺らいで、演技が半端になるのではないかという懸念があった。どんな演技をすればいいのかさえまだ掴みあぐねているのに。
しかし薫はそれでいいと言う。それを恐れる必要はないと。果たしてほんとうにそうだろうか。疑う気持ちがないわけではなかった。
――それでも、今の千聖は、Pastel*Palettesの白鷺千聖だった。丸山彩というアイドルの持つきらめきを隣で見つめて知っている。そんな彼女の視線の先にある夢に向かって、共に歩みたいと思っている。
信じてみようかと、千聖は思った。幼馴染を、丸山彩を、そして自分を。思い返せば、ジュリエットを演じたときだって、千聖は屋根裏部屋で埃を被っていた自分自身を『白鷺千聖』に昇華してみせたのだ。
「……余計なお世話よ、薫」
喫茶店を出たふたりは、しばらく連れ立って歩いていた。千聖は適当な理由をつけて店の前で別れようかとも思ったが、今日くらいはいいかもしれないという気分になっていた。
ふと遠くの川辺に鷺を見つけた千聖は、しかし何も言わなかった。それは千聖にとって、名前にその字が含まれているものの、だからといって親しみがあるわけでもない、ただの水鳥に過ぎなかった。それにはしゃぐような歳でも性格でもない。すくなくとも、薫といるときは。
「見てご覧、千聖! あれは白鳥かな」
「馬鹿ね、こんなところにいるはずないでしょう。あれは鷺よ」
千聖は考える。もしも鷺を見つけたのがPastel*Palettesのメンバーと一緒にいるときで、はしゃいでいるのが彩や、あるいはイヴだったら? 見て見て、おっきい鳥がいるよ! あれはなんという鳥ですか? フィンランドでは見たことのない鳥です! ……すくなくとも、自分の態度はもっとやわらかいものであるような気がした。
「白鳥は水面の下で足掻くって言うでしょう。脚が見えていたら鷺よ」
「へえ、千聖は物知りだね」
鷺より白鳥のほうが余程親しみを覚えると、千聖は常々思っていた。努力は人に誇示するようなものではない。けれど欠かすわけにはいかない、して当然のもの。そうやって白鳥は日々泳いでいる。
鷺は羽ばたいてどこかへ飛んでいった。
そろそろ別れの時間だった。千聖には家まで送ってもらうつもりなどなかったし、千聖がそう望むなら、薫はついてくるようなことをしないだろうと、千聖はわかっていた。
「……鷺は……いったいどこで努力しているのかしらね」
それは、あまり意味のない呟きだった。答えを求めるわけでもない、ひとりごとに近い何か。それでも薫は律儀に答えた。
「これまで生きて、こうして飛んだからには、それでもどこかで人知れず努力していたのだろうね」
生きて、飛んだからには。それは千聖の胸のうちに何かをぐるぐると巡らせたが、具体的な形になることはなかった。たぶん、Pastel*Palettesと、彩と、自分のことを考えていた。それだけはなんとなく自覚していた。
それからありふれた挨拶をして、千聖と薫は別れた。それじゃあ。またいつでも歓迎するよ、今日はありがとう、『千聖』。……じゃあね、薫。
薫は、かつて読んだ雑学本のことをちらりと思い出していた。白鳥は、世間で言われるように足掻いているわけではなく、浮力を利用して存外優雅に泳いでいるらしい。けれど終ぞ、それを口にすることはなかった。単に言いそびれただけさ。誰に言うでもなくひとりごちて、薫は帰路についた。

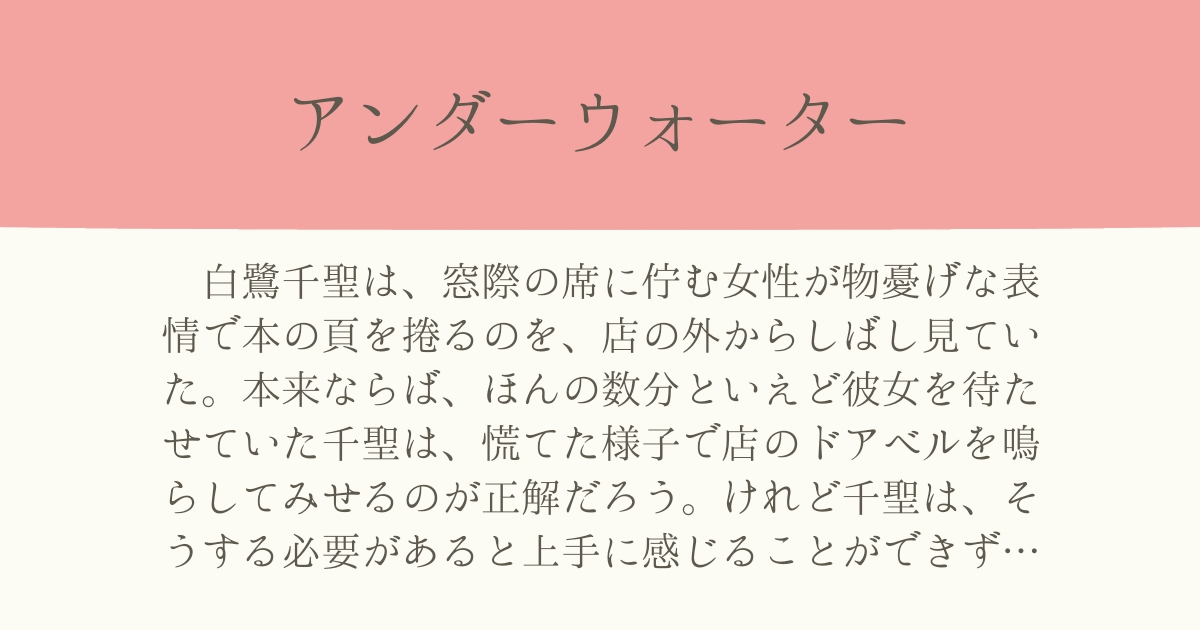
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます