かおちさ:大学生のかおちさがバイクに乗って夜明けの海を見に行く話です
まだ日も昇らない午前四時十二分、瀬田薫は着信音に起こされた。咳払いをひとつ。液晶を確認。
幼馴染の名前。白鷺千聖。
「……やあ、千聖。おはよう」
電話口の向こうで千聖が何も言わないので、薫はすこし大袈裟に息を吸って、溜めて、それから挨拶をした。果たしてそのささやかな音は千聖の耳に届いただろうか。薫はどちらでもよかった。急かされたように感じてほしくはないし、すわ切られたかとも思ってほしくない。いずれにせよ、そういう時間がないといいし、あったとしてもすこしでも短いとよかった。
今日は平日だが講義はなく、予定こそあれこんなに早起きする必要はなかった。もちろん朝にだって儚いものはたくさんあるから、それはそれで素敵なことではある。
ただ、千聖から薫に電話をかけたことなんて数えるほどしかない。薫はその一つひとつをよく覚えていた。そしてこんな早朝に電話をかけてきたことは、今までに一度もなかった。
「薫、去年バイクを買ってたわよね」
「ああ」
「タンデムできる?」
「もちろん」
そこで千聖はすこし沈黙した。四時十四分、十五分。薫の目は徐々に闇に慣れてきていた。
「……夜明けを見に行かない? 夜明けの海を」
「十五分で君の家に行くよ。髪を結んで、動きやすい服で待っていてくれ」
なんの迷いもない即答だった。それ以外の返事を薫は最初から持っていなかった。
午前四時二十八分、ライダースジャケット姿の薫が千聖の家の前に着くと、低めの位置で髪を縛った千聖が待っていた。デニム姿は彼女の細い足を際立たせる。久しく履いていなかったものだが、体型が変わっているはずもなかった。
「待たせたね」
フルフェイスのヘルメットを手渡す。薫は最初にバイクを買ったときからヘルメットをふたつ揃えていた。二人乗りが法的に可能になるのは一年先だというのに。でも、そうでないのは変だから。
そしてそれが可能になったのはつい先日のことで、だからタイミングがよかったのだ。一年寝かせたこのヘルメットをはじめて使うのは千聖だった。
今日という日が千聖にとってどんな日なのか薫は知らなかったし、彼女が何も言わないのなら知らないままでもよかった。けれど、そう、――間に合ってよかった。
「別に待ってないわ。着替えて髪を縛るのに十五分しかくれないほうが急ぎすぎじゃないかしら?」
「気が利かなくてすまない。他でもない君からの誘いなんだ。居ても立っても居られなかったのさ」
そう言うあいだも薫はバイクから降りなかった。千聖はエスコートの不要なお姫様だから、それでよかった。薫のうしろに跨り、腰に手を回す。ぬくもりなんてなかった。夜の寒さが染み込んだ身体は、むしろつめたい。それでもその瞬間、ふたりは確かにふれあっていた。
振動から加速が伝わる。風が頬を叩く。もっと着込んでよかった。千聖はすこし後悔しながら、なすすべもなく薫を抱きしめていた。力加減に気を遣っていたのは数分前の話で、もうそんなことは言っていられなかった。それでも薫のスピードはそう速くなく、つとめて安全運転だった。会話はない。声を張り上げてまで話すことなど何もなかった。
海岸沿いを走るようになったのは、随分経ってからだった。空はもう白みはじめていて、これが見たかったのかどうか、千聖はよくわからなかった。ただ、きれい、と思った。それと、間に合うようにもっと飛ばしてもよかったのに、とも。けれど考えればわかることで、千聖の生命を預かった薫がそれを第一にしないわけがなかった。
浜に降りることのできそうな場所でバイクが止まり、薫は気障ったらしくヘルメットを外した。夜明けの光を浴びながら微笑む薫は、きれいだけれど千聖にはすこし退屈だった。幼馴染のきらめきは千聖にはちっとも眩しくなくて、Pastel*Palettesととして歌い、演奏してきた楽曲の数々がなぜだか頭でリフレインした。アイドルという光。丸山彩の歌声。白鷺千聖の人生のバック・グラウンド・ミュージック。
スニーカーでも砂浜は歩きにくかった。足が沈んで、砂を蹴って、靴の中に入り込む。
「座るかい?」
「……歩きたいわ」
薫のポケットの中のハンカチは、千聖が座るときに地面に敷くためのものだった。あるいは濡れた足を拭くための。けれどどうやら使われることはなさそうで、薫はまったく、それでよかった。千聖が求めないことは、なんだってしたくなかった。
夜明けの薄紫色は世界の調和そのものだった。水平線を眺めて、ふたりはあてどなく歩いた。それだけ、本当にそれだけで、朝焼けが終わるまで、ただただそうしていた。千聖はずっと目を細めながら太陽を見ていた。
「薫は、何を見ていたの?」
熱心とは言わないまでも、今の千聖は薫の見る世界に興味があった。薫が何を見ているのかなんて、あの頃は考えたこともなかった。たとえ隣に立っていても見ているものは違う。それでも隣に並び立つことはできる。Pastel*Palettesが教えてくれたことだった。
「月が見えなくなっていくのを見ていたよ。もうかなり薄いけれど、ほら、あのあたりにある」
薫が指さす先には、言われてみればうっすらと月があった。今にも消えそうな、けれど確かにそこに在り続ける月。薫の見つめている世界。
「儚い?」
「……ああ、とても儚い」
「そう」
それが儚いことは千聖にもわかった。千聖なりに。薫の言う儚いのすべてを千聖は知りようもないけれど、それでも今はそう思った。刹那の共感。それは千聖にとっても儚いものだった。
「そろそろ戻りましょう。事務所でレッスンがあるから」
「仰せのままに、千聖」
今日の薫がやけに静かであることには、千聖も気づいていた。薫は常に千聖の意志を尊重するが、今日はことさら慎重になっているように思えた。
それは千聖のためであり、薫のためでもあった。千聖がここまで突飛な形で薫を頼ったことはなく、声をかけられてうれしいなんて気持ちばかりでもないのだろう。
……薫にできることなら薫はなんだってしたいけれど、千聖がされたくないことは決してしたくない。かといってとても心配しているというふうでもない。薫は千聖を信じていたから。千聖が在りたい千聖のために、千聖を信じる薫のために、薫の水面はただ凪いでいた。
「……今度、人を殺すわ」
薫はすこし間を置いて、うん、のような曖昧な相槌を打った。それだけで、薫が何もかも受け取ったことを千聖は確信した。何歩か進んでから、彼女は再び口を開いた。空はもう当たり前の顔をして青い。
「恋人を殺してしまう映画よ。随分前に探偵役を演ったけれど、犯人になるのははじめてね。探偵のいるミステリーではないけれど」
成人を控えた千聖は、女優として転機を迎えつつあった。これまでに演じたことのない役柄で、世界に爪痕を遺そうとしていた。
今度こそ薫は何も言わなかった。全身で千聖に関心を寄せながら、それでも、何も。相槌すら。
「……今、ちょっとは自分が殺されるかもと思った?」
それは場に不釣り合いな冗談だった。薫がそんなことを思うわけがなかった。千聖はそんな女優ではないから。
「いいや。……千聖のことを考えていたよ。千聖を見ているときは、いつだって」
それはきっと核心だった。
千聖と薫の脳裏にはきっと同じ少女がいた。ある時まで当たり前に側にいたのに、もういない女の子。あの日、千聖が遠ざけて、薫が見送った、普通の女の子。ふたりが揃って立ち会っていたのに、ふたりは共犯者ですらなかった。そんな甘美な響きは似つかわしくない。
千聖は今日、“忘れてしまった話”をするために、薫を呼んだのだ。
「薫は……人を殺すって、どういうことだと思う?」
動機は人の数だけ、なんて話が求められていないことは明らかだった。迂遠に、けれど確実に、ふたりはあの日の話をしていた。
やや長い沈黙だった。
「……何もできない、ということかな」
薫はずっと、その返事を持っていた。持ち続けて生きてきた。沈黙は彼女の躊躇そのものだった。
ふたりはどちらともなくいつの間にか立ち止まっていた。漣の音が耳について、千聖は薫に向き直る。……棒立ちの薫を見るのは、随分と久し振りだった。本当にこの世が舞台なら、今、彼女は。
「……そうね」
何もできない。ふたりにとってのそれは、どうしようもなくそうだった。そうするよりほかない。すくなくともそのときは、それ以外に何も取りうる手段がない。
たぶん、ただの確認だった。けれど千聖は、それを薫と確かめたかった。ひとりの女優として、今では役者の幼馴染と。
「薫」
陽光はまぶしいくらいなのに、肌寒い。ぬくもりは光に遅れて訪ねてくる。薫も千聖ももう、それぞれのぬくもりを知っている。帰る場所がある。
「私は後悔してないわ。私が選んだから、今の私がいるんだもの。……すくなくとも、あの文化祭の日の選択は、間違いなく私の意志だもの」
あの幼き日は、あまりに世界が狭くて、限られていて、それ以外に選びようがなかったのだとしても。選んだとすら言えない、強いられたものだったのだとしても。『ロミオとジュリエット』を演じた日は、そうではなかったから。
「千聖」
薫のテンポは今度こそ乱れなかった。そういえば、薫はこんなふうに、愛しくてたまらないという声音で自分を呼ぶのだ――千聖は今更のように思った。
「……千聖。私は君のしあわせな人生を……笑顔を、いつだって願っているよ。忘れてしまっていいから、必要になったら思い出してくれ。きっと駆けつけてみせよう」
それは薫のまごうことなき本心だった。お気に入りの言葉でも、気の向くままに誇張した言葉でもない。心の底から薫はそう思っていた。
「今日みたいに?」
「今日みたいに」
余計なお世話よ、と言おうかと千聖は思った。けれどそれをすんでのところで飲み込んだ。
「……薫が必要なときなんて、もうこの先あるのかしら」
自分でも驚くほどやさしい声が出た。千聖はなんとなく、自分は大人になったのかもしれないと思った。大人びた子供ではなく、子供だった大人に。だとすれば、自分をここに連れてきたのはPastel*Palettesだ。Pastel*Palettesは、千聖の青春だから。
「なくたっていいさ。千聖が笑顔でいてくれるならね」
薫があまりに満足げで、千聖はありがとうと言ったっていいかもしれないと思った。けれどそれを言ったが最後、薫が泣いてしまうかもしれないから、やめた。泣き顔を見たいような気もしたけれど、それはどうにも子供っぽかった。今日の薫にかおちゃんみたいな顔をさせるのは、たとえすべてが瀬田薫なのだとしても、なんだかひどいことのようだった。
千聖はすこし笑って歩きはじめて、薫もそれに倣った。潮風がつめたくて、海はもうよかった。次に来るのは夏だ。スケジュールを合わせて、Pastel*Palettesで。そのときは楽しい海になる。子供のようにはしゃいで、青春のように笑うのだ。それが今の千聖の世界だった。
「薫は本当に……やさしいわね」
「当たり前じゃないか。千聖は大切な幼馴染なんだ」
千聖は薫の人間としての在り方ぜんたいの話をしたつもりだった。そういうことじゃないわ、と言おうとしてやめた。薫はついさっき言ったばかりなのだ。千聖を見ているときは、いつだって千聖のことを考えているのだと。
「……いつかまた、同じ舞台に立つこともあるかしら」
「……ああ! 本当にうれしいよ、千聖から共演の話をしてくれるなんて……さっそく各所に話をつけようじゃないか」
「いつかの話よ、今すぐじゃないわ。私、これでも忙しいのよ」
忙しい女優で、忙しいアイドル。たまの休日には花音とお茶をして、また芸能界へ。それが白鷺千聖だ。薫と幼馴染で、ライバルの。
「演目は……そうだな、『走れメロス』なんてどうだい?」
「あなた、私の頬をぶてるの?」
「……ぶってみせよう、役者だからね。君も思い切りぶってくれ」
千聖は想像する。赤い頬で笑いあい、そうして言うのだ。きみはまっぱだかじゃないか。薫は衣装を脱いでなおその皮膚でその魂で役者なのだと、世界に高らかに告げる。
そんな日が訪れたら、きっと素敵だ。
来たときのように、薫は千聖にヘルメットを手渡す。こんなことをするのは最後かもしれないと、多分ふたりとも思っていた。
「必要なものは置いてあるし、直接事務所に向かってくれる?」
「オーケー」
エンジンを吹かして、会話が終わる。凱旋がはじまる。それぞれのホームに帰るのだ。
帰路、薫が何か言った気がした。それは風に掻き消されて千聖の耳には届かなかったけれど、何を言ったのか考えてみた。答えに辿り着くことはなく、いつの間にか事務所の裏口についていた。きっともう彩は来て、練習している頃だろう。あるいは他のメンバーも。千聖のひだまりが、千聖を待っている。
薫は千聖が去ってからもしばらく動かなかった。それからスマートフォンを取り出して、もうすぐ練習に合流するよ、待たせてすまないとメッセージを送った。四時二十分に送った遅刻の連絡には既読がついていて、薫は微笑して画面を消した。

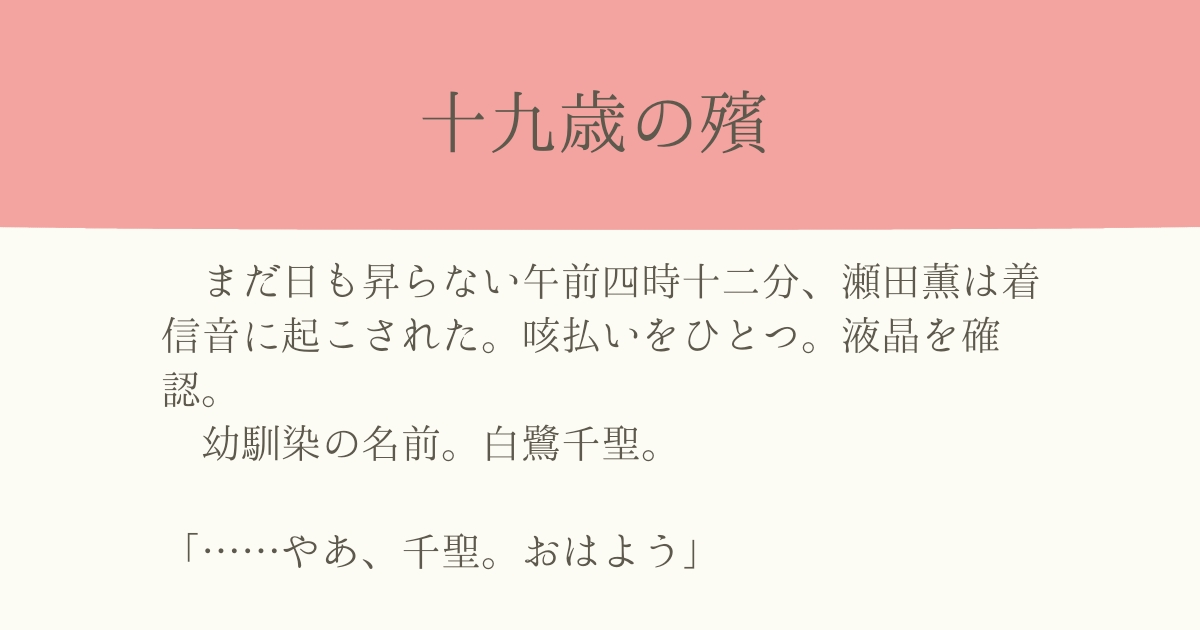
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます