瀬田薫夢:“神”を待つ家出少女が薄暮の公園で瀬田薫に会う夢小説です
・直接的な性描写はほぼありませんが、夢主の設定上、売買春の描写を含みます
神様が見つからない夜だった。
神様候補はいくらでもいて、いつだってすぐに見つかって、そうしてあたしはあたたかいお湯を手に入れるのに、今夜は誰もあたしを見つけてくれない。いつもは途中でうざったくなって、適当な神様に決めてからは他のダイレクトメッセージに返信しないくらいなのに。べったりした不安がコールタールみたいにおなかの奥に詰まってる。
ひとりだと急に怖くなるから、夜は嫌いだ。
今日もインターネットには神を待つ家出少女がたくさんいる。こんなふうに不安な女の子が、たぶんこの街にも何人かいる。
家からそう遠くはない公園で暮れてゆく陽を眺めていると、鴉の鳴き声に混ざってどこからか声が聞こえてきた。ここはもっと儚く情熱的に、いや、儚い哀愁を……そしてギターの音色。音楽のことはよく知らないけれど、これはきっとギターだ。たぶん違法の無料で音楽が聴けるアプリが消えてしまってから、めっきり音楽を聴かなくなった。聴いていた頃だって、通信制限がひどいから月頭だけ。月頭にたくさん聴いた曲を曖昧にハミングして、音楽のない月末を過ごす。今は月頭さえ音楽がない。サブスク? のアプリは有料なのか無料なのかよくわからないから落としていない。でも流石に、ギターの音くらいはわかる。
怪しい。とても怪しい。けれど、とてもきれいな音だ。興味を持って近づいてみると、そこにいたのは大人っぽい、けれどこの近辺の高校の制服を着た女のひとだった。公園のベンチに腰掛けているだけで、駅や街で見かける広告みたいにキマッている、雰囲気のある女のひと。あたしはわりと童顔で、背が低くてちんちくりんで、それが神様にはよくウケるけれど、大人っぽいひとにいつも憧れている。
彼女の制服はここらではそこそこ有名な私立の進学校で、どんな学校なのかあたしにはさっぱり想像がつかない。あたしが袖を通している制服の高校も、とりたてて頭が悪いわけでも不良が多いわけでもない普通の高校だと思う。同じ学舎にあたしみたいな女の子がいるのかはわからない。いたらびっくりするな、と思う。そんな感じの学校。教科書をぜんぶロッカーに詰めて、下着の入ったぺらぺらの鞄で、毎日ちがう家のちがうシャンプーのにおいで通う、あたしの学校。たまにラブホテルの無臭のシャンプー。神様の家のシャンプーがぜんぶこれだったらいいのにな、とよく思う。
「やあ、子猫ちゃん。私のギターに聴き惚れてしまったのかな?」
「……子猫ちゃん?」
あたしに向けて言っているのだと気づくまでにしばらくかかった。結構な間が開いたはずだけれど、そんなのまるきりなかったように彼女は言った。
「……私はバンドをやっていてね、新曲について頭を悩ませていたんだ。とびきり儚い曲にしたいのだが……」
彼女が急に自分の話をはじめたのでびっくりしてしまった。そういう神様は多い。聞いてもいない自分の話をぺらぺら喋って、それであたしがすっかり乗り気になったと思って、そのままセックスに縺れ込む神様。そういう神様は、大抵すごく自分勝手だ。
彼女にはそういう嫌な感じがなくて、不思議だな……と思っていると、ぱちりと目があった。視線が交わる。彼女が笑う。
「儚い曲? バラードみたいな?」
「バラードとは限らないさ。この世界のすべてが儚いからね」
「ぜんぶ儚いんなら、なんでもいいってことにならない?」
「……そんなことはないさ。この曲で届けたい儚さはどんなものだろう? そう考えると悩みは尽きないからね」
「へえ……そういうものなんだ」
変なひと、と思った。よく出会う神様とは全然ちがう、変なひと。
「もしよければ、考えているメロディーをいくつか聴いて、感想を教えてくれないかい?」
「いいけど、あたし音楽とかあんまり詳しくないよ」
「構わないさ」
彼女がギターを抱え直したので、あたしは彼女の隣に腰掛けた。いいにおいがする。きっと彼女はあたしと違って毎日このにおいなのだろう。いいな。
彼女が指を動かすと、空気が震えて音がした。面白い。ギターをこんなに近くで見るのははじめてだった。たまに神様の家でギターケースを見かけることはあるけれど、それはインテリア同然だった。ギターは音を出す楽器なんだ。それだけのことで楽しくなって、メロディの善し悪しはよくわからなかった。
「どんな気分だい?」
サビ? っぽい部分を弾いたのだろう。それが終わって彼女が問いかけた。あたしはてっきり「どうだった?」とか「よかった?」とか尋ねられると思っていたから、口の中に準備していた「すっごくよかった」を慌ててしまい込んだ。
自分の気分について深く考え込むことなんて、いつ以来なのかわからなかった。もうずっとあたしの中は、なんとなく不安で、なんとなくさみしくて、なんとなくイライラして、なんとなくうれしい、そんなぼんやりとしたものが常にちいさなコップからあふれかえりそうで、こぼしてしまわないようにそろりそろりと歩くので必死だった。こぼさないことに必死すぎて、こぼれそうなその水がなんなのか考えることを忘れていた。
改めて考えてみたけれど、その水がなんなのかはよくわからなかった。昔はわかっていたんだろうか? 忘れてしまったんだろうか? それもよくわからなかった。けれどあたしは今とても落ち着いていて、水面がおだやかなことはわかった。それを彼女に伝えたいのに、どうすればいいのかわからなかった。
「あのね、えっと……すっごく、すっごくよかった」
結局口にできたのはそれだけのことなのに、彼女は心底うれしそうに笑った。
「それはよかった」
よかった。あたしにもわからない内側のことを彼女がわかるわけないのに、彼女もよかったんだ、と思うと、うれしくてたまらなかった。
「よければもっと聴いてくれないかい? いくつか考えているんだ」
「うん。いくらでも」
どうせ今夜は、何もないのだから。
「ありがとう。それじゃあいくよ。次はもっと激しく燃えるような儚さを追求してみたんだ」
そう言うと彼女はすっくと立ち上がって、あたしに向けてウインクをした。それがあまりにもキメキメで、あたしはなんだかおかしかった。変なの。でも、かっこいい。
はじまった音はたしかに激しくて、情熱的に盛り上がった。音がぐるぐる回っているみたいで、やっぱり、すごくよかった。いつの間にか爪先がタンタン地面を叩いていて、これがリズム! 本当に音楽みたいだ! あたしはもう音楽の一部だった。この夕暮れの音楽を構成する、あたしはひとつの要素になっていたのだ!
演奏を終えた彼女は沈みかけた夕陽を背に立っていて、忘れたくないな、と思った。燃える夕陽を背負う彼女を、いつまでも記憶に留めておきたい。そのくらいかっこよくて、まぶしかった。
「……すごい。本当にすごい。さっきの演奏も素敵だったけど、今のもすっごくよかった。本当に素敵」
革命が起きたみたいに素晴らしかったのに、あたしの紡ぐ言葉はあまりにも拙くて、それが悔しくてたまらなかった。
さっきまで燃えていた陽が沈む。光の残滓が空を紫色にする。
「ありがとう。君という聴衆に出会えて本当によかった。おかげで新曲をどうしたいのか見えてきたよ。……君との運命的な出会いに感謝して、もう一曲弾かせてくれないかい?」
「え……」
「私のわがままにすこしだけつきあっておくれ」
そう言って彼女はあたしの隣に腰掛けて、指先を弦にふれさせた。音が鳴る。音が鳴る。音楽が生まれる。
どうしよう、と思った。彼女は自分のわがままだと言った。だったらあたしも、わがままを言ってもいいだろうか? 神様にかわいいと思ってもらうためのわがままじゃなくて、あたしのためのわがままを。
「待って!」
それはあたしがすごくすごく久し振りに出した勇気だった。迷い切る前にもう言っていた。叫ぶみたいな勢いで、そんな声は久し振りに出した。ベッドで出すばかっぽい横隔膜の震えじゃなくて、あたしがあたしの意志で叫ぶ言葉。
「あの……もし嫌じゃなかったら、録音しても……いい、ですか……」
敬語なんて使ったのはいつ以来だろう。スマートフォンを握りしめて、怖くて彼女の顔を見られずにいると、ヒュウ、と風が吹いた。
「もちろん私は構わないよ。ただ、ノイズが入るだろうし、後できちんと録ったものを送ることもできる」
それはなんだか違う気がしたけれど、でもそう言ってくれるなら……と思いかけたところで、彼女は続けた。
「でも、今この瞬間の音は今にしかないからね。風の音も鳥の声も思い出になるだろう。それもとても素敵だね」
雨が止んだように、霧が晴れたようにうれしかった。あたしが欲しかったものが急にわかった。あたしは今この瞬間が欲しい。ずっとずっと忘れたくない。だから、今この瞬間の音楽が欲しいのだ!
「……うん……」
涙が出そうだった。最後に泣いたのはいつだろう? 泣くのはなんだか不思議だ。自分に価値があるみたいで。
あたしはそっとアプリを起動して、録音開始のボタンをタップした。ティロリン、と陽気な音がして、彼女が笑った。あたしもちょっと笑った。
音楽はゆっくりとはじまった。ときどき彼女がハミングして、あたしはそれに耳をすませた。
ゆるやかな音色からいろいろなことを考えた。風のゆくえはどこだろう、虹のふもとはどこだろう、明日のあたしはどこだろう。
今あたしの頬をなでた風とそのゆくえはつながっている。先週見つけた虹にもふもとがきっとどこかにある。明日のあたしは今日ここで彼女の音楽を聴いているあたしのつづき。流れる音楽がすべてをつないでくれる。
世界は広くて、あたしはきっとどこにだって行ける。だってあたしは、今ここにいるから。
――ああ、これは、きっとマーチングソングなんだ。あたしの音楽。彼女がくれた、あたしの音楽!
演奏が終わった。聴いている間は永遠みたいだったのに、終わっても永遠に思えるから、不思議だ。永遠にもいろいろあるのかもしれない。もう一度、かわいくて間抜けな音がする。ティロリン。録音が終わった。
「……すっごく、儚かった。ありがとう」
「感謝するのは私のほうさ。君のおかげで、君と出会えたから生まれた音楽だからね」
儚いってなんだろう? 実はあまりよくわかっていないけれど、この気持ちに儚いという名前があるのだとしたら、とても素敵なことだと思った。
「……ね、今の……今の曲ね、あたし、なんだろ、すごくわくわくしたよ。考えたこともなかったけど、なんか、もし、旅行とか……? 旅行じゃなくても、ちょっと電車に乗るときとかでも、そういうときに聴きたいなって思った。……あ! 考えてることと違ったらごめんなさい……でも、なんか、そういう……ごめん、あたしこういうの全然で……」
彼女が放つきらめきに対して、あたしの言葉はあまりにも拙い。悔しかった。こんなきれいな夜なのに、あたしの何もかもが及ばない。
「ああ、本当にありがとう。言葉はなんだっていいのさ。君の感動を君が私に伝えようとしてくれたこと、それが私に伝わったこと。それだけでじゅうぶんじゃないか。私は本当にうれしいんだ」
あたしはついに泣いてしまった。どうしてだろう? よくわからない。でも、この世界にあたしの音楽があって、何度でも今を思い出せるのは、たぶん……たぶん、しあわせみたいなことだった。
「……この世は舞台、人はみな役者。私たちはなんにだってなれる。つまり……そういうことさ」
そのときあたしは、きっと本当にうれしかった。今までずっと眠っていて、目が開いたような気分だった。
神様と居るとき、あたしはいつもさびしくて甘えたがりの女の子になる。そういう女の子になって神様と居ると、いろんなことが楽になる。難しいことを考えなくていいし、やさしくされることも多い。相手がどうしたいのかわかって、自分がどうすればいいのかわかる。そのすべてが嘘ではないし、何もかもが演技というわけでもない。
でも、あたしは、もっと別の……きっとなんにだってなれるのだ。どんなあたしでもいい。あたしがなりたいあたし。それがあたし! 駆け出したいほどうれしかったし、駆けて向かいたい先は彼女だった。
「この世は舞台……?」
「シェイクスピアの言葉さ」
「シェイクスピア……」
「そう。シェイクスピアは劇作家であり詩人でもあった。その言葉はどれも素晴らしく儚いよ」
彼女がときどき詩的なのは、たくさん言葉を知っているからなのだろうか。それとも、あたしと違って自分についてよく考えているからなのだろうか。シェイクスピアを深く愛しているからなのだろうか。
あたしも、読んでみようかと思った。明日、学校に行ったら、図書館に行ってみよう。そうすれば、すこしは彼女に近づけるだろうか。なりたいあたしになれるだろうか。ギターは……お金がないし、当分無理だろう。まずはシェイクスピアからだ。その先にギターも音楽もあると、きっと信じて。
「あの……! よかったら、あなたの……名前を、教えてくれませんか。迷惑になるようなことはしないし、だから……」
「……私の名前は瀬田薫。羽丘演劇部の役者で、ハロー、ハッピーワールド! のギター担当で、そして王子様の、瀬田薫だよ。いつでもどこでも会いに来てくれ」
役者もギターもわかるけど、王子様? 不意に差し込まれた不思議な言葉に、泣くのも忘れて笑ってしまった。でも、彼女が王子様だというのなら、王子様なのだろう。王子様って、おりこうさんのヒロインをお姫様にしてくれるだけのひとじゃないんだ。
「あたしは……あたしの、名前は……」
あたしには名前がふたつある。本名と、ハンドルネームと、旧姓も入れるならみっつ? なんて言おうか、迷った。
そういえば、と思い出した。まだ家に帰るのが当たり前に好きだった頃、呼ばれていた名前がある。愛おしげに、大好きだよって言うみたいに、呼ばれていた名前。あたしが無邪気だった頃の名前。
彼女に呼ばれたいと思った。瀬田薫さんに、あの頃の名前で、あたしを呼んでほしい。
「あたしの名前は……」
* * *
あたしの日々は、変わらないけれどすこしだけ変わった。相変わらず家には滅多に帰っていないし、毎日ちがうにおいのシャンプーで登校する。けれど、放課後には辞書を引きつつシェイクスピアを読んで、ドン・キホーテで買った安っぽいイヤホンで音楽を聴く。彼女がくれたあたしの音楽。そうすると、なんだか前を見て胸を張って歩ける。胸の内の水をこぼさないように下ばかり見て必死だったあたしじゃない。
羽が生えたみたいだった。あたしはどこにだって行けて、なんにだってなれる。
あのメロディを思い出すたびに、あたしの水は何度だって無限に湧き上がるのだから!

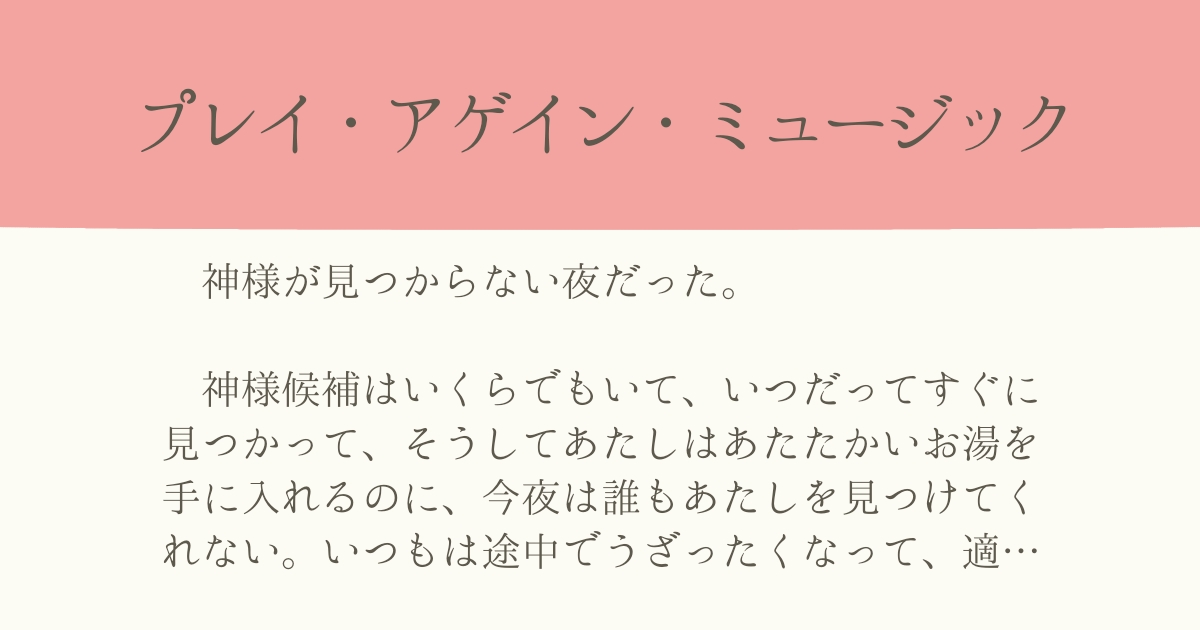
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます