あやちさ/かおちさ:彩とのしあわせを模索する千聖の話です
・R-15程度の軽微な性描写を含みます
白鷺千聖は瀬田薫の家に向かっていた。
肌と肌がふれあったとき、それを快く思う人間と、戸惑ってしまう人間がいる。千聖はどちらかと言えば後者だった。
何も鳥肌が立つわけではないが、なんとなく落ち着かない気持ちになる。昔に比べれば随分と慣れたが、若宮イヴのように喜びをハグで表現したいとは思わないし、五人でセルフィーを撮るときも、ほんのわずか息を詰めてしまうことがある。思えば両親も妹もあまりべたべたとくっつくような人ではないし、幼馴染と肌がふれた記憶もあまりない。
そういう自分が嫌だ、ということはないし、そういう自分を自覚せざるを得ない状況をしばしばもたらすPastel*Palettesが嫌だ、ということも断じてない。Pastel*Palettesは千聖にとってかけがえのない居場所だった。むしろ、ハグにあまりいい態度を取らない自分について詮索されず、過度に配慮されることもないのが有り難いとさえ思っている。
だから、それが問題になるのは、丸山彩との関係においてのみだった。
千聖が彩と素肌をふれあわせるようになって、しばらく経つ。
心地いいし、気持ちいい。けれどそれと同じくらいのおそれがあることを、千聖は認めなければならなかった。
彩はひたむきで、一生懸命で、肌を重ねるたびに千聖の快楽を育てていった。けれど千聖のおそれは、だからといってなくなるものではない。むしろ熱が増せば増すほど、おそれは冷たく際立つ。千聖は胸の奥底に一欠片の氷を仕舞っていた。
おそれとはなんなのか。
かつて千聖はつまらない女だと言った。彩は千聖も夢を見ていたのだと言った。千聖が彩を愛していて、彩が千聖をだいすきで、そうしてふたりは今ここにいるのに。千聖は彩と出会ってたしかに幾分か救われているのに。彩と同じ温度になることが、千聖にはできない。
たぶん、千聖はそれが申し訳なかった。彩というひだまりを裏切っているような気がして、どこかやましい。彩がどんなに特別な女の子でも、千聖はこの愛に耽溺しきれない。それを自覚するたび、彩がよりいっそう愛おしくなり、己のつめたさが身に染み渡る。
千聖はこれまで、そういう自分が嫌ではなかったし、今も嫌ではない。そして、彩がそういう自分を嫌うこともないだろうと、今では確信めいて感じている。信じている。なのにこうして詮無いことを考え続けている。
それはいかにも恋のようだと、いつか演じた役を想った。
薫の家まではあっという間だった。身体に馴染んだ道程は、何も考えなくても間違えない。いっそ退屈なほどに。
「いらっしゃい、千聖。さあ、あがって」
「……お邪魔します」
長くこの家を訪ねなかった期間はあるが、薫の誘いを承諾することのある今ではさして久しいわけではない。かといって頻繁に来るわけでもない。仮に薫の誘いをすべて受けたってそう頻繁にはならないだろう。
両親は不在とのことで、リビングに通される。珈琲か紅茶か尋ねられ、紅茶と言いかけて珈琲にした。千聖は紅茶を好むが、だからこそ飲む場面を選びたかった。
「……手挽きのミルなんてあったかしら」
キッチンカウンターの向こう、薫が豆とともに取り出したミルを見て尋ねる。ただ千聖の目にふれる機会がなかっただけで随分前からあったとしても不思議ではないが、薫はうれしそうに笑った。
「先月、母がね。最近凝っているんだ」
そう言ったそばから薫は豆を挽きはじめ、ガリガリと音が鳴るので千聖は黙った。うるさいというほどではないが、進んで話をするような音でもない。
沈黙すると、改めて薫の家の空気が肌に染み込んできた。自室のように落ち着くのとはすこし違う、けれど懐かしい場所。しかしそれはどこかざらついた落ち着きで、やはり稀でいいのだと、千聖は思う。千聖にとって、今や“忘れている”在りし日の自分を薫が覚えていることは、ときどき必要に感じるが、むしろそうでない人間といるほうが居心地がよかった。
千聖がかつて剥がしたかった薫のメッキは皮膚にほかならないのだと、薫の舞台を直視した今ではわかっている。それは喜ばしくもあり、どこかせつない事実だった。
珈琲の香りが鼻についてふっと我に返った。薫は沸かした湯を注いでいるところで、水が滴るのをぼんやりと眺める。ゆるやかな時間が流れている。
「……薫は、今も生魚は嫌い?」
カウンター越しに声をかける。千聖自身はあまり料理をしないが、この家のキッチンはきっと薫の母がこだわって作ったのだろうと、この歳になれば察せられる。薫は物の所在を自然に把握していて、ここに立つこともそれなりにあるのだろう。
「ああ……今でも、生の魚介類だけは受け付けないよ」
適当な言葉がなかった。
「気持ち悪いってよく言っていたわね。あの頃なんて泣いて食べなかった」
「千聖……!」
普段の千聖ならこのまま過去の話をして薫をからかったが、今日はそうしなかった。
「じゃあ、人肌は?」
薫は息を詰まらせて、伺うように千聖を見た。その顔があんまり真剣で、千聖はなんだかかわいそうなことをしているような気がしてきた。
珈琲ができあがっていた。
「おいしそうね」
「……うん……」
千聖は、前に進みたくて、今日ここに来た。
並んでソファに座り、ミルクを垂らした珈琲を、砂糖は入れずに飲む。三人は余裕で座れるソファにふたり。薫は家族との団欒で並んで座ったりするのだろうか。
おいしい。きっといい豆なのだろう。薫の淹れ方がどこまで本格的だったのかは知らないが、そこらの安い珈琲よりは断然おいしかった。酸味が華やか、フルーティーなどと言われる類のものだろうが、千聖はあまり詳しくなかった。
「深刻に捉えないでちょうだい。ただ、幼馴染っていうわりに、私たち、あまりべたべたくっついていた記憶がないでしょう」
ちらと横目で薫を伺う。うつくしい横顔だと思う。千聖は今に至るまであまり顔が縦に伸びなかったからこそ、子役から女優へとなめらかに移行できた。薫は違う。千聖が気づいたときには薫の肉体はめざましく変化していた。ふたりはちがういきものだった。
「千聖はあまりそういうことが好きではないと思っていたからね」
「……あの頃から?」
「……そうだね」
そうだったのか、と千聖はそれだけを思った。薫にそう思わせるような態度を自分がとったことがあるのか、本当に思い出せなかった。
珈琲をひとくち飲む。
ひょっとしたら、あの頃の薫が気を使わずに自分に踏み込んでいたなら、今頃こんなことで悩まずに済んだのかもしれない。けれど薫がそんなふうにやさしいのは昔からずっとそうで、苦笑するよりほかなかった。
薫。名前を呼ぶ。こと恋においては、今の千聖は薫より怖がりかもしれない。私、もっとちゃんと、彩ちゃんと……その先の言葉はうまく見つからなかった。
はたと、薫はほんとうは自分にもっとふれたかったのだろうかと思い至ったそのとき、こつりと、薫の小指が千聖のそれにふれた。
ちがう。
そのとき千聖はどうしようもなくわかってしまった。違う。薫ではないのだ。自分にとって、その温度は、そのひとは、薫ではない。もう。
「大丈夫だよ、千聖」
大丈夫。それはいつかも聞いた言葉だった。
「君はちゃんと、彼女を既に選んでる。だから、大丈夫なんだ」
ぐずつく子供に言い聞かせるように、薫は大丈夫と繰り返した。千聖は頑是なく泣きわめきたい子供ではなかった。なのにどうしてか、それが自分に必要だったのだと理解できた。
薫は千聖に選ばれないために小指を伸ばしたのか。そっと、そうしてすぐに引っ込めて。千聖がそう気づいたとき、薫は再び口を開いた。
「何も不安に思うことなんてないさ」
不安。それは彩とのことでもあり、薫とのことでもあった。自分が薫に途轍もなく残酷なことをしている可能性を、千聖はもうとっくにわかっていた。彩と一緒なら、どんな不安も一つひとつきっと乗り越えてゆける。そして薫との間の不安は、薫が何もかも引き受けてしまうのだ。
文化祭の日に薫が用意した選択肢を千聖は選ばなかった。薫は選ばれたかったのだろうか。千聖は考える。すくなくとも目の前にいる薫は、選ばれようとはしていなかった。けれど薫は、みずから選んでそうしている。
薫の微笑があんまりやさしくて、だから千聖は言った。
「私、彩ちゃんと……しあわせになりたいの」
しあわせに何が必要なのか、明確な答えは知らない。けれど千聖は、たしかに彩とすはだかで笑いあいたかった。それはほんとうのことだった。
「君ならきっとなれるさ、千聖」
「送っていこうか?」
「ひとりで帰れるわ。……なんだか不思議ね。あの頃は私が薫を送っていたのに」
千聖が遠い記憶を掘り起こしてからかうと、薫はわかりやすく恥ずかしがる。けれどひと呼吸ののちにまた日頃の顔に戻って、言う。
「私は、私を送り届けて家に戻ってゆく千聖を眺めるのも好きだったよ。千聖はいつも太陽に向かって歩いていたから。千聖のことが私はいつだってまぶしかったんだ」
「ここから西に家があるだけでしょう」
「……またいつでもおいで、千聖」
「……そうね」
そうして千聖は帰路についた。すこし迷って振り向くと、目を細めた薫がいた。
* * *
彩が衣服をひとつずつ脱いでいくのを、千聖はじっと見つめていた。千聖は服を着たままだった。それは千聖のおねがいで、わがままだった。私を脱がす前に、はだかになってほしいの。
できたよ、千聖ちゃん。
すはだかの丸山彩はうつくしかった。健康的に引き締まった肉体は、千聖の細さとは違う。
そのときの彩に羞恥があったのかどうか、千聖にはわからなかった。ひょっとしたら、千聖のことばかり考えて、自分の恥ずかしさなんて頭になかったのかもしれない。そのくらい、千聖には彩がまぶしく見えた。本当のところは、わからないけれど。
彩が千聖を抱きしめる。布越しの熱。千聖は彩の素肌をなでる。
自分は卑怯だと、ほんの一瞬、考えた。それを遮るように彩は言う。千聖の胸の内など知りようもないはずの彩が。この間、駅前のお店のマネキンがちょうどこの服を着ててね、千聖ちゃんに似合いそうだなって思ったの。やっぱり、すっごく似合ってる。
「彩ちゃんが好き」
自分の中のどのあたりなのかわからない場所から、脈略もなく不意にこぼれた言葉だった。千聖は自分の中に未開の荒野や銀河の果てのようなものがあることをはじめて知った。言語でも論理でも開拓できない遠く深い内側の熱を、ひとはせめて恋と呼ぶのかもしれない。そして思い返せば、千聖の中の彩はずっとそこにいたようにも思えた。
氷の軋む音が聴こえた気がした。水は脚の間から滲む。
彩は千聖の深いところまで見つめてふれるのに、どうして千聖のメッキを剥がさないのだろう。彩はいつだってそうだった。彩の前ではこれまでに何度もみっともない姿を晒してきたはずなのに、彩の隣に立つときが、千聖はいちばん純金だった。
千聖は自分がもう大丈夫なのだと、どうしようもなくわかった。ねえ、彩ちゃん。私を脱がせて、あなたの手で剥き出しにして。

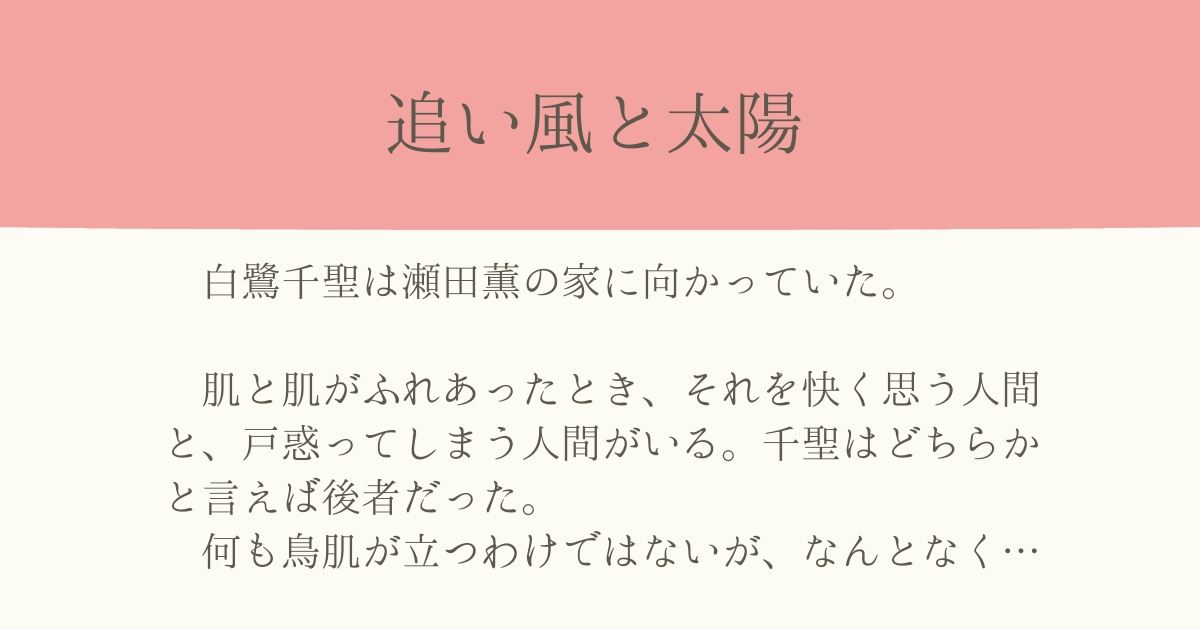
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます