解散の決まった404がオープンカーでドライブに行く話です
「よ、おまたせ」
キザったらしくサングラスを上げた伊吹藍は、屋根を開けた黄色いポルシェで志摩一未の眼前に滑り込んだ。
話は数日前に遡る。
異動の辞令が下り、404バディの解散が決定した日のことだ。世界が春に向かいつつある中、ありふれた出会いと別れの中に志摩と伊吹のそれもあった。
今度の公休、空いてる? 空いてる。じゃさあ、ドライブ行こうぜ。休みの日にまで? 密行は密行、ドライブはしたことないじゃん? 車借りてー、夕陽に向かって走ろうぜ。青春かよ。
いつもと変わらないような、どこか寂寞の滲むような、不思議な肌ざわりの会話があった。まるでエピローグみたいだな、と志摩は思って、その思考とは関係なく承諾した。最初から断る気はなかったのに、伊吹はうれしそうだった。
だがこんな派手なオープンカーとは聞いていない。衆目を集めるという意味ではメロンパン号といい勝負だ。一瞥しただけで志摩はかなり帰りたくなっていた。サングラスをかけ直して得意げに笑う伊吹には、この華やかな車がよく似合っている。きゅるっとした女の子とか迎えに行けよ。
「こんな車どこで借りてきたんだ」
「え? レンタカー屋」
「なんだってわざわざこんな派手な車に……」
「どうせ借りるんならイカした車がいいっしょ」
「あー、とりあえず屋根閉めろ屋根」
「オープンカーをオープンしないでどーすんだよ」
そう言いつつも伊吹はおとなしく従った。閉めたところで派手なものは派手だな……と志摩は腹を括り、ポルシェ・ボクスターの助手席に乗り込んだ。
春先のわりに風のおとなしい晴天は、絶好のドライブ日和だった。低い車体から眺める景色はメロンパン号とも今の機捜車ともちがう。たしかにシートの座り心地はいい。
「志摩ちゃんテンション上がんねえの? オープンカーだよ? 聞いて? 感じて? このエンジン音をさー」
最高……。噛み締めるように呟いて今にも歌い出しそうな伊吹を横目に、志摩は軽く憂鬱だった。良くも悪くも目立つのは慣れているのでまだいいが、彼と組んだその日のことが否応なしに思い出されて口角が下がる。
「忘れてないだろうな? 俺たちは誰にも車を貸してもらえなかったバディだ。その理由は初日に機捜車を一台廃車にしたから。伊吹お前、ぜっ……たいに事故るなよ」
「でもあれから今日までは、一度も廃車にしてない」
「そんなことでカッコつけるな。辞めるまで一台も廃車にしないのが当たり前なんだよ」
「廃車にしたの志摩ちゃんだけどね」
お前と組んでなきゃああはならなかった、という言葉を飲み込んだ。まるで後悔しているみたいなことを言いたくなかった。
とにかく、今日は必ず煽られても無視しろよ。そう言うと、伊吹は合点承知之助、と笑った。彼は忘れた頃にその返事を使い、志摩はそれを何度も聞いた。それだけの日々が降り積もっていた。
「この車、山道が怖いな」
「山道? なんで?」
「頂上で腹を擦る。車高が低い」
「俺なら擦らない」
「根拠のない自信だな」
まるで平素通りのやりとりを重ねながら、志摩は内心、伊吹がいつもと変わらない明るさであることに安堵していた。
伊吹が警察官になってから、彼の持っているものが周囲に評価されたのは、四機捜がはじめてだろう。異口同音の「足が速い」。奥多摩での日々。伊吹はあたらしい場所でも、のびのびと走れるだろうか。ほかでもない志摩こそがそれを信じて疑っていないはずなのに、なぜだかふと考えてしまう。有り体に言えば心配しているということだが、それにしては面映いものがあった。
いつか彼が定年まで勤め上げて振り返ったとき、最も充実した輝く日々は、機捜404でなくてもいいのだ。むしろこれから先こそ、もっと。ふと彼がベトナム人留学生を見送ったときのことを思い出した。ああいう楽観的で無責任とも言える祈りの切実さが、今になってどうしようもなくわかる。わかってしまう。わかったような気になってしまう。
一度は遠ざけようとしたくせに、よくもこんなことを考えたものだと自嘲した。過去は悔やんでもなくならない。それでも、今ここで彼の未来を想うとはそういうことだった。随分と都合のいい人間だな。志摩は思う。都合上等、ブーメラン上等……とまでは行かずとも、やはり甘んじて受けるよりほかなかった。慣れ親しんだ1HIT。
仕事でさんざん通った道をオープンカーで走るのは、奇妙な心地だった。仕事と同じように隣に伊吹がいるのに、仕事ではない。そしてその仕事も残り数えるほどしかない。
「お、あれ本物のメロンパン号じゃない?」
赤信号。そう言われて伊吹の視線の先を見れば、たしかにメロンパンの販売車があった。
「ひょっとして、あれも警察車両だったりして〜」
「ネットに画像が出回ったせいでメロンパンは当面無理。あの車も使えなくなって、張り込み用として復活させるために塗り直したか張り替えたかって聞いたけど、たしか……、……とにかく、もうメロンパンじゃないナントカ号になってる」
「えっ、メロンパン号、もうメロンパン号じゃないの」
「もうメロンパン号じゃないの。……あれも俺たちが廃車にしたようなものだな」
車を二台も使用不可に追いやるバディがどこにいるんだ。一台では笑えないのに、二台になると笑える気がするのが不思議だ。
「みんな覚えてんのかなー」
「すくなくとも、俺とお前が関わったひとたちは……たぶん覚えてる」
あのとき、メロンパン号が警察の車だと発信してくれた彼らは。志摩と伊吹が、何かのスイッチになれたかもしれない彼らは。
「だとしたら、なんかうれしいなー」
「……信号、青」
アクセルを踏み込んだ瞬間のなめらかな振動は、車にさほど興味のない志摩でも朧げにすごいと感じるものだった。すごい、以上のことはわからない。おそらく伊吹は感じているのだろうが、それが志摩に伝えられることはない。仮にどんなに言葉を尽くしたところで、完全にわかりあうことはできない。
「さっきのメロンパン、一個六百円だったな」
「えっ、じゃあすっげーうまいのかな」
「メロンパンに四百円以上は出せない」
「なんか前もこんな話しなかった? ……ああでもさ、一個千二百円のメロンパンとかあったら、逆に買いたくならない? そんなにすんならどんだけうまいんだろーって」
「……メロンパンのうまさは、メロンパンの枠から出られるのかな」
「……どゆこと?」
メロンパンによって得られる幸福を金銭に置き換えたとき、それがメロンパンであるからには、四百円以上の価値にはならない。メロンパンとはその程度のものだ。すくなくとも志摩にとっては。コストパフォーマンスという言葉が流行って随分経つが、それより前からこういう物差しはひとそれぞれにある。無論、メロンパン愛好家なら惜しみなく千二百円でも一万円でも出すのだろう。そして伊吹は、メロンパン愛好家でもないのに出せる。
「千二百円を使うなら、メロンパンよりうまいもんが食えるんじゃないかってこと」
「でも千二百円のメロンパンだよ?」
「メロンパンはメロンパンだろ。メロンパンの域を出ない」
「でもメロンパンに革命を起こしてるかもしれないじゃん」
「革命ね……」
血腥く、それでいてどこかきらびやかな響きだ。伊吹の言葉を聞きながら、志摩は密行とドライブがちがうということを理解しはじめていた。当たり前だが、入電がない。入電がすくない日もあるにはあるが、そもそも今日は入電を待っていないのだ。それは心持ちの部分が大きく異なる。どうでもいい話も、大切な話も、何にも遮られることなくとことんできてしまう。このふたりきりの密室で。
街を抜けたポルシェは高速道路を走っていた。平日の午後はそう混雑していない。この車がどこに向かうのか、志摩は聞かずにいた。そもそも目的地があるのかどうかもわからない。それでいいと思っていた。
「……いざ辞令出て解散ってなって、改めて考えたんだけどさー」
そう切り出した伊吹の横顔は、微笑をたたえて穏やかだった。
「考えたのか」
「考えたよ? 何、ばかにしてる?」
「いや、すごいと思ってる」
改めて考えるということは、過去を振り返るということだ。志摩は自分でも驚くほどこの相棒に心を傾けてきた。ほんとうに、驚くくらい。人生のエポックと言ったっていいほどに。伊吹にとって、志摩と過ごした日々はなんだろう。
しまぁ。締まりのない間延びした声が志摩を呼ぶ。すっかり身体に馴染んだ、自分の名前の形。
「ありがとね。あと、ごめん」
「……それは、それぞれ何に対してのものなんだ」
謝られる覚えなんて、今更ひとつもなかった。身に覚えのないことを謝られるのはこうも怖いものかと驚く。それは、志摩にとっての伊吹という存在の大きさにほかならなかった。
「四機捜で志摩と一緒に、いろんなやつ追っかけて、いろんなやつ捕まえて、それで俺は、間に合ってよかったーとか……間に合わなかったな、とか思ってきたけどさ」
伊吹はそこで言葉を区切った。ちらりと志摩のほうを見て、サングラス越しに目が合う。前見ろ前、高速だぞ。目だけで言う。前を向き直る。
「俺のこと捕まえててくれたのは、志摩なんだなーって。だから、ありがと」
彼の脳裏にあるのは、蒲郡を逮捕してからのことだろうと、志摩は察した。たしかにあのとき、志摩は懸命に伊吹を捕まえていた。彼が閉じきってしまわないように、取り返しのつかないことをしてしまわないように。最適解も出せないまま、ただがむしゃらに追いかけ、捕まえ、寄り添おうとした。
けれど忘れもしない。志摩は結局、自分のことで精一杯になってからは、伊吹から逃げた。久しく忘れていた自分の奥底にある汚泥は、ただ沈殿していただけで、決してなくなったわけではなかった。懐かしい汚濁に身を浸して、彼と出会った日のあの感動さえ自分が嘘にしてしまったことが、きっと悲しかった。彼はもっときれいな空気を吸って生きるべきだ。自分の隣よりもっとマシな酸素で、心と脚を動かすべきだ。あのときはそう思っていた。
それでも、志摩は伊吹とここにいる。ここまで来た。それは志摩の覚悟にほかならず、だから感謝を受け入れた。こそばゆく、痛い。
「……で、ごめんのほうは?」
続きを促すと、伊吹は困ったように笑った。そんな顔をするのか、お前。志摩はたぶん、せつなかった。俺がさせた顔なんだろ。そんな必要ないのにな。
「俺がもっと早くこのことに気づいて、今みたいにありがとうって志摩にちゃんと言ってたら……久住捕まえるときも、志摩はひとりでやろうとしたりしなかったんじゃねーかなーって」
だから、ごめん。
「ま、今日まで志摩と相棒でいられたし、いろいろあったけど久住も捕まえたし? 謝ることじゃねーのかなって思ったけど、見逃してたスイッチがあったって気づいたらどーしても言いたくなってさあ。……それに、今こうやって話しておいたら、これがまた何かのスイッチになるかもしれねーじゃん」
衝撃だった。理屈を並べ立てるのは得意なほうだと自負していたが、刹那、志摩の頭の中は完全に空白になった。一拍置いて、混沌。
ちがうんだ。お前は何も悪くない。だってお前はあのとき恩人の岐路に間に合わなくて、そんなの苦しくて当たり前で、お前はそれでもひたむきで、お前に何かしたかったのは結局のところ俺のエゴで、それすら中途半端で、お前が謝ることなんか、何も。桔梗家の盗聴器の記憶に追いつかれ、影に肩を叩かれる。あのときだって俺は、お前は。
とても伊吹のほうを見ていられなくて、けれどそっぽも向けなくて、斜め前を眺めた。途切れない防音壁。
……そうして不意に、わかった気になった。ほんとうのところはわからないから、そんな気になっただけだけれど。
――ガマさんも、こんなふうだったのかな。
蒲郡の事件をひとりで深く受け止めていた伊吹を、よく覚えている。だって隣で見つめていたから。それが、四機捜に配属されて慌ただしく過ごしていた日々を悔やむ在りし日の声に、姿に、重なった。
お前にできることは何もなかった。蒲郡は志摩に伝言を託して、連れられていった。伊吹にそう言いたくなる気持ちが、志摩の中にもたしかにあった。お前は何も悪くない。俺が悪い。俺の責任なんだ。俺がどうしようもないから。俺が悪かった。それは俺の荷物なんだ。お前が持つ必要なんてない。お前はお前の大事なものだけ持って走れ。そこに俺はなくていい。
……息を吸って、吐く。まだ足りない。伊吹の隣で吸う酸素を、また吸う。全身の細胞があたらしくなることを願って。
「俺は、お前と走れてよかった」
それだけを、かろうじて言った。これでいいのだろうか。正解なんてわからなかった。数多の被疑者を誘導してきた弁舌は、相棒を相手にするとなんの役にも立たない。いつだってそうだった。
「お前と……伊吹ともっと走りたかったよ」
逡巡の末に、付け加える。何もかもほんとうで、何ひとつ嘘ではなかった。運転席に視線を投げると、伊吹はすこし目を見開いて、くちびるをふるわせていた。
……俺も。ややあって彼が言い、志摩は堪らなくなって目を閉じた。
「そろそろ休憩するか」
サービスエリアを示す標識を見てそういうと、伊吹はそれを汲み取って曖昧な返事をした。
「なんか腹減らない? うどん食おうぜ」
「半端な時間だなあ」
「半端な時間にうどん食うのなんて慣れっこじゃん」
「……まあいいか」
そう話している間にサービスエリアに入る。そういえばこの車、保証はどうなってるんだ。車上荒らしに遭った場合も弁償とかあるのか? それは流石にかなり嫌だし、そうなればたとえ公休だろうが犯人を全力で追いかけてしまうかもしれない。俺がそうしなくても伊吹は駆け出すだろうが。……志摩がそんなことを考えている間に車は停まり、エンジンが切られていた。乗っている間はそう気にしないが、降りてみるとやはり派手だ。こんな車で都内を走ったのかと思うと、もはや楽しい。
そこで提供されていたうどんは、特に名物というわけでもないごくありふれたものだった。値段相応のうどんの味がする。付加価値があるとすればロケーションだが、目の前の男とはこれまでさんざん共にうどんを食べている。……けれど、これからその機会はうんと減る。そこに値段以上の価値を感じている自分がいることを、志摩はみとめた。とうにうどんは、ただのうどんではなかった。
「うまいな」
「うん、うまい。……あ、ポテトとかアメドとか、あれまとめて言うやつ、なんだっけ?」
「ホットスナック?」
「そうそれそれ。外にさあ、ホットスナックの自販機あったじゃん。真冬の深夜にまたここ来ようぜ」
「なんでわざわざ」
「さっむい真冬の深夜に、自販機の前で凍えながらホットスナックができあがるのを待つの、楽しくない?」
志摩はこどもの頃を思い出した。そんな記憶がたしかにある。父親に渡された五百円玉を握りしめて、弟と自動販売機に向かう。他のきょうだいは車の中で眠っていて、オレンジ色の光の中でフライドポテトができあがるのを震えながら待っていた。それは楽しい記憶だが、四十路を控えた今それをやってクソ寒い以外の感慨を持てるだろうか。
持てるんだろうな。この男とふたりなら。いつかの冬の密行を思い出す。吐く息の白ささえおかしくて笑うような、そんな冬の夜があった。
「それはちょっと楽しい。ちょっとな」
「だろ〜? 今年の冬は決まりだな」
もう相棒じゃない冬も、こいつと会ってるのか。伊吹があんまり自然で、志摩はひそかに感動した。はじめて彼と迎えた朝のように。
リフレイン。刑事じゃなくてもお前の人生は終わらない。己の醜悪を煮詰めた悪夢で繰り返した言葉。そして考える。相棒じゃなくなっても俺たちは……適当な言葉を探しあぐねて、やっぱり相棒だった。あるいは相棒という言葉のまま、その内側で革命が起きたのかもしれなかった。
車を返す時間だというので、そのまま戻ることになった。どこに行くでもなく、ほんとうにドライブだった。運転を代わろうとすると、事故るなよ、と茶化しながらも伊吹は鍵を放って寄越した。
運転席に座り、小ぶりで上品なハンドルを握ると、なんだかテンションが上がってきた。伊吹ほどの繊細さはなくとも、幾許か込み上げるものがある。志摩の高揚を察知したのか、したり顔で笑う伊吹を無視してアクセルを踏み込もうとして、ふと思い立って窓を開けた。窓だけではない。ポルシェのソフトトップも。風が吹き込む。密室が破られ、世界とつながる。
「ま、せっかくだからな」
今度こそ走り出す。風はもちろん、感じる地面が近い。伊吹を笑えない程度には気持ちよかった。
「……志摩ちゃん!」
風に負けないよう張られた伊吹の声がよろこびそのもののように響くので、志摩はもう、それでよかった。
「なあ志摩、このままずっとふたりで走ろうぜ」
ばかか帰るぞと言うところのはずが、笑ってしまって言えなかった。だいたい、今の伊吹をばかと言うなら、それは志摩へのブーメランだ。だって、志摩も。
ポルシェの黄色が濃度を増して、夕焼けがはじまろうとしていた。愛しの街が、彼らを待っている。志摩は今なら六百円のメロンパンを買ってみたかった。

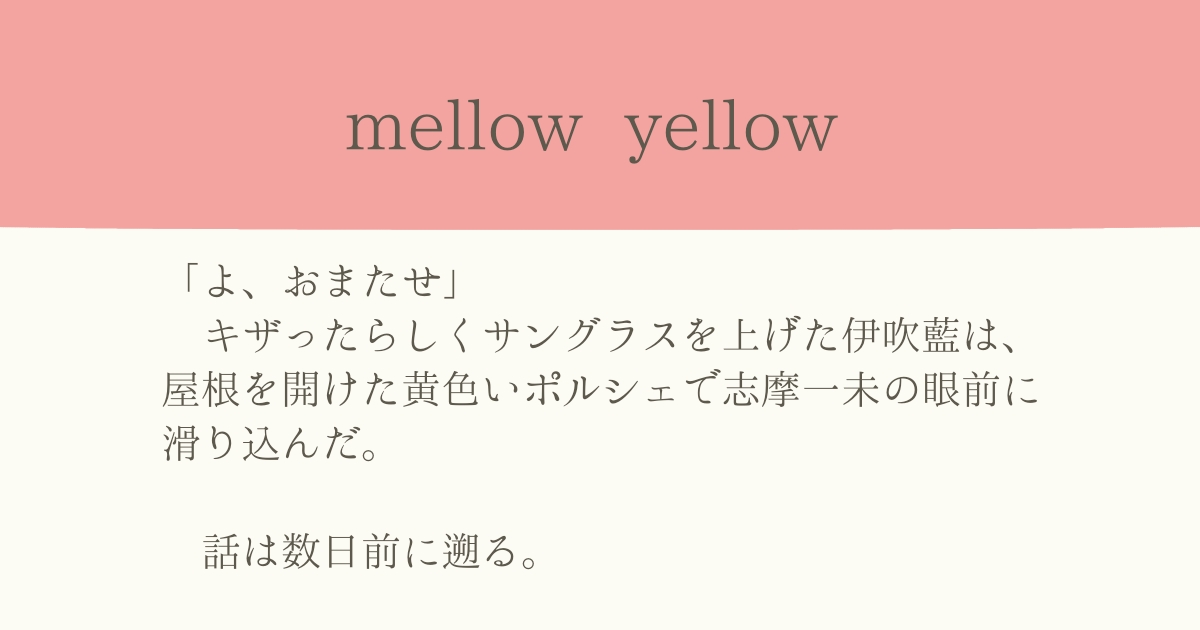
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます