受験生の少年が404に出会う寒い夜の話です
・未成年者の喫煙は身体に甚大な悪影響を及ぼします。また、未成年者の喫煙を容認する行為を推奨する意図を、本作は断じて持ちません。
夜は寒いから嫌いだ。
冬はもちろん、夏でも夜はなんとなく寒い。日が落ちて、立ち並ぶ家々の窓がまぶしくて、ぶらぶらと歩いていると腹の奥に隙間風が通る。けれど別に、家にいても寒い。夜から逃げられる場所はどこにもなかった。
いちばん寒いのは予備校からの帰り道だ。帰り道と言いながらも、自分がほんとうに帰っているのかわからない。迷子みたいだな、と思う。でも、帰る場所がわかっていて、見つけてもらえるまで泣ける迷子のほうが、ずっといいものような気がする。
冷え込みが激しくなればなるほど近づく試験に周囲はどんどん空気をひりつかせるけれど、自分はうまくその波に乗れなかった。だってもうずっと寒かったから、今更。ふと脳裏を二〇二〇の素因数分解が過る。二の二乗かける五かける一〇一。毎年どこかの大学が出題するという西暦の素因数分解。紅白を観ると落ちるぞと笑う講師の言葉。あの歌合戦を家族四人で観た大晦日は、随分と遠くにあるように思えた。
ふたつ並んだ自動販売機のひとつの前にカードをかざしていると、隣に現れた男が小銭を入れてボタンを押した。だが、ガタゴトと音を立てて出てきた飲み物を、彼はなぜか一向に手にしなかった。それを横目に見ながら、すこし緊張する。
「……君、いくつ?」
どうしよう。思わず声のほうを窺うと、目が合う。こんなところで誰かと会ったことなんてなかったのに。無視を決め込むことにして、踵を返した途端、ぐっと腕を掴まれた。強い力だった。離さないと言わんばかりの。
仕方なしに振り返ると、自分とそう背丈の変わらない、柔和そうな男がそこにいた。腕を掴む力だけが、男の出で立ちとちぐはぐだった。
「未成年者喫煙禁止法。二十歳未満は煙草を吸ってはならない。……知ってるよね」
男の姿を飲料の自動販売機が照らしている。自分の前にあるのは、煙草の自動販売機だった。
自分の姿を思い出す。コートを着ているがその下は学生服で、鞄の中には参考書。予備校には浪人生もいるけれど、自分が二十歳と言い張れないことはよくわかっていた。手の中にメビウス。
「それtaspo? 見せて」
「……はい」
差し出してからようやく、この男はいったい何者なんだと思い至った。でもそれを尋ねるのは怖くて、男を観察しようとしたが、これといって特徴を掴むことはできなかった。どこにでもいそうで、ただすれ違って記憶にも残らない、そんな男。なのに自分の腕を掴んで引き止めた、奇妙な男。顔を上げるとまた、視線がぶつかる。片耳にイヤホン。男は急にやわらかく笑って言った。
「……よく似てる」
一瞬なんのことかわからなかったが、男が視線を落とした先にtaspoの顔写真があることに気づいた。
「お兄さん?」
「はい……あの、お使い、兄貴に頼まれて……それで……」
しどろもどろに答えながら、自分の内側に不安とはちがうそわそわした気分があることに気がついた。これはなんだろう。変な感じだが、嫌な感じではない。模試なら焦って手汗で鉛筆を落としていただろう頃、不意にわかった。
うれしい。
うれしかった。何が? ……兄貴に似てると言われたことが。どうして? だって。
「お兄さんのこと、好き? 煙草買ってこいって、未成年なのにこんなの押しつけられて、言うこと聞いちゃうくらい」
顔に出ていただろうか。そういえば、このひとはなぜ急に押し黙った自分に何も言わなかったのだろう。そもそもわざわざ声をかけて捕まえたのだって、なぜ。
「……はい」
どうしようもなくうれしかった。家の中で、もう兄貴は最初からいなかったみたいだから。
兄貴がいなくなって、もう一年近く経つ。
いなくなったといっても、まったくの音信不通ではない。家に帰ってこなくなってからも、ときどきメッセージのやりとりは続けていた。両親はもうぜんぜんで、兄貴とつながっているのは、この家には自分しかいない。
志望校に受からず滑り止めの滑り止めに進学した兄貴は、雰囲気が変わった。最初はうるさかった両親も、自分が受験生になると同時に何も言わなくなった。今度は失敗できないから。夜中に両親がそう話しているのを耳にした。失敗ってなんだろう。
張り詰めていた頃の兄貴より、変わってからの兄貴のほうが、ほんとうは好きだ。親が眉をひそめた明るい茶髪も、泥酔して大笑いしながら帰ってきて翌朝には何も覚えていないのも、普通のことみたいに煙草を買いに行かされるのも、好きで、うれしくて、安心した。
でも、家族四人で紅白を観ることはなかった。たぶん、それがいちばん安心のかたちをしているのに。いつものように自分にtaspoを押し付けて、そのまま兄貴は帰ってこない。
「志摩おそーい。何やってんの?」
そう言って現れた男は、兄貴の友達にいそうな、けれどそれよりどこか品のいい出で立ちをしていた。すらりと背が高く、すこし怖い。腕を掴む手を離した男が、こいつすっごい足速いから、と言った。逃げても無駄ということだろうか。
「ちょっと立ち話」
「ふーん……え、それ煙草?」
「兄貴のお使いだと」
「何それ、自分で買えばいいのにね。いくらこんな寒いからってさあ」
男が口を開いた途端、さっきまでの恐怖は不思議と立ち消えてしまった。兄貴が茶髪になったときと似た感覚だった。最初は驚いたけれど、一言二言話してみればいつも通りで、すぐに大丈夫になった、あのとき。
「あの、おふたりは……」
「俺らはね〜警察のひと」
内ポケットをまさぐって、取り出した手帳を掲げられる。だから自分の腕を掴んだのか。……これ本物? はじめて見たな。まさか捕まる? ひょっとしてまずいのでは。呑気と焦燥が同時に去来して、なぜかすこし笑った。息が白い。
「自分でもちょっと吸ってみたりするの?」
さっき志摩と呼ばれていた男が言った。あとから来たほうとは逆で、彼は黙っているより喋ったほうが怖い。
「吸、わない、です……」
嘘ではない。ただ、届ける兄貴がいないだけで。兄貴の部屋の学習机には、もう十箱以上のメビウスが積み上げられていた。寒さが一段とひどい夜に買っていたら、いつの間にかそんなふうだった。
「伊吹は?」
「え俺?」
「若い頃、吸ったりしたの」
「や〜俺十七んときだっけ? 一瞬吸ってみたけど、にげーしくせーし即やめた。オラオラするために吸うのもさー、なんかちげーじゃん?」
「茨城のヤンキー」
からかうように笑った志摩さんは、どうしてかもう怖くなかった。……このひと、ぱっと見ちょっと怖いけど、茨城のヤンキーだったんだ。
「でもいいの。いやもちろん煙草はよくないけど、それでも、今の俺は刑事だから」
よくわからないけれど、清々しい言葉だと思った。おとなの言葉だと、思った。
「もし君が喫煙していたら」
「してないって言ってんじゃん」
「さっきのお前の発言に素で引いてたからしてないだろうと思ってるよ。もしもの話」
「志摩ちゃんそのために俺に話ふったの? も〜ほんと疑い魔神」
「……もし君が喫煙していて」
「うわシカト」
「君のお兄さんがそれを容認してtaspoを貸していると判断されたら、君のお兄さんは罪に問われることになる。貸しただけで条例違反になる地域もある」
なんだそれ、と思った。
「そんなの……だって、俺が吸ったんなら、悪いの俺じゃん。なんで兄貴が……」
「君がまだ未成年、こどもだから」
「……おとながさ、考えなきゃいけねーの。君たちみたいなこどもが、まっすぐな、正しい道を進めるように」
なんだそれ。なんだよ、それ。
なぜだか無性に腹が立った。自分が夜の迷子であるように、兄貴だって、きっと迷子なのだ。だってそうじゃん。親にずっと無視されて、家にいたくなくて、見つけてくれるおとながいなくて、そんなのって、迷子だ。泣いても意味のない、迷子。
「……でも」
また、あの隙間風が吹いた。
「でも兄貴のこと考えてくれるおとなはいなかったじゃん!」
自分の出した声に、自分で驚いた。こんなに大きな声を出したのはいつ以来かわからなかった。自分の中で何かが燻り続けていることには薄々気づいていたけれど、こんなふうに主張したいことがあるなんて思っていなかった。通りすがりの知らないおとなに言ったってしょうがないことなのに、我慢する前に叫んでいた。
「……お兄さん、何か大変なの」
すこしの沈黙のあと、口を開いたのは伊吹というらしい男のほうだった。頼りない自動販売機の光でも、彼の表情に嘘が混ざっていないことは、なぜかわかった。
「お兄さんも、君も」
もうひとりがそう言い添えて、混乱した。自分と、兄貴が、大変。
家に帰ってこないといっても友人のところに転がり込んでいるらしい。大学も自主休講だなんだと言いつつ行っているらしい。アルバイトをして友人に幾らか宿代を払っているらしい。すくなくとも兄貴はそう言っている。その通りなら、ありふれた大学デビューをしただけなのかもしれない。
「……わかりません……」
周囲の緊張に馴染めないのが怖い。気を抜くとすぐに時間配分を忘れてしまうのが怖い。受験に失敗するのが怖い。親に見放されるのが怖い。でも合格することも、兄貴を裏切るみたいで怖い。
「わかんないです……」
兄貴の近況報告にそれがほんとうなのか尋ねられない自分が嫌だ。家族四人が揃うことなんてもうないのかもしれないのが嫌だ。毎年みんなで紅白を観ていたことを、もはや自分しか大事にしていないのかもしれないのが嫌だ。兄貴が私立に行ったからって当然のように公立狙いなのが嫌だ。
それらすべてが大変と言えるのか、自信がなかった。自分だけがひどく繊細で、こんなの普通なのかもしれない。……だって、誰も悪くないような気がする。そうでないなら、みんな悪いということになりそうで、それも恐ろしかった。
「……兄貴、俺は連絡とれるけど、うち帰ってなくて、親ずっと兄貴シカトしてて、今もで……兄貴みたいになるなって、俺は予備校行かされて、でも受かるのも落ちるのも怖くて」
彼らは黙って自分の話に耳を傾けていた。家での突き刺さるような沈黙とはぜんぜんちがう静けさに、泣きたい気分だった。
「わかんねえ……」
問題を解いて答え合わせをすることを日々淡々とこなしているのに、不意に投げかけられた問いの答えは見つからなかった。解答集がこの世界のどこかに存在するのかも、わからなかった。
「俺が煙草買って帰っても、もううち兄貴の家じゃない……」
「さみーなぁ」
ぽつりと、伊吹さんが言った。
「なんか話聞いてたら寒くなってきた。このへんがスススーって。寒くない?」
彼が大仰なジェスチャーでこのへんと指し示したのは、ちょうど鳩尾のあたりだった。そこだ。いつも隙間風が通るのは、そこ。なんでわかるんだろう。どうして、わかってくれたんだろう。
ずっと、ずっと寒かった。寒いって、思ってもよかったんだ。奥歯をぐっと噛み締めた。涙が出そうだったから。
「お前それもしかして」
志摩さんはためらうようにそこで言葉を切った。伊吹さんに向けて言おうとしたことが、見ず知らずのこどもにどう響くのか探っているようだった。
「もしかして、さみしいって言いたいのか」
さみしい。
その言葉が今の自分に適切なのか、まったくわからなかった。なのに背後から殴られたような衝撃があり、脚に力を入れる。さみしい。さみしいのかな。
どうすればいいんだろう。どうすれば、寒くなくなるんだろう。
「兄貴……兄貴も寒かったら、どうしよう……」
口からこぼれた言葉に、自分で驚いた。
「お兄さん、なんかヤバいことやってるの?」
「たぶん、やってないです……たぶん」
たぶん。兄貴の言うことがほんとうなら。
そのとき、志摩さんが自動販売機の前で屈んだ。自分のせいで取りそびれた飲み物を受け取り口から回収する。ペットボトルのコーヒー。そしてポケットから出した小銭を入れた。
「好きなの選んで。あったかいの」
「……え」
「俺たちにできることはすくない。こんなのあげたって、君たちのその寒さをどうにかしてやることはできない。……でも、ほんとうに大変なことになる前に、誰かを頼って。警察でも福祉でも、なんでも。大袈裟なくらい泣いても喚いてもいいから、そのときは、俺たちを……君たちに間に合わせてほしい」
その言葉のすべてをうまく飲み込めたわけではなかった。ただ、大袈裟という言葉だけは、妙に鮮明だった。大袈裟でも、いいんだ。
きっとすごいことを言っているはずの志摩さんは、なぜか苦しそうだった。志摩さんは悪くないのに。むしろこんな俺を呼び止めて、話を聞いてくれたのに。
煙草をポケットに仕舞い、甘い紅茶のボタンを押した。好きでも嫌いでもないけれど、どこでも見かける商品で、なんとなく目についたから。志摩さんに手渡されたそれを、受け取る。
「……ありがとうございます」
「……」
感謝しているのはほんとうなのに、志摩さんは難しい表情で黙っていた。
「道が見つかるといいよな。むじーけどさ」
伊吹さんが言った。
「……道」
「俺は、俺のこと考えてくれるおとなに出会って、警察官になりたいって道が見つかって、そんで上京してきたの。道が見つかったらさ、それはもう家出じゃないじゃん?」
道。不思議と温度が感じられる言葉だった。迷子の自分と迷子の兄貴。家と道。頭の中でうまくつながったわけではないけれど、手の中の紅茶があたたかくて、ほっとした。安心するのは久し振りのような気がした。
やりたいことも将来の夢もない。ただ周囲のおとなが勧めるままに決めた進路。それが彼の言う道と同じでないことは、わかった。紅茶を見つめ、ラベルを撫でる。好きなものを選べと言われたのに、悩みもせずにボタンを押した紅茶。選ぶのは難しい。
「家出じゃない家出は、たぶん旅立ちだな」
「だな、少年」
旅立ちだと言った志摩さんの顔は、すこしだけ兄貴に似ていた。兄貴がこんな顔をしていたことはあっただろうか。思い出せない。でも、兄貴っぽい。
兄貴は旅立ったんだろうか。それともまだ家出中なのだろうか。……いつか、自分は旅立てるだろうか。思い描こうとした風景はぼんやりしていて、未来にそれが訪れるのか、とても定かには思えなかった。
でも、旅に出たいとは、思った。
ふたりと別れてぶらぶらと歩きながら、いろいろなことを考えようとしたけれど、それがうまく像を結ぶことはなかった。既に家に着いているはずの時間なので、歩道の隅に立ち止まって、母親にメッセージを送った。もうすぐ着く。立ち上げたアプリをしばらく見つめて、兄貴とのトーク画面を開く。
また考える。あまり遅いと親に問い詰められるだろうけれど、この問いに制限時間はない。兄貴と何を話そう。
最近どう。何かやりたいことあるの。俺はぜんぜん。俺もうすぐ誕生日だよ。十八。年末も帰ってこないの。……兄貴の帰る場所がもうあの家じゃないなら、しょうがないけどさ。……しょうがないけどさ。俺みんなで紅白観るの好きだったんだよ。……しょうがないけどさ。別に兄貴は悪くないじゃん。なんにも。
――年明けたら初詣一緒いかね?
――俺タスポ借りパクしてんだけど
――一年も笑
それだけを送って、スマートフォンの画面を消した。
とりあえず、受験はがんばろう。親がもうだめでも、自分は兄貴とつながっていたい。自分が家を出たいのかはまだわからない。親だって、兄貴にあんな態度をとるくせに、自分は嫌いになりきれない。受かっても落ちても道を探そう。なんだか途方もない気がするけれど。
そして、また隙間風が吹いたら、あの甘い紅茶を飲もう。兄貴に渡したいのは、煙草より紅茶だった。

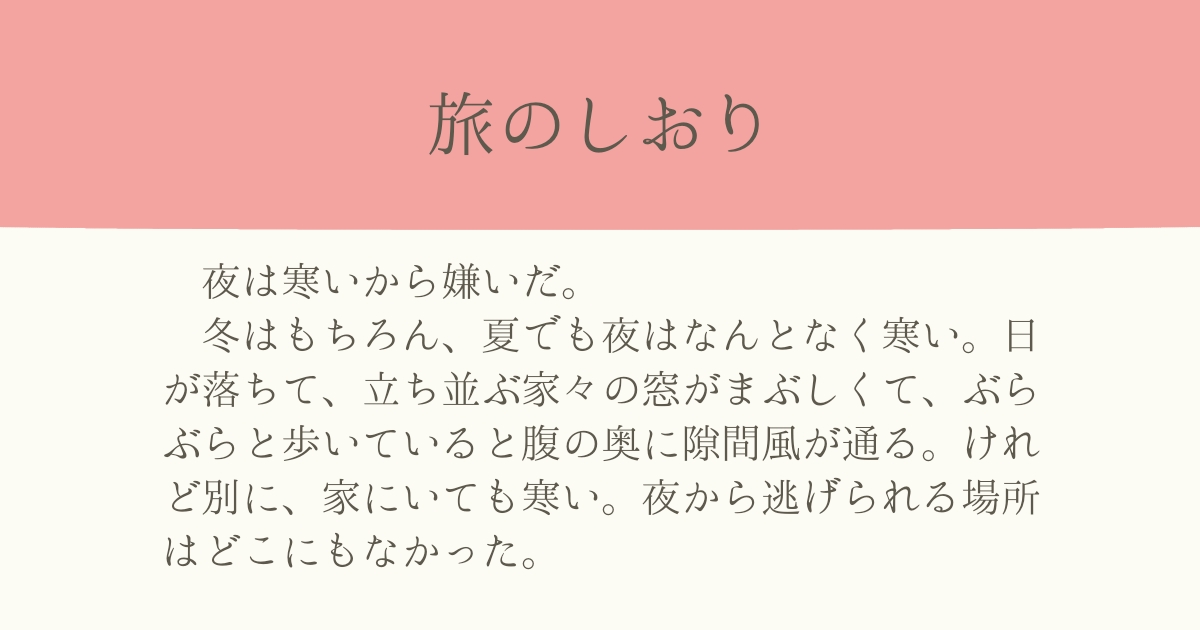
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます