2020年夏、復興五輪2020√の伊吹が本編の伊吹のもとを訪ねてくる話です
伊吹藍が目を覚ましたとき、彼の体内時計はおよそ午前四時頃だろうとあたりをつけていた。世界はまだ暗く、夜明けにはやや遠い。最近は暑く湿っているが、そこまで寝苦しかったわけではない。なぜ目を覚ましたのかといえば妙な気配を感じたからで、彼はすぐさまそれを探った――探るまでもなかった。
慣れ親しんだマットレスの傍らに、ひとりの男が立っていた。カーテン越しに差し込む頼りない月明かりでは、何者なのか判断がつかなかった。
ほとんど反射的に男を拘束しようと身動ぎしたところで、男のほうがしゃがみこんだ。その動作に緊張や焦燥といったものはなく、泰然としてさえいた。そうして伊吹は目を凝らし、男と顔を合わせる。
――果たして男は、伊吹とまったく同じ顔をしていた。
「……夢?」
伊吹はそう呟いて、男の観察を続けた。男の周辺の空気は、ほとんど自分と同じように感じた。つまるところフインキ――薄闇に溶け込む呼吸のリズム、身体の揺らし方、視線の動かし方、そういうもの――が似ている。そっくりさんというには、肉体以外の要素まであまりに近い。けれど何かがたしかに違った。言葉にできない何か。匂い立つ影の気配。それを根拠に自分ではないと言い切ることは、伊吹にはできなかった。自分との差異であるはずの部分が、どこか懐かしく思えたから。
「夢でも、幽霊でも、なんでもいーよ」
男が口を開いた。
「なんか録音した自分の声聞いてるみたい」
素直な感想を述べると、男が笑った。
「俺も」
伊吹の勘が告げていた。どうやら目の前の男は、ほんとうに“伊吹藍”らしかった。
「で? なんなの、お前」
「東京湾マリーナ」
男の言葉に目を見開くと、満足げに男が笑う。男の笑い方は、けれどどこか痛々しかった。俺もいつかはあんな感じだったな。それを眺めて伊吹は思う。だがそれはもう過去のことだった。今からちょうど、一年くらい前。
「オーケーオーケー。東京湾マリーナから生きて帰った俺ね。……俺はー、お前がそこで見た、あの夢の俺」
伊吹は刹那、俺はこいつなんかとはちがうと思った。怒りにも似た衝動で、この男を否定したかった。
「志摩が死んじゃって、久住殺して、で俺も死のうとして、死んだんだけど、なんっか死ねねーんだよなあ。死んで、目ぇ覚めて、そのたんびに久住がおはよーさんって言うから、殺して、死んで、起きて、殺して……って、ずーっと繰り返してんの、俺」
そう語る男をじっと見つめるうち、伊吹はなぜか、彼が自分なのだと、ただ納得することしかできなくなった。すべてが腹に落ちてしまった。眼前の男はたしかに伊吹自身で、同時に今ここにいる伊吹ではない。これが夢なのかどうか、伊吹はもはやどうでもよくなっていた。だから思考を先に進めて、立ち止まる。
「……ん? どゆこと? 死んだら死ぬでしょ」
「だーからそれができねーんだって。目が覚めるたびにさー、ちょっとずつちがう世界にいんだよね、俺」
俺の話をいつも真面目に聞いてくれる志摩はすげえ。とりあえず伊吹はそれがわかった。それから、この男にはもう志摩がいないのだと思い至って、腹の奥が軋んだ。
「てかお前さあ、なんで志摩のこと訊かねえの」
伊吹がそう言うと、男は泣き出しそうに笑った。
「普通訊くでしょ。つーか俺より志摩に会いに行きゃいいのに」
「バカ。普通も何もねーの、もう俺にはさ」
顔向けできねえじゃん。久住殺した回数も覚えてないのにさ。
その声があまりにひとりごとじみていて、こいつほんとうにひとりぽっちなんだ、と伊吹は思った。やっぱり男は笑っていて、その表情筋の使い方に覚えがあって、自分の頬まで痛い気がした。
「会いに行こうよ」
「ぜってーやだ」
「いいじゃん。とりあえず外歩きながらさ、なんか話そうぜ」
散歩散歩。そう言って、伊吹はすっくと立ち上がり、顔を洗いに洗面台に向かった。男はじっと屈んだままでいたが、身支度を終えた伊吹を見上げ、観念したようにみずからも立った。
「いろんな俺に会ってきたけど、なんかお前がいちばん他人みたいな感じ」
「……俺はお前見て、ああ俺だなーって思ってるけどなー」
自分のぶんのマスクを着けて、男にも不織布のそれを差し出す。ここはそうだったなー。男が言ってマスクを受け取る。そうして連れ立って、伊吹と男は外に出た。
まだ日は昇らないが、夜と朝のにおいが混ざっていた。これがほんとうに夢なら寝た気がしないだろうな、と伊吹は考えたが、起きてしまえば忘れる類のものにも思えた。忘れたくねえな。なんとなくそんな気がした。
「ちがう世界のいろんな俺って何?」
今はとにかく、このもうひとりの自分と話がしたかった。ふとかつて志摩と幽霊の話をしたことを思い出す。会ったことがあるわけではないが否定するだけの根拠もない。そんなものいるわけないと言われるかと思っていたのに、志摩はたしかそんなことを言った。
「分駐のソファで寝てて、カウンターからパチンコ玉が落ちてきて、顔に当たりそうになってキャッチすんの。覚えてる? ピタゴラ装置。まだ志摩が死にたいやつだって知らない頃。あのとき半分寝てたけど」
「あー、あとできゅうちゃんからも聞いた。スイッチね」
「それ。そのピタゴラのスイッチがさ、ちょっとずつちがってる世界を、一個一個覗いてんの」
「想像つかねーなー」
「志摩と出会わなかった俺もいたし、ガマさんと出会わなかった俺もいた。志摩じゃない相棒とそこそこうまくやってる俺も、刑事をやめた俺も」
「……ガマさんに間に合った俺も?」
「それは知らねえ。でも、たぶんどっかにいるよ」
「そっか」
それからしばらく、伊吹は黙って歩いた。男も何も言わなかった。その間、人生ってすげえな、と思った。
「……ん?」
不意に勘が働いて、伊吹は足を止めた。
「何」
「道間違えたかも」
「え、お前志摩んち行ったことあるんじゃないの? 超フツーに歩いてたじゃん」
「いやあるけど駅からだったから、うちから直接はない。感覚で歩いてたけどなんか離れてる気がする。てかお前のほうが知ってんじゃないの?」
「行ったことない」
「使えねえな〜何がちがう世界だよ一回くらい行っとけよ」
「は? お前喧嘩売ってる? 言っとくけど俺まだ志摩に会う気ないからね。てかスマホは?」
「あるけど号室しか覚えてないから意味ない」
「お前こそ使えねえじゃん」
伊吹は吐き出しそうだった言葉を飲み込んで、ひとつ深呼吸をした。吐いて、吸って、吐く。自分と喧嘩をするのは変な感じだった。待て、待て、待て……ここにはいない志摩の声を聞く。よし、もう大丈夫。
「……わかった、こっちだ」
勘の指し示すほうに指を向け、伊吹は歩く。男は一拍遅れて着いてきた。
「根拠は?」
「勘。お前のは?」
「俺の勘はなんにもー」
「俺なのに?」
そのとき、遠くで電車が走る音がした。おそらく先程から走っていた。始発にはまだすこし早いはずだから、貨物列車だろう。
男には働かず、伊吹には働く勘。ということは、ただの勘ではないはずだ。意識に上らないだけ、言葉にならないだけで、きっと根拠がある。男が知らず、伊吹は知っていること。そこから導かれる何か。
「あ!」
わかった。誰かに説明できるくらい、わかった。伊吹はうれしくなって男のほうを振り返った。
「列車の音が遠すぎ」
男が胡乱げな顔をしたので、伊吹は焦れったくなった。なんでわかんないかな。これまで多くのひとにそう感じてきたが、今ならそこで終わりにせず、さらに進める気がした。志摩に言葉を砕いてもらわずとも。
「だーかーら、志摩んちのそばで前聞いたのより音が遠いんだって。やっぱこっち曲がったほうがいいよ。もうちょい線路に近いほう行こ。俺の勘は当たる」
再び前に向き直り、伊吹は歩く。その半歩うしろを男はついてくる。振り返らずとも、男が傷ついたような気配を漂わせていることが伊吹にはわかった。きっとまた痛そうに笑っていることも。
男が永遠に喪ってしまった未来が自分なのだと、伊吹はようやく理解できたような気がした。
「志摩と幽霊の話になったことがあって」
「幽霊って俺じゃん」
曖昧に笑って、伊吹は続けた。
「証拠がないからいるとは言えないけど、いないって断言できる証拠もない、って言ってた」
「うわ、志摩っぽい」
「俺もおんなじこと思った。……そんで、いてほしいかいてほしくないかで言ったらどっち? って訊いたの。そしたら、志摩はいてほしくないんだって」
「へー」
「いるほうが残酷だから、って。俺それ聞いて、会いたいひとの幽霊に会えたり会えなかったりするのはたしかに残酷だよなーって思ってたけど、……幽霊にとっても残酷なんだろうな」
いつの間にか、男は伊吹の横に並んでいた。薄っすらと白みはじめた、けれどまだ夜の静けさを残した街を、さまよえる幽霊とふたり歩く。湿気の多い空気は、すこしだけ潮風に似ていた。
「どうやったら成仏できんだろうなあ」
「ジョーブツ」
「どうせこれから死んでまたちがう世界に行くんだろ? 嫌じゃん。ここで成仏しとこうぜ」
「成仏ってなんだよ」
「いや俺もよくわかんねーけどさ、とにかくお前が安心できるようにするってことなんじゃねーの。幽霊に間に合うとか間に合わないとかあるのかわかんねーけど、このままバイバイはしたくねえじゃん」
あの夢の中、捨てられてなどいないと突きつけられた凶暴な犬のことを、伊吹は想っていた。とっくに捨てた気でいたのに、自分の中にずっといた犬。今となってはほんとうに捨てたつもりでいたのかも怪しい。ただそう思いたかっただけだ。
凶暴な犬に負けた自分の成れの果てが、伊吹にはもう、さみしい迷い犬に見えていた。捨てたくないと、思ってしまった。
既知の道に行き当たり、志摩の住むマンションはもうすぐそこだった。朝焼けがはじまっていて、世界も目覚めつつあった。どうしようかな、と伊吹は思う。なんとなく、この幽霊が夜から抜け出すところを想像できなかった。
「志摩に生命線見せたの、覚えてる?」
「あったなーそんなことも」
「手相って、生きてる間に結構変わるらしいよ」
「それも志摩に聞いたの?」
「や、陣馬さん。なんか、奥さんが毎年通ってる占い師がいるんだって」
「陣馬さんそういうの信じてなさそう」
「女ってのはなんであんなに占いが好きなんだーって言ってた」
「隊長が聞いたら怒りそ〜。朝の星座占いとか楽しいのにな」
「ねー。一位だとテンション上がるし。やっぱ気が合う、流石自分」
「で? なんの話?」
「あぶねっ。そう、手相は変わるんだって。ねえちょっと手相見せて」
男が適当に手を出したので、しばし立ち止まり、伊吹はその手相を眺めた。手相を見るにはまだ暗かったので、スマートフォンのライトで照らす。自分のてのひらと並べて睨んだ。
「なんか違う?」
「や、わっかんねえ。一緒じゃない?」
「えー、なんかショック……俺頑張るわ」
「何を?」
「……毎日? 自分の生命線に負けてらんねえし?」
男はまた、すこし痛そうに笑った。
スマートフォンをポケットに仕舞い、伊吹はまっすぐ男の顔を見た。同じ顔、同じ生命線の、もう死んだ幽霊。
「お前さあ、俺なんかさっさと消えればいいって思わねーの? 見たくもないでしょ」
男は伊吹に尋ねた。伊吹はただ、やだな、と思った。そんなことを言うのは、嫌だ。
「……最初は一瞬思ったけど、今はちげーよ。お前も俺だし、俺はいつお前になるかわかんねーし、でもだからってお前を捨てるのは、ちげーじゃん」
けれど、だから、むしろ。
「俺と来る?」
夢でよかった。最悪にならなくてよかった。そう安堵したことを、伊吹はよく覚えていた。けれど、その最悪だって、たしかに自分なのだ。何かの弾みで一線を越えて、転がり落ちた自分。
「このまま死に続けるより、俺といればよくない? 俺は死ぬまで生きるしさ。そんで、一緒に成仏のやり方を探す。どうよ」
いつの間にか、すっかり朝と呼べる景色になっていた。背中に夏の太陽の気配を感じる。男の顔に、もう笑みはなかった。
なあ、伊吹。伊吹藍。
男の名前を口にして、そういえば呼んでいなかったと、伊吹は思った。そうだよな。俺は伊吹藍で、こいつも伊吹藍。
名前を呼んだら、身体が動いた。勝手に、自然に、本能のままに。伊吹は目をつむり、両のてのひらを合わせる。そうしたくなったから、そうした。
「いていいよ、ここに」
目を開けると、男は消えていた。けれど伊吹は、男がいなくなった気はしなかった。
伊吹が歩くと、影もついて歩いた。太陽はその姿を惜しげもなく晒して、やはりもう朝だった。
志摩の家の呼び鈴を鳴らそうとして、早朝であることを思い出し、周辺をひとっ走りしてから再度訪ねた。それでも連絡もなしに訪ねるには早すぎて、インターホン越しの志摩の声は不機嫌そうだった。相手が伊吹とわかるや否やそれが心配の色を帯びるので、伊吹は申し訳ない一方でどこか楽しくなってしまった。
「朝っぱらから何しに来たんだ」
「えー……なんだろ、志摩ちゃんが俺の生命線見たいかと思って……?」
「は? ……いや、……上がれよ。取り敢えず手洗いうがい」
おじゃましまーす……。控えめにそう言って玄関で靴を脱ぐと、なぜか一気に申し訳なさが優勢になった。だがすぐに、上げてくれたのは志摩だし、と開き直ることにした。
「ねえやっぱ俺帰ったほうがいい? あつまかしくない?」
「お前それ厚かましいって言いたいのか? ……まあ伊吹が覚える必要はない言葉かもな」
「えっ照れる」
「褒め……いや、褒めたのかもな……」
つい今しがたの出来事を、志摩に聞いてほしいのかどうか、よくわからなかった。上手に説明できるとは思えなかったし、それよりもっととりとめもない話をしたいような気もした。だがいずれにせよ、志摩はちゃんと耳を傾けてくれるだろう。その時間の貴重さを想って、伊吹はこっそり笑った。今はどこも痛くなかった。

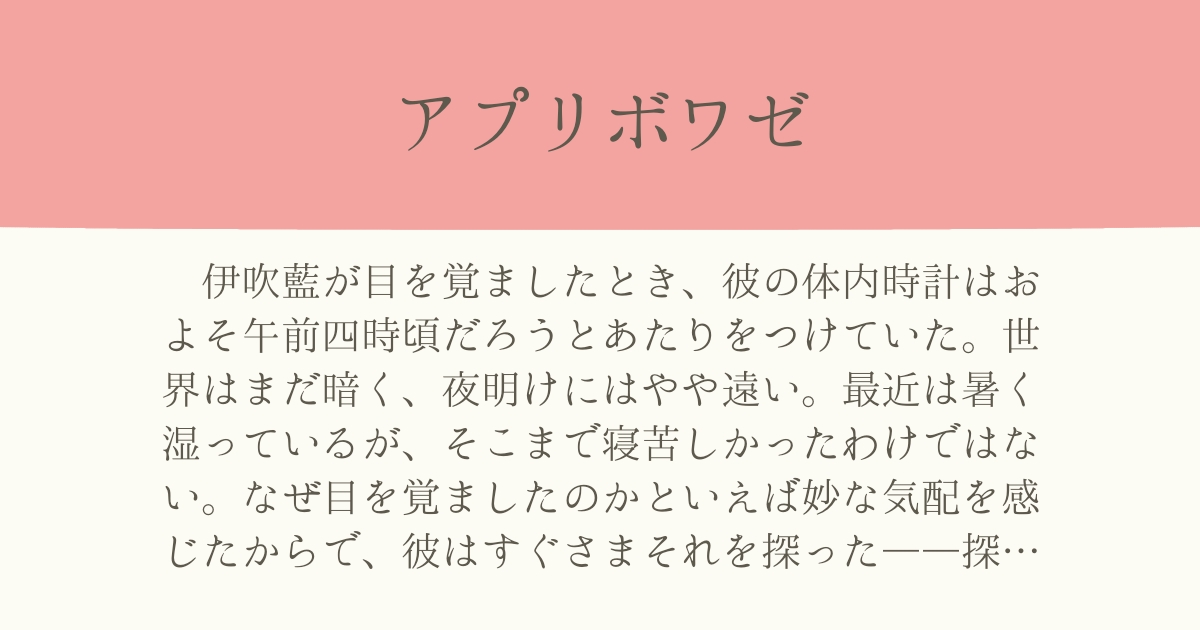
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます