密行中に旅行の話をする2021年夏の404の話です
放送終了1周年と、彼らとともに続いてゆく日々に寄せて
「志摩さあ、北海道行ったことある?」
伊吹藍の切り出す会話はほとんど唐突だが、必ずしも彼の思考が突拍子もないわけではないと、志摩一未は既に知っていた。
ハンドルは志摩が握っていた。車内は涼しいが、前方のアスファルトは陽炎で揺らめいている。いくつかの記憶を引き連れて訪ねてくる、湿度の高い東京の夏。
「ない。今日の気温、もう四十度近いらしいな」
「暑いわけだなー」
「伊吹は? 北海道」
「志摩ちゃんとおそろーい。やっぱ涼しいのかなあ、北海道」
「涼しいとまでは行かなくても、まあここよりはマシなんじゃないか」
この茹だるような暑さとマスクの息苦しさのコンボには悲しいことに慣れてしまったが、慣れたからといって暑くないわけではない。暑い。あのメロンパン号に比べたら車内の空調の効きはいいが、外に出た瞬間には軽く目眩がする。
こんな仕事なので――というのは言い訳がましいかもしれない。たとえ時間があったとしても積極的に旅行がしたいとは思わない――志摩は旅行の経験に乏しかった。幼少期にしても、きょうだいが多いと遠出は難しい。伊吹がかつてこぼした過去も、旅行との縁は浅そうだった。確かめたことはない。
「でもさー、ここよりもっと暑いとこでも生きてるひとがいると思うと、人間ってすげえよなあ」
「それ冬も言ってたな」
伊吹の暑いだの寒いだのを、志摩はそれなりに多く聞いてきたし、志摩自身もかなり言った覚えがある。来年の夏にはめっきり聞かなくなるだろうそれは、だからといって感傷を招くわけではない。なぜなら今この瞬間、外が暑すぎるから。
「みんなすげえし負けてらんねー。今いちばん熱いのってどこなんだろ」
「去年はたしかデスバレーが五十度超えてたな」
「デスバレー? なんかカッケェじゃん。どこにあんの」
「アメリカ」
「行ってみてえなあ」
「行きたいのか五十度に」
刑事なんて仕事でなくとも気軽に旅行ができなくなって久しい。誰しもがすぐには行動に移せない前提の旅行の話は、空想めいてかえって気安かった。旅行が楽しいのは理解するが、そこにはどうしても面倒がつきまとう。その楽しい部分だけを小突いて遊ぶような、浮ついた会話だった。
「そういや……やっぱいい」
「え、やっぱいいつって話さないことある? ないでしょ? ほら〜セイセイセイ」
「ご自慢の勘で当ててみろよ」
「おいおいめんどくさくなってきてるだろ。めんどがらないで、大事な相棒とのコミュニケーション」
「これだけ過ごしてまだお前と話すことがあることに俺は毎日驚いてるよ」
ほんとうに、よくもこれだけ話してきたものだと思う。服の下に隠した古傷や生傷をいたわるような瞬間もあったが、ここまで来ると、どうでもいい話を延々とできることも、それと同じか、あるいはそれ以上にすごい。ビスケットが無限に湧くポケットを、志摩は連想した。叩いて割れてるだけなんじゃないのか、あの歌。
「……ラブの話じゃない?」
T字路、赤信号。この程度の動揺を運転に響かせることはなく、車はゆるやかに止まる。眼の前の横断歩道を数名が渡っていた。
「流石、野生の勘」
伊吹はひとをよく見ていて、それを志摩は知っている。伊吹がどこまで自覚しているかは怪しいが、彼はひとの機微を捉えるのが抜群にうまい。志摩はしばしば伊吹に見抜かれる覚悟をするが、今となっては、彼のまなざしはほとんど不快なものではなかった。伊吹は稀有で不思議な人間だったし、それに新鮮に驚かされる瞬間がしばしばある。
「旅行好きの元カノがいたんだよな。北海道土産も貰ったことあるの思い出した」
「あー……」
ぬるく、やさしく、やわらかい、けれどどこか茶化すような含みのある、完璧な発声だった。伊吹のこういう声を、志摩は尊敬していた。伊吹はたしかに言語化を不得手としているが、表現が下手なわけではない。言葉にならない部分はむしろ誰より雄弁だ。
だがそれも、志摩が伊吹を見つめる中で獲得した感性ゆえに、そう思っているのかもしれなかった。大切なスイッチを見逃さないよう、後戻りできない道に進んでしまわないよう、志摩は伊吹を注視していた。伊吹のサインと、志摩のキャッチ。どちらがすごいのか、もはや判然としない。
「ドタキャンでもしたの」
「いや流石に……近場でもいいから行こうよって何度も誘われて、そのたんびに、俺は無理だから行きたいなら友達でもなんでも誘えばって言って……疲れた」
「……むずかしーねー」
「別れるとき、実はほかの男と三回は旅行してたよって聞かされて、それは反省した」
「え、三回? てかもしかして、その北海道土産も?」
「いや、それ貰った頃はまだそこまで」
赤から青に変わる。アクセルを踏み、右折する。信号が空気を読むことはない。過去の話をしていても、車は発進させなければならない。
「その頃はもう仕事が忙しすぎて、それにかまけて、もうぜんっぜん相手のこと見てなかったんだなって」
志摩が自分のキャパシティを自覚したのはそのときだったし、あるいはそれよりずっと後かもしれない。その頃の志摩には、それを受け止める余裕さえなかった。
桔梗への思慕が静かなものに変質したとき、飲み潰れた陣馬を介抱したとき、九重の成長にひそかに胸を打たれたとき、伊吹にできることを必死に探していたとき――そういう相手を慮る瞬間のすべてが、過去の罪への罰だった。自分に欠けていたもの、自分が見過ごしてきたもの。三度の浮気。薫るウイスキー。未だに気づいていないことが、ひょっとするとたくさん。
「……その子はさあ、旅行するなら誰でもよかったんじゃなくて、志摩と行ってみたかったんだろうなあ」
そう言う伊吹の声は、しんみりというよりも、どこか弾んだものだった。
「お前なんでそんな楽しそうなの」
「え? だってラブの話じゃん。楽しいっしょ」
「とっくに終わってるけどな」
「終わっても、なんかキラキラしたのは残るじゃん?」
すごいな。志摩は思う。くだらない、取るに足らない、どうでもいい話を繰り返す中で、伊吹はときどき、すごいことを言う。そういうとき、志摩は伊吹が他者であることを強く感じる。自分からは生み出され得ないものを、伊吹は軽やかに生み出す。
「定年退職したらさあ、旅行とかしてみるのもいいよなあ」
「今より時間に自由があっても、その頃には体力的に……まあ伊吹は大丈夫か」
伊吹がいつか今ほど走れなくなるということを、志摩はうまく想像できずにいた。彼の足が速いのは、駆けて向かいたい場所と、そこに辿り着きたい意志が明確だからだ。いつか彼の肉体が彼の意志に追いつかなくなるとき、自分の心がどう動くのか、しばしば志摩は考えていた。半ば本気で、こいつ死ぬまでこの調子なんじゃないか、という気がしていた。
そういう楽観にも似た期待は、志摩にはあまり馴染みがなかった。軽いのか重いのか、熱いのかつめたいのか、判然としない感情だった。
「いくつになっても元気な藍ちゃんなんだぜ〜」
そう言ったきり、伊吹は何か納得したように何度も頷いた。それを横目にちらりと見て、志摩は黙々と運転した。伊吹が何に納得したのか、それは志摩にはわからない。志摩の隣にいる伊吹は、志摩にはわからない脈略で、そういう顔をすることがあった。
こんな仕事だから、あるいはこんな仕事でなくとも、志摩にとって分析は習慣だった。それは様々な場面で反感を招いてきたが、伊吹との関係においては悪いばかりではなかった。不可解なことを思索して説明するのは呼吸と同じようにできる。だが志摩には、伊吹が永遠に開拓し尽くせない荒野のように見えることがある。そういう時間が、志摩は嫌いではなかった。不思議なことに。
「何」
伊吹がこちらを見ているのが、志摩は肌でわかった。俺はお前を理解しきれないし、お前が何を考えているのか、お前に教えほしいよ。お前が教えてもいいと思っているなら。そういうものをただ一言、何。
「刑事ってさ、すげえ大事じゃん」
ややあって、伊吹はそう切り出した。
「刑事は俺のなりたい自分で、今はそうやって生きてっけど、じゃあ刑事じゃなくなったらどうなるんだろーって。定年まで勤め上げるぞーそれまでひとつでも多く間に合わせるぞーひとりでも多く助けるぞーってやってるけど、……そのあとのことって、なんかさ、怖えじゃん」
先のことはわからない。定年まで刑事でいられるのか、そもそも生きているのか、それを確信することは志摩にはできない。怪我、病気、あるいは諦観や疲弊。そういうものは時を選ばずにやって来る。刑事以外の生き方も、やってみればそう悪くないかもしれない。
それでも、今こうして伊吹の言葉を聞く志摩は刑事だ。
「……そうだな」
そうだな。怖いよ。伊吹にとって刑事でいることがとても大切だと、知りながら隣にいる今は、すくなくとも。自分がいつかまたそれをどうでもよく感じてしまう可能性のほうが、余程怖いけれど。
「でもさー、さっき旅行とかいいなー、日本一周とか、世界一周とか? してみたいなーって思ったら、そんな怖くねえかもって」
「え、一周?」
「そそ、俺が走りで志摩がチャリで」
「俺も行くのか。しかもチャリ」
「一周しようぜ〜」
誰が行くかよとは、志摩は言えなかった。言いたくなかった。
「まー走りがしんどくなったらさ、バイクとか乗ってもいいじゃん? 会ったひとたちとなかよくなって、そこのうまい店とかキレーな場所とか教えてもらってさ」
「バイクも体力使うだろ」
「ま、引き際は見きわめつつ? 行けるとこまでは風切って走ってたいじゃん」
志摩が真っ先に考えたのは、高齢者の運転免許証の自主返納についてだった。実際に乗るのはほんの数年だとしても、バイクに乗る伊吹は、なんとなくいいものに思えた。何に乗っても似合うだろうし、それによって間に合う何かもあるだろう。
「お前行く先々で現地のひととなかよくなって、別れ際に泣かれてそう」
「泣かれるのはやだなあ。バイバイするときは笑ってたほうがいい」
「伊吹のほうが泣いてるかもな」
「そしたら志摩が慰めてよ」
「ほんとに俺も行くことになってるのか」
「あたり前田のクラッカーじゃん」
古っ……言うでもなくぼやき、それでも志摩は、たぶん気分がよかった。孤独死によって誰かに迷惑をかける可能性を懸念しながら老いるよりも、幾分かいいものに思えた。
だからといって、そういうものにまったく身を委ねてしまうことができるかと言われれば、それは志摩には難しかった。定年までの残り三十年近い時間、それだけあれば人間はいくらでも変わる。変えられないものもある。
「……別に俺じゃなくても、これから先、もっと一緒に行きたいやつができるかもしれないだろ。友達でも恋人でも、相棒でも。そんな先の話に俺を……」
「カッチーン」
それも古い、というかそれを口に出すやついるのか……とは、志摩は言わなかった。間違えた。それがすぐにわかった。やり直したいと思えた。
「悪かった」
かつての恋人がほかでもない志摩とこそ旅行したかったのか、今となってはわからない。それはあくまで伊吹の見立てでしかない。けれど、また間違えてしまったことは確かだった。
すぐに謝ることができてよかった。志摩は思う。伊吹が怒っていると示してくれてよかった。それを自分が汲み取れてよかった。カッチーンは古いが。
「俺は今、俺と志摩のハナシを、志摩とお話ししてたの」
「悪かったよ。ごめん」
伊吹が満足げにしているのが気配でわかった。それがどうしてなのか、今は訊かずともわかった。ウインカーを出し、左折。
「定年したら、俺と日本一周、あわよくば世界一周。約束な」
「約束ね……」
約束なんて、エトリの尻尾を掴めずにいた頃にゆたかとしたのが最後だった。履行できるか不確かな約束は荷が重い。あのときはゆたかが安心して生きてゆくために必要だと判断したから、半ば誓いのような心持ちで約束をした。元いた家に無事に帰れたからよかったものの、もしもあのまま膠着していたらと思うと、口の中に苦いものが込み上げてくる。
「ああ約束って言っても、別に守んなくていいやつね」
「は?」
「ホントのことにならなくてもさ、こう……自分の中に約束があったら、それだけで行きたいとこよりもう一歩先まで走れる気しない? だからー、約束。俺と志摩の」
そんなさみしいこと言うのか、お前。難色を示したのは自分のくせに、志摩は思った。自分勝手もいいところだ。あのとき蒲郡にぶつけた言葉が返ってきた気がした。何があってもあなたは。そんなの、自分にはとても背負えない荷物のくせに、他人にはよくもまあ言えたものだ。ブーメラン。
約束さえあれば、相手がそれを裏切ったって構わないというのか。自分がそれを大事にしてさえいれば、一歩先まで走れるというのか。彼の切るゴールテープの先に何があり、誰がいるのか。誰がいてくれるというのか。彼を信じ、彼が信じたひとはもう。けれどせめて、誰か。
――俺は今、俺と志摩のハナシを、志摩とお話ししてたの。
誰かって、俺か。
気づいてしまったな、と志摩は思った。気づいたからって、絶対に守るよとはどうしたって言えない。そんな性分ではないし、そう言ってしまったら、それはそれでまた何か間違えそうな予感があった。
「……今度、パスポートでも取りに行くか」
悩んだ末に、志摩はそれだけ言った。
「しまちゃん……!」
「暴れるな助手席で運転中に」
そのくらいなら、まあ、言える。言った。伊吹と一緒に、あるいはひとりで、はたまたほかの誰かと、使う機会があるのかはわからない。身分証も足りている。それでも、果てしない約束に近づくための行為を、志摩はせめてしてみたかった。
「パスポートって更新とかいるんだっけ」
「五年か十年に一回」
「じゃ、五年に一回、志摩と一緒に更新だな」
定年まで使わないなら十年でいいだろ、と脳裏をちらりと過ぎったが、まあ五年だな、と志摩も思った。朧気にだって見えやしない未来に向かうのに、現在地を確認するチャンスは多いほうがいい。そのときにはもう、それぞれの場所で生きているはずだから。
「いつかヨボヨボのじーちゃんになってもさ、パスポートのスタンプ眺めて、志摩といろんなとこ行ったな~って思えたらいいよなあ」
「ゲートの自動化が進んでるから、その頃にはもうあのスタンプもあんまり残ってないんじゃないか」
「えっそうなの? なんか顔とか見比べて確かめてんじゃないの?」
「顔認証システムがあるし、事前に登録しておけば今は指紋でも通れる。昔ながらの有人ゲートはこれから減っていくんじゃないか」
「なんか駅の改札みたい。あれもタッチのやつ専用が増えて、切符のとこ減ったよなー」
「いろんなものがどんどん変わっていくんだろうな」
「負けてらんねーなあ。ハイテクに負けないじーちゃんになろうぜ」
「もう既に負けかけてるだろ」
「これから挽回すればいい。問題ナシ。……まあでも、わかんないのって楽しいかんな。いろんなひとが頑張って、いろんなものが新しくなって、そういうのって、なんか感動すんじゃん?」
「お前はほんとうに老後まで言ってそう」
それをこの目で確かめられるのか。やはり断言はできないし、期待することも難しかった。けれど、心のひとかけらがざわついていて、それはたぶん、わくわく、とも呼べる何かだった。志摩はそれをそっと仕舞う。いつか取り出して眺めたくなるときが来る気がしたから。未来の自分が放り投げない保証はどこにもないが、今したいことはそれだった。
「いつかの夏にさ、もうすんげえ寒いとこ行って、地球すげえ人間すげえって感じたいなあ。そんでなんか叫びたい」
「スケールがでかいな。空港で着替える羽目になりそう」
そういえば、そんなところまで行くなら日本語が通じないのか、と今更のように志摩は思い当たった。だが、伊吹がいれば問題ないだろう。言語が違っても、必要なコミュニケーションは取れる人間だ。同時翻訳のアプリケーションや機器だって、今よりずっと高性能になっているかもしれない。
そんなことを考えて、おかしくなった。いつの間にか志摩の中で、その可能性は――約束のようなものは、すこしリアルになっていた。
「でもそう考えたら、志摩も地球みたいだし、みんな地球みたいなのかも」
「……は?」
自分と地球がまったく結びつかず、志摩は混乱した。まさか推測の余地もないほどほんとうに突拍子もないことを考えているのだろうか。お手上げだった。わからない。そこに楽しさを見いだせるかと問われれば、この二年とすこしの間に、できないとは言えなくなっていた。
「なんだそれ」
「ええ? むじーなあ。……なんかさ、暑いとこも寒いとこもいっぺんにあるじゃん。熱いのとつめたいのも、やさしいのと厳しいのも。地球も人間も。そういう複雑な感じ? 地球まるごとっぽくない? ……って、なんか志摩見てたら思ったんだよねー」
「まるごとメロンパン」
「まるごと地球人間」
「すごい比喩だな」
「いいたとえだろ」
志摩は、この地球上に存在する差別や暴力、格差や貧困、旅行なんて困難なほどの情勢不安、そういうもののことを考えていた。おぞましいものであふれかえる猥雑な惑星。けれど伊吹の言う地球は、そういうものではないだろう。もっとうつくしい、希望のある青い星。
グランドキャニオン、トロムソ、ウユニ塩湖、エアーズロック、キリマンジャロ、万里の長城……ローカルなスーパーマーケット、近所で評判のパン屋、太った野良猫、公民館でのちいさな祭り……肉眼では見たことのない風景が、フロントガラス越しの東京と朧気に重なる。憤怒も憎悪も悲哀も寂寞も知りながら、それでも伊吹はこの街を、この星を、そこで暮らす人々を愛している。
そのとき志摩には、助手席に座っているはずの伊吹が、はるか遠くにいるように思えた。茫洋たる宇宙の彼方に浮かぶきらめき。遠い未来への約束。回転する地球。たしかに地球かもしれない。志摩と伊吹は軌道に乗ってしばしば近づき、あるいは離れる。たとえ一生を費やしても、互いのすべてを理解することなどない。永遠に開拓し尽くせない彼の荒野。永遠に立ち入れない彼の永久凍土。人間にとっては長い時間が過ぎ去ったあと、この軌道がふたつの惑星を再び近づけることがあるのか、わかるはずもなかった。
ふと頭に浮かんだロケットのイメージに、志摩は笑った。自分も大概、突拍子もない。
「まるごと地球人間はダサいけど、まあ悪くない」
どこまで通じ合ったのか知る由もないが、伊吹も笑った。
――警視庁から各局。
入電。弛緩した空気が変わる。近い局、どうぞ。聞きながら伊吹が無線に手を伸ばす。機捜四○四。またしばらくは灼熱の中で働くだろう。
ひとまず、今は今を。ここにある肉体と、ここにある車両で、ここにある仕事を、ここにいる相棒と。ひとまず。

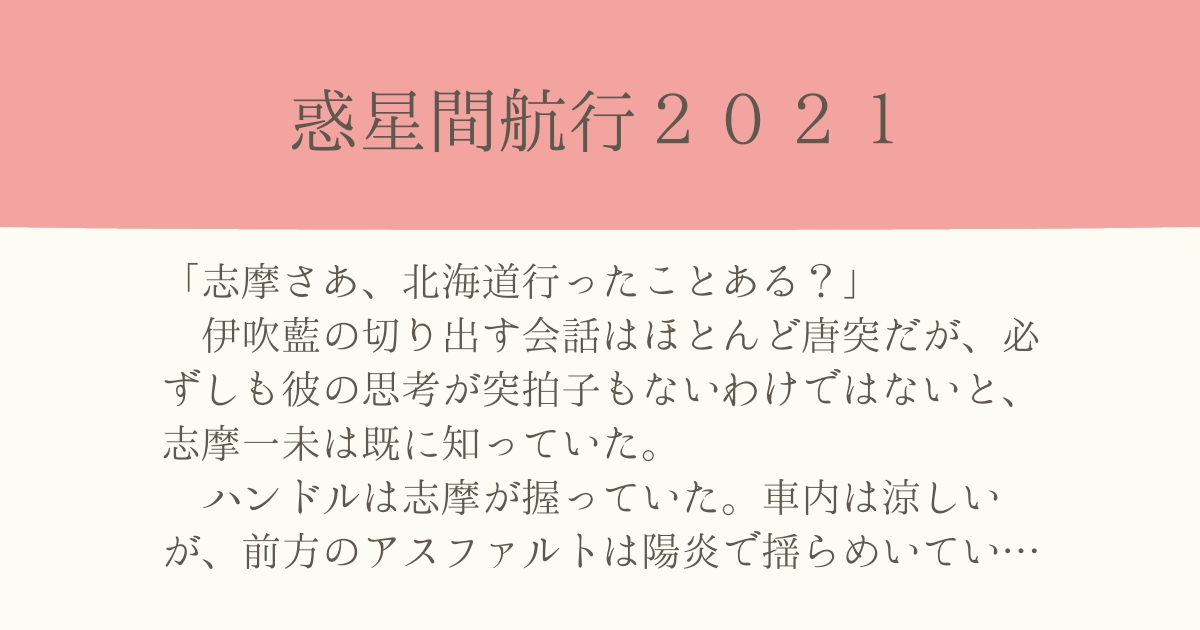
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます