五十路の404がホットケーキを焼いて食べる話です
ちらほらと空席のある半端な時間の電車に揺られながら、志摩一未はメッセージアプリを立ち上げた。夕焼け手前の空はまぶしく、最近乾きがちになってきた目をしばし閉じて労る。膝に乗せた鞄の重みがだんだんと気になってきた。それはたしかに重かったが、そう感じさせる気持ちの問題もあるだろう。
若い頃は移動に疲れるという感覚がわからなかったが、三十路を迎える頃にはよくよく理解していたし、五十も近い今となっては、仕事以外で無理をすることもそうそうない。帰宅を延ばさず正解だった。体力は職業柄あるほうだろうと思っているが、この歳になればもうすっかりおじさんだ。明日はゆっくりして、それから仕事に戻ろう。
しばしそう思案して、志摩はまぶたを持ち上げた。放置され薄暗くなっていた液晶をタップし、スクロールして名前を探す。
――ホットケーキ食いに来ないか
それだけ送ったメッセージに返事があったのは、夜八時を回った頃だった。志摩はちょうど自宅近くのクリーニング屋から帰宅したところで、いいタイミングだった。
「ホットケーキって何?」
返事といっても寄越されたのは通話で、元気そうな声で伊吹藍は喋った。彼はいつも「もしもし」を言わない。
「知らないのか。小麦粉とかベーキングパウダーとか混ぜてフライパンで焼いたものだけど、まあ大抵はホットケーキミックスを買ってきて……伊吹?」
「んふふ。志摩が意地悪言うとき、俺が邪魔しないで聞いてたら困るの志摩ちゃんのほうだって、去年あたり気づいた」
「は? なんだそれもう言わねえ」
「それただのやさしいひとね」
決して頻繁に会うわけではない相棒との付き合いは、細く長く続くうちに手の内をほとんどなくしていた。志摩も伊吹もこの年月ですくなからず変わったのに、彼とのコミュニケーションが変わった気はあまりしない。だからといって飽きるわけでもなく、ふたりの間にはしっくりくる空気が流れ続けていた。
明日なら行けるとのことだったので、じゃあまた明日と通話は終わった。
翌日の昼下がり、伊吹は予定通り志摩を訪ねてきた。彼はあれから官舎を出たが、志摩は転居をしていない。引っ越す理由もそうしない理由もなく、ずるずると契約を更新していた。同世代の人間は一時期ちらほら家を買っていたが、もはやさしたる感慨もない。退職したらもっと郊外に……と思わないではないが、もうここが終の棲家でいい気もする。惰性。
「志摩ちゃんホットケーキ好きなの?」
「そうでもない。なんか焼きたくなって、でもホットケーキってひとりで焼くものじゃないだろ」
「そう? 俺たまにひとりで焼くよ。いくつか積んで、上にバターのっけるやつ」
「おお、本格派。……そういうもんか」
台所に立ち、昨夜の帰りしなに買った材料を並べ、適当なボウルに入れる。ホットケーキミックス、卵、牛乳。多少のダマは気にせず混ぜたくる。こぼれなければそれでいい。こぼれたところで拭けばいいだけだ。
「俺なんかしたほうがいい?」
「いや、焼けたそばから食ってくれればいい」
「お、ワイルド〜。なんかそういうのあるよね、犬のやつ」
「犬? ……ああ、わんこそば」
「それそれ。わんこケーキだな」
「わんこそばはお椀、器のほう。犬蕎麦ってなんだよ」
「だって『おわんそば』じゃなくて『わんこそば』じゃん。わんこは犬」
「……細かい男はモテない」
「あっ出た、志摩たまにそういうヤ〜な逃げ方するよね。絶対そっちのがモテないでしょ」
「うっぜえ……」
そう言いながら笑っていた。こういう攻め方は四十手前でどちらからともなく封印し、四十後半になる頃、これまたどちらからともなく解禁された。自分の焦りというよりは、お互い変な気の使い方をしてしまっていたように思う。開き直ったあとは、ただ楽しいだけだった。
フライパンをあたため、第一陣を流す。きれいに丸く広がった。濡れ布巾にフライパンを乗せる工程を真面目にやったことはない。何かしら意味はあるだろうが、そこまでこだわる動機がなかった。伊吹ひとりならおそらくやるんじゃないかという気がしたが、彼は何も言わなかった。
「そういやお前、はむちゃんとはよくぽちぽちやってたのに、俺には電話してくるよな」
「だって志摩って文字だけだとなんか常に不機嫌そうだもん。てかはむちゃんとは今もぽちぽちしてるし」
電話。志摩は相棒の電話には必ず出るし、出られなければ折り返す。メッセージにも返信する。だが、若い世代のように延々やりとりするようなことは、どうしたって難しかった。だからといってわざと無愛想な文面を送っているわけではないが、伊吹の性分はありがたかった。数年前に組んでいた年下の相棒は「志摩さんって歳のわりに即レスですよね」などと言っていたが、そのあたりの匙加減は今でもよくわからない。
「おじさんにハートマーク送られてもうれしくないだろ」
「俺はうれしいけどなあ。まあ笑うとは思うけど?」
「想像しただけでイラッとする……うわ、きれいだな、テフロン加工が生きてる」
フライ返し――最近めっきり使っていなかったので、今朝洗っておいた――で裏面を覗かせたホットケーキは、記憶の中にあるそれよりも数段きれいな焼き色をつけていた。年季の入ったフライパンでないせいか、ガスコンロでなくIHヒーターであるせいか、理由は判然としない。
「ほんとだもううまそう。なんかいいな、休日〜って感じ」
漠然とした言葉だが、たしかに、と志摩は思った。休日って感じ。たしかにそうだ。
香ばしいかおりが漂う。緊張が途切れるせいか、熱や油、あるいは生地の関係か、二度目以降は大抵いびつな形になる――そういう記憶が志摩の脳裏に蘇った。嗅覚と記憶の深い関連は志摩自身よく知っている。
「てかさっきの何? ひとりで焼かないってやつ」
「……昔、休みの日に父親が作ってくれたことがあって。今思えば数えるくらいだったような気もするんだけど、なんとなく思い出して」
いつかの休日。ホットケーキを待ち侘びるきょうだい。焼き上がったそれを、末の子から順番に食べていく。蜂蜜をかけたり、かけなかったり。早い遅いの差こそあれ、みんなが焼きたてを食べられる。絵本のように厚いものを何段も重ねたものでなくても、バターの欠片が乗ったものでなくても、たぶんそれはいい思い出だった。
「中学のときだったか、食いたくなって作ったんだけど、なんか物足りなくて。そしたら弟に見つかって俺のぶんは?とか言われて。まあ焼いて食わせたら……ああこれか、って」
話しながら、要領を得ないな、と志摩は思った。いつになくたどたどしい言葉がもどかしかったが、ここ数日は、こういう時間をこそ求めていた気がした。
「それが志摩のホットケーキだったんだ」
志摩のホットケーキ。すとんと腹に落ちてくる言葉だった。一枚目のホットケーキが焼き上がり、掬い上げて皿に乗せる。フォークの側面で適当にひとくちぶんに切り、口に運ぶ。熱い。
「そういうこと」
伊吹にフォークを勧めて、彼も笑って食べた。今日、伊吹が来てくれてよかったと、志摩は思った。
皿が一枚。フォークがふたつ。ボウルとお玉とフライパン。ふたり。伊吹のホットケーキはそうでないのに、彼は志摩のホットケーキに従い、台所に立ってフォークを咥えている。あ、うまい。久々に食うとやっぱうまいね。志摩は感動をごまかすように、二枚目のホットケーキを焼きはじめた。
三枚、四枚とホットケーキを焼きながら食べた。伊吹はうまそうによく食べたし、志摩も焼きながら結構摘んだ。タピオカは一口でギブしてたのにホットケーキは食えんだね。まあ昼食ってないから。
皿の上が料理で満たされることはない。未完成のままなくなって、それでよくて、それがいいのが、志摩のホットケーキだった。
「ねね、志摩がいいなら俺も焼いていい?」
「じゃあ頼む」
最後の一枚。余った生地をすべて投入したので、これまでのものより幾分か大きかった。焦ればうまくひっくり返らないのは目に見えていたので、ふたりしてしばし待った。
「……今日、ありがとな」
「何が?」
「来てくれて。明日からまた仕事だから、俺の都合だけど、助かった」
「そういや志摩、昨日も休みだったの?」
「今日までな」
「連休? いいじゃん」
「あー……忌引きで。父親が」
「……」
伊吹は刹那、迷うように目を泳がせた。それから、そっか、とだけ言った。志摩は湿っぽい空気にしたいわけではなかったし、変に気を使わせたいわけでもなかった。だから、つとめてさっぱりと話した。
「ほかのきょうだいのほうが仕事に融通効くし、親戚のこどもも来てるからだんだん盆正月と変わらない空気になるし、この歳なのにいいひといないのとか言われだして、さっさと退散した」
「……それってさー、今日、志摩にとって、すっげえ大事な日だったってことじゃん」
ゆっくりと言葉を探すように、伊吹は喋った。年月を重ねるうち、そういう伊吹を目にすることはしばしばあった。そんなに真剣に考えてくれなくたっていいと志摩は思ったが、逆の立場ならそうはいかないことも容易に想像できたから、黙って聞いた。
「機捜の頃って、俺ら仕事で組んでたし、仕事は待ってくれないじゃん。だから、お互いがこう……刑事に戻る? スイッチになるのは、ふつうってか、自然だったじゃん」
うん。志摩は相槌を打った。伊吹を屋上に迎えにいったあの日。伊吹の言わんとすることがなんとなくわかって、けれどやっぱり、志摩は待った。
「でも今は、志摩が連絡くれなきゃ今日だって会ってないし、俺はなんにも知らなかった。志摩が昨日俺のこと誘わなくても、俺が予定合わなくても、志摩は明日からきっちり仕事してたと思うけど。……でも、なんか……すげえなあ。……すげえ」
なまじ思い出を共有している家族を、自分の儀式めいた感傷に付き合わせるのは、どこか重かった。上手に結べない喪服のネクタイも、義母や義父の経験からあれこれ手際よく手配するきょうだいも、流石にくたびれたふうの母親に寄り添うのも、退屈した甥や姪の相手をするのも、決してどうでもよくはないから、やはり妙に重かった。
何も知らない伊吹が、志摩のホットケーキに付き合ってくれた。それがちょうどよかったし、志摩にはそれでよかった。それがいちばんだとさえ思えた。
「そろそろ焦げないか?」
「あっやべ」
あわててひっくり返したホットケーキは、焦げているとまではいかないが、こんがり、と形容すべき色になっていた。けれどこの大きさなので、おそらくこれでちょうどよかったのだろう。
「サンキュー志摩ちゃん。間に合った〜」
ありがとね、と神妙な声で伊吹が言うので、その含みを察しつつ、志摩は軽く答えた。
「別に結婚してなくても、ホットケーキが食いたくなったとき、それに付き合ってくれるやつがいるんだから、それでいいだろって、思ったよ」
「……そうかも」
最後の一枚はきれいな円形をしていた。いつか伊吹のホットケーキも作ってみたいと、志摩は思った。そんな気分の日が来たら、伊吹は志摩を招いてくれるだろうか。
それは定かではないが、明日の志摩はきっと刑事だった。

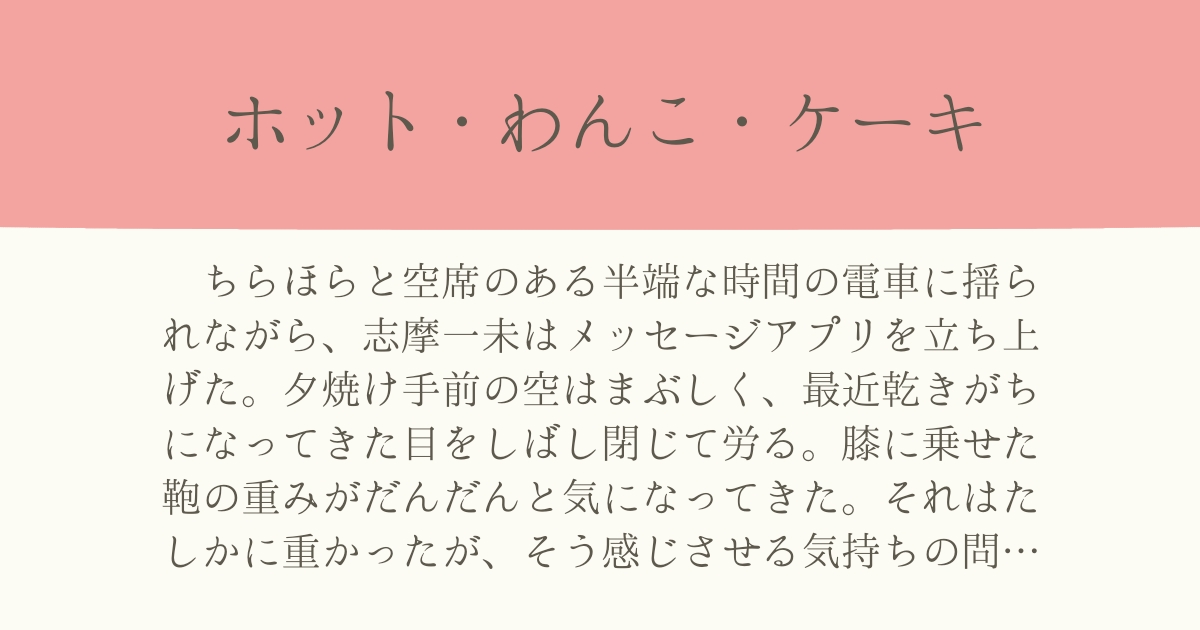
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます