ついてない日の志摩といつもどおりの伊吹の話です
自宅から分駐所に到着するまで、すべての信号が赤だった。バインダーを開いて字句を書きつけようとしたら、ペンのインクが切れていた。分駐所のシャワーを使い、全身を濡らしてから、シャンプーがないのを思い出した。ほかにも細々、多々。
そういう日だ。そういう日か、と志摩一未は思う。イッツ・ノット・マイ・デイ――そんな言葉があるらしい。ついていない日。苛立ちはある。だがその一方で、どこか安堵している。たまに訪れるあらゆる幸運から無視される日が、志摩は嫌いではなかった。そういう日は必要な帳尻合わせだから存在する。なんとなく、そんな気がしていた。
だが、今日はどうだ。
信号待ちをしていたら同じく出勤してきた伊吹に話しかけられた。伊吹に借りたペンでメモを書いた。伊吹に差し出されたシャンプーで髪を洗った。だから、志摩は自制していた。
何かの拍子に心が揺らいだら、伊吹を疎ましく感じてしまうかもしれなかった。
伊吹は何も悪くない。ただ困っている相棒を当たり前に助けただけだ。そして当然、伊吹以外の誰だって悪くない。悪いのは――。
身勝手な、ただ自分が納得するためになっているだけの自罰的な気分を、伊吹は尽く邪魔してくる。それを喜んでいない自分がいることが、今の志摩の罰の形だった。
* * *
「あ」
「どしたの志摩ちゃん」
「靴紐が切れてる」
「俺あたらしいの持ってるよ」
「……お前靴紐の替えまで持ち歩いてんの」
「いつだって走れる藍ちゃんだかんな〜。あったあった、はい」
「……ありがとう」
けれどそのありがとうだけは、ただただ感謝であるべきだ。余計な雑念があってはならない。そう伝わってくれないと困る。志摩はつとめてそう思い、言った。なぜなら志摩は刑事だから。

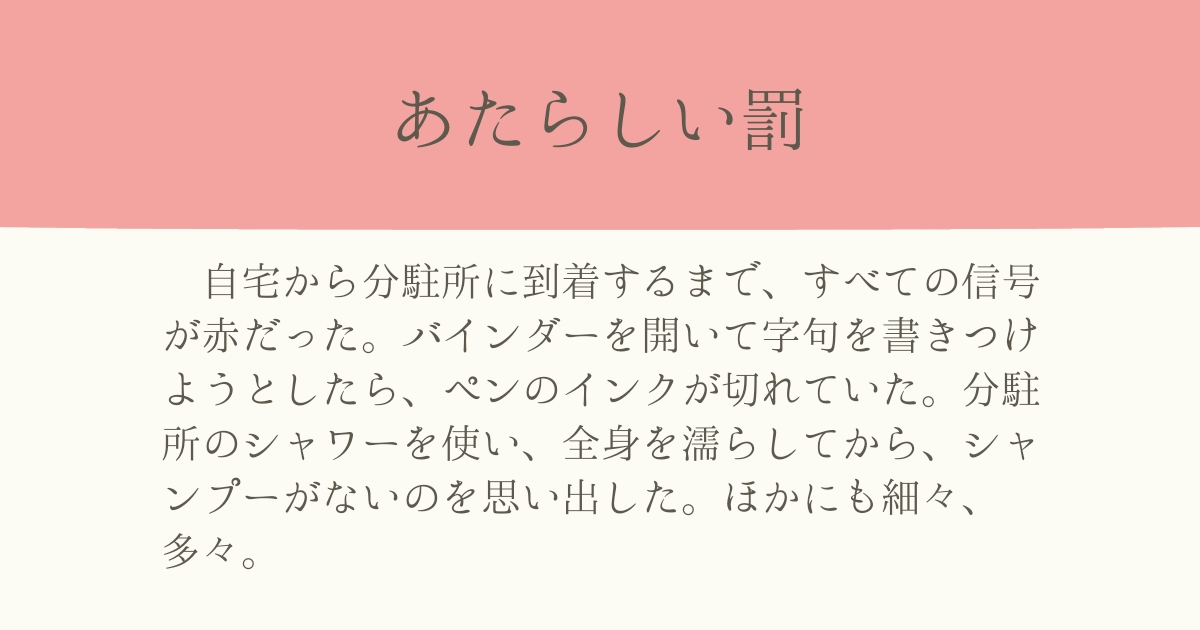
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます