猿彦と海斗が一緒に過ごした最初のクリスマスの話です。
※サンタクロースの秘密についてのおはなしです。サンタクロースがプレゼントの用意と配達以外に何をしているのか知らないひとは、まだ読まないでください。
「これがクリスマスか!」
イルミネーションに彩られた寒空の下。桃太郎がそう言うのを、伏見海斗は聞いていた。夕食の支度をしていた猿彦が、切らした醤油を買ってきてほしいと言うので、買ってこいと言い直させて意気揚々と飛び出すと、なぜか桃太郎もフードの中に潜り込んできたのだ。商店街にはツリーが飾られ、こころなしか賑々しく、年の瀬そのものといった有り様になっていた。寒さのせいか、桃太郎はいつもよりも膨らんでいる。
「ひよ太郎がクリスマス知ってるのウケるな」
「猿彦が知っていたことは俺も知っているからな。モミの木があちこちに飾られて、大事なひととケーキや七面鳥を食べる日なのだろう?」
ひよこがチキン食っていいの? と海斗は言わなかった。この冬に至るまで、既に言ったことがあったから。猿彦の用意する食卓には調和のために様々な食材が並ぶし、鶏肉が載せられたこともある。桃太郎はうまそうに啄んでいたし、むろん海斗はいつものように猿彦のすべてに感謝して食べた。うまいまずい以前に、猿彦の作る食事は猿彦の作る食事だ。常に尊く、素晴らしい。それを食べ続けるために海斗は敢えて料理を学ばなかったくらいだ。
「あと、いい子のところにサンタクロースが来たり」
「サンタクロース?」
「……ひよ太郎サンタ知らないの? 猿彦は知ってたのに?」
それは海斗にとってすくなからず意外なことだった。猿彦の知識が桃太郎に共有されたことは海斗も知っているし、なんならずるいと常から思っている。だというのに、桃太郎がサンタクロースを知らないなんて、そんなことがあるだろうか? だって。
「サンタクロースとはなんだ?」
「んー、クリスマスイヴの夜、いい子にしてたこどもの枕元にプレゼントを置いていく、赤い服着た白髭のおっさん……かなあ」
だって、海斗のために猿彦はサンタクロースになろうとしてくれたのに。
* * *
猿彦の人生は、様々な変化にさらされながら編まれてきた。
時が流れて世は移ろい、数多のものが生まれ死ぬ。受け取るもの、断ち切るもの、つながるもの、きっと忘れてしまったもの。はじめて洋装に身を包んだとき、はじめて苗字を名乗ったとき。知らない手順の結婚式に出たとき、知らない手順の葬式に出たとき……猿彦は変化を感じながら、しかしそれに順応してきた。
クリスマスを祝う習慣はいつの間にか猿彦の身近にあり、彼はそれをあるがままそういうものと理解していた。街中にツリーが現れ、イヴにはケーキやチキンが売られ、皆が買って家に帰る。それが終わればあっという間に正月が来る。どちらかといえば、猿彦の意識は皆続々と挨拶に来る正月に向かっていた。
冬に連れて行かれる人間は時代とともに随分減ったが、それでも冬場は衛気が薄くなりやすい。自然、猿彦は忙しかったし、何よりそちらのほうが大事だった。
海斗のために家を定め、彼の訪問が当たり前になった最初の冬のことだった。いつものような食事をしながら、ふと海斗が言った。
「二十四日、泊まりに来てもいい?」
「……何か、あったのですか?」
「ううん。何もないけど、たぶんママ帰ってこないから」
「予定があると?」
「毎年そうだから。えーっと、一昨年? 家にいたときは、なんかすごい機嫌悪かったし。今年はわかんないけど、どっちでも猿彦と一緒がいいな」
そのときようやく、猿彦はクリスマスという行事のことを思い出した。鬼が出ればTAOが動くし、猿彦がその指示を出すことも多い。クリスマスの鬼退治も経験したが、近年その日は正月同様なるべく猿彦自身が動いていた。クリスマスは皆が家族や恋人と過ごすのだと知っていたから。
……だからつまり、そういうことなのだ。
「わかりました。当日は着替えを忘れずに。布団を干しておきましょう」
「布団って干すの?」
「はい。晴れ続きの日に外に干すとふかふかになります。雨や雪が降らないよう思兼神に祈っておいてください」
その夜になり、猿彦はクリスマスを誰かと過ごすのははじめてなのだと思い当たった。妻の存命時はまだクリスマスが定着しきっておらず、猿彦からすればあたらしく感じる……乗りそびれたとも言える文化だった。
ケーキやチキンが売られているのは知っている。しかしそれを買った人々は、家でどう過ごすのだろう? 自分ひとりなら困ることもないが、問題は海斗もそれを経験していないであろうことだった。……猿彦は海斗にふつうの人生を歩ませてやりたかった。そのためには、猿彦自身が現代のふつうを知っている必要がある。
猿彦ひとりでも、世の移ろいは身につまされているつもりだった。しかし、こどもという常に最もあたらしい存在と関わるには、もっと世界に深く踏み込まねばならないのかもしれない。海斗はすくなくとも今のところは雛鳥のように猿彦の背を追っているのだから、三百年ぽっちで仙人を気取って浮世離れするわけにはいかないのだ。ひとを導くのは難しい。単に鬼退治の手管や忍者の心構えを教えればよいのではない。それを痛感すればするほど、あんなに追った主君の背中が遠かった。かつて自分に与えられたものの途方もなさに、打ちひしがれる思いだった。
「クリスマスといえば、やっぱりケーキとプレゼントかな」
幸いなことに、三百年前に道を誤らなかったおかげで、猿彦はひとりではなかった。ちょうど誰かを頼ろうと考えた折、訪ねてきたのは比良坂正一だった。縁側に並んで座った正一は、にこやかにそう答え、茶を啜った。
「プレゼントですか?」
「そうそう。イヴの夜にはいつもより豪華な食卓を囲んで、最後にケーキを食べる。そわそわしながら眠って、クリスマスの朝に目が覚めると、枕元にプレゼントが置いてあるんだ」
「なぜ直接渡さないのですか?」
「ああ、そのプレゼントはね、サンタクロースがくれるんだ」
「サンタクロース、ですか」
「うーん、フィンランドに住んでいると言われる、真っ赤な服に白い髭のおじいさんでね、トナカイの引くソリに乗って空を飛んでやって来るんだよ。いい子にしていたこどもたちの枕元にプレゼントを置いていくんだ。煙突から入るとか靴下に入れるとか、あとはミルクとクッキーを用意しておくとか、ほかにもいろいろあるけどね」
「情報量が多すぎて、今時の若い子の話を聞いているみたいです」
猿彦の頭の中で、この時期よく見かける赤い服やつけ髭とサンタクロースがつながった。皆がしていた格好はそういうことだったのか。合点がいくと同時に、煙突……? とも思っていた。このあたりで煙突のある建物といえば、銭湯か火葬場くらいのものだ。
「猿彦さんからすればみんなそうでしょう」
正一は朗らかに笑った。……煙突はさておき、猿彦には何より解決すべき課題があった。
「今年のクリスマス、海斗はうちに泊まります。サンタクロースは海斗の所在を把握できているでしょうか」
正一は、妙に後ろめたいような、申し訳ないような顔をしていた。
正一の背を見送りながら、猿彦は困っていた。
サンタクロースは大人がこどもに見せる夢であり、彼からのプレゼント……ということになっているものは、大抵そのこどもの親が用意するものらしい。海斗にはどう考えても猿彦が用意すべきだったが、彼の欲しいものがなんなのか、猿彦には皆目わからなかった。自分の少年時代を思い返して役に立つはずもない。
この季節の親は、こどもの欲しいものを知るために四苦八苦することもあるらしい。いっそ本人に尋ねるべきだろうが、猿彦は腹芸を途轍もなく不得手としていた。嘘をつくのも隠しごとをするのも下手だ。猿彦の嘘が見抜かれることは、サンタクロースという夢の終焉を意味している。それは猿彦が海斗にしたいことではなかった。海斗は聡い子だ。猿彦の隠しごとなど簡単に露見するだろう。
困った猿彦は、またしてもひとを頼ることにした。電話の向こうの山県景勝は、師匠として海斗との関わりも深い。何か知っているだろうと期待したが、彼の返事は呆気なかった。
「海斗は猿彦が用意したものならなんでも喜ぶだろ」
「……そうだとしても、何を用意すればいいのか見当もつきません」
真面目に考えてください、と茶化す気にはならなかった。猿彦の選択の結果、海斗が鬼喰になったのは事実だ。海斗の関心が猿彦ばかりに向くことを、猿彦は責められない。
「近頃の子ならゲームだなんだと欲しがるだろうが、海斗は興味ないだろう。相手の求めるものを考えるのは美徳だが、これに限っちゃ意味がない。猿彦が海斗にあげたいものを考えるほうがよっぽど建設的だ」
「俺が海斗にあげたいもの……」
あげたいものは、いくらでもあった。健康的な食事、あたたかな寝床、清潔で身体に合う衣服、抱き締められる経験、安心――かつて猿彦自身がもらったすべてを、あの少年に。それらのうち、包装されたプレゼントの形を取りうるものはなんだろう。
やがて思いついたひとつの案を、猿彦は景勝に伝えた。必要な情報は景勝が知っていた。景勝も少年に目を配り、気になっていたのだろう。外泊の連絡は景勝からしてくれるということだったので任せ、礼を言って電話を切り、外出の支度をした。夕方に差し掛かっているから、補導の心配はないだろう。夜ばかりでなく平日の昼も稀に声をかけられる。彼らの目が本来それを必要としている少年たちに届くよう、猿彦はそれを邪険にはしなかった。
そうして来るクリスマスイヴは、つつがなく終わりつつあった。終業式から直接来るために朝から着替えを持って出たのだと海斗は弾んだ声で言った。冬季の早い日没、いつもより豪華な食卓、きれいなケーキ……見様見真似のあたらしい習慣を、海斗はしきりに喜んだ。はしゃいで眠ろうとしない彼をよく干した客用布団に押し込んで、眠っていることを確かめる。
猿彦は知らず細く長く息を吐いた。腹芸はできないので、今日一日はサンタクロースのことを考えないようにしていた。それは存外難しいことではなかった。ただ目の前の海斗のことを考えていればよかったから。
気配を消して立ち上がり、そのまま部屋を出る。押入れの奥に仕舞い込んだプレゼントを静かに取り出し、足音を殺して愛しいこどもの元へ戻る。襖の向こうの気配を探り、眠りの深さに安堵する。鬼退治以外でこうも忍者のようなことをしたのは久し振りだった。
猿彦が気づかなかっただけで、子を持つ世の親たちも、今頃こんなふうなのだろうか。海斗の枕元にプレゼントを置きながらそう思い至ったとき、彼の胸に去来したのは……たぶん、世界への親しみのようなものだった。その感慨は、頼れる仲間や守るべき生命に向けるものとは微妙に違う気がした。どちらかといえば、妻が存命だった頃に幾度か感じたものに似ている。
深夜の静かな部屋の中で、猿彦はきっと人々の営みの真ん中にいた。言葉を交わしたり身体にふれたりするのとは違う形で、世界に足を踏み入れている。やがてそれが引き連れるであろう寂寞がちらと脳裏を掠めたが、今日ばかりはと追いやった。特別な夜だから。特別な夜になったから。今夜の猿彦は、顔も知らない誰かときっと一緒なのだ。
翌朝、猿彦が食事の支度をしていると、ちいさな軽い足音が台所に向かってきた。幸いまだ火は使っていない。菜箸を置いて振り返る。
「猿彦! これ……」
振り返れば海斗はどこか呆けた顔をしていて、けれど両腕でしっかりとプレゼントを……スニーカーを抱いていた。うれしさとは違う海斗の表情から、あまりいいプレゼントではなかったかもしれない、と猿彦は考えた。
「中敷きもありますが、大きさが合わなければ交換できるそうです。まずは家の中で履いてみてください」
「これ、猿彦がくれたの!?」
「……」
猿彦は硬直した。慣れない腹芸はすっかり昨夜で終わった気になっていた。やってしまった。どうしよう。咄嗟にうまい言い訳などできないことはわかりきっていた。だが自分のそういう性質こそ言い訳にはならない。目の前にいる、このひとりの少年の、たった一度きりのこども時代のためには。
「サンタクロースが……そう、言付けていました……」
結構な沈黙ののち、猿彦はそう絞り出したが、海斗はまるで耳に入れずに喜色満面の笑みを浮かべた。
「猿彦からのプレゼントだ! やったあ! ありがとう猿彦!」
「……俺からのプレゼントで、よいのですか」
「だって、いちばん欲しかったプレゼントは、猿彦がくれるプレゼントだから」
海斗はそう言うが早いか、さっそくしゃがみこんで靴に足を突っ込んでいた。そのちいさな手に靴紐はまだ早いだろうから、マジックテープ式の靴。どういうものが人気か、すこやかな足でいられるか、まっすぐ走ってゆけるか。恐縮するくらいにこやかな店員に気圧されながら相談して選んだ靴。海斗がもっとほかの道を選んでも彼と伴走してくれる靴。
「なんで俺のとこにはサンタさん来ないんだろうって思ってたけど、今はどうでもいい。一回も来たことないサンタからもらうプレゼントより、猿彦のプレゼントがいい」
ぴったりだと笑う海斗の頭を撫でながら、猿彦は漠然と理解していた。海斗は大人になったのではない。海斗はもう海斗になっているのだ。その靴でどこに旅立ってもよいのだと、猿彦はついぞ言えなかった。
「大事にする! ずーっと履く!」
「足に合う靴を履くことのほうが大切です。窮屈な靴を履き続けると、骨が歪むこともあります。合わなくなったら教えてください」
「そしたらまた猿彦があたらしいのくれる?」
「……次は、貴方の気に入るものを一緒に選びましょう」
「えーっ。猿彦が選んだのがいい」
「……貴方が選んで、なぜそれを選んだのか俺に教えてください。靴も服も、貴方の身の回りのものは、貴方自身が好ましく思うものを、貴方が選びなさい」
海斗がぱちぱちとまばたきをするのを、猿彦は静かに見ていた。このくらいの時分のこどもは何をどこまで理解するものだろう? ……だが、そのように考えることには、たぶんあまり意味がなかった。海斗の答えは海斗の中にある。海斗が猿彦を追ううちは、都度振り返って向き合うしかないのだ。猿彦が間違ってしまわないか、そこにいる海斗に確認しながら。
「……海斗。食事にしますから、手を洗って。靴は玄関に、きちんと並べて置いてきてください」
「うん!」
* * *
「桃さんに共有されたのは意味記憶だけです。大神実命がどう判断したのかわかりませんが、サンタクロースはエピソード記憶として扱われたのでしょう」
三人、あるいは二人と一匹で囲む食卓には、いくつかの副菜と味噌汁、それから肉じゃがが並んでいた。
肉じゃがはいつの間にか定番の家庭料理になっていて、猿彦もしばしば作るようになった。全国を転々としていた頃に豚も牛も食べたが――一般に肉じゃがの肉は東西で異なるとされる――どちらも好きだった。今日は豚肉だ。
「猿彦にとってのサンタクロースは、記憶ではなく思い出ということか」
「そうなります」
そのとき海斗がどんな顔をしていたのか、猿彦と桃太郎はたまたま見ていなかった。あのときいらなくなったサンタクロースがそれでもきっと大切なサンタクロースの思い出であることを……そうであればこそどこまでも猿彦との思い出であることを、今の海斗はもちろん理解している。海斗の日々はよろこびにあふれて続いてきたし、これからもそうなるだろう。

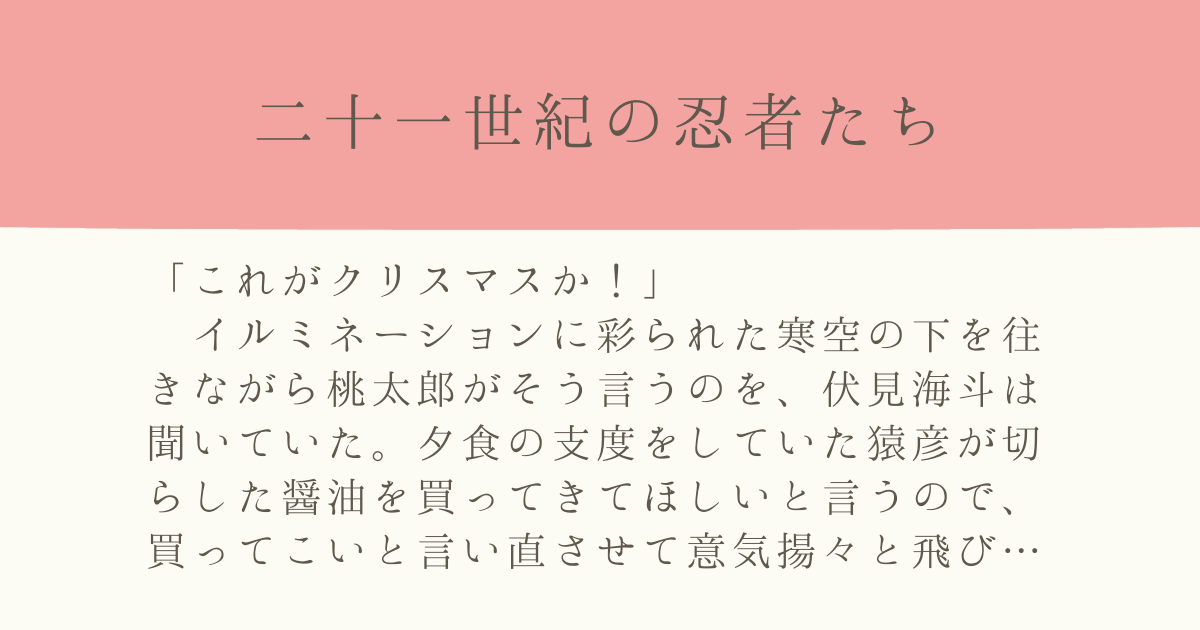
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます