双黒:再会後にカレーを食べる話です
家に帰ると、幸せの香りがした。
中原中也は幾つか帰る家を持っているが、頻繁に使うところは限られている。そしてその高層建築の一室には、太宰もまた頻繁に訪れた。「この太宰治、嫌がらせには余念がない。退屈な人生の慰みに君を使わせて呉れ給え!」とかなんとか彼は言って、いつの間にか合鍵を持っていた。中也は太宰を一発殴って鍵を奪った。奪ったと思ったらそれはフェイクだった。そんなことが四度あり、それ以降中也は諦めた。
しかしながら、彼がその家に帰るのは実に半年ぶりのことだった。西方の小競り合いを鎮圧し、随分と久方ぶりの帰郷だったのだ。
玄関の扉を開けると、随分と空気が柔らかかった。半年も無人にしていたとはとても思えない程。そして鼻腔を擽るこの――
「邪魔しているよ」
「……た、だ、い、ま」
「……お帰りなさい。簡単に掃除はしたから。どうせ夕飯はまだだろう? まあ食べたくなかったら明日の朝にでも温めてくれ」
重低音ではきはきと、あからさまに嫌そうに告げられた帰宅を、太宰は肩を竦めて言葉面は歓迎した。似合わないエプロンをつけて、鍋をお玉でかき混ぜる姿は、凡そ太宰のものとは思えなかった。
「手前、何やってんだ?」
中也は訪問者の存在を認識しながらも常日頃通りの所作で帽子を取りコートを脱いだ。皺にならないようきちんと仕舞う。彼の習慣は太宰に乱されたりはしない。
「見ての通り、咖喱を作っている。マフィア随一の料理上手と謳われた私の咖喱を食べる権利を君に与えよう」
「ポートマフィアにはこんな言葉があった。『太宰治の料理を食うと碌なことにならない。但しその誘いを断っても碌なことにならない』。知ってたか? あと手前はもうマフィアじゃねえ」
「それは初耳だなあ。こんなに美味しいものを敬遠するなんて、それはそれは愚昧な人間のすることだよ」
お玉で掬った咖喱をどこから取り出したのかわからない小皿によそって一口、太宰は微笑して中也に小皿を差し出した。此奴だって食べたのだからまあいいだろう――中也はそう判断して口をつけた。
「……美味いな」
「でしょう」
中也は内心感嘆した。店に出しても遜色ない味だと思った。甘口だが、甘口なりに、おいしい。
「市販のルゥなんて使っていなくてね、咖喱粉と小麦粉から作っているんだ。流石にスパイスから調合とは行かないが、幾つかハーブを混ぜてある。美味しくないわけがない。二年間をかけて辿り着いた味だ」
「腐った魂の自殺嗜癖のくせに、料理ができるなんざとんだ矛盾野郎だな」
二年間。その時間に何かを思わない中也ではなかったが、敢えて指摘することはなかった。
「お褒めに預かり光栄だよ。米は蒸らしているところだから、あと三分もすれば食べられる」
図ったようなタイミングだ。薄気味悪い男だ――中也はそう思ったが問い詰めはしなかった。経験上、答えが得られるわけもないとわかっていたし、帰宅したら食事の用意があるというのは、決して嫌なものではなかったからだ。
食べるということは、生きるということだ。料理を作るということは、生きたいという意志の表れだ。太宰は死にたい死にたいと嘯きながら、生命存続の営みを当然のように行う。
「中也、手を洗って嗽をしておいで。『きらきら星』を歌いながらね」
「ままごとがしたいなら女装でもしてから来いよ」
「君が脱がせてくれるなら考えよう」
「エイジプレイかよ……」
中也は太宰に背を向け、上げた手をひらりと揺らすとリビングを出ていった。
手を洗う。嗽をする。どちらも生きることにゆとりのある人間がする行為だ。切羽詰まった人間はそんなことはしない。或いはゆとりがあっても、物種な人間はしないだろう。しかし太宰はそれをしろという。中也は太宰の嘗てないセンチメンタルを察知した。そして同時に、だからなんだ、とも思った。
水音が心地よかった。太宰を殴った手袋は洗濯機の中に放られていた。
リビングに戻ると、ローテーブルに咖喱が二皿と水の入ったコップがふたつ並んでいた。不揃いな皿。スプーンの形も異なっている。一組はこの家にもともとあったものであり、もう一組はいつの間にかこの家にあったものだ。ここにはそういうものが沢山ある。
ふたり並んでソファに腰掛ける。目の前には湯気立ち込める咖喱。
「いただきます」
太宰が殊勝に手を合わせたので、中也もそっと手を合わせた。それは、己の生きる糧となった命を思う行為だ。それをする自殺嗜癖の心理は、中也には想像がつかなかった。
米とルゥと卵、それからソースを絡め、一口。
「癪だがやっぱり美味えな……」
「だろう。感謝し給えよ」
ごくごく普通の咖喱だった。角が落ちるほど煮込んだ野菜と、大蒜で炒めた牛スジ。薄口の出汁。シンプル、素朴、純朴。およそ太宰とは似ても似つかない咖喱だった。いや、ある意味では彼そっくりなのかもしれなかった。ただ、咖喱を作る彼は、どこか『らしく』なかった。
「……星の王子様咖喱ってあるだろ。あれくらいの甘さ……いやそれよりはマシか……でも美味え……」
「辛いのは嫌いなんだよ。ちなみに隠し味は味の素だ」
「隠し味は隠したままでよかったんじゃねえのか」
「真の隠し味はハーブだよ。どんなハーブを入れたか想像もつかないだろう? 私が死んで、この咖喱が懐かしくなったら、精々必死になって探すといい」
「誰が探すかよ」
喋りながらも咖喱は減ってゆく。
「ねえ中也、お酒出してよ」
「半年前に赤と日本酒以外大体開けちまったからなあ。そもそも咖喱に酒ってどうなんだ」
「だからこそ冒険するんじゃあないか。タンカレーとか飲んでみない?」
「洒落かよ……」
「でもジンって案外イケそう」
咖喱は家庭の味である。多くの人にとってはそうだろう。彼らにとってそうなのかは彼ら自身しか知らない。彼らは互いの過去を、半生を、歴史を、物語を、知らない。
しかしそれでも、なんとなく、咖喱は幸せの食べ物である気がしていた。そしてその咖喱をなぜだか一緒に食べていた。
「中也って意外とよく噛んで食べるよね」
「っつーか手前なんで此処に来たんだよ。其方とウチとで戦争始まってんだろ?」
「君に会いたかったから。もうすこし言うと、セックスしたかったから」
「……あ、そ」
馬鈴薯がほろほろと解けてゆく。
「もっと浪漫チックな方がよかった?」
「風呂なら好きなときに使えよ。半年掃除してねえから掃除しとけよ」
玉葱は甘く柔らかい。
「そんなあからさまに拗ねないでよ。あと私時々この家使ってたから風呂は綺麗だよ」
「何やってんだ手前は……俺の残り香で抜いたとか言い出すんじゃねえだろうな」
「それはない。寝たのは君のベッドだったけど。ああ、コンポとテレビは触ってないから安心して」
人参さえも柔らかくなっている。
「真逆俺のベッドに他の女を連れ込んだりしてねえだろうな」
「……」
「……何黙ってんだよ」
「……中也の想像力に心底呆れ果てて声も出せなかった……」
中也は大きく舌打ちをした。
温かい咖喱は胃に染みてゆく。いつの間にか皿はふたつとも空になっていた。
ふたりとも、咖喱を食べるのが上手だった。米だけ、或いはルゥだけが残らないように、バランスよく器用に食べる。上手いのは太宰の盛り方かもしれなかった。
「風呂」
それだけ言うと中也はすっくと立ち上がった。
「えー、私お酒飲みたい」
「勝手に取って寝室に持っていってろ。俺も飲みてえ。……馳走になったな。美味かった」
「それは重畳」
リビングにひとり残された太宰は、皿を流しに入れてしまうと晩酌の吟味を始めた。
中也と入れ替わりに太宰は風呂へ入った。中也が濡れ髪を拭きながら寝室に入ると、サイドテーブルにはポートワインが置かれていた。港。ポート。中也は顔を顰めながらもタンブラーに注いで一口飲んだ。そしてベッドに腰掛けた。拘りなくワインにタンブラーを選ぶあたりが太宰だった。
中也は太宰の変質を感じていた。ずっとわからない男だったが、それでも何か変わってしまった。彼は時折、まるで太宰が『正しさ』へ向かっているような感覚を覚えていた。かつては時に肩を並べ時に背中を預けていたはずの男が、遠くに行ってしまったような。中也は彼の消えた空白を清々したと表現したが、微かな寂寥は彼にペトリュスを開けさせるという形で表出した。
不意に、中也の脳裏に探偵社員の国木田独歩の顔が浮かんだ。
「……なんか、甘ったりィな、手前」
だから、そう、きっと『だから』、風呂から上がり寝室の扉を開けた太宰に掛けられた言葉はそれだったのだ。甘い咖喱。甘い酒。甘い彼。
太宰の頬を水滴が伝った。髪から垂れた水だった。中也はタンブラーを置いた。太宰は探るような視線を中也に向けた。
「おいで、坊や」
中也は感情の乗らない声でそう言うと、ベッドに深く腰掛けすこし開いた脚の間を示した。
「気持ち悪っ、どうしたの中也……もう酔ってるの……」
「さっき手前がやったことだよ」
太宰はこれが『遊び』の一部であることを理解していた。すべてが既に前戯であったし、或いは既にセックスであった。だから太宰は、苦笑しつつも中也に従い、中也に後ろから抱えられる格好になった。
「相変わらずちいさいなあ」
「五月蝿え」
中也は太宰の髪の毛をタオルであくまでも優しく拭った。太宰はされるがままになっていた。
「……君さあ」
どこか幼い口調で太宰が言った。演出なのか、素が出たのか、中也はいつもわからない。
「私のこと、もう相棒だと思ってなかったんだね」
元相棒。
中也の手が止まった。
「……手前には、あの国木田とかいう男がいるじゃねえか」
「彼は……そう、なるのか……そうか……」
太宰は数度、そうか、そうかと口にした。噛み締めるように。噛み砕くように。飲み下すように。
「……私には、相棒という概念そのものが、君だったよ……」
そう言って太宰は振り返った。散った雫。押し倒された中也。不意のくちづけ。脱がされる服。暴かれる身体。
抱くけど、いい? 太宰の瞳はそう請うていた。中也は黙って目を閉じた。再度重なったくちびるは先刻のキスで濡れていた。なんとなく中也が瞼を開くと、太宰は酩酊したような顔をしていた。それに無性に腹が立って、中也は太宰の頭を髪の毛ごと掴んで引き剥がした。太宰の顔は驚きよりも不満を湛えていた。
「言っとくけどな、俺を置いていったのは手前だし、俺をひとりにしたのも手前なんだよ。大体な、手前がいなくなってから周りの奴らにどれだけ『太宰治の元相棒』扱いされたと思ってんだよ。俺だって――」
そこからはもう滅茶苦茶だった。
中也はわかっていた。自分は太宰を革命できない。それどころか、太宰が汚泥の中に留まることを望んでいる。
太宰はわかっていた。自分が善人の道化になろうとしていることを。それが中也と道を違えるのだということを。
彼らはわかっていた。互いが互いにとって一番ではないことを。けれど、それとはまったく別の次元で、互いのことがどうしようもなく特別なのだと。彼らはそれを、『大嫌い』だと呼んだ。
目が覚めると、幸せの香りがした。
「起きろ太宰、仕事はいいのか?」
「今日はサボり……今日マフィアから逃げたことにするから宜しく……」
「あっそ。咖喱、今ならあったけえから」

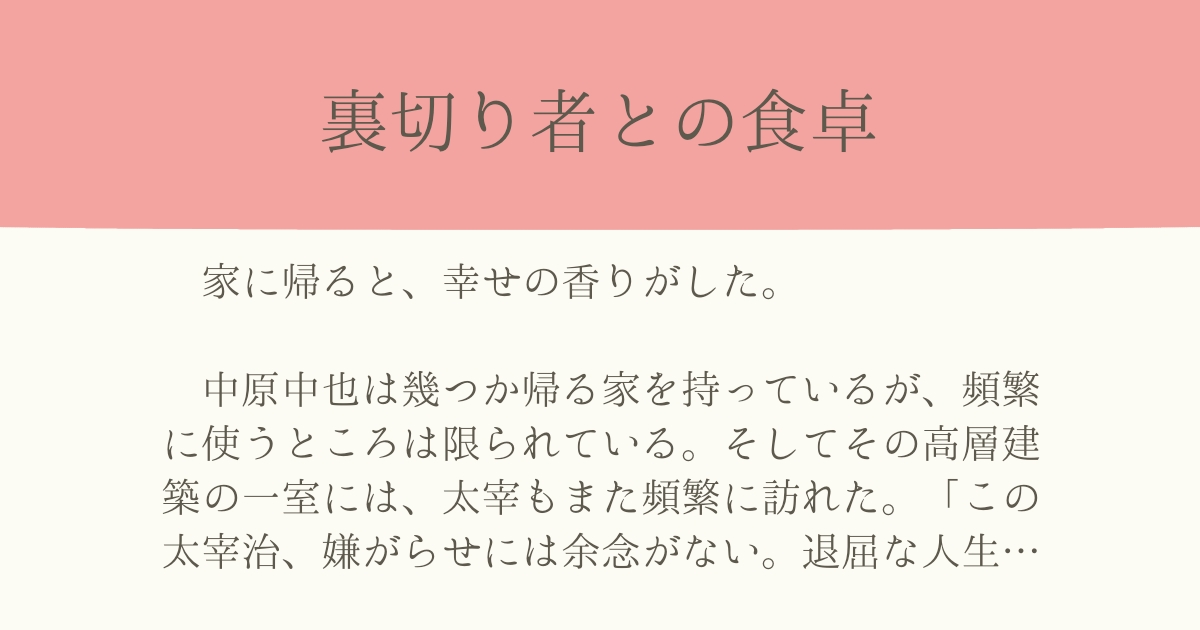
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます