双黒:太宰と中原が穴兄弟の話です
果てなき倦怠の情交だった。微温湯に長く浸かっているような気分だった。中也はきっと、目の前に太宰がいなければ、指の先に皺が寄っていないか目視で確認したことだろう。しかし太宰がいなければ、彼とセックスしていなければ、そもそもこんな気分は味わっていないのだった。
中也の家の、中也の寝台。テレビ画面は海洋生物ドキュメンタリーを映していた。ちいさめの音量は、互いの微かな喘ぎを拾うのを決して邪魔しない。それが却って鬱陶しい。けれど大きかったら大きかったで、鬱陶しいに違いない。そういうものだった。
サイドテーブルにはマグカップが置かれていた。中身は白く弾ける伊太利の葡萄酒。太宰が容器に頓着せず酒を注いだ結果だ。
ふたりはなんとなく繋がったまま、なんとなく戯れていた。当たり前のように晩酌をして、当たり前のように同じ寝台に上がり、当たり前のように掛け布団を床へ放った。あの頃と同じように、無言の調和でもって。
しかし確実にあの頃とは違っていた。あの頃こんなにも緩慢なまぐわいをしたことがあっただろうか。
「ねえ、これ、絶対気持ちいいよね……」
「ああ、絶対……これは……」
絶対の約束は愛でなく快楽になされる。嘗てないスローセックスは嘗てない快楽を予感させた。しかし彼らはその快楽のためにそうしているわけではなく、ひょっとしたら情熱と若さの欠乏のためにそうしていた。
若さを失って手に入れたものはなんだろう、と中也は思った。そこでひとつの錯覚に気づいた。自分は本当に若さを失ったのか? ただ、今目の前にいる男を失っただけなのではなかったか? ――自分が若さだと思っていたものは、実は太宰だったのではないか……?
「……身勝手な男」
中也はぽつりと呟いた。すこし身体を動かすと、シーツの冷たいところに触った。ぐっと手を伸ばしマグを手に取り、葡萄酒をひとくち飲む。太宰はマグの把手を握る中也の手を上から包み、自分の口元に運んだ。中也が次に見た太宰の顔は、口元から透明な液体を零したものだった。
「どうせ君のことだから、青春時代に思いを馳せてたんだろうけどさあ」
太宰はそのまま中也の手をサイドテーブルに導きマグを置かせると、ピッと親指で葡萄酒を拭った。
「エスパーかよ……」
「今の私たちは、あの時代じゃないよ」
「青い春なんざ手前が真顔で抜かせる言葉かよ。真っ黒だったじゃねえか。今の方が余程手前は――」
中也はそこで言葉を止めた。彼とは見ている世界が違う。いや、そんなものはずっと違った。けれど、吸っている空気は同じだった。中也はそう感じていた。同じ空気を吸い、同じ空気を吐く。呼吸の交換。今は違う。
中也は目の前の男が無性に憎らしくなった。勝手に置いていった男。そうは言っても、決してついて行きたかったわけじゃない。そんなのは死んでも御免だ。そして生き方を変えようとする彼を止めたかったわけでもない。どうしようもないことなのだ。だからこれは、中也の我儘なのだ。
中也は何か意趣返しをせずにはいられなかった。太宰を押して身体をひっくり返し、自分が太宰に跨る格好になる。ツンときた快楽をやり過ごし、太宰の耳元に口を寄せ、耳朶をそっと噛む。
「……大庭くん」
甘くやさしく囁いて、身体を起こし太宰の顔を見てみれば、中也の気持ちは幾許か晴れた。
「こりゃ最高の眺めだ……」
「はぁ……何、百億?」
「百億の名画を売ってでも見てえ面だぜ」
「最ッ低……」
「手前だってしょっちゅうやってることだろうがよ」
* * *
話は数日前に遡る。
その日、持ち家のひとつであるアパートに中也が赴くと、部屋の前に女が立っていた。警戒しつつ話し掛けると、女は男を探しているのだという。
「此処は貴方の家なのですか? 私の探している男の人が此処に入ってゆくのを見たのですが」
中也には、この時点で話が見えていた。
「その男は、黒髪の長身で包帯塗れなんじゃありませんか」
女は目を見開いて中也を見た。高いヒールを履いて中也とそう変わらない背丈であるから、実際はかなり低身長であることが窺えた。小柄で細身で大人しい女。そういう第一印象だった。
「それなら俺の……まあ腐れ縁みたいなものですよ」
中也は妖しく笑った。解錠の音がやけに大きく響いた。
「酷い男だからな。あれはやめておいた方がいい。貴方には勿体無いから」
――上がっていけよ。
女は目を逸らしながらも拒まなかった。
* * *
「あの娘はどうだった?」
「悪くはなかったな」
「私は君の方が好いけどね」
「気色悪、ッ」
唐突にそんなことを言った太宰は再び中也を押し倒した。クッと中也のいいところを抉り首筋を柔く噛む。中也は躊躇なく太宰の背に手を回す。太宰は達しそうになり背を丸めようとする中也の肩をシーツに縫いつけ、恍惚と笑った。
「反って御覧よ。女の子みたいに」
中也は歯を食いしばり意図的に太宰の屹立を締め付けた。波打つように、搾り取るように、おねだりするように。
「ハ、あ……ちょっ、中也……」
「っざけんなよ、クソ太宰……ア」
先刻までの揺籃のような快楽とは違う、とめどなく溢れる洪水のようなそれに、彼らは目も眩む心地だった。快楽の質も量も違う。燻っていた甘い痺れが一気に弾ける。
「あッア、も、だめ、すご……だざッ、い……」
「は……中也、ねえ……」
ふたりは夢中でくちづけて、互いの吐いた空気を吸った。
* * *
女は太宰に遊ばれたのだ。手酷く振られたのか他の女と遊んでいるところを見たのか、とにかく何かしらの事情により痴情が縺れた。いつものことだ。そして女は太宰を尾行するに至り、太宰はそれを撒くためにこの家を利用したのだろう。
「ア……あの、貴方の、御名前……」
女の嬌声を聞きながら、これは太宰も聞いたものなのだろうかと、中也はぼんやり考えた。彼は女の揺らめく腰を突き上げながら言った。
「俺が本物の大庭だよ」
「そ、んな……じゃ、彼の名前は……」
「知りたいか? あの男は……」
* * *
「中原さん!」
太宰は聞き覚えのある名を耳に捉えたが、それが真逆自分を呼んだものであるとは露程も思わなかった。だから背後の女が太宰の腕を掴み目と目を合わせて再び「中原」と呼んでから、はじめてそれを理解した。
「中原さん、説明してよ! この間一緒に歩いていた女の人は……」
――成程、これも含めて百億か……。
太宰は密かに納得しながら、もう一度抱いておしまいにしようかな、などと中也に抱かれた女について思案した。

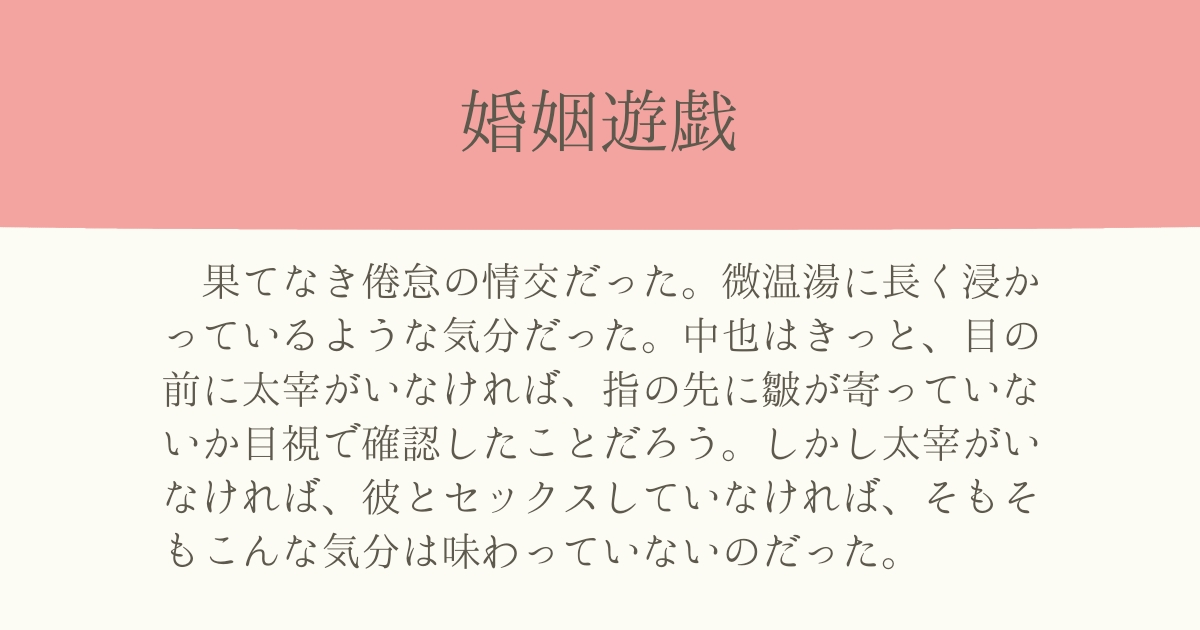
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます