赤安:ベッドの上で赤井が少年時代を回顧する話です
「全身の細胞が生まれ変わる感覚を知ってますか?」
ベッドの上のすはだかの男はそう言った。褐色の肌膚の指先が、精液の溜まった避妊具の口を縛って床に放った。彼の動きに合わせて揺れるくすんだ金の髪の毛は、さながらきらめく星だった。長くて深いキスをして、一呼吸の後だった。
「こんなの赤井がはじめてなんです。あなたとのキスで、僕は生まれ変わる」
降谷は赤井の顔を見つめて告げた。彼のブルーは無垢に似ている。堪らなくなって、赤井はもう一度キスを仕掛けた。彼の唾液は油のようだった。疲弊しきって軋む肉体になめらかな動作をもたらす潤滑油。
「知っている」
キスの合間に赤井は言った。もう一度答える。
「知っているよ、零」
赤井は死を受け容れるようにまぶたをおろした。降谷は彼の頭を抱えて撫でた。
果たして赤井はほんとうに、その感覚を知っていた。
* * *
赤井秀一がまだ少年で、イギリスに住んでいた頃のことだった。彼の住むアパルトマンの大家・チャンドラー夫妻は、その建物のみならず広大な土地を所有していて、そして彼の父親と縁があった。深い新緑の森一帯が大家の庭で、赤井はよくそこに赴いていた。夫妻に子供はなく、赤井はよくかわいがられていた。
ミスター・チャンドラーにはいくつかの趣味があった。紅茶をふたくち飲んだあとにジャムをひとくち舐めること、毎週土曜日の朝にハムと卵の朝食を作り妻に振る舞うこと、そしてなにより、若い頃からずっと続けている趣味は、射撃だった。
「深く呼吸をするんだ」
彼はしばしば赤井に射撃を教えた。……といっても、教えることはなにもなかった。赤井は銃に愛されていた。チャンドラーのしたことは、笑う赤子に「うれしいね」と言い、泣く赤子に「痛かったね」と言うのと同じことだった。赤井の才能を理論で説明し、赤井がいつか師となったときに困ることのないようにしたのだ。彼は銃が赤井の未来を左右すると確信していた。
「呼吸は肺では終わらない。全身に酸素を行き渡らせろ。全身の細胞を生まれ変わらせるんだ」
赤井少年はなにも言わない。チャンドラーの声が聴こえているかも怪しい。彼はなにも言われずともすべてをわかっていた。彼はそういう星の元に生まれていた。
「引き金を引くのはきみの意志ではない。きみの指先に天使が宿りひとりでに動くのを待て」
赤井にとってはもしかすると、チャンドラーの声は雑音かもしれなかった。それでも彼は語り続けた。なぜなら彼は、少年のことを息子のように愛していたからだ。
チャンドラーは赤井の才能の危うさを理解していた。神に愛された少年が人の世界で生きていくためには、その能力を支配できなくてはならない。論理的理解はその支配の一助となる。
的は静物ではなかった。生きた獲物を狩ることをハンティングといい、特に鹿を狩ることをストーキングという。彼はストーキングが卓越して上手だった。立派な牡鹿がそこにいた。四百ヤード先だった。
スナイパーの殺す命は唐突に途切れるわけではないのだと、赤井を見るチャンドラーはしばしば思った。あの牡鹿は、突如やってきた見知らぬスナイパーに命を奪われるのではない。彼の放つ運命の弾丸を待ち望みながら、これまでわたしの森の中で暮らしてきたのだ。そして来るべき時がやって来たから、彼の前に姿を現したのだ――そう思うのだった。
彼の指先に天使が宿った。牡鹿は運命に愛された。
「素晴らしい」
チャンドラーは短い言葉で赤井を讃えた。立ち上がった赤井は、土埃も払わずに牡鹿の元へ歩み寄った。見事に撃ち抜かれた牡鹿は赤井に温度で生命を誇示した。
「牝の方が美味いんだがな」
チャンドラーがぼやいた。
「でも、牡の方がいい」
赤井は横たわる牡鹿の角を撫でながら迷いなく答えた。
牡鹿は見事に裁かれ、余すところなく使われる。チャンドラーは赤井に生命への感謝を教えることも忘れなかった。刃を研ぐところからひとつひとつ丁寧に教えた。
チャンドラー家は、鹿を裁く際に頭を上に吊るす。後ろ脚を吊るす者も多くいるが、彼は彼の父親からそう教わり、赤井にもそう教えた。吊られた牡鹿の首に刃を入れ、刃を下ろして背中を開き、皮を剥ぐ。肉を削ぎ、切り分け、保存する。肉や皮に血をつけないため、刃はこまめに洗う。皮はなめしてミス・チャンドラーの友人に売る。
角はチャンドラー家の倉庫の壁に掛けられる。そこにはチャンドラー家の息子たちが狩ってきた鹿の角が並んでいる。赤井にはそれが許されていた。チャンドラーの愛だった。
* * *
赤井の脳裏を鮮やかな少年時代が過ぎった。赤井は無性にもう一度降谷を抱きたかった。それは性欲とは似て非なる欲望に思えたが、ともかく勃起を伴った。
牡鹿を殺すときの感覚を、キスによって降谷が味わっている。それが自分にとって快いことだと気づいた赤井は、絶望とも歓喜ともつかぬ衝撃を得た。赤井は降谷にキスで殺されているのだ。降谷の舌、指、髪、瞳……赤井になにかを訴える彼のすべてが弾丸だった。
愛している、と赤井は思った。それ以外、どんな言葉があるだろう。
赤井はたまらず降谷をうつぶせにして、降谷のうなじに噛み付いた。そのままくちびると舌を背骨に沿って這わせた。降谷の肌膚は剥がれない。しかしそうすることで、彼は幾許か素直になって、濡れた声で彼を呼ぶのだ。
ふたりの細胞は、こうして生まれ変わる。

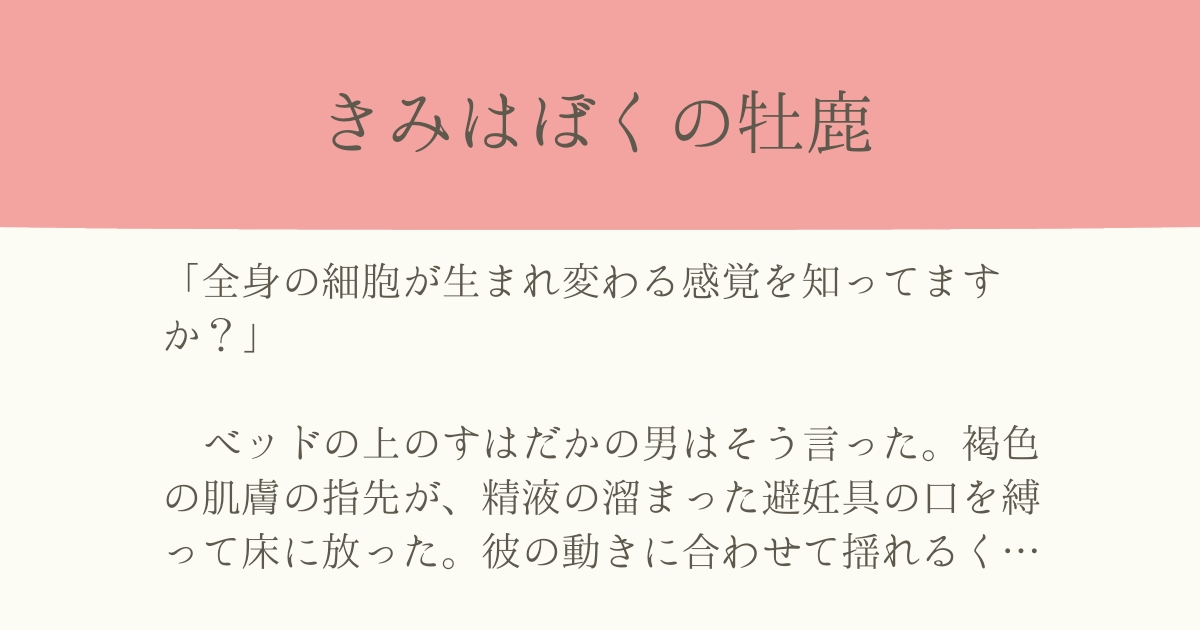
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます