赤安:沖矢昴の正体を暴く降谷零の話です
・オメガバース(赤井α×降谷Ω)
ある朝、目を覚ました途端、懐かしい、と思った。いや、あるいは懐かしいにおいに鼻をくすぐられるように目が覚めたのかもしれない。
身体を起こす。枕元の愛銃を確認。部屋の四方に視線を走らせ、異変がないか確認する。ひとまずの安心を得てから、ベッドを降りて洗面所に向かう。
朝は常に寂寥を連れている。なぜならここは他人の家だから。ここ数年、特に日本にやって来てから、朝が安堵を連れてきたことはない。しかしワシントンの自宅に帰ったところで、何か安らかなものが得られることはないだろう。マイ・スイート・オールド・ホームは、とうの昔に喪われたまぼろしだ。
我が物顔で工藤邸の廊下を歩く。ここには自分しかいない。だから今は自分が主だ。
郷愁は本能である。赤井はそう思っていた。具体的な懐かしい場所を知らなくても、ただ漠然と懐かしいと感じることはできる。ノスタルジー。ここではないどこかを求める感情。それが時折、今にも駆け出しそうなほど強くなる瞬間がある。もちろんだからといって本当に駆け出したりはしないが、それでも、ふくらはぎの筋肉がひくりと震えるような焦燥を覚える。ただ漠然と、目指す場所が英国や米国ではないことだけは理解していた。
今朝の郷愁はこれまで感じたことのないほど近くにあった。手を伸ばせば、足を踏み出せばもうすぐそこなのではないか。そんな期待があった。けれど赤井には理性があり、加えて彼は常人のそれを遥かに超える危険の中で暮らしていた。だからまずは洗面所で顔を洗い、歯を磨き、化粧をし、チョーカーを着け――沖矢昴となった。
チョーカーを身に着けるとき、赤井は言いようのない屈辱を感じる。世間一般に流通しているチョーカーの多くは、アナザー・セクシュアリティにオメガを持つ者が項を保護する目的で身につけるものだ。若者たちの間ではファッションとしてのチョーカーが浸透しつつあるようだが、多くの大人たちにとって、チョーカーとはオメガのものであり、首輪を連想するものだった。赤井もまた例外ではなく、服で隠れることになるとはいえ、チョーカーには抵抗があった。当然そんなことに文句を言っていられる場合ではないし、むしろ阿笠博士には多大な感謝を寄せているが、それとこれとは別だ。自分のセクシュアリティのイメージにそぐわない格好を強いられているのだ。赤井にとっては、女装をして生活せざるを得ないようなものだった。
アナザー・セクシュアリティ。第二次性徴期、精通後もしくは初潮後に判明する第二の性。アルファ、ベータ、オメガ。
希少なアルファとオメガについて、世界各地の神話は様々な形でその奇妙な性を説明している。しかし多くの宗教の行き着く先は二択だ。祀るか、呪うか。
しかし現代の技術はオメガのヒートをコントロールすることを可能にしている。ヒートとは糖尿病のようなものだと言われて久しい。治るということはないが、適切な投薬を続ければ生きてゆけるものだと。オメガはヒート期間であっても平素と変わらぬように外出することができるし、先進国の教育はアナザー・セクシュアリティを他者に尋ねたり教えたりすることの危険性を重く説いている。人々はそもそも他人がアルファかベータかはたまたオメガかなんて知る由もないのだ。
運命の番やオメガの巣作りなどという都市伝説も存在するが、誰もがそれに縋る滑稽さを知っている。教科書は極めて稀に発見されるそれらの事例を解説するが、必ず最後に「運命だけが幸福ではない」と述べる。そういう世界だった。
沖矢昴となった赤井は、胸をつく郷愁に惹かれるままに歩いた。ダイニング、廊下、やがて玄関に辿り着く。躊躇なく扉を開くと、そこには誰も、何もなかった。しかし濃厚な人の気配が立ち込めている。裏社会に生きる者の隠しきれないオーラとも、気配を消す能力に乏しい一般人の気配とも異なる、懐かしいにおい。外に出て、開いた扉による死角部分を確認する。
果たしてそこにいたのは、降谷零だった。
「おはようございます。沖矢昴さん。よければ僕とお喋りしてくれませんか?」
お喋りなんかより、もっと他に彼としてみたいことがあった。確かに彼はずっとうつくしく赤井を惹きつけて止まなかった。しかしこんなにも直接……性欲を掻き立てたことがあっただろうか? 呼吸が荒くなり、心拍数も上昇している。コントロールの術を知っているはずなのに役に立たない。身体の中心が今にも充血しようとしていた。つとめてゆっくり呼吸する。テイク・イット・イージー……。
「おはようございます。随分早いですね。お茶ぐらいしか出せませんが、それでよければ、どうぞ」
赤井には降谷の考えていることがまるでわからなかった。何か途轍もない思惑を抱えていることだけを察しながら、それでも部屋に招き入れた。彼を追い返すという選択肢は、最早存在していなかった。一体なぜ。こんなに突然。
彼が俺の故郷だ――
* * *
降谷はストレートで出されたダージリンにミルクを入れて口を付けた。飲み込んだのかはわからない。赤井は黙ってそれを眺めていた。彼がカップを置く。ソーサーとぶつかるかすかな音。
「僕は昨夜、横浜港にいました。そしてここに至るまでの記憶がありません。しかし僕は確信を持ってここに来ました。……これが何を意味するかわかりますか?」
「……何かのミステリーですか? すみません、それだけではわかりかねます」
降谷は至極楽しそうに赤井を見ていた。にこにこと笑う口許はともすれば幼ささえ感じさせるのに、それすら赤井に焦げ付くような葛藤を与えていた。
わかるための情報が不足していることだけがわかっていた。彼は既に手札を――ひょっとすると切り札を――見せているのではないか? そんな予感があるのに、その中身がわからずに苛立ちを覚えた。喉が乾いていた。紅茶を口に含んだが、味はわからなかった。
「オメガの巣作りはご存知ですか?」
「ええ。ヒート直前およびヒート開始直後のオメガが、番になりたいと願うアルファの衣類などを収集することですね。オメガにとってはまったく無意識の行動であり、収集中のことは記憶にない場合が多い」
「その通り。流石、お詳しいですね」
流石。その言葉には明確な含みがあった。すなわち「あなたはベータではありませんよね?」だ。赤井にしてみればこんなことは教科書にも載っている常識の範囲内だったが、降谷はどうやら「こんなにも詳しく記憶しているということは、あなたは〈当事者〉なのでしょう?」と言いたいらしかった。ベータの大多数はマイノリティの特性に関心が薄い。時代と共にアルファやオメガの間ですら都市伝説のように扱われるようになっている。しかしだからこそ、詳細な知識は関心の裏付けとして扱われた。実際には、赤井はこれらをアカデミーで徹底的に学んでいた。FBIで扱う犯罪事例には、しばしばアナザー・セクシュアリティが関係するからだ。
降谷はどうやらなんらかの性的な意図を持っているらしかった。まさか自分とのセックスを望んでいるのだろうか。降谷は沖矢の正体を赤井だと確信しているはずだ。セックスを人質にして沖矢の仮面を剥がせるなど、果たして降谷が考えるだろうか。まだ組織に潜入していた頃、バーボンのハニートラップの噂は耳にしていた。しかし彼が赤井を相手にそれを仕掛けるとは、赤井には考え難かった。そう思うのに、赤井は段々と身体を巡る情欲を無視できなくなってきていた。深く静かに息を吐き、脚を組み替えた。
「沖矢さん、僕はオメガです。そして次回のヒート予定日は明日。昨日から今日にかけて、僕はヒート抑制剤を飲んでいません」
赤井は言葉を失った。一瞬、彼がすはだかの状態に見えた。彼の肌など見たこともないのに。しかし赤井にとって、目の前の男は既にすはだかも同然だった。降谷は明確に赤井をアルファとして扱い、自らがオメガであると晒した。これは間違いなくセックスに至る手順だと赤井には思えた。今にもソファから腰を浮かせて彼の元へ向かいそうで、この場に留まることが困難だった。理性のすべてを本能が喰らい尽くそうとしている。抑制剤を飲んでいないオメガと顔を合わせたことなら、潜入捜査の試験として一度、潜入中にも数度ある。そのどれもを赤井は平然と無視してきた。なのに、今は。
「僕は帰巣本能でここまでやってきました」
彼のことが好きだ。彼と番になりたい。赤井の中のその感情は膨れ上がって理性を圧迫し続けていた。俺が彼の巣! それは何にも勝るよろこびだった。赤井はもう何も我慢する必要がないのだと悟った。そうして立ち上がって彼にキスをしようとしたそのとき、赤井のいとしいオメガは胸元からさわやかな朝に似つかわしくない拳銃を取り出した。
「僕が望む運命は沖矢昴ではありません。正体を現せ、赤井秀一。俺は貴様以外の運命を認めない。貴様が運命でないのなら貴様を殺す。……僕の運命は赤井だけだ」
赤井は不覚にも泣きそうだった。こんなにもいとおしい運命が自分を求めているだなんて。熱く滾るよろこびが全身を満たしているのがわかった。俺も君の運命になりたい。君から逃げる不誠実な故郷ですまない。左手でマスクを外し、まぶたを持ち上げる。眼前には、生まれる前から焦がれていた魂の故郷がいた。

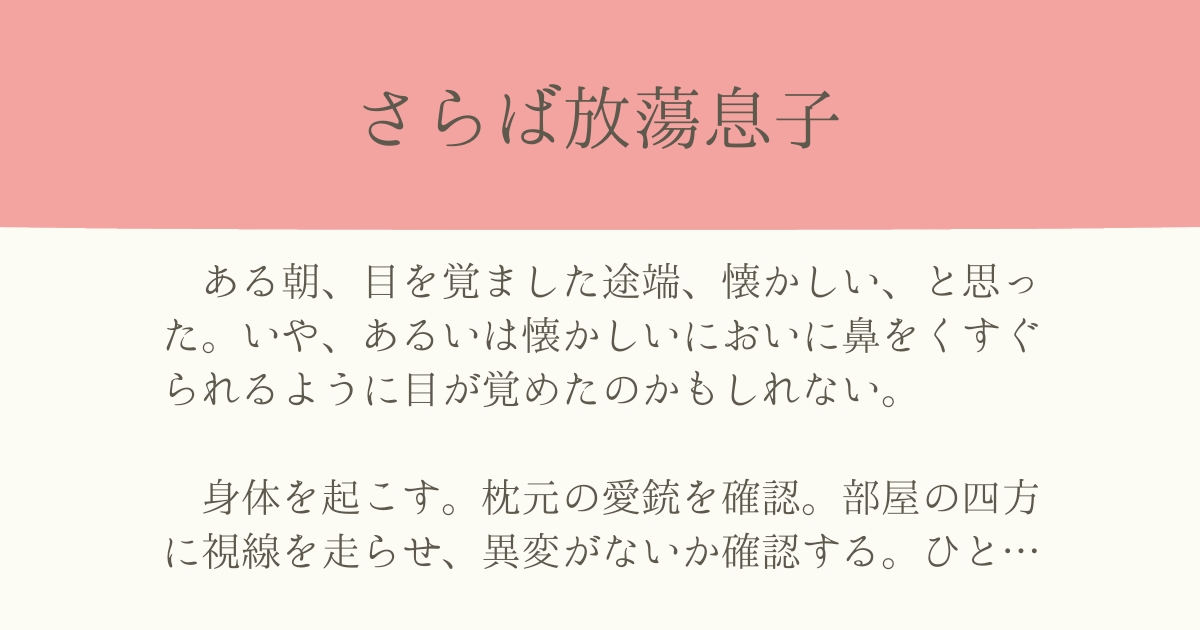
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます