エイプリルフールの404の話です
「しまぁ、なんか面白い嘘ついてよ」
「嘘をつけと言われてつく嘘はその時点で嘘として成立しないだろ」
四月一日。暦の上では四月最初の日でしかないが、世間はエイプリルフールで盛り上がっているらしい。
いつ、どこを起源としてここまで定着するに至ったのか、志摩は知らなかったし、然程の興味もなかった。年度はじめでどこも忙しいだろうに、各企業の広報担当はさぞ骨が折れるだろう。そのくらいの思い入れしかないし、警察官の仕事は変わらない。今日も今日とて密行だ。
だがまさか相棒から嘘を乞われるとは思っていなかった。付き合うのもばかばかしいが、それでもすこし考える。そうして思い当たったのは、昨夜ふと買った鞄の中身だった。
「あー、後部座席の鞄、俺の。その中」
「何? エイプリルフールってそういうのだっけ?」
そう言いながらも、伊吹は身体を捻って志摩の鞄の中をごそごそと弄った。遠慮のない手つき。
「……これ?」
訝しみながら伊吹が取り出したのは、コンビニやスーパーで流通している、ありふれたチョコレートだった。
「それ。冬季限定で、最近もう見ないって言ってたろ。……だから、過去に行って買ってきた」
「……マジ?」
嘘だ。伊吹のそれは相槌の一種であって、まさか本気にしているわけではないだろう。そう思って、志摩は続ける。
「マジ。お気に入りなんだろ」
「えっ、え、何これ、なんで? どこで買ったの」
「だから、過去に行って買ってきた。やるよ、それ」
「うわー、え? マジ? え?」
ほんとうのところを言えば、それは志摩の自宅の近所のコンビニで売れ残っていた最後のひとつだった。世界がどんどん春めいてゆくなか、コンビニの棚でぽつんと置き去りにされていた冬の名残り。それが目にとまった志摩は、伊吹のことを思い出した。そういえば、いつか彼がこれを。
「ありがとう……うわサンキュー志摩、俺ほんとにうれしい」
「はいはい、どういたしまして」
「……だってさあ、志摩はわざわざ過去に行って、俺が前ぽろっと好きだって言ったチョコ買ってきてくれたんでしょ? すっげえうれしい。ありがとう」
あんまりうれしそうに伊吹が言うので、志摩はすこしばかり焦った。過去に行って買ったなんて嘘だ。わかってるくせにそんなによろこぶなよ。
「だから嘘だよ。ほんとはたまたま――」
「あ待って待って、ストップストップ。種明かしとかいいから。要は、志摩が俺のこと思い出して、俺のためにチョコ買ってくれた。バレンタインでもないのに、てかバレンタイン何もなかったのに。そういうことでしょ?」
「……そうかもな」
助手席ではしゃぐ伊吹の気配を感じながら、志摩はやや気まずかった。嘘をつけと言われたからついただけで、こんなに無邪気によろこばれるとは思っていなかった。しかも彼は、嘘の中のほんとうの部分を捕まえている。伊吹があんなことを言わなければ、ただ目の前で食べて見せて、残りを横流しするように渡して、軽く礼を言われる程度だったはずなのに。
微妙な心地で車を流していると、道路の片隅に溜まった桜の花弁が視界に入った。四月一日とは本来ただそれだけの日だ。春の陽気が街を訪ね、多くのひとがあたらしい生活に飛び込む、ただそれだけの日。手の中の冬の残滓を見つめて笑う伊吹が、志摩にはまぶしかった。
「過去に戻るってどうやったの」
どうやらこの話はまだ続くらしい。志摩は当然そんな設定を詰めてはいなかったので、運転の片手間に思案した。いつかきょうだいに語り聞かせた寝物語のようだった。自分自身も眠い中、考えるより先に紡ぐとりとめのない話。ピリオドを打たれることはなく、眠りの扉が開けばその時点で霧散する、矛盾だらけのまぼろし。
「うちの近所の公園……今ちょうど桜が見頃の公園に、もう動かない遊具があって」
ほんとう。ここ二十年ほど、事故や老朽化を背景に、動く遊具は減少し続けている。そして現に、志摩の自宅からすこし歩いたところには、そういう侘しい公園があった。
「あの危ないからーってコンクリとかで下のほう固めてるやつ?」
「そう。なんかぐるぐる回って遊ぶの、あるだろ。桜の花弁を左手で三枚握って、過去に戻ってやりたいことを三回唱える」
嘘。時は戻らず、過去には行けない。もしも過去に戻れるのなら、志摩も伊吹もほかにもっとやりたいことがある。このやりとりが嘘であることの何よりの証左はそこにあった。ほんとうに過去に行けるなら、次の冬にまた販売されるであろうチョコレートを買うより、もう二度と取り戻せないものを追うだろう。
「じゃあ春しか戻れないんだ」
「春の夜だけ。唱えてその遊具に乗ったら、それが三周回って、そしたら過去に戻ってる。……ただし、三分間だけ」
たとえ嘘でも、語っているうちに妙に真実めいた質感を帯びることはある。あるいは、真実だったらいいのにという願望。だから、志摩は意図してそれを砕いた。
「え、三分前にしか行けないの」
「違う。過去に居られるのが三分だけ。だからその三分で、そこから一番近いコンビニに行って、それ買ってきた。終わり」
「……三分だけかあ」
そんな特撮があったな、と口にしてから志摩は思った。それから嘘の三八なんて言葉。嘘をつくときに咄嗟に使う数字には三と八が多いという話だが、果たしてほんとうだろうか。いつかの先輩刑事がそんなことを言っていたが、自分が後輩に聞かせるかというと信憑性の微妙な話だ。キリのいい数字を避けて三や八に偏る心理は理解できるが、三と八が出てきたら疑えとまでは言えない。……香坂にも、そんな話はしなかった。
「……昼時だな」
「お、そこのコンビニ入る?」
志摩は返事の代わりにウインカーを出した。空腹はまだ耐え難いほどではなかったが、そろそろこの嘘を終わりにしたかった。そうでなくても、密行中は入電によって食いっぱぐれることがあるので、食事をあまり先送りにしないようにしている。すこし気持ちが多いだけで、いつもどおりだった。駐車場に車を停め、後部座席の鞄を取る。
「そろそろ運転代わる?」
「頼む。なんか買ってくるけど」
「米の気分だな~。おにぎりの一番楽しそうなやつ買ってきて」
「はいはい」
「う~ん、二回言ったけど今のはちょっと心がこもってた。何考えてた?」
「お前それたまに言うけどさあ、そういうとき、だいたい突飛な新商品より結局ツナマヨのほうがうれしそうにしてる」
おにぎりの中で定番とされているものは、記憶にある限り志摩がこどもの頃から変わっていなかった。ツナマヨも、物心つく頃には定番の中のひとつだったように思う。それなのに、ツナマヨは今でもどこかあたらしい。コンビニで販売されているおにぎりのラインナップの中で、定着するに至った新商品はツナマヨくらいのものらしい。
「……そうかも。楽しいおにぎりってツナマヨのことだったのか……」
「お前の世界ではな。俺にはよくわからん」
「でも気づいてくれたのは志摩じゃん」
「ただの傾向と対策。行ってくる」
「行ってらっしゃーい」
平日午前、住宅街のコンビニは閑散としていた。レジには四十代前後らしき女性がひとり。都心部のコンビニには外国人留学生のアルバイトが多いが、そこからすこし離れるとパートタイム労働らしき主婦をよく目にする。
志摩はカゴを手に取り、自分と伊吹のぶんのおにぎりを適当に入れた。それからペットボトルのお茶をふたつ。そのままレジに向かおうとして、スイーツの商品棚の前で、ふと足を止めた。
――ご要望を受けて復活!
それは、数年前には店頭に並んでいたが、久しく見かけないものだった。志摩の脳裏で何かが光る。
――俺これ好きなんですよ。甘いものの店って、最近はもう行く時間もないですけど、ちょっと入りにくいじゃないですか。コンビニでこういうのが買えると、いい時代だなって思うんですよね。
どうして今まで忘れて、思い出しもしなかったのだろう。かつて香坂の住むアパートの屋上に行ったとき、そこには彼の好きだったコンビニスイーツがあった。パティスリーなんかどこも開いていない真夜中に、コンビニで買った甘味。あのとき志摩は、スイーツには口をつけず、ただ酒を飲んでいた。
そんな日がたしかにあったのに、それが店頭から消えたことに志摩は気づいてもいなかった。自分は飲めないくせして、志摩の好きだった酒のことを彼はちゃんと覚えていたのに。
それを手に取ろうか悩んで、やめた。伊吹の隣で食べるのは何かが違った。そもそも車中で食べるには向かない形状だ。……けれど、それがまた流通して、記憶がひとつ蘇ったのは、たぶん悪くないことだった。
「おかえり〜」
「飲み物お茶にしたけど」
「も〜志摩ちゃんただいまは? おかえりにはただいまでしょ」
「家じゃないだろ」
「陣馬さんは機捜車が我が家っつってたじゃん」
「……ただいま」
ふふ、お茶サンキュー。伊吹はにんまり笑って、手にしていたチョコレートを置いた。ずっと持ってたのかよ。こどもか。
「食わないの?」
「夏までとっとく。夏に冷蔵庫から取り出して、あ〜春に志摩が冬に行って買ってくれたチョコだな〜って思う」
「お前はリスか」
「あ、それ前アニマルチャンネルで観た。リスはいろんなとこに餌を隠して、そのまま忘れることもある。……いや俺は忘れないよ?」
「優秀だな。ついでに報告書と始末書の書き方も忘れないでくれ」
伊吹はきっとほんとうにチョコレートのことを忘れないだろう。ピートのにおいに囚われて、相棒のささやかな好物をすっかり忘れ去っていた自分とは違う。
「リスが隠したまま忘れちゃった木の実は、春になると芽を出して、森が豊かになるんだって」
「へえー……」
「お、知らなかった?」
「はじめて聞いた。伊達にアニマルチャンネル観てないな」
窓を開けてマスクを外したので、あとはふたりとも沈黙した。
おにぎりのラベルを剥がす。ツナマヨ。あんな会話があったのでなんとなく買ってしまったが、志摩がとりたてて楽しさを感じることはなかった。ただ、伊吹はこれが楽しいらしいとは、思った。そうしてぼんやりと、リスの忘却で保たれる森に思いを馳せた。
勤務を終えた志摩は、帰路にあるコンビニに立ち寄っていた。スイーツの棚。ご要望を受けて復活。それをひとつ手に取り、会計を済ませる。レジ袋は有料なので、断って鞄に直接入れた。やがて自宅に着き、玄関を解錠。靴を脱ぎ、マスクを外す。手洗いうがい。
そうして腰を落ち着け、包装を破いた。
次の当番勤務で見かけたら、また買って食べようかと、志摩は思った。復活してうれしいという顔で、伊吹の隣で。そしてこれから、楽しい気分をふと欲したら、ツナマヨのおにぎりを買ってしまうかもしれないとも、思った。

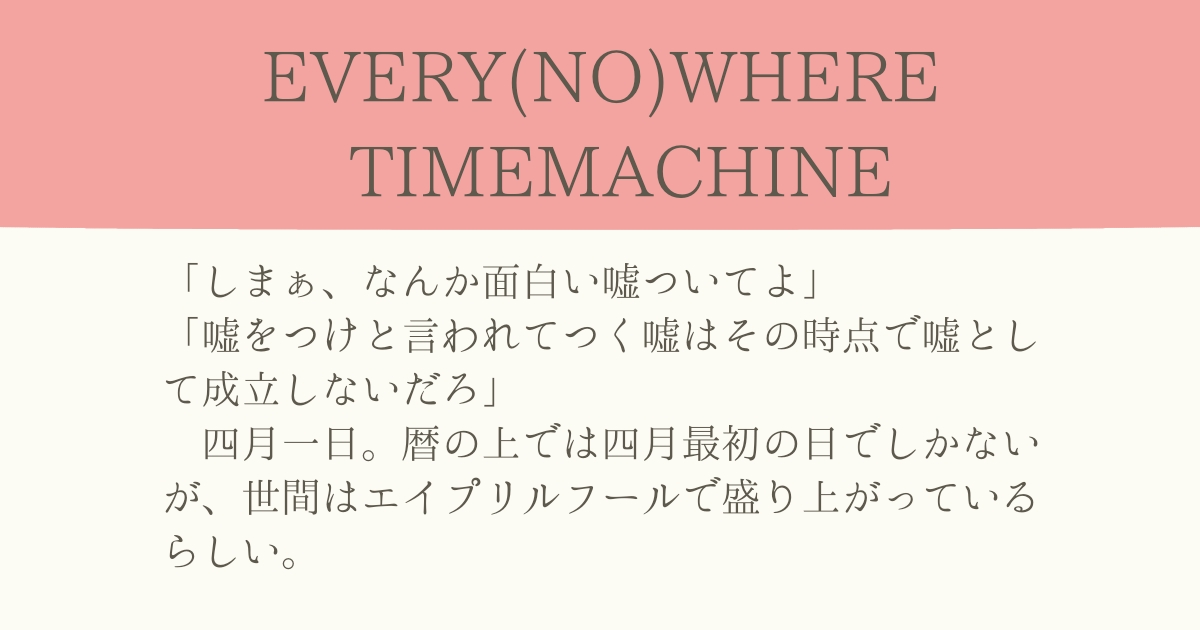
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます