最終話後、志摩が伊吹に電話をかける話です
その電話に大した意味はなかった。
志摩一未が帰宅して鞄の中身をあらためると、伊吹藍のサングラスが入っていた。今朝方、走り出そうとする伊吹に預けられたまま、返しそびれて持って帰ってきてしまったらしい。
もう寝ているかもしれないと思いつつも、もし探していたとしたら申し訳ない。すこし迷ってスマートフォンを手に取り、志摩は電話をかけた。
「めずらしーじゃん。どしたの」
三コール目で応えた伊吹の声から、志摩はかすかな緊張を読み取った。錯覚のようにも思えたし、心当たりだってない。先程まで寝ていた様子がないのはほっとした。引っ掛かりを覚えつつ、なんでもない用件なのだから、なんでもないように話す。
「お前のサングラス、俺がそのまま持って帰ってた。探してたら悪いと思って電話しただけ。悪かったな」
「あ! いや俺もすっかり忘れてた。わざわざサンキューな〜」
「それだけ。今度返す。じゃあな」
「じゃね〜志摩ちゃんおやすみ〜」
なんとなく習慣で伊吹が切るのを待っていたが、一向にその気配はなかった。お互いが相手を待つタイプだったとしても、一定の沈黙が続けばどちらかが電話を切るものだろう。実際、志摩の指先は画面をタップしようとしていたが、ふと耳が捉えた呼気が気になって、やめた。
意志だ。伊吹は、意志に基づいて、志摩が電話を切るのを待っている。なぜ?
――まあお互いさ、自由にやろうぜ。
そう言って伊吹が終わらせた電話を、ふと思い出した。その先に待ち受けていた最悪も。
そういえば、伊吹に電話をかけるのはあれ以来だった。志摩が相棒からの電話には必ず出るように、伊吹にもそういうものがあるのかもしれない。推測でしかないし、そうだとしても伊吹が自覚しているのかわからない。
志摩はもう一言、何か伝えてから電話を切りたいと思った。ふと頭に浮かんだ言葉が「いい夢見ろよ」で、なんだか笑ってしまった。
「何笑ってんだよ」
「別に。さっさと寝ろよ。……伊吹、……」
息を吸い込む。自分の喉がどう震えて、舌がどう動くのか、半信半疑だった。

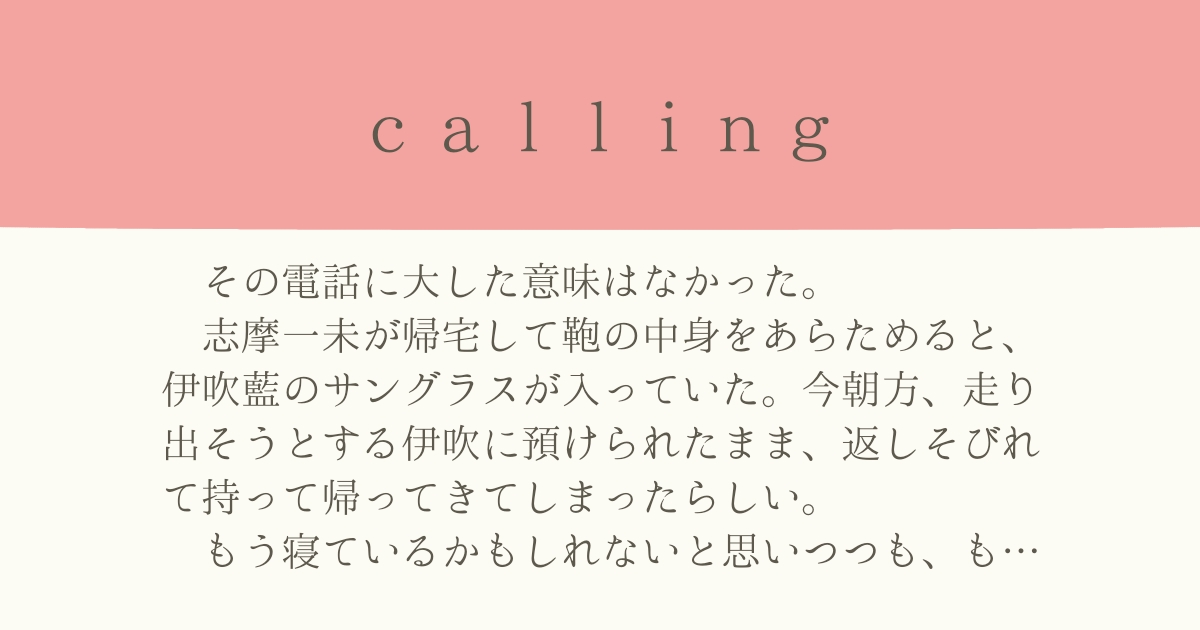
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます