福沢と乱歩:探偵双人時代のおしゃべりの話です
「社長が超推理を使えたらいいのにな」
ある日ラムネを傾けながら、乱歩は「あーあ」と心底残念そうに言った。福沢は半ば慣れ親しんだ諦観に襲われながら、そうだろうと思った。
乱歩と同じ世界を見てくれる人間は、きっといない。誰しも他人とまったく同じ世界が見えることなどないが、乱歩はとりわけ他者が遠い。福沢とて違いない。たとえ共に暮らしたことがあっても、同じ社で働いても、それは変わらない。
その種の諦観に、福沢はもう慣れていた。あるいはその覚悟はとうの昔に決めていたと言ってもいい。福沢は選んで孤独だったが、このこどもを迎えると決めたとき、彼の孤独を想った。自分は彼と共にいることを再び選んだ。しかしだからといって、乱歩の孤独は消えないのだ。
それは半分、杞憂に終わった。乱歩は人間を愛し、福沢を愛した。名探偵というアイデンティティ、名探偵という世界との関わり方を見つけた乱歩は無敵だった。時折諌めなければならないほどに。
半分はわかっていた現実だった。結局、乱歩の才能とは無関係に、人間は常に孤独だ。しかし乱歩はその才能ゆえに、他者と通じあう錯覚さえ得られない。その錯覚こそが人生のモルヒネだというのに。
「社長が超推理を使えたら、きっと眼鏡を掛けて僕を見てもらうよ。そうすれば、僕の胸の裡まで見える。なんだって見ていいよ。僕がどんなにか社長を好きか、社長は何もかも見たっていいのに」
そうしたら、もっと僕を褒める気が湧くんじゃない? ――カランと、ラムネの中のビー玉が音を立てた。
「……秘密を作らねばな」
長考の末、福沢はそう言った。
「お前がいつか私にも知られたくないような秘密を作れたら、そのときは」
普段なら、褒めてやる、と言うところだ。だが、福沢は言葉を切った。
「並んで酒でも飲むか」
違う世界を見ながら、ぬるい酩酊の中で。乱歩はつまらなそうな顔をしていた。

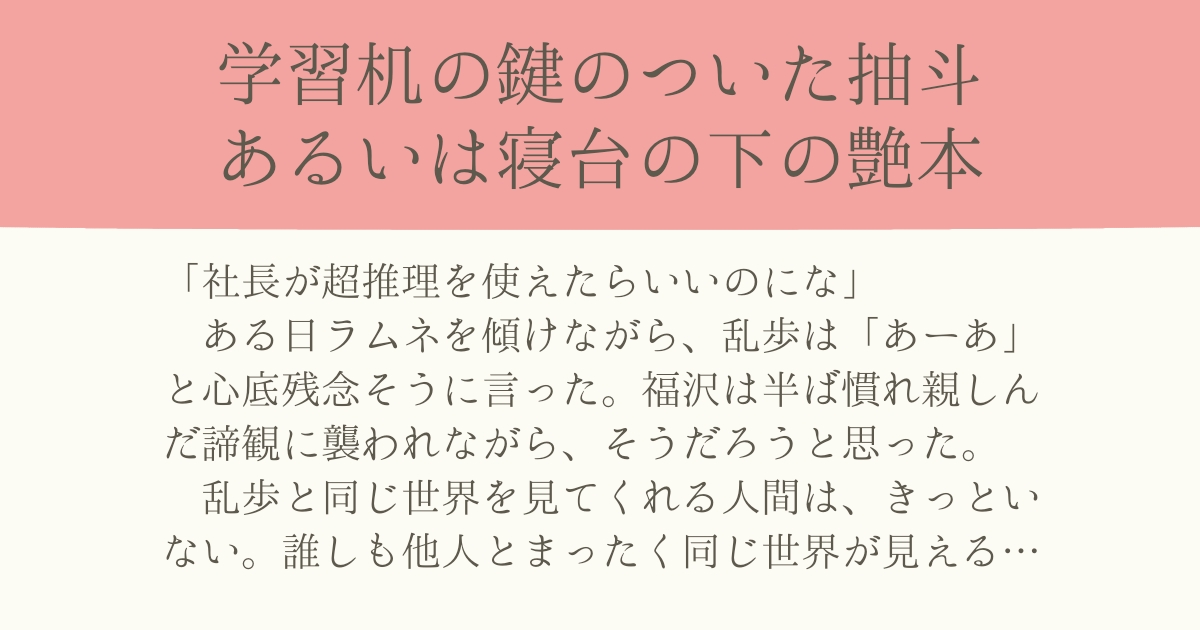
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます