2019年の春の終わり頃、車中でおしゃべりする志摩と伊吹の話です
「志摩さあ、たまに俺のことそーゆー目で見るよね」
慣れてしまいつつあったメロンパン号の助手席で、志摩は相棒に横目を向けていた。正面に目線を戻す。
「そーゆー目。どーゆー目だよ」
志摩は自分のまなざしがしばしば乱暴なことを知っていた。値踏みする、踏み荒らす……無粋で無遠慮なものの見方は、しかし刑事の志摩を助けた。志摩が知っていたのは、つまるところ自分の沈黙がやわらかくはないということだった。
伊吹はしばし言葉を探していたようだった。彼の沈黙は面と向かって言い難い表現に気を遣うようなものではなく、本当にただ、自分の感覚にふさわしい言葉を見つけようとしているのだろう。志摩は伊吹がそういう人間であると、もう知りつつあった。
しばらく横で唸っていた伊吹は、ついに納得したのだろうか。口を開いた。
「宝探しするみたいな目?」
「……は」
反射的に呆れと疑念を含んだ笑いをこぼしかけて、志摩はやめた。重要なのはそこではないと気づいたから。
「あるのか。お前の中に宝が」
「そりゃあるでしょ。みーんなそうじゃない?」
すごいなこいつ。俺がしているのは、そんないいもんじゃないけど。言わず志摩は考えた。だとすれば、志摩は宝箱を抉じ開ける野盗のようなものだ。伊吹はたぶん、鍵を探し当てられる人間だ。
「志摩ちゃんの中にもー、ビッグなお宝あるんじゃない?」
「開けてがっかりすんなよ」
「開ける?」
「宝箱」
「あ、金銀財宝ざっくざく! 的な? 俺なんかキレーな絶景とかのイメージだったわ」
「仲間と見られたこの景色が何よりの宝物?」
「そうそうそう、なんかそういうのあんじゃん。やっぱ志摩わかってんな〜」
志摩は白旗をあげようとする右手を左手で押さえつけているような気分だった。右手も、左手も、志摩自身だった。

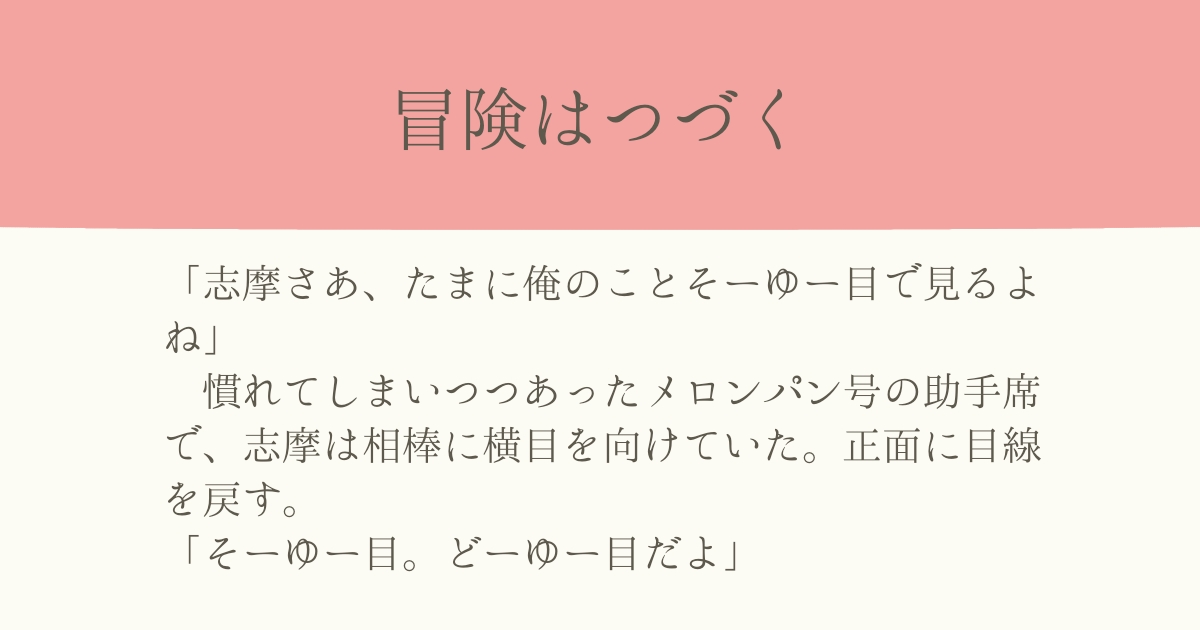
※コメントは最大1000文字、5回まで送信できます